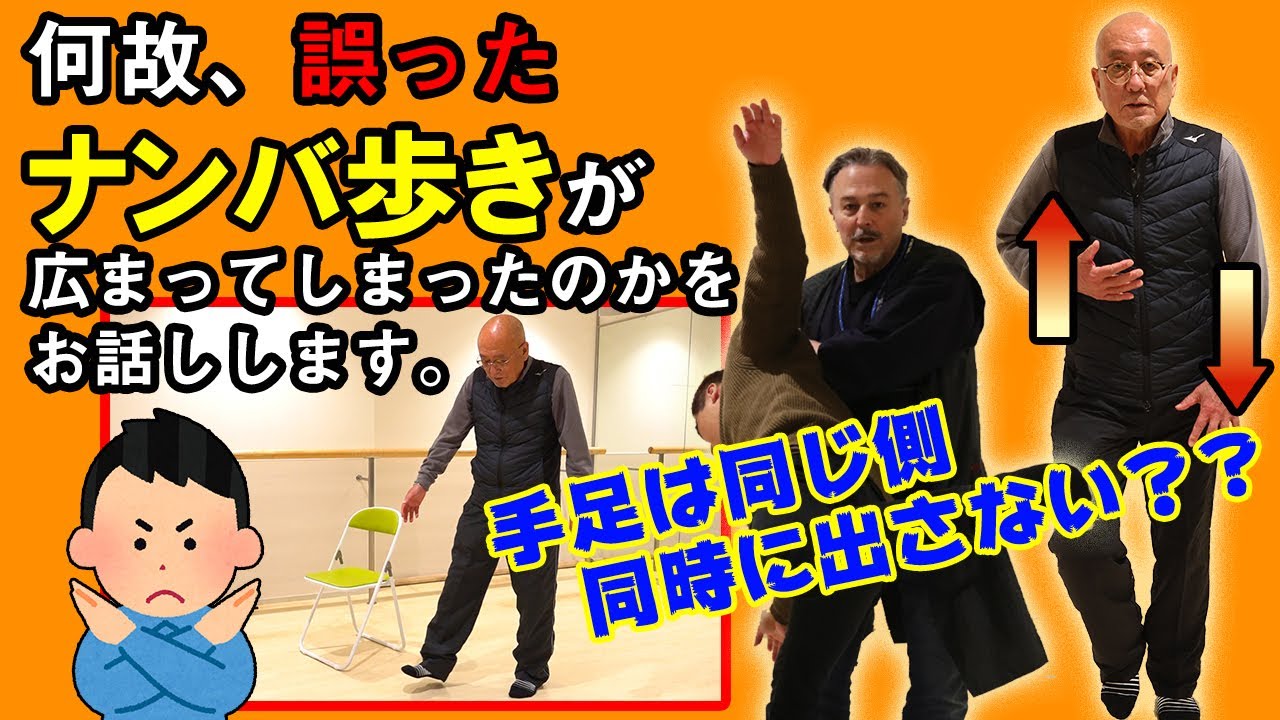今、ツイッターで「フィルムカメラ」がトレンド入していて驚いています。なので、カメラの話をちょっと。
「カメラマン」
「プロとアマチュアの違いはなんですか?」と聞かれると、「予備のカメラを持っていくかいかないか? だと思います」と答えています。
そう、カメラは機械であり、故障がつきものです。特に、現在のデジカメは「電気製品」ですから、故障の確率も高いです。
ですから、プロのカメラマンは「予備の機材」は必須で、心配性の私は、「予備の予備も必要だ」という考えでした。
さて、以前、「学校写真」をやっていた頃。
林間学校などで、けっこう過酷な登山とかに付き合わないといけないこともよくありました。
登山というのは大変なので、機材はなるべく軽くしたいものです。しかし、登山するような場所は、機材になにかあった際に、近くにカメラ屋さんがあるわけではなく、故障の修理も無理です。それに、荒っぽい使い方をするので、「岩にカメラをぶつけて壊してしまう」なんてトラブルも実際あるわけで、「予備の予備のカメラ」が必要になってきます。
しかし、「集合写真用の巨大なカメラ」を背負っている状況では、「機材は軽くしたい」わけで、あれこれ、いろいろ悩みました。
予備の予備を使用する確率は、かなり低いので、「重い、一眼レフをもう1台」というのは避けたいのが正直なところ。
そんな時、1989年に、コニカさんから、最適のカメラが発売されました。

Big Mini というカメラ。
変な名前ですが、35mmカメラで最小のサイズなのに、しっかりきれいに写る、つまり「価値が大きい」ということで、Big Miniという名前になったらしいです。
(写真は後継機種で、私が買ったのは最初の機種で、デザインがちょっと違います)
とにかく、小さかったです。この大きさと重さであれば、負担になりません。
そして、レンズは35mm単焦点。スナップ写真に最適です。本当はズームのほうがいいのですが、そうなるとカメラが大きくなります。非常用ということを考えると、35mm単焦点で十分です。さらにストロボも内蔵ですから、万全です。
単焦点ということもあり、画質もかなり良かったです。
というわけで、これを買ってからは、スナップ写真は、メインの「Nikon NewFM2 黒」と予備用の「Nikon NewFM2 白」と、この「Big Mini」の3台体制で万全のシステムとなりました。
ただ、これを実際に仕事で使ったことはありません。ラッキーなことに一眼レフ2台が両方とも壊れることはなかったためです。
「それだったら、不要だったんじゃないの?」
と思われるかもしれませんが、結果的に不要だったとしても、「予備の予備のカメラを持っている」という安心感があります。これが非常に大きいのです。このへんはプロカメラマンならではの感覚かもしれません。
仕事用カメラでは使いませんでしたが、同行の学校の先生が持ってきたカメラが故障した際に、「よかったら、これ、使って下さい」と貸したことが何回かあります。先生は予備のカメラなんか持ってきませんから、持参の1台が故障すれば「アウト」だったんですが、これがあったので撮影ができるようになりました。喜んでました。
それから、日光とか京都奈良などでは、同じ会社から来ている別のカメランといっしょになることも多かったのですが、若い、セミプロのようなカメラマンが、「Canon F-1は優秀なカメラだから絶対に壊れない。だから、予備のカメラなど不要だ」と言って、予備を持ってこなかったのですが、その、Canon F-1が現場で故障してしまい、私の方にSOSの電話が来て、「あの~ カメラ1セット貸してくれませんか?」と頼んできました。サブのFM2のセットを彼に貸しました。このときも、Big Miniがあったことで、「自分のカメラが万一故障したとしてもなんとかなる」という考えで、貸すことができたわけで、Big Miniが役立ったわけです。
このように、プロって、一見無駄に思えることをお金をかけてやっているものです。(だから、本物のプロの撮影料はそこそこ高額になるわけです。機材にお金をかけてますから)
ところで、後から思うに、「もったいないことしたなあ」という点があります。
というのも、せっかく「Big Mini」を持っていたんだから、それに、私用のフィルムを入れて、「個人の記録用に、写真を撮っておけばよかった」ということ。
当時はスマホカメラなどない時代です。仕事でいろんな場所に行き、きれいな風景も見ましたが、仕事で撮ったフィルムは全部「会社」に渡すわけで、手元にはそういった仕事の記録がまったく残っていないのです。
日本中、北海道から沖縄まで、けっこういろんな場所に行きましたが、それらの記録はほとんど残っておりません。今になって「あの時、あそこに行ったなあ」と思い出す際に、「写真屋なのに、写真がまったくない」のは寂しいものです。せっかく、BigMiniというカメラを持っていったんだから、個人の記録用に、これで写真を撮っておけば良かったのに、と、今になって激しく後悔しております。
「1行事=1枚」でもいいから撮っておけばなあ。。。残念。
まあ、こういうのも「フィルム時代」(=写真を撮るにはお金がかかる)ならではの事情ですね。
◎追記
このカメラが出る前のマニュアルフォーカス時代は、私は持っていませんでしたが、「オリンパスXA」というカメラ(※カプセルカメラと呼ばれ、非常にコンパクトだった)を、非常用の予備として持っているプロカメラマンを見たことがあります。あれも、小さくていいカメラでした。