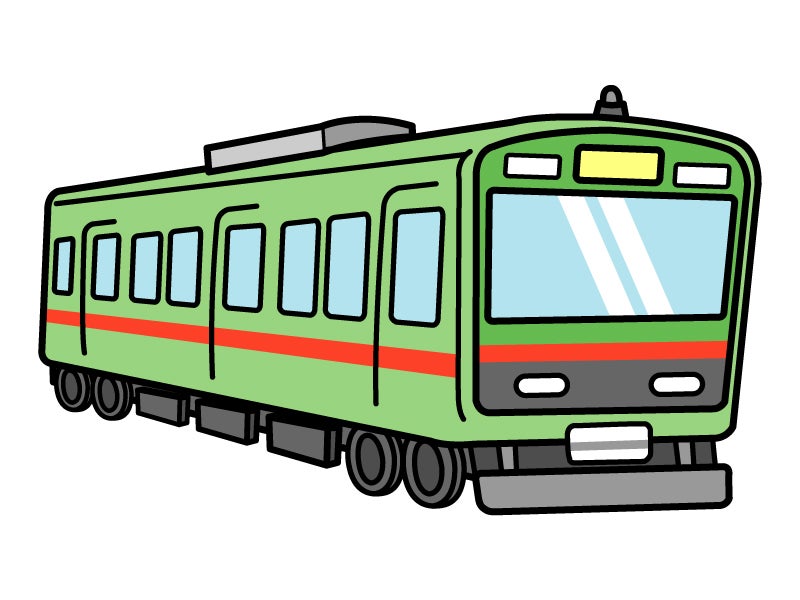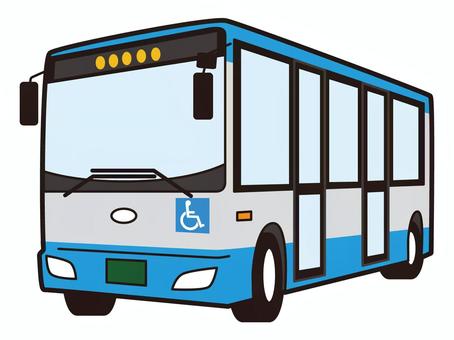宇都宮ライトライン。
「関東地方の全鉄道路線を完乗している」という自分としては、ここも当然乗らないといけないわけで、開業の2日目と3日目に乗って観光しました。
そして、念願の「1日乗車券」が11月から発売開始になり、早速、それを利用して、自分の趣味である「全駅乗降」(ただ、降りるだけではなく駅周辺もプチ観光する)をするために、再度、来宇してきました。

新たに「ラッピング車両」もできたそうで見てきました。バスケの選手が貼ってあります。

宇都宮駅東口から乗車します。

これが「1日乗車券」。紐がついていて「常時首からぶらさげて、よく見えるようにしておいて下さい」とのこと。
駅員がいないため、監視カメラで見ているから、そういう方法なんでしょう。ちょっと恥ずかしいけど、わかりやすくていいかも。

さて、前回の記事で「屋根に機械がいっぱい乗っていてみっともない」と書きましたが、LRTは床面がものすごく低いため、通常の電車であれば、各種機器は床下に置くのですが、LRTでは、床下がまったくない構造のため、屋根の上にあげるしかないんだそうです。このため、車体の重心も上の方へ行ってしまい、強風時などの安定性が悪いそうで。う~ん、なかなか難しいもんです。
さて、LRTの最大の問題である「ダイヤの乱れ」なんですが、「もう収まっているだろう。12分間隔でちゃんと走るだろう」と思ってましたが、全然だめでした。やはり、土日は、初めて乗車する観光客が多く、料金の支払いでどうしても手間取ってしまうようです。

各駅のホームには、こういう「案内」と「整理券発券機」があるんですが、これがわかりにくいです。文字が小さすぎて老眼にはまったく読めません。整理券をここで受け取るというのを忘れる人も多く、運転手に怒られていましたが、これじゃ、とり忘れるのは無理ないです。もうちょっと考えましょう。

案内は車内にも貼ってありますが、ひっそりとした感じで目立ちません。

せっかく、立派なデジタルサイネージがあるんですが、広告ばっかりで、乗車方法の案内が不十分です。
土日の「観光客が多い日」はプログラムを変えて、「乗車方法の解説」とか「観光ガイド」というものを強調して上映するといいと思います。観光客に地元の自動車販売店の広告を見せてもしょうがないですから。

運転席後方にある、料金収受機。これ1000円札しか使えません。1万円は無理でも、5000円は使えるようにして欲しいなあ。「5000円使えないの!」と困っている乗客がいました。スイカのチャージもできるのに「千円札オンリー」ではねえ。。。

さて、「全駅乗降」なので、すぐとなりの駅「東宿郷」で下車。周囲を散策し、12分の時間を消費して、また、すぐ次の列車に乗ります。

ここで気がついたのですが、「路面電車の駅は、道路の真ん中にある。信号が青にならないと、どこにも行けず待っている必要がある」ということです。当たり前といえば当たり前なんですが、この時間のロスはけっこう大きいです。
バスなんかだと「あ、バスが近づいてきた」とちょっと走って停留所に行けばバスに乗れますが、路面電車では、いくら走っても、信号が赤だと駅に行けず、乗りたい電車が無情にも眼の前を去っていくのを悲しい目で見ていないといけません。1本逃すと12分待ち(それも定時運行の場合だけ。ダイヤが乱れると30分待たされることもある)になります。
路面電車が通っている道路は大きな道路のため、信号の間隔もとても長いです。これがダイヤの乱れにもつながっているようです。
大勢の乗降者がある、ベルモールがある「宇都宮大学陽東キャンパス駅」の交差点の信号は間隔が特にすごく長いので、「余裕で乗れるはず」と思っても乗れなかったりして、非常に悔しいです。
(※運転手さんによっては、その心情を汲んで、駅で待っていてくれたりする親切な人もいます。でも、その行為でまたダイヤが乱れます)
このへんは、全駅乗降してよくわかった「路面電車の欠点」かもしれません。



そして、路面電車の欠点といえば、「交通事故」。
車と同じ道路を走っている区間では、すでに数件の事故が発生しています。
なので、開業時にはなかったいろいろな対策が行われていました。
これは、地元のドライバーが早く慣れることが大事です。

さて、ここは中間地点にあり、車両基地もある「平石」駅。
なんと、ここは線路が4本あります。将来的に予定されている「快速運転」の際に、「快速列車が各駅停車を追い抜く」駅になるはずです。
ただ、ここ一箇所だけで、うまく機能するのか? 完全な定時運行ができない路面電車で、うまく追い抜きできるのか? すごく難しい気がします。快速が誕生したらまた乗りに来ます。

ここは飛山城跡駅。
本当はここから歩いて、飛山城跡を観光しようと思っていたのですが、当日はものすごく寒く、そして、天気予報が外れて、雨。
晴れていれば、のどかでいい景色のところなんですが、観光はあきらめました。残念。やはり、宇都宮は寒いです。舐めてました。(地元の人は、ダウン、マフラー、手袋している人も多かったです。ウィンドブレーカーでやってきた私は馬鹿でした)

ここはグリーンスタジアム前。ここも千鳥式ホームですが、計4本の線路があります。将来的には、ここで折り返し運転する、「宇都宮駅~グリーンスタジアム前駅」の車両ができるらしいです。(ここから、終点の芳賀高根沢工業団地駅までは乗降客が減少するため)

この先の「ゆいの杜」地区は開発が進んで、住宅や商業施設がいっぱいあります。
私はカインズで手袋を買いました。あまりに寒いので。

そして終点の芳賀高根沢工業団地駅に到着。
実は路面電車の駅にはトイレ施設がありません。
この終点駅は駅舎のようなものがあって、広さもそこそこあるのにトイレがないんです。
近辺にもお店はまったくなく、寒いのでトイレも近い人が多い、観光客にとっては「え? トイレないの?」と嘆いていました。
前回乗車時にこの点を会社のほうに伝えましたが、仮設トイレの設置もしなかったようです。観光路線として考えているなら、もうちょっとお客さんへの配慮がほしいですねえ。
トイレに関しては、全19駅の中で、2駅だけあります。途中の

清宮地区市民センター駅には立派なものがありました。ここはトイレだけでなく、雨風をしのげる休憩室もあり、良かったです。
なお、芳賀町工業団地管理センター駅の近くにも「公衆トイレ」があるので、これも利用できます。
とにかく、明るい安村 じゃない 普通の鉄道のように「駅にはトイレが有る」というわけではないため、観光客や鉄道マニアの人は、事前にちゃんとトイレを調べておくほうがいいかと思います。工業団地のほうは、コンビニもほとんどないので、トイレ探すのは大変なんです。

清宮地区市民センター駅の前はカーブがあるので、撮り鉄さんのメッカになってました。

こうやって全駅乗降を達成し、帰りにはベルモールに寄って、「ステーキ宮」で食事をして、お風呂に入って、横浜に帰りました。
写真はベルモールの前の交差点の様子です。普通に走っている自動車と共存して走る路面電車。どうか、ご安全に。
鉄道マニアではなくても、十分楽しめる、素晴らしい路線です。どうか皆さん乗りに行って下さい。