ぼくは『源氏物語』を小説的に読んでいます。ぼくは物語の構造を読み取るのは得意ですが、古文を読み解く力というか本文の読解力や平安時代の文化の知識に欠ける部分があるんですよね。
実はぼくは平安時代の文化とか歴史とか、和歌とかもどうでもいいんです。いやどうでもいいというのは言いすぎですが、ぼくが一番興味深いのは、男女の関係が描かれていること。そこに尽きます。
それは性的な意味あいも含んでいますが、男がいて女がいる。そこに物語が生じる。その要素は、日本の古典文学も海外の文学もあるいは日本の現代の小説も同じだと思うんです。物語で最も面白いところです。
『源氏物語』における男女関係というのは、実は恋愛とはやや異なるんですが、それはまあともかく、恋愛というのは感情ですよね。主人公たちの感情の動きにぼくら読者も共感することによって、2人が結ばれれば、ぼくらも嬉しいし、悲恋に終われば悲しい。
それと同時に男女関係というのは、最も身近な〈他人〉との接触でもあります。〈自分〉のことはある程度分かる。でも〈他人〉というのは本質的に分からないものです。〈他人〉が自分のことをどう思っているのか、好きなのか嫌いなのか。
誰かを好きになるということは、〈他人〉のことをもっと知りたいと思うことです。それは未知への冒険にも似ていて、未知であればあるほど神秘的であり、知らなければ知らないほど知りたい気持ちは燃え上がるわけです。
それはじゃあ肉体的に結ばれれば、解消されるかというとそんなこともなくて、〈他人〉というのは〈他人〉であり続けます。絶対に知りえないものをなんとか〈自分〉の中に取り込もうとすることが恋愛であり、男女関係なのだろうと思います。
そういった男女関係におけるジレンマのようなものは、『源氏物語』でも描かれているというか、正確に言えば、男女がいればそこに生じ続ける問題なんですよね。そこに関しては、千年前だからどうとかいうことではなくて、いまだに新しさを持ってそこにあり続ける問題です。
ぼくが『源氏物語』で最も興味を持ったのは、空蝉というキャラクターです。空蝉というのは人妻で、光源氏を拒絶した人です。空蝉と光源氏が性的関係を持ったかどうかも解釈は分かれますが、まああったとするなら、一度関係があったにも関わらず、光源氏が忍んでくると上着だけ置いて逃げるんです。
空蝉というのは、蝉の抜け殻のことです。光源氏の手には蝉の抜け殻のように、空蝉の上着だけが残ります。光源氏は田山花袋の『蒲団』の主人公のように、空蝉の残り香に想いを馳せます。
なぜ空蝉は光源氏を拒絶したのか?
これがぼくにとっては非常に興味深いところだったんです。その空蝉の心理ですね。それについて触れていると長くなるので、みなさんがそれぞれ実際に『源氏物語』を読んで考えてみてください。
これはぼくだけが言っていることではないですが、人妻の恋愛を描き、それを心理的に読み取れるという構造は、フランス文学と共通するものがあります。
たとえば、ラファイエット夫人の『クレーヴの奥方』と比較している論文などがあります。
それは『源氏物語』とフランス文学との類似だけを表しているのではなくて、男女関係の基本的なテーマが描かれているということなのだろうとぼくは思います。
では、現代の男女関係と『源氏物語』で描かれる平安時代の男女関係はどんな風に違うのか、について考えてみたいと思います。
簡単に言ってしまえば、ハードルの差です。『源氏物語』には禁忌(タブー)の要素が強いということです。ぼくは思うんですが、男女関係で最も盛り上がるのって、この禁忌(タブー)がある時なんですよ。
たとえばシェイクスピアの『ロミオとジュリエット』を思い出してもらいたいんですが、モンタギュー家とキャピュレット家という宿敵同士の子どもだからこそあれは面白いんで、隣に住んでいるなんの障害もない2人の恋愛では意味がないわけです。
あっ、ちょっと脱線します。みなさん『君に届け』という映画をご存知ですか。
君に届け スタンダード・エディション [DVD]/多部未華子,三浦春馬
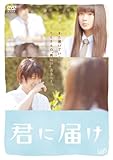
¥3,675
Amazon.co.jp
どうやらマンガが有名らしいですが、残念ながらぼくはまだ読んでません。当時、ぼくはSF映画を推したんですが、却下されて連行されてしまったんですが、この『君に届け』がめちゃめちゃ面白かったんです。
『君に届け』というのは、黒沼爽子(多部未華子)が主人公と言ってよいと思いますが、なんだか暗い子なんです。根はいい子なんですが、内向的なところがあり、髪の毛をだらんと垂らしているところが貞子に似ていると言って、本名の爽子ではなく貞子と呼ばれてなんだか怖れられるようになってしまっています。
貞子というのはあれですね、『リング』のテレビから出てくるおばけみたいなやつです。
そんな黒沼爽子が密かに想いを寄せるのが、クラスメイトの風早翔太(三浦春馬)です。それは厳密に言うと恋愛感情とは違うんですが、自分とは真逆のさわやかで人望もある風早くんに憧れを抱くんです。
そんな対照的な2人の恋愛というか、複数の一方通行の恋愛感情を描いた物語なんですが、この映画でぼくが一番面白かったのは、黒沼爽子にとってのハードルの設定です。
黒沼爽子が悩むのは、風早くんもいるであろうクラスのクリスマス会に出るか、いつも恒例の家族のクリスマス会に出るかです。このジレンマにすごく悩むんです。クラスのクリスマス会にも出たいけれど、お父さんが家族のクリスマス会を楽しみにしているであろうことを思うと、お父さんに言えない。
みなさんはすごく馬鹿馬鹿しい悩みだと思われるかもしれません。たしかにそうですよね、「クラスのクリスマス会に行きたいの」と言えばいいだけの話です。でもそれを言えない優しい黒沼爽子。本来ならジレンマにすらならないものがジレンマになっているという点で、非常に面白い設定だと思います。
世の中には男女の恋愛を妨げる様々な障害があります。宿敵の家の子供同士だったり、戦争など運命的に引き裂かれたり、決して結ばれてはいけない関係だったり、色々です。
そうした様々な大袈裟な障害の物語がある中で、クリスマス会がジレンマとして提示されて、それがしかも効果的に機能しているという点で、『君に届け』はとても面白い映画だと思います。
お父さんもいいです。一番の名場面はお父さんが言うあのセリフです。娘の方を見ないで言うのがぐっときます。実は胡桃沢梅(桐谷美玲)も相当いいんですが、長くなるのでこの辺りにしておきます。
ともかく、『君に届け』からなにが見えてくるかというと、男女関係はハードルの設定が重要ということです。それが世間的に見て大きいか小さいかは問題ではなく、当人にとってどれだけ切実かというのが重要になります。
『源氏物語』に話を戻します。男女関係を描いた物語でぼくらが面白いと思うために重要なのが、ハードルの設定だとするなら、『源氏物語』ほど面白いものはないということになります。
相手の気を引くだけで一苦労。相手の家に行くだけで大変な労力です。そして身分の違いなど様々な禁忌(タブー)があります。そのハードルの設定が現在に比べると非常に高いものになっています。
自分の思うままにどこにでも行けて、なんでもできる。誰とでも恋愛できる。そんな時代でないからこそ、男女の恋愛がすごく面白いんです。
ぼくらは今、恋愛をするならまずメルアドのゲットを狙うわけですよね。メールのやり取りから始まります。それが少し前の時代になると、電話のやり取りだったわけです。あだち充のマンガなんかを見ると、デートを申し込むのに相手の家に電話をかけます。
そうすると、相手の父親が出たりなんかするわけです。そして自分の家族になに話しているか聞かれたくないから、布団にくるまっていたりなんかします。そしてあんまり長電話をしていると、家族に怒られたり。これも1つのハードルですよね。
『源氏物語』は電話なんかないですから、手紙のやり取りになります。手紙のやり取りで恋愛がうまくいくかいかないか決まるだなんて、すごくハードル高くないですか?
そしてこの手紙1つを取っても、単に和歌のよしあしだけではなく、紙の選び方、文字など総合的なものが重要になります。手紙がダメならもうダメです。このハードルの高さ。
ちなみに恋愛において相手の容姿は重要ではないんです。正確に言うと、実際に相手の容姿を見て恋愛するわけではないということです。あの姫は美しいらしいよ、という伝聞でその女性に注目します。
まず家柄、血筋、そしてようやく始まる和歌のやり取り。いざ恋愛関係になっても、相手の家に通うだけで大変です。「ヘイ、タクシー!」じゃないわけです。なので、雨の日に訪れることが愛の深さを表したりします。
月をぼんやり見て、相手も今頃同じ月を見ているのかなあと感じることは、単なる和歌という文化があること、当時の人々が風流だったということだけではなくて、電話して「もしもし、月が綺麗だよ」とできないからこそなんですね。
相手のことをずっと考えていて、それを相手に伝えるすべがないからこそ、花を見てはその人を想い、月を見てはその人を想うわけです。そしてそれを和歌にして相手に伝える。そういうことなんです。
こうした平安時代の生活は、ぼくらから見ると古臭くて文化が発達していないと言えるかもしれません。ただ、その当時の人の気持ちに感情移入すると、現在よりもハードルの設定が高いということで読み取れます。なにをするにも現在に比べたら大変だということです。
それが抜群に面白いんですね。ぼくらでは想像できないようなものがハードルになりうる世界。形式としての魅力はそんなところがあります。
そして肝心の文章ですが、今の小説よりもより五感を刺激するものになっています。つまり、当時は電気がないわけです。明かりがないわけではないですが、パチッとスイッチを入れてつくわけではない。
それだけに、夜忍び込んでいく場面では、部屋の匂い、着物が立てるささいな音、相手を抱きしめた時の触感など、嗅覚、聴覚、触覚を刺激するような文章に心理描写が渾然一体となって描かれています。これがいいんですよ。素晴らしくいいです。
『源氏物語』に直接な性描写はないんですが、空間として濃厚なものが描かれているとは言えると思います。
そして『源氏物語』の主題的なものに触れるとですね、わりとエロい文学だと取られる部分がありますけど、そういった男性的な文学とは一線を画しているという認識は必要だろうと思います。
もちろん光源氏が中心的な人物になっていて、光源氏が子供の頃にされた予言の成就というか、光源氏が出世していく話ではあるんです。そうした長編小説のようにも読めます。
ですがその一方で、ここも様々解釈は分かれるんですが、まあ基本的には女性の作者が女性の登場人物を書き、それが主に女性によって読まれていたということでいいと思いますが、平安時代に女君はどのように生きていったらいいか、ということが大きなテーマになっているんですね。
つまり短編小説のように、様々な女君の物語があると読めるんです。そこには身分のジレンマ、愛しているのに愛されないジレンマ、出家したいけれど相手に引きとめられてできないなど、様々な要素があります。
その相手が光源氏という存在で共通しているだけで、重要なのは男性ではなく、女性の方だとも言えるわけです。そうしたいかに生きるべきなのか、というジレンマもかなり面白い部分です。そうしたテーマはある意味に普遍的ものがあるので、現代の小説に勝るとも劣らないものがあると思います。
というわけで、ぼくが思う『源氏物語』の魅力についてまとめてみます。
単に古臭い文化が描かれているというだけではなく、そこにある男女関係におけるハードルは、ぼくら現代の読者にとってはかなり高いハードルとして楽しめること。五感をより刺激する文章で描かれていること。いかに生きるべきかという普遍的なテーマが描かれていること。
そうしたところになると思います。みなさんも『源氏物語』に興味を持ったら、ぜひ読んでみてくださいね。マンガや口語訳から入ってももちろん大丈夫ですが、原文には原文の魅力があるとぼくは思います。簡単に言えば、曖昧さと現代語に置き換えないからこその美があります。ぜひぜひ。
≫『源氏物語』のページに戻る