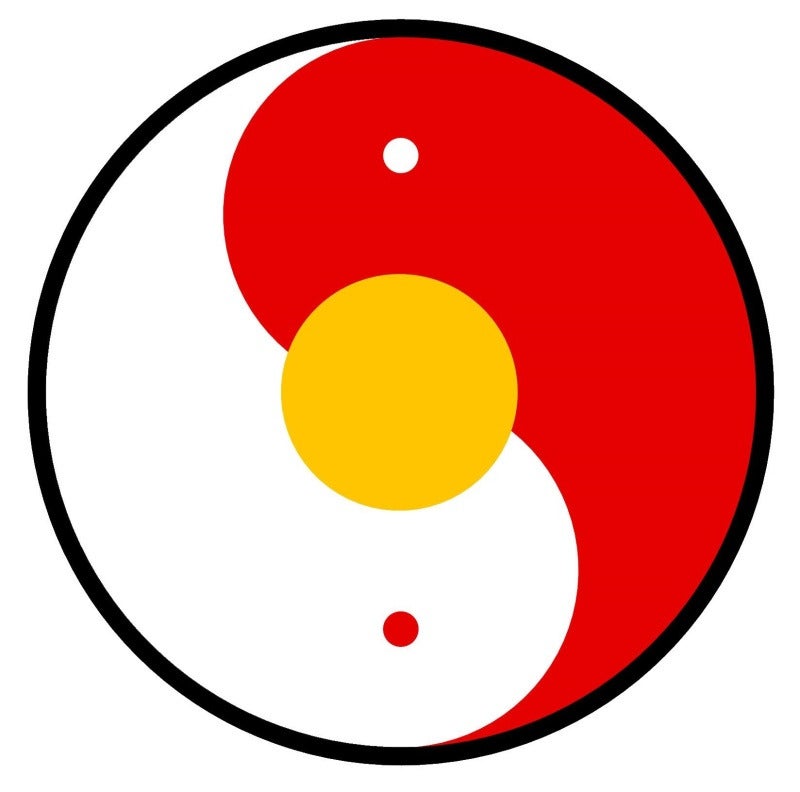“言語の起源論には、先ず祖語が人間に神から与えられ、そこから分化したという説と、人間の集団が進化の過程で、少しづつ単純なコミュニケーションから複雑なコミュニケーションへ移行する過程で言語が生じたという説とがあるわけです。
それではヨハネ福音書は、冒頭に、「初めに言葉があった。」ということで、言葉と神とは同じことであり、その神なる言葉が人間に与えられただけでなく、その人間も言葉によって産み出されたのだ、という立場に立つわけです。この立場に立ちますと、それだけで考え方を根本的に変化させなければならなくなります。言葉が人間以外のものから与えられたとすると、宇宙には人間よりも優れた知性がどこかに存在する、ということを前提にしなければなりません。そして、その知性を神的存在と呼ぶとなると、もう有神論に一歩足をふみ入れたことになります。
もうひとつ重要なことがあります。それは、あらゆる事物が言葉から成り立っているのではないか、という考え方です。日常使っている言葉は、喉頭部を微妙に振動させ、それを口と舌とで特定の音声にして発するのですけれども、もっと根本的に、目に見えるあらゆる事物、木だとか山だとか風だとか水だとか、そういうものがすべて言葉として発せられているのではないか、という考え方です。人間が声に出して発するものも言葉であれば、そもそも形があるものはすべて、形という言葉なのではないか、というのです。古代人にとって、言葉と形が同じだという考え方は、極く自然なものでした。言葉に物を作る力がある、と考えていたからです。例えば、誰かに、「病気になれ」と言うと、相手はその言葉の影響を受けて、病気になる、というのです。同じように、神が、「木が生えよ」と言ったら、そこに木が生える、というのです。古来、日本ではこの生きた言葉の力を言霊と言いましたが、同じ考えが、旧約聖書の『創世記』の冒頭にも出ています。神が「光あれ」と言うと、光が現われるのです。
この考え方が、神秘学の根本です。言葉という宇宙叡智の発現によって、森羅万象が生じたのが「自然」であるとすると、その宇宙叡智に由来する人間の言葉で創造された芸術、技術、産業、等々、そういう人工の所産もまた、同じ言葉の力によって生じたのですから、これも「第二の自然」である、と考えられます。だからこそ、人間は、大自然を理解するために、一つひとつの自然現象を人間の言葉(数も含まれます)に置きかえ、言葉の論理でそれを理解しようとするのです。このことをよく考えてみると、言語の問題は途方もない広がりをもっていることがわかります。いったい言葉とは何ものなのだろう、とヨハネは考え、言葉とは生命(いのち)のことであり、生命は、万物にその形姿を出現させる光のことに他ならない、と福音書の冒頭に記しました。言葉と形態と生命と光、この四つは、同じ神的存在の四つの側面を示している、というのです。
けれども、この考えは、決してヨハネの独自の考えなのではなく、古代ギリシャのイオニア学派の、例えばヘラクレイトスのような哲学者からヘレニズムの時代の哲学者たち、アレキサンドリアのフィロンのような人たちにいたるまで、受け継がれてきた「ロゴスの思想」のキリスト教化に他ならないのです。ですから、ヨハネ福音書の冒頭の、言葉こそが生命であり、光であり、創造の原点に言葉がある、という言い方には、古代人の深い宗教的な伝統が生きている、と思わずにはいられません。”
(高橋巌「神秘学から見た宗教 ―祈りと瞑想―」(風濤社)より)
*以前、エジプト人のキリスト教徒(コプト正教)の方から聞いた話ですが、アメリカで出版されている聖書の中には、このヨハネ福音書の「言葉は神であった」の聖句が、「言葉は神のようであった」と誤訳されているものがあり、コプト正教会は信徒達に『その(翻訳の)聖書は読んではならない』と通達を出しているのだそうです。日本語の聖書でこの『神のようであった』の訳になっているのはエホバの証人の新改訳聖書だけですが、たとえカトリックやプロテスタントの信徒の方であっても、言葉が神の顕現であるとまでは信じておらず、単なるコミュニケーションの手段でしかないと思っている方は多いのではないでしょうか。
*東方正教会には「イエズスのみ名の祈り」というものがあり、神の聖なる御名にたいする強烈な信仰が今もなお伝えられています。また、エドガー・ケイシーも「イエス・キリスト」の御名には実際に霊的な力があると語っています。エジプトのコプト正教会は、アルメニア正教会や現在もなおアラム語の典礼が行なわれるシリア正教会などと同じく、原始キリスト教の伝統を色濃く残している教会で、日本には京都府木津川市に聖母マリア・聖マルコ日本コプト正教会(TEL./FAX: 0774-26-4550 Email: japan@coptic.org.au)があり、来月10月8日にはコプトの新年(ナイルーズ祭)を記念して、京都市国際交流会館(KOKOKA)で『古代エジプトのコプト文化を紹介する特別講演会』が行なわれる予定です(入場無料、要予約、通訳あり)。
*この本「神秘学から見た宗教」の中で、著者の高橋巌先生は、『キリスト教では苦しみがあるから、この苦しみから逃れて天国に行く、というのではなく、苦しみを体験することが聖なる行為になります。この世に生きて、苦しみや痛みを味わうことができればできるほど、その人の魂は、聖なる方向に磨かれるという考え方です。このことを徹底して宗教の中で生かしたからこそ、キリスト教は重要なのです。』と書いておられますが、このコプト正教会の歴史はまさに殉教者の歴史であり、キリスト教各派の中でも最も長きにわたり、ひどい苦しみを味わってきた教会だといってもよいと思います。彼らの苦難の歴史は5世紀に非カルケドン派、つまり単性論と誤解されたことから始まったのですが、現教皇タワドロス2世は2013年5月にローマを訪問してローマ・カトリック教皇フランチェスコと会談され、2017年4月には今度はフランチェスコ教皇がアレキサンドリアを訪問されて、『どちらか一方の教会でなされた洗礼は、相手の教会でも有効だとみなす』という宣言を出されています。
(コプト正教会教皇タワドロス2世とローマ・カトリック教皇フランチェスコ)
・バール・シェム・トヴ(ラビ・イスラエル・ベン・エリエゼル)の言葉
“祈りにおいて、知っているかぎりのあらゆる集中の術をもちいる者は、まさに彼が知っていることだけを行うにすぎない。しかし、大きなつながりにおいて言葉を語る者は、その一つ一つの言葉の中に集中の全体がおのずからはいっていくのだ。というのは、どのしるしもひとつの全き世界であって、言葉を大きなつながりにおいて語る者は、あの上なる世界を目覚めさせ、ひとつの大きな業(わざ)を行うのである。”
(マルチン・ブーバー「祈りと教え」(理想社)より)
・いろは四十八文字の神秘
“お筆先は、いろは四十八文字と数字によって書かれたものであるが、それを拝読する人々の労苦と誤解を少なくするために、聖師はそれに句読点を付し、漢字を当てはめて、「大本神諭」として一般に拝読させておられる。
しかし、お筆先は世間一般の文章と違って、平仮名そのものが本文であって、漢字の方がルビに相応するものであることを忘れてはならないのである。
かえりみれば昭和七年頃の或る日、聖師の近侍の一人が、私の部屋を訪れ、
「聖師さまがあなたに、これをよく読んでおくようにと言われました」
と言って、和とじの書籍を一冊私に手渡して帰って行った。
それは活字で印刷されてはいたが、すべて平仮名で句読点のない、お筆先そのままの写しであった。
私は言われた通りに、その晩、それを独り拝読していったが、その内容は、いつも見ている大本神諭の通りで、別段に変わった個所はないようであった。
ところが、そのうちに、神諭拝読の際とは全然異なった意義が、稲妻のごとく私の心の中を照らすのを感じ、しかも、その意義の重要性なることに、思わず私は愕然として襟を正したのである。
翌日同時刻に、先の近侍の人が再び来て、
「聖師さまから、昨日お渡しした本をもらって来るように言われました」
と、本を持って帰って行った。
実は私としては、その本をまだ三分の一ぐらいしか読んでいないのであったが……。
その後、聖師さまからは「読んだか?」とも「何か感じたか?」とも、全然お話しもなく、私からも御生存中約二十年間、ついにそのことについて何も言わないままであった。
そして、その時私の心に映じたお筆先の解釈は、その真偽の程は今も私には判らないが、三十年後の今日も、それを忘れることができず、心の奥に強く刻まれていることだけは事実であり、それが現実の姿となって現われてくるかどうかは将来の課題である。”
(「おほもと」昭和35年7月号 葦原万象『言霊入門』より)
・「お筆先」は艮の金神様のお姿である
お筆先を読むものは、いはゆる変性男子(へんじょうなんし)を読むものなり、艮の金神(うしとらのこんじん)を読むものなり、出口の加美(かみ)を読むものなり。筆先には神のすべての心と、すべての行ひとを漏らさず載せられたればなり。
神の御心と変性男子の身魂を知らんとするものは、筆先を調ぶるに若(し)くものなし。筆先は艮の金神出口の加美の生ける御姿なり。故に艮の金神は、筆先にて世に顕はると宜り給へり。
天地を守り給ふ神の御心、万物を造り玉へる神の働きなぞ、ありありと伺ひ奉ることを得可きなり。
此の筆先によりて救ひの道も明らかになり、滅ぶる世も、栄ゆるなり。真実(まこと)に此の世の宝と讃へ得可きなり。(明治三七年一月八日)
(「神霊界」大正10年3月号 出口王仁三郎『筆の滴』より)
・「聖言」による内流
“「霊界物語」を拝読するとき、神の言葉を今承(うけたまわ)っているのだという心構えであれば、魂の中に入るけれども、何か小説でも読んでいるような心構えであれば、得るものが少ないのである。
声を出して読めば、自分の耳に神のお言葉が直接響いてくる。神の御声を聞きつつあるという心で読めば内流となるのである。
神は現実の世界に住む者に対しては直接内流はくださらぬ。そこで聖言に依って内流するのである。「霊界物語」は瑞霊の教であり、聖言なのである。これによって生命の糧は与えられるのであるから、物語を常に拝読するように心がけなくてはならぬ。物語の中に神は坐しますことをさとらなくてはならぬ。”
(「愛善苑」昭和25年7月号「瑞言録」大国以都雄編)
・「霊界物語」拝読の順序
“十三巻から読み始め、何冊か読み続けていた昭和三年の十一月(九歳のとき)のことです。
聖師さまが西日本方面をご巡教になるということで、大阪管下信徒で大阪駅に見送りに行かせていただきました。私も父に連れだってお見送りに行きました。大阪駅には五分間ほど停車していましたが、そのとき聖師さまにご面会いただき、おことばを頂きました。
聖師さまも窓から顔を出され、だれが来ているかご覧になり、それぞれに短い会話を交わされました。私は聖師さまと直接ご面会することは初めてのことでしたので、恥ずかしくて、父のマントの袖を持って隠れるようにしておりました。
聖師さまは駅のホームに並んでいる信徒の顔を一通り見ておられましたが、私の顔を見て『この子、どこの子や?』と尋ねられました。父が「はい、私の娘でございます」と申し上げますと、聖師さまは私の顔をじっと見られて、『あんたなぁー、霊界物語を読んどるやろ』とおっしゃった。
「はい」とお答えしましたら、続いて『十三巻から読んだな』と。
『今はそれでいい。もうだいぶ読んでいるから、そのまま七十二巻まで読み終えなさい。しかし、今度は一巻から順をおって読みなさいよ。むずかしくてもかまわない。字だけ読んだらよいのやから』
と言われました。
周りにいたある大人が「それじゃあ、もう一回、一巻から読み直したらええ」と言ったんです。すると聖師さまは、
『それは、あかん。霊界物語は水が流れるように読ましていただくものや。水は高いところから順番に流れてくるやろ。中流まできて、元の水上に戻ると逆流する。そんなことはダメや。水の流れるように読みなさいよ』と。
さらに、
『一巻から十二巻までに重大なこと、一番肝心なことが書いてある。これが大事なんやで』
とも教えていただきました。
だれも私が霊界物語を拝読しているなどとご報告していないのに、開口一番に『霊界物語を拝読してるやろ』と。しかも『十三巻から読んでるな』とおっしゃった。ご神書にある“神さまはお見通しである”ということは、だれがなんと言おうとそのとおりだと確信しました。四六時中、神さまはお見通しだ、だから曲がったこと、間違ったことはできないんだと、心にやきつきました。”
(「おほもと」平成七年八月号 中井和子「聖師さまが『あんたなぁー、霊界物語を読んどるやろ』と」)
*出口王仁三郎聖師は、「霊界物語」の拝読について繰り返し、たとえ内容が分からずともただ声に出して読めばよい、と語られています。そもそも「霊界物語」は頭で理解するものではなく、ただ素直に読んでさえいれば、心の奥底で何かが共振し始めます。
・「神語」の解釈
“昭和六年の夏でしたか、海外宣教について出口聖師は、次のようにお話になりました。
「大本の宣伝使は先ず「惟神霊幸倍坐世(かむながらたまちはへませ)」と唱えあげる「神語」が含んでおり、かつ顕わすところの御神徳をひろめて行きさえすればよい。仏教は六字の称号をとなえてアレだけ多くの衆生を救った。大本の神語「惟神霊幸倍坐世」は、名は実の主なりというごとく、ことごとく有名有実であり、絶対権威がある。
したがって神語は決して講釈してきかせたり、解釈を定めたり、説明を加えて内容を限定することは良くない。
日本人たると外国人たるとを問わず、誰にも、「カムナガラタマチハヘマセ」とそのまま奏上するように知らせるとよい。外人にはローマ字で書いてそのままを覚えさせ、そのままに発声奏上するように知らせるとよい。そうすれば神語奏上によって、無限大の御神徳は、随時随所、唱うる人々の相違によって、それぞれの御神徳が現われ来たり、どんな人も必ずや何等かの体験を得させていただくことが出来るものである」と、‥‥‥”
(「おほもと」昭和31年12月号 竹山清『世界改造の経綸』より)
・喉(のど)は未来の生殖器官(声変わりの霊的な意味) 〔ルドルフ・シュタイナー〕
“そして、何よりもまず、人間は生殖力に働きかけます。生殖力が今日とは違ったものになるというのは、多くの人々にとって表象しがたいものです。けれども、生殖の仕方は変わるのです。今日の生殖や生殖衝動は将来、他の器官に移行変化します。将来の生殖器官となるように準備されているのが喉頭です。今日、喉頭はただ空気の振動を作り出せるだけ、言葉の中にあるものを空気に伝えられるだけであり、言葉の振動に相応しています。が、やがて、喉頭からは言葉の律動が発せられるだけでなく、言葉は人間や物質に浸透されるようになります。今日、言葉は単に空気の振動となるだけですが、将来、人間はその似姿を言葉のように喉頭から発することになります。人間は人間から発生し、人間は人間を話し、作り出します。話し出されることによって、新しい人間が誕生するようになるのです。
このことが、現在私たちの周囲にあり、自然科学が説明できないでいる現象に光を投げかけます。生殖衝動は再び無性的なものへと変化し、かつての生殖の機能を担います。男性の人体組織は性的成熟期に喉頭に変化が生じ、声は低くなります。声変わりと、喉が将来、生殖器官になるということとは関連しているのです。神秘学は人生の諸事象を解明し、唯物論的な学問が説明できない現象に光を投げかけます。”
“魂によって体を変化させ得るという観点から考察することによってのみ、人間に変容が可能になります。神秘学的な、霊的な意味において優れた思考を通してのみ、心臓と喉頭の変形は行われるのです。今日人類が思考するものが、将来の人類となるのです。唯物論的な思考をする人は将来、奇怪な存在を作り出し、霊的に思考する人は未来の器官に働きかけ、美しい人体を発生させます。”
“真の認識をもって未来に生きようとするなら、これらのことを知らねばなりません。これらのことは人類の中で作用する力であり、これらを認識、顧慮しなければ、目隠しをして世界の中を歩むようなものです。善悪いずれかの方向に向かおうとする力を認識しようとしない者は、人間の義務を怠ることになります。認識のための認識はエゴイズムです。高次の世界を見るために認識しようとする人はエゴイストです。この認識を日々の生活において直接実行しようとする人が、人類の未来への進化に奉仕しているのです。霊学の中に存在するものをつねに実行に移すことを学ぶのには、非常に大きな意味があるのです。”
“唯物論から脱却し、このような指導的な役割を傲慢、高慢さからではなく、義務から行う霊的な協会を考えねばなりません。未来を準備するために、人々は協力しなければなりません。けれども、地域的に結集するのだと思ってはなりません。種族はもはや問題にはならないので、地域性の概念は意味を失っています。健全な未来を作るために、全地球上の人々が霊的に協力することが問題なのです。それゆえ、この最も深く物質の中に嵌(はま)りこんだ時代において、四百年前に、日常生活のすべての問いに答えられる実践的な霊学が薔薇十字会によって打ち建てられたのです。”
(ルドルフ・シュタイナー「薔薇十字会の神智学」平河出版社より)