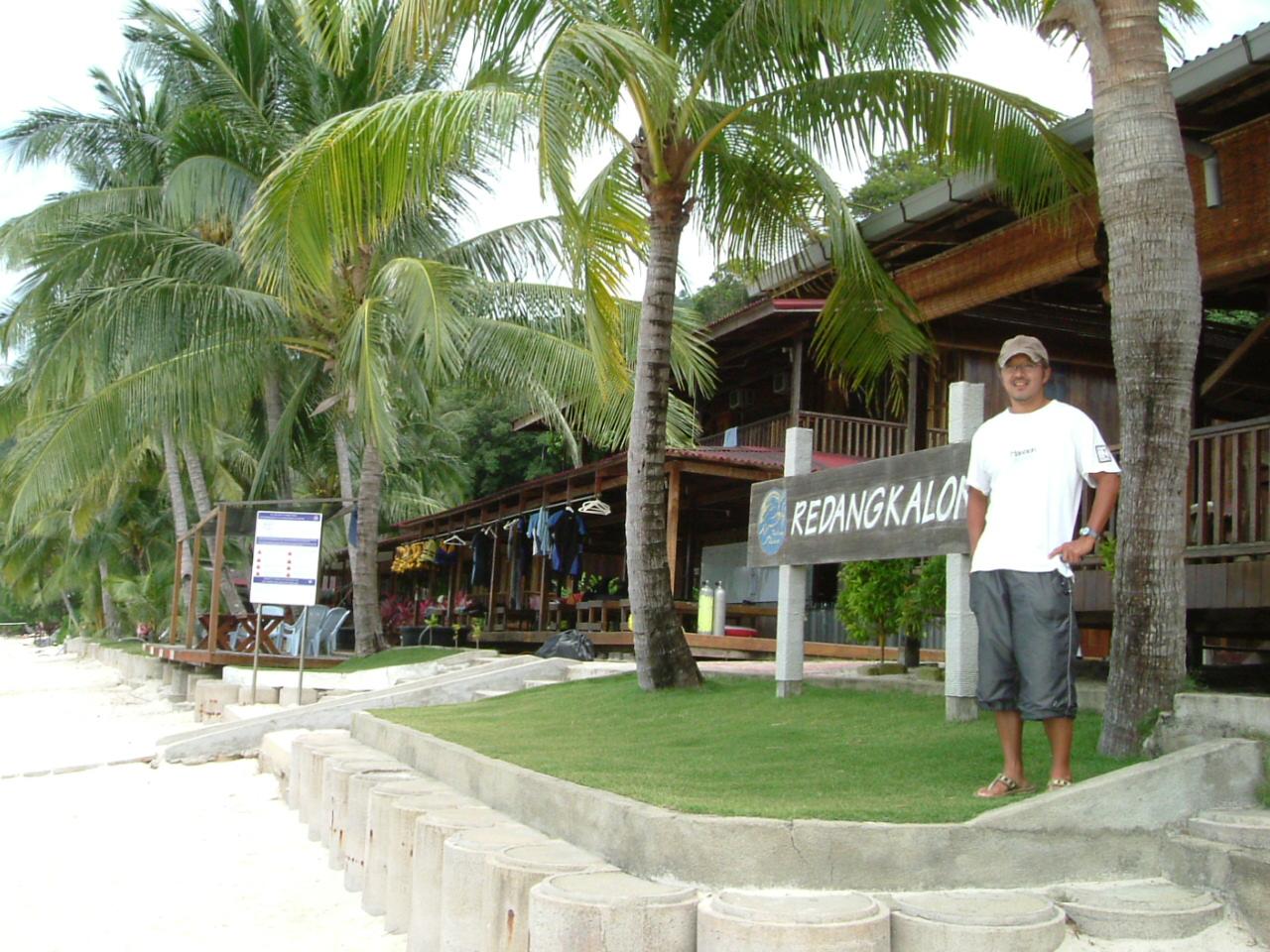象の夢を見たことはない
日々の雑記帳
プロフィール
カレンダー
最新の記事
ブログ内検索
お気に入りブログ
ブックマーク
月別
このブログのフォロワー
2007年12月14日(金)
『ゲド戦記』 宮崎吾朗
テーマ:映画ひどい。
宮崎駿は1992年『紅の豚』(原作・脚本・監督)で一旦地に落ちた。それまでが凄かったので、個人的な趣味の強い作品であるコレも、まあ道楽みたいなもんなのだなと思ってはいたが、プロデュースでかかわった1991年『おもいでぽろぽろ』(製作プロデューサー)ですでにおかしかった。1994年『平成狸なんちゃら』(企画)でジプリとしても回復不能なところまでいき、これではと思ったのか1995年『耳をすませば』(脚本・絵コンテ・制作プロデューサー)で「なんとかすくなくとも監督は後進に」とおもったのだろうけど、興行はふるわず。
紆余曲折の末、1997年『もののけ姫』(原作・脚本・監督)でもとの鞘におさまることで復活。歯がゆかっただろう。
2001年『千と千尋の神隠し』(原作・脚本・監督)で、監督業から再度手を引いた。
2002年『猫の恩返し』(企画)興行ふるわず。『おもいでぽろぽろ』『耳をすませば』『猫の恩返し』は、悪い作品ではないのだが、宮崎の名がまずあったので、映画会社や製作側としては、市場評価としては期待値以下という結果になった。名前を使うほうが悪いが、ファンは期待しますわ、そりゃ。
で、2004年『ハウルの動く城』(脚本・監督)で再々度監督復活。。お疲れ様です。
で、本題、宮崎吾朗の2006年『ゲド戦記』(原案)。絵がひどい。背景や人物などすべてが手抜きで、テレビ用に時間に追われて作ったものかと思った。これまで、ずっと積み上げてきた技術がすっかりチャラになったのかと。あまりのひどさに、やはり、アニメーションは手作業の家内制手工業で、CGなんかと違い、技術として残らないという、ものとして残らない旧世紀以前の文化だということまでも、露呈させてしまった。
脚本もひどい。人間描写が全然できていない。これじゃ、声優さんもたいへんだったろう。現実の観察能力がまったくないのかとおもって、年齢を確認したら1967年生まれとある。おいおい。。いままでなにを見てきたのか。
吾朗、ポスターみたいな絵はうまいらしい。たしかにポスターは、キャッチーでよい絵だった。だが、動画と絵はまったく違うものである。ときどき、昔のヨーロッパの港の絵のようなシーンがでてきて、絵としては塩野七生の小説的な雰囲気があってよいのだが、動画になっていると、まったく絵としても死んでしまっている。もったいない。
動画は、絵とは、違う才能と技術が要求される。構図が動くので、それにあわせてどう絵を動かすか、構図自体をどう動かすか、という感覚がおそまつ過ぎる。
これを日本の劇場でみたら、泣くに泣けなかっただろう。マレーシアやインドで200円とか300円くらいでみるのなら、まだましだが。
なんで、親父の資産で勝負するのだろう。ありえない。そりゃ、家族会議にもなるし、親も口きかんくなるわ。それで結果がこれじゃ、親もたいへんである。まあ、私も人のことは言えない。
こないだ『どろろ』を見たが即死した。『蟲師』もおんなじなのだろうか。日本映画、もはや過去のスタイルで作られているものは終わっている。韓国は、映画システム自体が変化した。これには、大統領の影響による政策の変化もかかわっている。日本映画も、インディーズやCMからの人材で、二局化はしていた。レコード界も同じだが、今、大手製作会社の金とコネにものをいわせた巻き返しが始まっている。だが、韓国映画界のように、過去のしがらみをまったく切り離さないと、死に体はかわらない。これは、電機業界などのほかの業界でも同じ。
今、社会の閉塞感が問題になっているが、なんで閉塞しているのかを言い切っていない。原因は『老害』なのだ。原因は老害。
若い芽はまったく違う分野で出てきている。たぶんシステム自身が、そっちの分野で新しく形成されて、社会システムがまったく違ったものになるだろうし、事実そうなってきている。狙うなら、そっちだな。
AD
2007年12月13日(木)
『李陵・山月記』 新潮文庫
テーマ:中島敦「隴西の李徴は博学才穎、天宝の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃むところ頗る厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかった。」
きれいなリズムと語感をもった文体で、まったくすばらしい。
中国の『人虎伝』を典拠にしているので、その物語性というものに内容は負っているんでしょう。彼がこれを選んだ理由というのは彼自身をこの物語のなかに見たというその一点だけであるような氣もします。
よっぱらった人が、トラといわれるのは、手に負えないところと、鈍いところを指しているとおもうのだけれど、自尊心があまりに強すぎると、自らを鈍くしてしまうことがあるようで、鈍くなることに自分で気がついていないのがトラのトラたる所以らしい。ほんとのトラは鈍いとは思えないのだけれど。
さて、この物語のわからないところは、「臆病な自尊心と尊大な羞恥心」とで虎になったと李徴が語るところである。高校のときに教科書で読んだときもよくわからなかったのだが、今でもよくわからない。
尊大な自尊心と臆病な羞恥心といわないところが非凡なところなのだろうけれど、それはさておき、羞恥心を持った状態で絶対的な自尊心は抱けない。。ん?ああ、だから臆病な自尊心なのかと、今、はたと膝を打った。
あと、高校のときも思ったのだが、この短編、妙に女々しいのである。なんでだろうとおもってずっと考えていたのだが。。
そう、これはトラになりそこねた男がトラに憧れる話なのである。なんのことはない、中島敦、彼の私小説であった。彼の病の話なので、本来の『人虎伝』の物語性が逆に失われてしまっているのかもしれない。人虎伝を知らないのでしかと言えないけれど。
なお、彼、中島敦は袁傪でもある。袁傪が、虎となった李徴が詠みあげた詩について「成程、作者の素質が第一流に属するものであることは疑いない。しかし、このままでは、第一流の作品となるのには、何処か(非常に微妙な点に於いて)欠けるところがあるのではないか」と思ったとのくだりがある。わざわざ、解説で暗喩で指摘してくれているのが、新潮文庫、心憎いのだが、典拠の『人虎伝』ではこの種の批判はなく、「文甚だ高く、理甚だ遠し(深遠である)」とあるそうだ。
実際、彼が認識していたように、ここでも、実は彼のこの作品と『人虎伝』との二重写しになっている。ここを変えたことによって本来の『人虎伝』の物語性が損なわれてしまったとも言える。決定的に欠けてしまった。
典拠と見比べなければわからないところに本論を隠すことが彼の気位の高さを表しているといううがった見方もできるが、同様にそれを隠すところに彼の羞恥心も読み取れる。まあ、そんなとこでしょう。
誰かが言ってた様に、「中二病 です」っていう診断で終わるのがもっとも賢い書評のような気もします。その方は、「あまりに痛切で死ぬかと思いました」と言われているので、そういう自覚のある人にはよい短編なのかもしれません。私は、まだ自覚がないので、小学生なのでしょう。そういう点で鈍いので、彼らより私のほうがトラに近いのかもしれません。ばんざい。トラだ。
2007年12月11日(火)
【メモ】 開発効率化について
テーマ:お仕事『システムの急所をついて、なぜを三回繰り返す』
場当たり的な施策は、諸悪の根源である。
スタンバーグ(Robert Sternberg 1949~ アメリカの心理学者)は、高い知能をもつ被験者は低い知能の被験者と比べ、「問題の枠組み化」に時間をかけることを発見した。
「問題の枠組み化」とは問題を定義し、分析し、それについて述べることである。
なお、スタンバーグの理論によると、知的行動の根底には3つの段階がある。
(1)メタコンポーネント
作業行動や実行の際の計画と規律
(2)業績コンポーネント
実行するにあたって使われる戦略や方法
(3)知識習得コンポーネント
蓄積した情報の符号化や解釈。つまり経験、記憶、
そして以前得た知識をもとにした新しい洞察による学習
この段階はどうでもよいが、問題の枠組み化によって、筋のいいシステムとそれ以外のシステムが完全分離する。
『混乱したら基本に戻る』
システムが複雑化すると、ヘソがわからなくなる。もっとも大事なことは、最大の急所を押さえることである。そうしないと筋のよい解決は得られない。
以上、2点のみが開発効率化の骨子である。
自働化については、上記が成り立っていて有効になるものなので、開発効率化のための下部構造である。
手段を目的にしないこと。
2007年12月10日(月)
『意識と本質』 岩波文庫
テーマ:井筒俊彦『対話と非対話 -禅問答についての一考察-』
「言語にはそれぞれ独特の「現実」の区切りがあって、それらの無数の区切りが意味的単位の綿密な網目になって人の心をしばり、一つのきまった世界像を意識に押し付けてくる。この網目を抜けるのは容易なことではない」 p309
「言語は、第一義的には認識範型あるいは分節形態の体系であり、ある言語社会に生まれた人は、無意識のうちに、その言語の分節形態を通して「現実」を分節し、それの提供する認識パターンによって世界を見る、というより、むしろ世界を創り出すのです。こうして各言語は、それぞれ一つの独自な世界像を確立するわけでありまして、従ってその言語を母国語として話す人々の心に既成の、つまりあらかじめ分節された世界の、ヴィジョンを押し付けることにならざるを得ない、と大体こういうような主張であります」 p394
「巨視的次元の体験内容が言葉で伝達できる性質のものであるということは、それがもともと言語的「現実」分節の所産だからであります。今までお話ししてきたことから、それはすぐおわかりいただけると思います。
体験の巨視的次元とは「公共的に観察できる」事物事象からなりたっているといわれますが、それは別の言い方をすれば、体験の巨視的次元が名称あるいは名前の領域だということです。感覚的、感情的、情緒的、あるいは理性的にいろいろな事物や事象が、名称によって与えられる意味的指示に従ってそれぞれ他とは違ったものとして識別され確立されて互いに他に対して自己を主張する存在領域で、それはあるのです。あるものがある名前をもつということは、それがそれ自身としてはっきり分節されているということにほかなりません。この意味で、巨視的世界は言語分節の世界であります。」 p395
「ところで禅の修行の道の第一歩は、このようにして巨視的次元に生じた意味的凝結体を、観想によって次々に-というより、できることなら、一挙に-溶かしてしまうことにあります。言語的意味分節論の見地から申しますと、座禅とは、意味的に凝結している事物を溶解して、もとに戻すために考案された方法であると申せましょう。」
p396
-------------------------------------------------------
以上が、禅における、言語分節世界から「一者」の次元への旅路の意味論なのだが、実は、言語分節世界から、一者世界にいたるまでに、イメージの世界を通る。
ここが、芸術でのミソになってくるもので、このイメージの世界、井筒さんはあんまり詳細には言及されてないけれど、分節しきれてなくて、まだ民族的な世界観を色濃く残している。また、その奥というか、その下部の、さまざまな民族に共通したイメージというものまで含んでいて、どこまでがどうということはある程度までしか明らかになってない。ユングの本などをみると、錬金術やら、聖書やらスーフィーなどの研究で、ある程度まであきらかにしようされていて、今もその延長線上の研究などで或る程度まで見えているようだが、諸説が入り乱れての攻防状態である。クオリアというのもこのイメージの世界と密接にかかわってくる。
イメージの一例をあげると、フロイトの夢分析で馬は男性の象徴だが、日本人においてはこれはかならずしも当てはまるわけではない。十字架のシンボルはキリスト教的世界観をもつ西洋人には現れるが、日本人には現れないし、逆に日本の曼荼羅的なシンボルが、文化基盤の異なる民族にあらわれることは稀である。
一方、水が浄化のイメージを持つことは、多くの民族で共通して見られたりする。
実は、こういうイメージは固定しているわけではなく、非常に流動的で、現在、たとえば、韓国でキリスト教徒が爆発的に増えているのだが、キリスト教的世界観が、それまでの彼らが韓国民族として共通にもっていたイメージを、フィルタリングしたり変容させたりするところまで来ているようである。
現実世界で、自分たちが言葉を覚える際の感覚を思い出せばわかるが、それは視覚的、嗅覚的、聴覚的、触覚的、味覚的イメージと結びついている。これらのイメージは、なにも言語的に分節されて意識に刷り込まれるだけではなく、無意識下にも、民族的、宗教的、文化的、家族的、個人的背景をもって、総合的なイメージとともにインプリンティングされる。子供のころにインプリンティングされるものもあれば、大人になるまでに、あるいは大人のなってからもインプリンティングされたり、またそのイメージが変容したりするようなので、どこまでがどうという明確な線引きはできないが、その線引きはスペクトラム的な様相をおびてあきらかに存在する。
これは身体の構造とか姿勢とか生活習慣にまで影響するし、それらと相互的にからみあう。流動的ではあるが、人として社会性を保つ、あるいは、生活をする、あるいはただ単に生命を保つという意味での恒常性を保つために一定の範囲に留まりもする。生物として、人間として、個人として、家族の一員として、ある会社の一員として、国民として、民族として、世界の一員として。
話をもどすが、いま、たとえばテレビゲームのキャラクターデザインやストーリーデザイン、映像美術、音響美術などを含んだ商品マーケットがボーダレス化しているが、そこにおいて、上記の禅的アプローチを行うこと、また、上記「一者」次元にたどり着いたあとの再分節化という下降ラインで体得できる見地(もし、そういうものがあるとすればだが)でものを眺めることができても、無意識下で把握したイメージを、作品としてはたして表現できるかというのは、一般論としてどうなのかは、私は正直わからない。再分節された結果、やっぱり元の木阿弥の世界に戻ってしまったりもするんじゃないかとも思う。
ただし、個人として、そういう上昇、下降体験をすることによって、なにものかを創り出している芸術家は、たくさんいるようだ。ここで私がいう芸術家は、今の美術界ではなく、山野の人として、ある社会人として、一般人に溶け込んでいたりする人であって狭義の芸術家には逆に少なかったりするのかもしれない。現代美術とか、とくに私より年上の世代で、デュシャン以来、ばかな哲学的見地や、技術論や工芸論にへばりついている人のうちにはあんまりいない。
なお、この体験は、禅だけではなくて、たとえば昔、フロイトがやってたように、見た夢を記述してりすることによっても断片をつかんだりすることはできる。だが、いわゆるユングの本の書かれているような、物語を感得するまでいたることはなかなかないようだ。
-------------------------------------------------------
【コラム】 脳の研究から導き出される驚愕の新マーケティング論
(R25 - 11月26日 11:02)
消費者の脳内の反応を見て広告効果を分析する「ニューロマーケティング」という手法が、欧米で注目を集めている。耳慣れない言葉だが、それってどんなものだろうか?…ということで調査してみた。
近年、fMRI(機能的磁気共鳴画像診断装置)やMEG(脳磁図)などの脳計測装置・技術が発達し、意思決定に関わる脳活動の直接計測が可能になった。それにともなって、消費者が製品や広告を見た時に「脳がどのように反応・活動するのか」を実験で計測して、マーケティング戦略に生かそうとする試みが行われているのだ。
この分野の実験結果として有名なのが04年の米国における清涼飲料水の事例である。被験者にブランド名を伏せてA社とB社の商品を飲用させると、満足感に関わる脳部位は両社とも同じ様に反応したが、ブランド名を告げた状態ではA社の飲用中は複雑な思考や評価を司る「内側前頭前野」が強い反応を示した。この結果から、A社の広告メッセージが消費者個人の選択に関わる脳領域に影響を与えた=効果的な広告展開をしている、と結論づけられた。
ところで、日本ではどうかというと、ブランドと脳活動の関係についての研究は理化学研究所で行われているようだが、まだまだこれからといえるだろう。
では今後はどのような方向性・発展が見込まれているのか? 電通消費者研究センターの佐々木厚氏に聞いてみたところ
「研究の方向性は『fMRIやMEGなどの脳計測装置で、広告や商品に対する脳活動を分析する方法』と『幅広い認知実験を通じて購買行動に関する推測を行うこと』の2つと考えている。この分野は経済・消費行動を通じて人間を解明する科学といえるので、単なるマーケティング分野にとどまらない研究になるのではないか」とのこと。
将来的には、どんな広告を展開すれば消費者の購買意欲を引き出せるかが科学的に解明される…そんな日が来るのかもしれない。
(R25編集部)
-------------------------------------------------------
現状、上記技術の応用で、どういうキャラクターが人に購買意欲をおこさせるか、とか、どういうストーリーがどの国の人に受け入れられやすいかなんていう傾向がわかるような気が、素人考えではする。
将来的には、さらに、そういうイメージを得る際のデザイナーや芸術家の脳電位状態なんていうのから、逆にその電位状態を判定する簡易版の機械なんかが売り出されて、ゲーム会社の社員一人一台とか割り当てられ、「あ、きょうは電位がさがってるから、調子わりーんで、創作作業はできないなあ。ルーチン作業やるか」なんていう世の中になるのかもしれない。
やれやれ。またまた効率化である。菩薩行ってのは、たいへんです。私もそのうち菩薩行復帰します。とういか復帰したい(苦笑)。
2007年12月08日(土)
肚
テーマ:心と体日本語には、なにかを決心するときなど、心の意味で「腹」を使う用語が多い。いわく、「腹を据える」「腹を決める」「腹をさぐる」「腹づもり」などなど。腹を立てるとか腹を抱えて笑うなんていうのもある。
これらのうちで、肚っていう字で置き換えられるものは、臍下丹田を表す場合がある。腹をくくる、腹をすえるっていうのは、臍下丹田のことだと思う。
一方これらの言葉を英訳する場合には、腹なんていう語は出てこなくて、determineとかmake one's mindとかやはり心という言葉を使う。キリスト教的世界観あるいは古代ギリシャなどでは、心は脳になく心臓にあるとされてきた。
こういう身体的な言葉というものには、身体的意味、もっというなら身体そのものがくっついている。
つまり、日本人は腹を、西洋人は胸を身体の中心に据えることが多いのではないか。西洋人といってもまあ定義があいまいであるが。。
要は、なんらかの運動をする場合や、立つ姿勢などにおいても身体の中心の意識をどこに持つかによって動きが変わってくる。西洋鎌は立って草を刈るようにできているが、日本の鎌は、腰を折るもしくはしゃがんで刈らざるを得ない。のこぎりでも、押すときは胸をつかったほうが切り易いし、ひく場合は、腰をつかったほうが楽である。腰と書いたが、臍下丹田は、へそのした3寸、骨盤のラインのところにあるので、同義として用いられることもある。腰をすえるっていうのは、お尻ではなくてあくまでも腰である。
そういうふうな身体的な重心の持ち方の違いが、ダンスと舞踊、椅子と畳なんていう、よく言われるようなところに出てきているのだが、これは重心だけではなくて、いわゆる「気」をどこに持つかというもっと大事なところにも関係してくるようだ。いわゆるチャクラとしてどこを重要視するか、あるいは実際にどこのチャクラを廻し易いか。
身体にも曼荼羅はあると思うのだが、西洋人の曼荼羅と日本人の曼荼羅は図形が違っているのかもしれない。