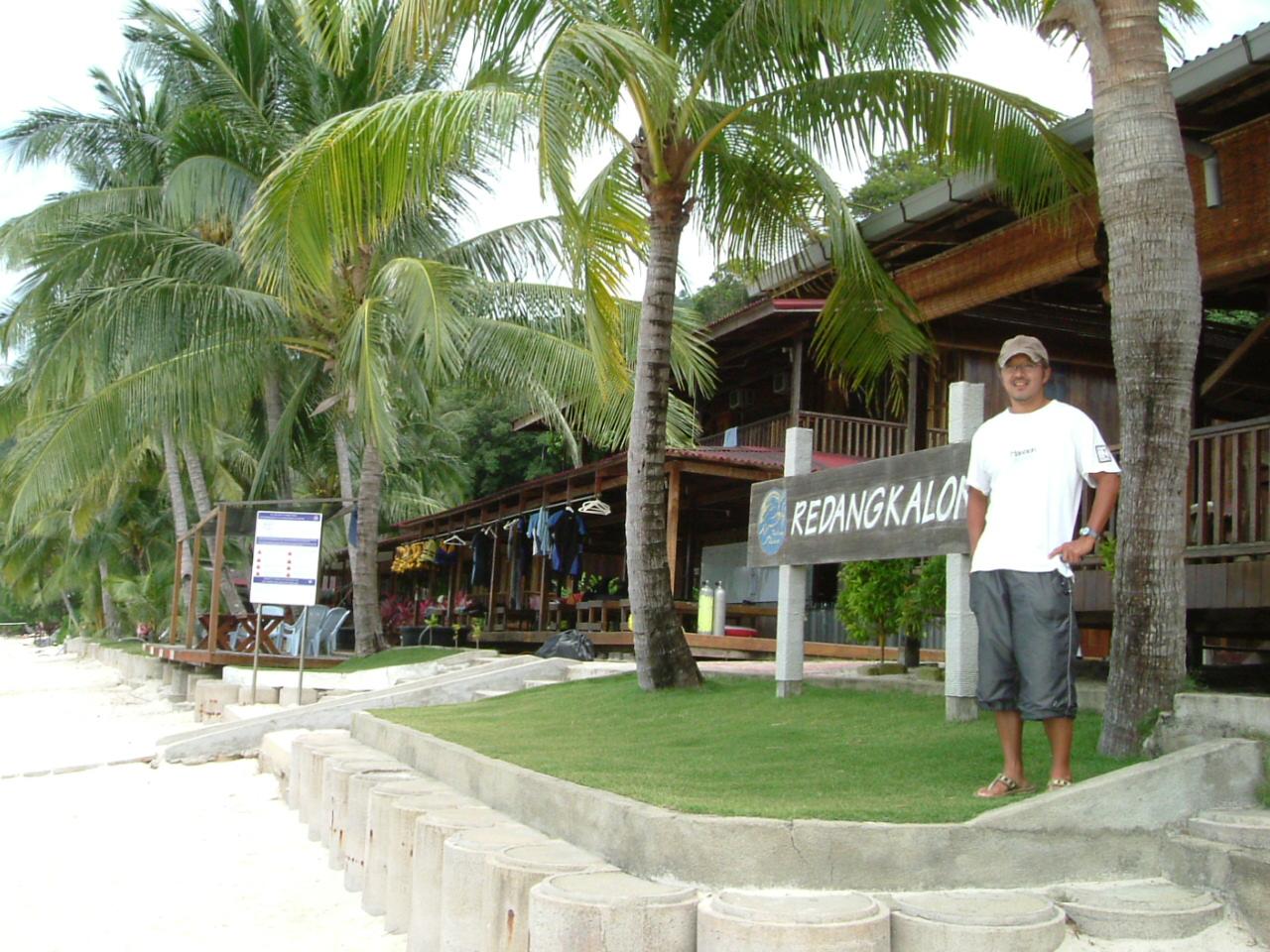象の夢を見たことはない
日々の雑記帳
プロフィール
カレンダー
最新の記事
ブログ内検索
お気に入りブログ
ブックマーク
月別
このブログのフォロワー
2008年01月29日(火)
直観と人情は磁気共鳴の夢をみるか
テーマ:つぶやき女の人の勘とか、けんかしてるときの会話内での飛躍で男どもが図星をさされて黙り込まざるをえない経験をしたときの彼女たちの発想方法が、いったいいかなる経緯で成立するのかを考えることは興味深い。
どうも、そのとき、彼女たちの意識・無意識のなかで、人とモノ、人と事象というものが等価的にマッピングされて繋がっているような気がする。マッピングといっても、論理的なものではなく、「なにかあの感じ」という、それらの現実のモノや事象を一度夢の中へひっぱり落としたら、同じものとして扱われているような、そういう無意識内での同様の感覚・感情・価値を抱くようなものの間でのすり替えが起こっているような、そんな気がする。
意識内では、視覚、聴覚、触覚などの感覚器官から与えられる信号は、まったく別のものとして処理されるが、それが記憶されるときは、ある感情や価値とともに記憶されて、心的表象をもつ別のものとなっている。
ケンカなどで興奮した心理状態、それらはある身体状態から引き起こされる場合もあるが、そういう状態となったときに、同一のもの、同列のものとして記憶されているそれらが、無意識上でマッピングされて出てくる。
無意識内で扱っているのは、本質的なものである。それは現実世界で、表象としてまったく別のモノやコトとして現れているのだが、その関連性は意識では気づかない。論理的じゃないので通常の科学的な計測の範疇からいまのところは逸脱している。そういうものだ。どうもそれらには一定の法則がやはりあるようで、図星をさされるという事実でわかるように、それもまた真理なのだが。おそらく、心理実験的に検証できるものだとは思うが、まだそういうものはみたことがない。fMRI を使って間接的にでも検証できるか?
ある無意識レベルまでいくと、「心的事象」と「物質として表れているこの世界」は等価のパラレル関係となる。世界のあらゆるものが心的エネルギーをもつものとして心の中にマッピングされるのだが、それには個人の層もあれば、家族の層もあるし、それらを貫くものもある。一般には無意識はいくつかの心理層として考えられているが、実際はもっとダイナミックなものなのかも知れない。そこで通じる本質というものは、実際我々が生きている世界でも事実だったりする。
真理であるならば、掴めるはずである。「魂があれば、かたちに出るはずだ」というのは、青山二郎の言葉だが、彼が小林秀雄に常に突きつけていたのは、そういうことだろうと思う。クオリアを研究して、小林秀雄賞なんぞを貰っているくせに、そういうことがわかっとらんヤツもいるが。。
自分ができないことをできると思える範囲にいる人には、評価は厳しいものだ。自分も、青山二郎も。人情っていうのはそういうものだが、最近はええ歳して、そんなこともわからん大人が増えてきた。やれやれ。
AD
2008年01月28日(月)
コミュニケーションの妙味
テーマ:ブログコミュニケーションの妙味は、傷つくことにある。
自分の無知を指摘される。弱点を指摘される。弱さを突かれる。考え方の変換を迫られる。
プライドを傷つけられることによって成長できる。それは、なまぬるい、自分だけで出来る成長を超える部分がある。
自分自身の存在の変換を迫られるまでに追い詰められたら上出来である。ひとりではなかなかそこまでは行き着けない。
相手をわざわざ傷つける必要はないが、あまりに傷つけるのを恐れる必要もない。
言いたいことは言う。傷つく気概のない人は、逆に思っていることを言えないものである。
傷つくことと傷つけることのアンビバレンツ。生きることの強さは必要だ。
2008年01月26日(土)
体を使うイメージ
テーマ:心と体仕事で、体をつかった作業をする場合、『頭と体を隅々まで使っているか?』を自問しながら作業を行うと、集中して作業できるようだ。
ちゃんと両手を使うこと。足を動かすこと。体を動かすことで頭も活性化する。
ある作業者を見ていて、彼は頭がいいなあ、作業がはやいなあと感じたことがあったが、そのとき彼は、両手をちゃんと使っていた。両手を使うと、作業効率が良いのである。
日々そういうことを自分に課していると、日常のどんな作業でも、効率よく作業できるようになる。
よい職人さんは、体のあらゆる部分を有効に使う。親父の仕事を見ていたが、体の使い方に理があるのだ。
そういうのは自分でやってみないとわからない。こういうのは、訓練でしか覚えられない。頭だけで、考えてもどうにもならない。
どんな作業でも、最初はイメージ通りにうまくはいかない。そんなに、簡単なものではない。
そういうときにどうするか。
『頭と体を隅々まで使っているか?』
たぶん、そこから始まるし、作業で迷ったらそこに戻ってみること。
2008年01月24日(木)
信ずることと知ること
テーマ:小林秀雄 『考えるヒント3』は、小林秀雄の講演集だが、一番最初に「信ずることと知ること」という題での講演が書かれている。
『考えるヒント3』は、小林秀雄の講演集だが、一番最初に「信ずることと知ること」という題での講演が書かれている。
科学的な経験というものが、人間の経験というもののすべてではない。人は何かを信ずるものだが、その信じるもののなかに人間の経験というものがある。人間の経験というものはもっと豊かなものだ。もっと戦慄すべきものだったりもする。
異常体験であれ、自分が確かに経験したことは、まさに確かに経験したことであるという、経験を尊重するしっかりした態度。自分の経験した直観が悟性的判断を超えているからと言って、この経験を軽んずる理由にはならぬ。柳田国男さんの学問とはそういうもので、私はそれに感銘を受けたと。そして、柳田さんのお化けの話を引用し、こう結んでいる。
「…と、柳田さんははっきり言っています。懐中にあるものとは、言うまでもなく、私達の天与の情(こころ)です。情操教育とは、教育法の一種ではない。人生の真相に添うて行わなければ、凡そ教育というものはないという事を言っている言葉なのです」
灰谷健次郎は教育について、「子供に添う」ということをよく言われていた。教えるという姿勢では、知識は与えられるけれど、知恵は与えられない。
「相手の身に添う」ことではじめて生きたなにものかを共有できる。それは、自らを伸ばす方法でもある。
知恵というのは、教えることで与えることもできなければ、与えられるものでなく、みずからが得るものである。
どうせなら共有しようぜっていうのが、たぶん灰谷さんが言おうとしてたことでもあり、それがこの小林秀雄の人生の真相に添うという言葉にどこかでつながってくるんじゃないのかなとも思う。
2008年01月22日(火)
テンパらないこと、マニュアル
テーマ:心と体テンパらないことの極意は、以外にも、集中することである。
テンパっている心の状態を考えればわかる。
なにかに囚われているからテンパるのだと思ってしまうのだが、実はちがう。テンパる、それは状況に意識を集中していないからである。
浮き足立っていること。それがテンパっていることの実態らしい。
集中すれば、瞬時におのずと何をすべきか判断できるように動物はできている。
野性というのは、テンパらない。キジも鳴かずば撃たれまいというのは、己が発見されそうになってテンパったから鳴いたわけでなく、発見されそうになったヒナから注意をそらすために鳴いたのである。己を犠牲にして。
そういう状況でも、何を一番にすべきかわかっているのが野性というものだ。
そういう追い詰められた状況以外のときに、人であればよい。問題を枠組み化し、作業計画・行動を立てる。マニュアルは必要だから存在する。実態に合わなければ変えていくものがマニュアル。追い詰められたときにも、指針になるようなものが本来のマニュアルのあるべき姿である。だが、そこまで練られたものは本当に数少ない。
追い詰められたときに集中すべきもの、よいマニュアルには、多分、そういうことが書いてあるものなのだろう。キジにとって、自分の命よりヒナの命といったような。
何に集中すべきか、そういう暗示を読む人に与えられないマニュアルは、よいマニュアルとはいえない。
テンパらないためには、集中すること。
「テンぱらないことマニュアル」っていうのがあれば、そういうことが書いてあるかも知れない。
まだ、よくわからないけれど。