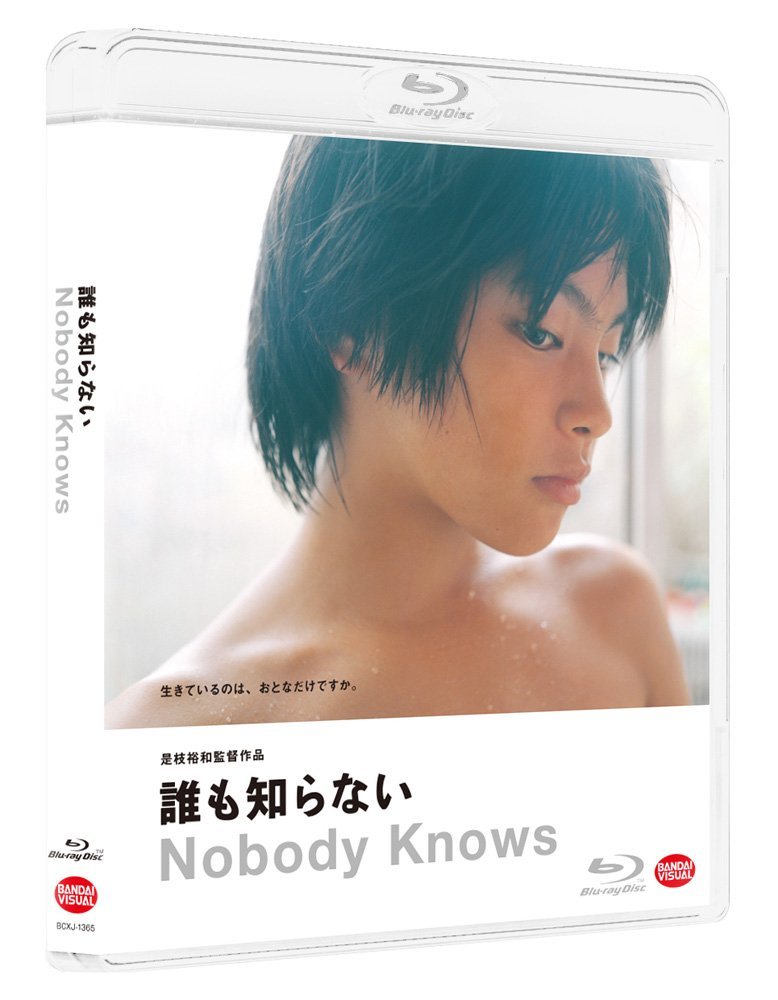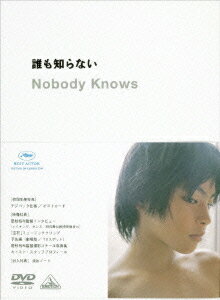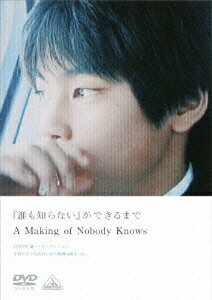誰も知らない
いつも、ありがとうございます(^-^)ノ
こうして映画について書いてるんですが…自分で書いてても、なんだか私は正論に従って映画作品をあれこれ語ったり、社会に対する批判までしてるような感じで、努力して書いてる分、説教くさくなってるように思えてきて、それは本来、私がそうは書きたくなかった感じになってるんじゃないかなあと反省することしきりです![]()
映画は面白ければいいというのがありますが、映画を観て感じたことを書く時、やっぱり人様に読んでいただくものでございますので、正しいか間違ってるかとか、一般的な道徳に照らし合わせてどうだとかも書くんですよね。
しかしそれがお仕着せに型どおりなもので、自分が考えてのものではなかったら読んでいただいても中身がないようなものかもしれません。
私は正直に書くようにしているけど ―― 。
読まれてあんまり傲慢に感じられたら、またコメント欄でご指導くださいまし。
と、自戒の念を確かめつつ ―― 今月6日でしたが、是枝裕和監督の2004年の作品『誰も知らない』を観ました…![]()
※ 映画の内容に触れていますので、知りたくない方はご注意ください。
5歳から12歳までの4人の子どもたち、明、京子、茂、ゆきはそれぞれ父親の違う異父兄妹です。
下の3人は家主に許可を得ずにアパートに住むため、外に出ることもベランダに出ることもできず、4人は学校に通っていません。
長男の明だけが買い物などのために外出を許されています。
母親の福島けい子さんは仕事をしていますが、4人の子どもたちを満足に生活させるためには度を越した節約が必要だったのだろうか。
それでもお母さんが帰ってくると子どもたちは嬉しいし、お母さんと子どもたちの関係は悪くない…ように見えました。
ところがお母さんに恋人ができて、お母さんは自分自身の人生のためにそちらへ行ってしまい、子どもたちは4人だけで暮らしていかなければならなくなります。
最初はある程度まとまったお金が届いたので、明はそれでやりくりして何とか子どもたちだけで暮らしていこうとしますが、お金は届かなくなってしまう。
子どもたちは自力で暮らしていかなければならなくなる。
正直に書きますね。
観る前は観ていて苦しいだけの映画かと思ってたんですが、私には少し違いました。
母親のけい子はいなくなり、子どもたちだけで暮らしているんだけど、最初は痛々しいとか可哀想だとか思いませんでした。
『ロビンソン・クルーソー』や『十五少年漂流記』のようにどうやってサバイバルできるのかというような、一種の不思議な興奮もありました。
一つには私が、虐待や過干渉するような親だったら一緒には暮らさない方がいい場合があると考えているからでしょうね。
あるいは何らかの集団に受け入れてもらえても、いじめやそこでの孤立でもっと苦しくなるかもしれない…と悲観的に考えるからでしょう。
4人の子どもたちの関係はいいようだし、それならできる限り自分たちで暮らしていける可能性があったら嬉しい、と思ってました。
そういった視点もありましたけど、特に長女の京子が母親にもっといてほしいと思っていること、他の3人もそうだということもわかるので、それではどうすればいいだろうと考えてました。
母親のけい子はもちろんネグレクトの罪を犯していますが、しかし映画を観ていて、私はなぜか彼女に怒りを感じなかったし、批判する気にもなれなかった。
それはけい子が子どもたちを怒鳴りつけたり、暴力を振るったりする人ではなかったからかもしれない。
彼女は確かに自分が考えたルールを子どもたちに強いていて、それは確かに世の中では違反なんだけど、彼女の「ズルさ」も生きていくのには必要なものだ。
人間、自分のためには嘘もつく。
けい子は確かに親としてあるまじきことをしたし、いい加減な人だけれど、悪しき親にはまた別の様々な形があり、また虐待をした親たちには親たちで言い分もあるだろう、と思う。
4人の子どもたちを育児放棄したのか![]()
それなら厳罰を![]() という批判は私にはできなかった。
という批判は私にはできなかった。
けい子はまだ少し若く、自分の子どもたちよりも自分の恋愛と自分の人生を優先させてしまったのだ。
もちろんみんなで彼女一人を責めてもいいのだけれど、それで問題が解決していくとは思えない。
映画では描かれないけどけい子はその後ずっと罪の意識に苛まれて生きていくのかもしれない。
それが彼女の懲役刑なのかもしれない。
ただ、映画を観ていて私は、けい子がもしも裕福な男性と結婚して、その男性が4人の子どもたちをとても好きになって、けい子ともども愛してくれたなら、状況は一変するかもしれない、とオプティミスティックに考え続けていた。
それは私が映画や小説などに期待する安心の発生である。
けい子が新しい男性と恋愛し、新しい配偶者を求めたのは間違いだとは言えない。
ハッとするほど優しい気分になったのはコンビニエンスストアで働く女性(タテタカコさん)が明たちを気にかけていることです。
彼女自身、お店では弱者の立場のように見えたけど、それだからこそ人が困っていることを心配できる人なのかもしれない。
困っていない人は困っている人に無頓着なのかもしれないから。
同じコンビニエンスストアで働く男性(加瀬亮さん)が明に賞味期限切れの商品を渡す場面も嬉しかった。
あの優しさを誰もが持っていてほしいと思う。
でも、子どもたちは優しい人たちから助けてもらい、「ほどこし」てもらうだけでいいのだろうか。
今、これを書きつつ、私にはまだこうだという答えが書けない。
映画の中で特に胸がチクチクと傷んだのは ―― 同年代の友達がいなかった明が、ゲームを用意することで友達を得ることはできたんだけど、結局はアパートの部屋が彼らの「たまり場」になってしまい、京子やゆきが居心地悪く感じているし、茂が邪魔者扱いな場面です。
是枝監督は「生(なま)」の感情を思い出させてくれます。
あの状況は京子やゆきにとってはしんどいものだったでしょう。
私は自分の忘れていた記憶を思い出しそうになって、とても苦しかった。
ゲームで友達を作るものいいんだけど、野球に加わった時の明が一番彼らしいのだろう。
この作品は是枝監督が、1988年にあった実際の事件から着想を得て作ったそうです。
その事件を当時、私は知っていたのか…わからないんですが、ひとまず、今は詳しくは調べませんでした。
でもザッと事件の概要を知ると、映画と実際の事件は部分的に違うようです。
その違いは恐ろしいものですが、つまりゆきの死因なのだけど…是枝監督はそれを事件の通りには描けなかったのだろうか。
描くと、子どもの荒っぽさや抑制の効かなさが際立つが、何よりもさらに悲痛な気分になったかもしれない…。
映画の後半は、子どもたちの暮らしがより荒れ果てたものとなり、強い困惑と焦れったさを感じる状況となりますし、明の性格も苛立ちから変化しているようです。
明が出会う少女(韓英恵さん)…彼女はいじめられており、彼女自身、深刻な心持ちだったと思うけど、明たちの部屋に居場所と安らぎを得る。
私は明たち4人とあの少女の交流がとても好きだった。
明にとって恋愛だったのだろうか。
少女は明を助けたいお金のため、いわゆる「パパ活)をするが、明はそのお金を汚らわしいと感じたようだった。
とても悲しいことが起こって、それは取り返しのつかないこと、あまりにも重いことなんだけど、明は彼がすべきだと考えることをします。
その時、付き添うのは少女で、私はとても神聖な気分になった。
それについて何も言いたくはない、というような。
大人たちのいないところで子どもたちだけがああしたからだろうか。
ゆきが乗りたがっていたモノレール。
私は子どもたちの優しい思いは、この宇宙の神聖だと感じた。
もしも弔いがあるのなら、あああるべきだと ―― 。
映画は ―― 母親・けい子が捕まって断罪され、子どもたちにはしかるべく大人たちの救いが向かう ―― という終わり方ではなかった。
映画は ―― 悪人が断罪され、気の毒な被害者たちに救済が待っている ―― そう思ってるのだけど、この映画は違った。
あとは観た私が考えるよう託された ―― ということなのだろうか。
映画を観ていて怒りや憤りを感じなかったかといえば嘘になります。
4人の子どもたちの父親(木村祐一さん、遠藤憲一さん)には、いやもっと、何かしてあげるべきだろ、と怒りを感じてしまった。
でも、思いやりを示せず落胆を与えるなら、子どもたちも彼らと関わることを望まなくなっていくだろう。
よく知らないのに明が商品を盗んだと断じて詰め寄ったコンビニエンスストアの店長さん(平泉成さん)にはもっと憤りを感じてしまった。
子どもたちは時々ああいう経験をするものだし、それは一生忘れられないものだ。
だから真実を語って助けてくれたあの女性を、明はずっと忘れないだろう。
部屋は汚れていったけど、今度はガスや電気や水道が無慈悲に止まったので部屋で料理ができず、また少し片付いていた。
そこが4人の居場所だったんだけど、私は元来、ゴミ屋敷に人々が眉をひそめたりするのが好きではないのだ。
清潔ではない身なりの人を誰かが蔑む時、この世の最も醜いものを感じる。
母親に置き去りにされた4人の兄妹が子どもたちだけで暮らしていく光景は決して醜いものではなかった。
かと言って彼らの生活力を信じられるほどには私も呑気ではなかった。
ただ、母親がいない間に子どもたちが経験したことは絶対に無意味ではない。
できうる限り、親がいない状況でも自分たちで切り抜けられるようになったら、何不自由なく恵まれてるのに口先だけの大人たちの1000倍立派。
世の中には苦しい状況にいる子どもたちが大勢いる。
裕福な家庭で暮らして学校に通っていても地獄のような毎日を送っている子もいる。
今度は「金持ちの子」「ぼんぼん」とわざわざあげつらう日常も決していいものではないし、いじめに悩まされて勉強に集中できないような学校なら行かない方がずっといい。
子どもたちにとって何が正しいのか、どうあるのが正しいのか、そんなこと一概には言えないでしょう。
私はといえば映画を観て…人はなぜ生まれ、苦しみ、いつも心配していて、困っている人に手を差し伸べないのかを考えていた。
自分自身、誰かの役に立っているわけでもないのに…。
映画の中の子どもたちが好きだった。
愛おしくて、彼らが幸せであることを願った。
その幸せの意味すら知らないのに。
映画は忘れそうになっていたことを思い出させてくれる。
私は『誰も知らない』を観て、知らない人たちの今を考えていたくなった。
今日も読んでくださり、ありがとうさんです☆⌒(*^-゜)v
Dare mo shiranai
Nobody Knows
아무도 모른다
中国大陆 無人知曉
香港 誰知赤子心
澳门 誰知赤子心
臺灣 無人知曉的夏日清晨
2004年製作/141分/日本
劇場公開日:2004年8月7日
配給:シネカノン
監督・脚本・編集・プロデューサー 是枝裕和
ゼネラルプロデューサー 重延浩 川城和実
企画 安田匡裕
企画協力 小林栄太朗 李鳳宇
アソシエイトプロデューサー 浦谷年良 河野聡
ラインプロデューサー 田口聖
撮影 山崎裕
録音 弦巻裕
美術 磯見俊裕 三ツ松けいこ
スタイリスト 小林身和子
ヘアメイク 酒井夢月
音響効果 岡瀬晶彦
音楽 ゴンチチ
挿入歌 タテタカコ 「宝石」
助監督 熊谷喜一
キャスティング 新江佳子
スチール 川内倫子
製作担当 白石治
福島明 - 柳楽優弥
福島京子 - 北浦愛
福島ゆき - 清水萌々子
福島茂 - 木村飛影
福島けい子 - YOU
水口紗希 - 韓英恵
広山潤(コンビニの店員) - 加瀬亮
中延司(コンビニの店長) - 平泉成
吉永忠志(大家) - 串田和美
吉永江理子(大家の妻) - 岡元夕紀子
宮嶋さなえ(コンビニの店員) - タテタカコ
杉原博信(タクシーの運転手) - 木村祐一
京橋和孝(パチンコ屋の店員) - 遠藤憲一
井澤真一(少年野球の監督) - 寺島進
村野友希
田中慶太
第57回 カンヌ国際映画祭(2004年)
コンペティション部門 男優賞受賞 柳楽優弥
9月に観た映画
1日 メメント(2000年)
3日 ジュラシック・ワールド 新たなる支配者(2022年) クライモリ デッド・エンド(2007年)
4日 ボストン1947(2023年)
5日 ファーザー(2021年)
6日 誰も知らない(2004年)
9日 憑依(2023年)
10日 ドッグ・ソルジャー(2002年)
11日 ランサム 非公式作戦(2023年) ある用務員(2021年)
13日 ゴジラ キング・オブ・モンスターズ(2019年) 怪物 モンスター(2010年)
14日 10 クローバーフィールド・レーン(2016年) クローバーフィールド・パラドックス(2018年)
15日 ヒルズ・ハブ・アイズ(2006年)
18日 大好きだから(2017年) THE LOST 失われた黒い夏(2005年) ザ・ウーマン(2011年)
19日 スロータージャップ (2017年)
20日 クローバーフィールド HAKAISHA(2008年)
21日 グッドフェローズ(1990年) ゴーストランドの惨劇(2018年) ベオウルフ / 呪われし勇者 ディレクターズ・カット版(2007年)
23日 ハングマンズ・ノット(2017年) ヘレディタリー/継承(2018年)