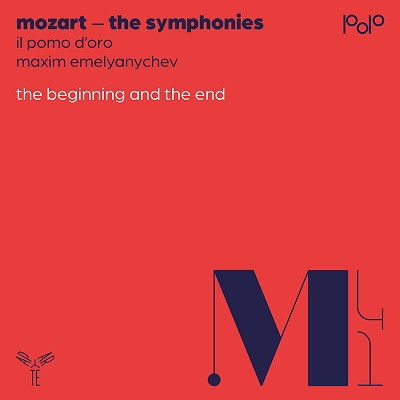Franco Fagioli (Pentaton) 96Khz/24bit

モーツアルトがオペラの中でカストラートによって歌われることを想定した曲を随分と作っていたことをこのアルバムを聴くまで気に留めた事もなかった。
モーツァルトのオペラというと普通は4大オペラということで、ダ・ポンテ三部作のフィガロ、ドンジョバンニ、コジファンテゥッテと魔笛があまりにも有名すぎて他はあったんだっけと思ってしまうくらいだが。。
実際モーツアルトは17ものオペラを完成させている。その作品群の中で配役としてカストラートが歌う場面も普通にあったのだろう。現代では去勢された男性歌手というのはいないでしょう。このアルバムではそのオペラからのアリア。及び宗教作品などを収録してある。
歌うのはトップ・カウンターテナーのフランコ・ファジョーリ。魅力はやはり、女性歌手では難しい男性ならではの豊かな声量とその迫力。
今ではソプラノ歌手によって歌われる華やかで有名な『エクスルターテ・ユビラーテ』にしても、もともとはカストラートを想定して作曲されたものなので、これを聴くとモーツアルトが想定していた『歌』というものは、しなやかで優美というよりも結構力強いものなのだと想像することができる。それにしても、この歌手はなかなか凄い。
演奏もKammerorchester Baselが脇を固めて言うことなし。とても楽しく聴けたアルバムだった。
2023-485