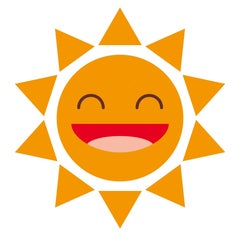『宝探すなゲーム』
【登場人物】1名(不問1)
【ジャンル】ヒューマンドラマ
【上演時間】30分
【あらすじ】
「いいか。よく聞け。私が死んだ後、庭にある桜の樹を絶対に掘り起こすな」
亡くなった父の秘密を暴くため、俺は葬儀の翌日、スコップで桜の樹を掘り起こす。
そこに隠された親父の願いとは……。
【本編】
親父の胃に悪性の腫瘍が見つかったのは会社を辞めて3ヶ月が経った頃だった。
親父は高校を卒業してすぐに地元の小さな工務店に就職した。
馬車馬(ばしゃうま)のように働いて、会社を全国に支店を構えるほどに成長させた。
勇退後、これからの余生をどう過ごすか考えていた矢先の出来事だった。
がんの発覚から入退院を繰り返し、一年が過ぎようとしていた頃、ついに親父は亡くなった。
遺影写真には、ゴルフコンペの写真が使われた。
数人のゴルフ仲間と一緒ににこやかに笑う、親父の元気そうな写真。
「あの人は寂しい頭髪を気にしていたから、この写真なら文句を言わないわね」と帽子を被った親父の遺影を見て母さんは笑っていた。
会社の役員だった親父の葬儀は盛大に行われた。
市長だの議員だの、生前の親父と関わりがあったかもわからない人が大勢訪れた。
喪主を務めた母さんは、その一人一人に深々と頭を下げて言葉を交わしていた。
その隣で俺は、ただ無表情に、母さんに合わせて小さく頭を下げていた。
たまに声をかけられても「ああ、はい」と曖昧に頷くことしか出来なかった。
向けられる冷ややかな視線がチクチクと胸を刺した。
葬儀を終えて出棺。火葬。精進落とし。
全てを終えて家に着く頃、母さんの隣でただ突っ立っていただけなのに、精神的疲労で倒れそうだった。
ぼんやり座り込んで、俺より疲れているはずの母さんが黙々と手荷物を片付けている姿を眺めていた。
出棺の時、母さんは親父の頬に手を添えて静かに泣いていた。
決して仲の良い夫婦ではなかったから、母さんの涙の理由はわからなかった。
いわゆる一つの儀式のようなもので、そこには何の感情も含まれていないのではないか。
そんな風に思えた。
やっと終わった。
これでようやく静かになる。
それに、それなりの額の保険金を貰えるはずだ。
もしかしたら、このまま一生働かなくてもいいかもしれない。
いくら入ってくるのか知らないが、頃合いを見て新しいPCが欲しいと母さんに頼んでみよう。
いや、周辺機器もまとめて買い換えようか。
考えただけで口元が緩むのを抑えきれなかった。
そうと決まればやることは一つ。
俺は疲れている母さんを労るように、「俺がやるよ。母さんは休んでていいから」と玄関に積まれた荷物を片付け始めた。
高校生の頃、俺は将来を期待されたスキー選手だった。
1年の時にインターハイのジャイアントスラロームで準優勝し、オリンピックの強化選手に選ばれた。
初めて海外の大会に参加した時、慣れないゲレンデの状態に戸惑い練習中に転倒した。
俺の選手生命はその時の膝前十字靭帯(ひざまえじゅうじじんたい)の断裂によってあっけなく幕を閉じた。
リハビリを行って日常生活に支障は出ないレベルに回復したものの、膝の状態は完全に元には戻らなかった。
怪我の後、一度だけスキー場に行ったことがある。
緩い傾斜を気楽に滑ることは出来た。
だが、スラロームのトップスピードは高速道路を走る車と変わらない。
一秒でも早く、少しでも前へ。
タイムを短縮させることは刃物を尖らせることに似ていた。
先端を鋭くすればするほど切れ味は増すが、折れやすくなる。
再びそこへ足を踏み入れるのが怖かった。
もう二度と競技の世界には戻りたくなかった。
スキーを辞めてから親父と言い争うことが増えた。
反抗期を拗らせた俺は、親父の言葉になんでも逆らうようになった。
高校卒業後、特に目標もないまま大学に進学。
そこで出会った奴らの影響でアニメやゲームにハマっていった。
虚しくも賑やかな大学生活を終え、見事に就職活動に失敗した俺は、晴れて就職浪人という名の自宅警備員となった。
毎日部屋に閉じこもり、何もせず何も生み出さない日々。
ネットゲームで強くなればなるほど、リアルの俺は弱くなっていった。
「いつまでこんな生活を続けるつもりだ」
大学を卒業後、顔を合わせるたびにそんなことを言っていた親父も、半年が経過する頃には何も言わなくなった。
何かのきっかけで俺が変わるのを気長に待つことにしたらしい。
母さんは変わらずに毎月の小遣いと、毎日の食事を用意してくれた。
ある日、「あなたの将来が心配よ」と愚痴られた。腹が立って「そのうち働くからほっといてくれ!」と怒鳴ってからは、何も言わなくなってしまった。
ただ時々、悲しそうな視線を感じることがあったが、俺はそれに気づかない振りをした。
引きこもり生活が三年目を迎える頃、俺は社会復帰を諦めた。
中学の頃、ライバルだった奴は、国内大会で優勝し、メダル候補と騒がれている。
高校時代、何をやっても俺より下だったアイツは何をしているだろうか。
大学時代、子分のように扱っていた後輩はどこに就職したと言っていたか。
もう俺はそんな奴らにも、誰にも勝てる気がしなかった。
ここからいくら努力をしたところで、何もやってこなかった空白の二年間の差を埋められるとは到底思えなかった。
停滞した二年間じゃない。
後退した二年間だ。
何より、努力をするために必要な情熱を俺は持ちあわせていなかった。
このまま何もせず、誰にも迷惑をかけずに生きていこう。
幸いなことに親父のおかげで家計は貧しくはなかった。
贅沢をしなければ、両親にそれほど迷惑はかからないだろう。
そう高(たか)をくくっていた。
そうして六年。
あっという間だった。
六年間といえば小学校に入学した子供が卒業するまでの長い時間だ。
あれほど色んなことがあった六年間。
それと同じ時間を暗い部屋の中で無為に過ごしてしまった。
親父が退職して家にいる時間が長くなると、出来るだけ顔を合わせないように、深夜に部屋を出て行動することが多くなった。
母さんから親父が入院すると聞いた時は、これでまた過ごしやすくなると思った。
退院する度に、また窮屈になると辟易していた。
親父が入院中、母さんに頼まれ、親父の着替えを持って何度か病室を訪れることがあった。
会う度に痩せ細っていく親父を見て、ただ漠然と、こうやって人は死に向かっていくのかと他人事のように感じていた。
親父と最後に言葉を交わしたのは、親父が亡くなる一週間前だった。
病室のベッドで苦しそうに細い呼吸を繰り返していた親父が小さく俺の名前を呼んだ。
「なんだよ」
口元に耳を寄せると、親父はゆっくりと、まるで大切な秘密を打ち明けるように、こう言った。
「いいか。よく聞け。私が死んだ後、庭にある桜の樹を絶対に掘り起こすな」
どういうことかと尋ねたが、それきり目を閉じてしまった親父は何も答えてはくれなかった。
葬儀の翌朝、俺はその時のことを思い出していた。桜を掘り起こすなと伝えた後の、親父の満足そうな寝顔。
桜か……。
我が家の庭には一本の大きな桜が植えてある。
道路に面した側にあり、春に花が咲き誇る頃は通行人が足を止めるほどの見事な桜だった。
子供の頃、お花見と称して母さんと一緒に桜の樹の下でご飯を食べていたのを、偶然友達に見つかって恥ずかしい思いをしたことがある。
樹齢何年かは知らないが、少なくとも俺が生まれる前からずっとそこにある。
その桜の下に何が埋まっているのか。
母さんにも息子にも知られたくなかった親父の秘密がそこに眠っている。
わざわざ言わなければバレることもなかったのに。
病気になって、判断力が落ちていたとしか思えない。
まさか死体が?
いや、そんな物騒な話ではないだろう。
浮気の証拠。俺の出生の秘密。先祖代々の隠し財産。それとも親父のへそくり。変態な画像が大量に保存されたハードディスク。
そんなわけないか。
俺は好奇心を抑えきれなかった。
母さんが用事で家を出たのを見計らい、俺は納屋からスコップを探しだした。
掘り起こすなと言われれば、掘り起こしたくなるのが人の性(さが)。
親父の言うことなんか聞いてたまるか。
根本近くを三十センチほど掘ると、スコップの先端がカツンと音を立てた。
掘り出すと、それは海苔が入っていた四角い缶だった。
ついに宝箱を発見だ。
缶はサビもなく状態がよかった。
少なくとも埋められてから一年は経っていないように見えた。
意外に軽い。揺さぶるとカタカタと何かが入っている音がした。
何重にも貼られたテープを剥がして蓋を開けた。
中には折りたたまれた紙が入っているジップロックの袋があった。
封を開けて紙を広げた。
「タヌキの置物を動かすな」
たったそれだけ。
親父の手書きの文字。
なんだこれ?
これが死ぬ間際にどうしても隠したかった親父の秘密なのか?
さっぱりわけがわからなかった。
タヌキの置物といえば、あれしかないだろう。
玄関に置かれた信楽焼。
じいちゃんが誰かから貰ったものらしい。
小学生の頃、我が家に遊びに来た友達は、身長一メートル程の大きなタヌキを見て驚いていた。
物心ついた頃からタヌキは玄関にいたので、幼い頃、俺はどの家の玄関にもタヌキがいるのだと思っていた。
俺は玄関に向かいタヌキの置物を慎重に持ち上げた。
その瞬間、不意に懐かしい思い出が蘇った。
俺はこのタヌキを、親父と一緒に持ち上げたことがある。
あれはまだ小学校低学年の頃、親父が作った「宝探しゲーム」をしていた時だ。
家の中に隠された紙を見つけて、その指示に従っていくと隠された宝物を見つけることが出来る。
場所だけではなく、なぞなぞやクロスワードが書かれていることもあった。
誕生日やクリスマス、ことあるごとに親父は俺に宝を探させた。
宝物はゲームの度に違っていて、お菓子だったり、おもちゃだったり、ゴーグルや手袋だったりした。
「タヌキの置物を動かせ」
その時は確かそんな指示だった。
小さな俺がタヌキを抱えて動かそうとした時に、「危ない危ない」と親父が走ってきて手伝ってくれた。
親父が俺の後ろから手を伸ばし、二人でタヌキを持ち上げたのだった。
その時に背中に感じた親父の体温や匂いまで思い出すことが出来た。
置物の底と台座の間に紙が挟まれていた。
拾いあげると、また文字が書いてある。
「納屋にある古時計の蓋を開けるな」
そうか。そういうことか。
ようやく気がついた。
これは親父が俺のために仕掛けた、最後の「宝探しゲーム」だ。
いや、書かれている内容は「宝探しをしろ」ではなく「宝探しをするな」なのだから、「宝探すなゲーム」と言ったところか。
古時計の蓋を開けるなと言うのだから、わざわざ開ける必要もない。
しかし、それでは親父の指示を受け入れたことになる。
それはなんだか癪だった。
親父の言うことなんか聞いてたまるか。
しかし、この「宝探すなゲーム」がどれくらい続くかは知らないが、親父の遊びにつきあってやるのも馬鹿らしい。
親父の指示に逆らって、このまま紙を探し続けても、それこそが親父の思惑通りなのだろうから、どちらを選んでも不愉快だった。
どうせ大した宝でもないだろう。
ここでやめてしまおうか。
一瞬そう思ったか、「桜の樹を絶対に掘り起こすな」と言った時の親父の顔は真剣だった。
このゲームの末に隠された宝物はいったいなんなのか。
それを確かめられるのは俺だけだ。
俺がやらなければ誰にも見つけることは出来ない。
仕方ない。
やめるのはいつでも出来る。
もう少しつきあってやるか。
納屋にある古時計はすぐに見つかった。
ゼンマイ仕掛けの年代物。
俺が幼い頃は居間の柱に掛けられていて、ボーンボーンと寂しい音色を響かせていた。
じいちゃんが生きていた頃、童謡に出てくる大きな古時計とおじいさんは、この時計とじいちゃんのことなのかと思ったこともあった。
時計の背中にある蝶番を開けると、やはりそこにも紙が隠されていた。
「洗面台の下にある草津で買った入浴剤の箱を開けるな」
次は洗面台か。
浴室に移動し、洗面台の下に備えつけられてた棚の扉を開くと、未使用の洗剤や入浴剤が大量に保管されていた。
昔は毎日違った入浴剤を入れて、その色や香りの違いを楽しんでいた。
一番楽しんでいたのは母さんだった。
入浴剤を両手いっぱいに抱えて「今日はどれにしようか?」と笑顔で俺に相談していた。
いつの間にかブームが去ってしまい、大量の入浴剤は使われないまま棚の中で眠っていた。
草津で買った入浴剤……。
おそらくこれだ。家族旅行で草津温泉スキー場に行った時に母さんがホテルの店で買ったもの。
使うタイミングを見計らって、結局使われなかった可哀想な入浴剤。
少し凹んだ箱を開けて、紙を取り出す。
「客間にある右端の額縁を探すな」
右端の額縁……。
客間に移動し、いくつも並んだ額縁の右端を確認する。
飾られていたのは、俺が中学の県大会で優勝した時の賞状だった。
こんなの、いつまでも飾る必要なんてないのに。
額縁の後ろに置かれた丸筒(まるつつ)を開ける。
中を覗いて丸く収められた紙を引っ張りだした。
「玄関に敷かれたマットの裏を見るな」
やれやれ。いったいいつまで続くんだ。
ゲームはまだまだ終わらなかった。
隠された紙を探しだし、また次の紙を探す。
その繰り返し。
紙を見つける度に浮かび上がる家族との思い出。
飽きたら辞めるつもりでいたはずなのに、途中から意地でも宝を見つけてやるという気持ちになった。
「書斎の棚の左下にある青いファイルを見るな」
親父が書斎と呼んでいた親父専用の物置き部屋。
ゴルフバッグや仕事で使っていた道具が所狭しと置かれている。
本棚の左下にはA4サイズで厚さが5センチほどある大きなブルーのファイルが一つだけあった。
背表紙に「①」と書かれていた。
ファイルを開き、俺は息を呑んだ。
小学校の時の「学校だより」が透明のフィルムに挟まれていた。
赤ペンで囲まれた四角の中に俺の名前があった。
学年スキー大会、3年生の部、第1位。
こんなの取ってあったんだ。
俺が初めて1位になった時の学校新聞だ。
嬉しくて何度も両親に自慢した。
スキー大会の前に練習につきあってくれた親父に感謝した。
そうだった。
俺はこの時からスキーに没頭したんだった。
4年生の部、1位。
5年生、1位。
6年生、1位。
6年生の学校だよりには、赤丸の下に親父の文字で「4連覇おめでとう」と書いてあった。
初めて地方新聞に小さく名前が乗った中学のスキー大会。
県大会優勝。市の広報誌に掲載された写真とインタビュー。そして、高校1年のインターハイ準優勝。
それから先は、何もなかった。
こんなにでかいファイル買うことなかったんだ。
①ってなんだよ。②も作るつもりだったのか。
なに勝手に期待してんだよ。
俺にスキーを教えたこと自慢したかっただけだろ。
きっと、会社の飲み会で俺のこと、あることないこと喋ってたんだろ。
ほんの数ページで途切れたスクラップ。
それから先の、大量の空白のページに心が押し潰されそうだった。
めくってもめくっても、何もなかった。
ごめんな。
期待に応えられなくて。
何度も「またスキーやらないのか」って言ってたのに。
根性なくて、情けない息子でごめんな。
最後のページまでめくると、そこに「机の右上の引き出しを開けるな」と書いてあった。
ふらふらと親父の机に向かい、椅子に腰を落とした。
引き出しを開けた。
ビスケットの缶が入っていた。
「これが最後だ。この箱を絶対に開けるな」
黒のマジックで缶に直接書かれた文字を指でなぞる。
病気のくせに。あんなに具合悪そうだったのに、なんでこんなこと……。
俺が部屋に籠もっていた間に、苦しそうな顔をしながら、真剣に「宝探すなゲーム」を作る親父の姿が目に浮かんだ。
紙を探しながら、久し振りに親父と語り合った気がした。
もっと早く。
生きている間に、もっと沢山話しておけばよかった。
これが最後。
親父とのゲームが終わってしまうのが寂しかった。
箱を開けて、折りたたまれた紙を取り出す。
「真面目に働いて、母さんを安心させるな」
バカ野郎。
親父の言うことなんか、絶対に聞くもんか。
おしまい。
【登場人物】1名(不問1)
【ジャンル】ヒューマンドラマ
【上演時間】30分
【あらすじ】
「いいか。よく聞け。私が死んだ後、庭にある桜の樹を絶対に掘り起こすな」
亡くなった父の秘密を暴くため、俺は葬儀の翌日、スコップで桜の樹を掘り起こす。
そこに隠された親父の願いとは……。
【本編】
親父の胃に悪性の腫瘍が見つかったのは会社を辞めて3ヶ月が経った頃だった。
親父は高校を卒業してすぐに地元の小さな工務店に就職した。
馬車馬(ばしゃうま)のように働いて、会社を全国に支店を構えるほどに成長させた。
勇退後、これからの余生をどう過ごすか考えていた矢先の出来事だった。
がんの発覚から入退院を繰り返し、一年が過ぎようとしていた頃、ついに親父は亡くなった。
遺影写真には、ゴルフコンペの写真が使われた。
数人のゴルフ仲間と一緒ににこやかに笑う、親父の元気そうな写真。
「あの人は寂しい頭髪を気にしていたから、この写真なら文句を言わないわね」と帽子を被った親父の遺影を見て母さんは笑っていた。
会社の役員だった親父の葬儀は盛大に行われた。
市長だの議員だの、生前の親父と関わりがあったかもわからない人が大勢訪れた。
喪主を務めた母さんは、その一人一人に深々と頭を下げて言葉を交わしていた。
その隣で俺は、ただ無表情に、母さんに合わせて小さく頭を下げていた。
たまに声をかけられても「ああ、はい」と曖昧に頷くことしか出来なかった。
向けられる冷ややかな視線がチクチクと胸を刺した。
葬儀を終えて出棺。火葬。精進落とし。
全てを終えて家に着く頃、母さんの隣でただ突っ立っていただけなのに、精神的疲労で倒れそうだった。
ぼんやり座り込んで、俺より疲れているはずの母さんが黙々と手荷物を片付けている姿を眺めていた。
出棺の時、母さんは親父の頬に手を添えて静かに泣いていた。
決して仲の良い夫婦ではなかったから、母さんの涙の理由はわからなかった。
いわゆる一つの儀式のようなもので、そこには何の感情も含まれていないのではないか。
そんな風に思えた。
やっと終わった。
これでようやく静かになる。
それに、それなりの額の保険金を貰えるはずだ。
もしかしたら、このまま一生働かなくてもいいかもしれない。
いくら入ってくるのか知らないが、頃合いを見て新しいPCが欲しいと母さんに頼んでみよう。
いや、周辺機器もまとめて買い換えようか。
考えただけで口元が緩むのを抑えきれなかった。
そうと決まればやることは一つ。
俺は疲れている母さんを労るように、「俺がやるよ。母さんは休んでていいから」と玄関に積まれた荷物を片付け始めた。
高校生の頃、俺は将来を期待されたスキー選手だった。
1年の時にインターハイのジャイアントスラロームで準優勝し、オリンピックの強化選手に選ばれた。
初めて海外の大会に参加した時、慣れないゲレンデの状態に戸惑い練習中に転倒した。
俺の選手生命はその時の膝前十字靭帯(ひざまえじゅうじじんたい)の断裂によってあっけなく幕を閉じた。
リハビリを行って日常生活に支障は出ないレベルに回復したものの、膝の状態は完全に元には戻らなかった。
怪我の後、一度だけスキー場に行ったことがある。
緩い傾斜を気楽に滑ることは出来た。
だが、スラロームのトップスピードは高速道路を走る車と変わらない。
一秒でも早く、少しでも前へ。
タイムを短縮させることは刃物を尖らせることに似ていた。
先端を鋭くすればするほど切れ味は増すが、折れやすくなる。
再びそこへ足を踏み入れるのが怖かった。
もう二度と競技の世界には戻りたくなかった。
スキーを辞めてから親父と言い争うことが増えた。
反抗期を拗らせた俺は、親父の言葉になんでも逆らうようになった。
高校卒業後、特に目標もないまま大学に進学。
そこで出会った奴らの影響でアニメやゲームにハマっていった。
虚しくも賑やかな大学生活を終え、見事に就職活動に失敗した俺は、晴れて就職浪人という名の自宅警備員となった。
毎日部屋に閉じこもり、何もせず何も生み出さない日々。
ネットゲームで強くなればなるほど、リアルの俺は弱くなっていった。
「いつまでこんな生活を続けるつもりだ」
大学を卒業後、顔を合わせるたびにそんなことを言っていた親父も、半年が経過する頃には何も言わなくなった。
何かのきっかけで俺が変わるのを気長に待つことにしたらしい。
母さんは変わらずに毎月の小遣いと、毎日の食事を用意してくれた。
ある日、「あなたの将来が心配よ」と愚痴られた。腹が立って「そのうち働くからほっといてくれ!」と怒鳴ってからは、何も言わなくなってしまった。
ただ時々、悲しそうな視線を感じることがあったが、俺はそれに気づかない振りをした。
引きこもり生活が三年目を迎える頃、俺は社会復帰を諦めた。
中学の頃、ライバルだった奴は、国内大会で優勝し、メダル候補と騒がれている。
高校時代、何をやっても俺より下だったアイツは何をしているだろうか。
大学時代、子分のように扱っていた後輩はどこに就職したと言っていたか。
もう俺はそんな奴らにも、誰にも勝てる気がしなかった。
ここからいくら努力をしたところで、何もやってこなかった空白の二年間の差を埋められるとは到底思えなかった。
停滞した二年間じゃない。
後退した二年間だ。
何より、努力をするために必要な情熱を俺は持ちあわせていなかった。
このまま何もせず、誰にも迷惑をかけずに生きていこう。
幸いなことに親父のおかげで家計は貧しくはなかった。
贅沢をしなければ、両親にそれほど迷惑はかからないだろう。
そう高(たか)をくくっていた。
そうして六年。
あっという間だった。
六年間といえば小学校に入学した子供が卒業するまでの長い時間だ。
あれほど色んなことがあった六年間。
それと同じ時間を暗い部屋の中で無為に過ごしてしまった。
親父が退職して家にいる時間が長くなると、出来るだけ顔を合わせないように、深夜に部屋を出て行動することが多くなった。
母さんから親父が入院すると聞いた時は、これでまた過ごしやすくなると思った。
退院する度に、また窮屈になると辟易していた。
親父が入院中、母さんに頼まれ、親父の着替えを持って何度か病室を訪れることがあった。
会う度に痩せ細っていく親父を見て、ただ漠然と、こうやって人は死に向かっていくのかと他人事のように感じていた。
親父と最後に言葉を交わしたのは、親父が亡くなる一週間前だった。
病室のベッドで苦しそうに細い呼吸を繰り返していた親父が小さく俺の名前を呼んだ。
「なんだよ」
口元に耳を寄せると、親父はゆっくりと、まるで大切な秘密を打ち明けるように、こう言った。
「いいか。よく聞け。私が死んだ後、庭にある桜の樹を絶対に掘り起こすな」
どういうことかと尋ねたが、それきり目を閉じてしまった親父は何も答えてはくれなかった。
葬儀の翌朝、俺はその時のことを思い出していた。桜を掘り起こすなと伝えた後の、親父の満足そうな寝顔。
桜か……。
我が家の庭には一本の大きな桜が植えてある。
道路に面した側にあり、春に花が咲き誇る頃は通行人が足を止めるほどの見事な桜だった。
子供の頃、お花見と称して母さんと一緒に桜の樹の下でご飯を食べていたのを、偶然友達に見つかって恥ずかしい思いをしたことがある。
樹齢何年かは知らないが、少なくとも俺が生まれる前からずっとそこにある。
その桜の下に何が埋まっているのか。
母さんにも息子にも知られたくなかった親父の秘密がそこに眠っている。
わざわざ言わなければバレることもなかったのに。
病気になって、判断力が落ちていたとしか思えない。
まさか死体が?
いや、そんな物騒な話ではないだろう。
浮気の証拠。俺の出生の秘密。先祖代々の隠し財産。それとも親父のへそくり。変態な画像が大量に保存されたハードディスク。
そんなわけないか。
俺は好奇心を抑えきれなかった。
母さんが用事で家を出たのを見計らい、俺は納屋からスコップを探しだした。
掘り起こすなと言われれば、掘り起こしたくなるのが人の性(さが)。
親父の言うことなんか聞いてたまるか。
根本近くを三十センチほど掘ると、スコップの先端がカツンと音を立てた。
掘り出すと、それは海苔が入っていた四角い缶だった。
ついに宝箱を発見だ。
缶はサビもなく状態がよかった。
少なくとも埋められてから一年は経っていないように見えた。
意外に軽い。揺さぶるとカタカタと何かが入っている音がした。
何重にも貼られたテープを剥がして蓋を開けた。
中には折りたたまれた紙が入っているジップロックの袋があった。
封を開けて紙を広げた。
「タヌキの置物を動かすな」
たったそれだけ。
親父の手書きの文字。
なんだこれ?
これが死ぬ間際にどうしても隠したかった親父の秘密なのか?
さっぱりわけがわからなかった。
タヌキの置物といえば、あれしかないだろう。
玄関に置かれた信楽焼。
じいちゃんが誰かから貰ったものらしい。
小学生の頃、我が家に遊びに来た友達は、身長一メートル程の大きなタヌキを見て驚いていた。
物心ついた頃からタヌキは玄関にいたので、幼い頃、俺はどの家の玄関にもタヌキがいるのだと思っていた。
俺は玄関に向かいタヌキの置物を慎重に持ち上げた。
その瞬間、不意に懐かしい思い出が蘇った。
俺はこのタヌキを、親父と一緒に持ち上げたことがある。
あれはまだ小学校低学年の頃、親父が作った「宝探しゲーム」をしていた時だ。
家の中に隠された紙を見つけて、その指示に従っていくと隠された宝物を見つけることが出来る。
場所だけではなく、なぞなぞやクロスワードが書かれていることもあった。
誕生日やクリスマス、ことあるごとに親父は俺に宝を探させた。
宝物はゲームの度に違っていて、お菓子だったり、おもちゃだったり、ゴーグルや手袋だったりした。
「タヌキの置物を動かせ」
その時は確かそんな指示だった。
小さな俺がタヌキを抱えて動かそうとした時に、「危ない危ない」と親父が走ってきて手伝ってくれた。
親父が俺の後ろから手を伸ばし、二人でタヌキを持ち上げたのだった。
その時に背中に感じた親父の体温や匂いまで思い出すことが出来た。
置物の底と台座の間に紙が挟まれていた。
拾いあげると、また文字が書いてある。
「納屋にある古時計の蓋を開けるな」
そうか。そういうことか。
ようやく気がついた。
これは親父が俺のために仕掛けた、最後の「宝探しゲーム」だ。
いや、書かれている内容は「宝探しをしろ」ではなく「宝探しをするな」なのだから、「宝探すなゲーム」と言ったところか。
古時計の蓋を開けるなと言うのだから、わざわざ開ける必要もない。
しかし、それでは親父の指示を受け入れたことになる。
それはなんだか癪だった。
親父の言うことなんか聞いてたまるか。
しかし、この「宝探すなゲーム」がどれくらい続くかは知らないが、親父の遊びにつきあってやるのも馬鹿らしい。
親父の指示に逆らって、このまま紙を探し続けても、それこそが親父の思惑通りなのだろうから、どちらを選んでも不愉快だった。
どうせ大した宝でもないだろう。
ここでやめてしまおうか。
一瞬そう思ったか、「桜の樹を絶対に掘り起こすな」と言った時の親父の顔は真剣だった。
このゲームの末に隠された宝物はいったいなんなのか。
それを確かめられるのは俺だけだ。
俺がやらなければ誰にも見つけることは出来ない。
仕方ない。
やめるのはいつでも出来る。
もう少しつきあってやるか。
納屋にある古時計はすぐに見つかった。
ゼンマイ仕掛けの年代物。
俺が幼い頃は居間の柱に掛けられていて、ボーンボーンと寂しい音色を響かせていた。
じいちゃんが生きていた頃、童謡に出てくる大きな古時計とおじいさんは、この時計とじいちゃんのことなのかと思ったこともあった。
時計の背中にある蝶番を開けると、やはりそこにも紙が隠されていた。
「洗面台の下にある草津で買った入浴剤の箱を開けるな」
次は洗面台か。
浴室に移動し、洗面台の下に備えつけられてた棚の扉を開くと、未使用の洗剤や入浴剤が大量に保管されていた。
昔は毎日違った入浴剤を入れて、その色や香りの違いを楽しんでいた。
一番楽しんでいたのは母さんだった。
入浴剤を両手いっぱいに抱えて「今日はどれにしようか?」と笑顔で俺に相談していた。
いつの間にかブームが去ってしまい、大量の入浴剤は使われないまま棚の中で眠っていた。
草津で買った入浴剤……。
おそらくこれだ。家族旅行で草津温泉スキー場に行った時に母さんがホテルの店で買ったもの。
使うタイミングを見計らって、結局使われなかった可哀想な入浴剤。
少し凹んだ箱を開けて、紙を取り出す。
「客間にある右端の額縁を探すな」
右端の額縁……。
客間に移動し、いくつも並んだ額縁の右端を確認する。
飾られていたのは、俺が中学の県大会で優勝した時の賞状だった。
こんなの、いつまでも飾る必要なんてないのに。
額縁の後ろに置かれた丸筒(まるつつ)を開ける。
中を覗いて丸く収められた紙を引っ張りだした。
「玄関に敷かれたマットの裏を見るな」
やれやれ。いったいいつまで続くんだ。
ゲームはまだまだ終わらなかった。
隠された紙を探しだし、また次の紙を探す。
その繰り返し。
紙を見つける度に浮かび上がる家族との思い出。
飽きたら辞めるつもりでいたはずなのに、途中から意地でも宝を見つけてやるという気持ちになった。
「書斎の棚の左下にある青いファイルを見るな」
親父が書斎と呼んでいた親父専用の物置き部屋。
ゴルフバッグや仕事で使っていた道具が所狭しと置かれている。
本棚の左下にはA4サイズで厚さが5センチほどある大きなブルーのファイルが一つだけあった。
背表紙に「①」と書かれていた。
ファイルを開き、俺は息を呑んだ。
小学校の時の「学校だより」が透明のフィルムに挟まれていた。
赤ペンで囲まれた四角の中に俺の名前があった。
学年スキー大会、3年生の部、第1位。
こんなの取ってあったんだ。
俺が初めて1位になった時の学校新聞だ。
嬉しくて何度も両親に自慢した。
スキー大会の前に練習につきあってくれた親父に感謝した。
そうだった。
俺はこの時からスキーに没頭したんだった。
4年生の部、1位。
5年生、1位。
6年生、1位。
6年生の学校だよりには、赤丸の下に親父の文字で「4連覇おめでとう」と書いてあった。
初めて地方新聞に小さく名前が乗った中学のスキー大会。
県大会優勝。市の広報誌に掲載された写真とインタビュー。そして、高校1年のインターハイ準優勝。
それから先は、何もなかった。
こんなにでかいファイル買うことなかったんだ。
①ってなんだよ。②も作るつもりだったのか。
なに勝手に期待してんだよ。
俺にスキーを教えたこと自慢したかっただけだろ。
きっと、会社の飲み会で俺のこと、あることないこと喋ってたんだろ。
ほんの数ページで途切れたスクラップ。
それから先の、大量の空白のページに心が押し潰されそうだった。
めくってもめくっても、何もなかった。
ごめんな。
期待に応えられなくて。
何度も「またスキーやらないのか」って言ってたのに。
根性なくて、情けない息子でごめんな。
最後のページまでめくると、そこに「机の右上の引き出しを開けるな」と書いてあった。
ふらふらと親父の机に向かい、椅子に腰を落とした。
引き出しを開けた。
ビスケットの缶が入っていた。
「これが最後だ。この箱を絶対に開けるな」
黒のマジックで缶に直接書かれた文字を指でなぞる。
病気のくせに。あんなに具合悪そうだったのに、なんでこんなこと……。
俺が部屋に籠もっていた間に、苦しそうな顔をしながら、真剣に「宝探すなゲーム」を作る親父の姿が目に浮かんだ。
紙を探しながら、久し振りに親父と語り合った気がした。
もっと早く。
生きている間に、もっと沢山話しておけばよかった。
これが最後。
親父とのゲームが終わってしまうのが寂しかった。
箱を開けて、折りたたまれた紙を取り出す。
「真面目に働いて、母さんを安心させるな」
バカ野郎。
親父の言うことなんか、絶対に聞くもんか。
おしまい。