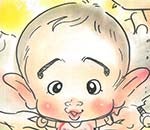「下校中に現れた不審者! その正体!!」からの続きです。⇒
発達障害の経過診断として、2年ぶりに療育でIQ検査をしてもらいました。年長時にはIQ120ちょいでしたが、新小3の時点でのIQは100を下回りました。数値だけ見るなら知能の低下が認められました。IQは相対評価なので、2年間で他の子の方が良く伸びた、とも言い換えられます。
2年前の診断結果はこちらです。
IQは偏差値と同様に、同世代(年月齢が同じ)子供と比べるとどの位置にいるかという指標です。IQ100が平均、一般的にIQ70~130が「普通の子」と定義されています。早生まれであることを考慮するなら、学年単位でならもっと低い値になるでしょうね。それでも一応、知的障害はないとの診断結果でした。発達障害グレーゾーンと呼ばれるカテゴリに区分されます。
2年前にも書きましたが、知的障害を伴わない発達障害グレーゾーンの場合、療育ではトータル指標のIQよりも、凸凹具合の方に注目します。保育園の頃には凸っていた部分が大きく出ていたゆうくんですが、小学生になりの凹の部分が検査結果に大きく表れてきたようです。
心理士の先生からの指導として、「持って生まれた特性(凸凹)は、一生、治らない」というアドバイスがあります。そのため療育では、「我が子の特性をありのまま受け入れて、社会生活で困らないようにトレーニングしていこう」という考え方が基本です。
例えばゆうくんはワーキングメモリに障害があり、「改善は見込めない」と断言されています。無理なトレーニングで何とかしようとするのではなく、メモリ不足を前提としたサポートや対応を考えていくことになります。
※「ワーキングメモリはトレーニングで鍛えられる!」とする説もありますよね。脳機能に障害がない定型発達児(普通のお子様)であれば、そうした訓練が有効であることは否定しません。
■ 同世代の子より凸っていた特性
① 知覚推理(PRI)
・合理的な推理能力は、同世代のお子様より凸っているとの診断結果が出ました。基本的に特性は一生変わらないので、前回と同じ診断結果ではあります。理数系を伸ばしてあげて下さい、との助言でした。
・単純な課題をやらせるよりも、複雑な課題に取り組ませた方が本人のモチベーションは上がるそうです。へー、へー、へー。まあ、「できない自分を受け入れられないので、挑戦から逃げる」という特性もあるので、自分が解けない難題は嫌がるんですけどね! ちょっと背伸びしたぐらいの問題がベストなんですが、1人1人にそうした問題をチョイスしてくれるような個別対応は、集団指導塾だと期待できません。うーん、悩ましい!
・特に「視覚優位」だと指摘ありました。図形問題が得意な訳でもないので、「え? そうなの?」という感じですが、臨床発達心理士の診断なので、きっとそうなのでしょう。
心理士の先生とは視点が異なると思いますが、中学受験の観点で研究されているマスター先生の記事なども参考にしながら、今後の勉強法に意識して取り入れていきたいところです。
② 言語理解(VCI)
・こちらは凸っている訳ではありませんが、年齢相応との診断結果でした。良くはないけど、悪くはないというカンジです。事柄を理解して、合理的に考える能力は問題なし、とのことでした。
■ 同世代の子より凹んでいた特性
① ワーキングメモリ(WMI)
・他の計測値は、平均、平均よりやや上、平均よりやや下、といった検査結果でした。ところが、ワーキングメモリだけは違います。
「境界域を越えて低い」
という診断結果が、明示されています。ええ、まあ、分かってましたよ? 心当たりありまくりよ?
・算数なら、一瞬前に扱った数値を忘れるので、計算式の途中で数字が変わってしまうというケアレスミスが生じます。国語なら、文章読解において本文を読み終わった頃には、本文の前半部分を忘れています。設問に取り掛かるころには記憶がリセットされているので、また本文から読み返しです。
・中学受験において、かなり致命的な特性です。でも、それでも何か対策を考えなければいけません。暗算ではなくメモ算にするとか、印付けを徹底させるとか、工夫はしていますが、結果にはつながっていませんね。
・特に「聴覚劣位」だと指摘されました。音声情報からの記憶を苦手としているそうです。音声で指示された内容を、素早く把握して行動に移すことが出来ません。口頭での指示とセットで、紙にも書いて見せてあげてください、というアドバイスを頂戴しました。
② 処理速度(PSI)
・前回の検査方式は幼児でも受検できる「田中ビネー知能検査」でしたが、今回はもう少し高めの年齢層が対象となる「WISC(ウィスク)」でした。そのため検査結果の項目が若干異なっています。処理速度は同世代のお子様より凹んでいると診断されました。
・複雑な課題と比べて、単純な課題では特に集中力が低下したそうです。単純作業の反復などは不得意で、そうした課題が続くとミスも増えていくとの診断です。あー、はいはい、知ってる、知ってるー。たぶお式とか、国語ドリルとか、すっごい嫌々やっていますからね(汗。パパも単純作業は苦手なので、気持ちは分かります。
・処理速度を落としているもう1つの要因。それは「外部からの指示への反発」「自分なりのこだわりの強さ」です。課題の指示に従わず、自分なりのルールでクリアしようとして、時間を使ってしまう傾向があったそうです。そうなんです。テキストや先生から指示された解法通りには解こうとしないんですよね。中学受験で最重要な特性は「素直さ」だとされています。その「素直さ」が絶望的に欠如しています。
・板書を見て理解する「視覚情報」の扱いは得意だが、板書を書き写す「単純作業」は推奨しないとの助言もありました。
ダメじゃん!! 浜学園の板書主義と、相性最悪じゃん!!!!
まー、その特性も承知しているので、パパ塾100%で代替しているんですけど。療育的には「本人の特性に合わないことを無理強いしてはいけない」で終わりなんですけど、中学受験ではそうも言っていられないのが困ったところです。
③ その他(コミュニケーション能力)
・この辺りは療育を始めた保育園の頃から変わっていません。一生、変わることはないでしょう。発話できないため、ぬいぐるみで代弁させないと検査を受けられなかった状況も前回と同じです。実は人生においては、学業への直接的影響なんかより、はるかに深刻な問題だったりします。
・コミュニケーション能力については、療育を検討すべきか否か悩んでいる親御さんに、強く伝えたいことがあります。追って別記事にまとめます。
療育は特性を治療してくれるものではありません。そして、療育の効果を得られる年齢には、タイムリミットがあります。新小3になったゆうくんにとって、療育の役割は終わりが見えてきました。後はもう、持って生まれた特性を受け入れて、どうやって工夫していくか、です! 人生、配られたカードで勝負するっきゃないのさ!!
⇒「時は待たない! 発達グレーの療育卒業物語(その1)」に続きます。