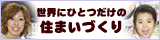大工さんが現場で柱などにカンナをかけている姿。かっこいいですよね。
今は現場でカンナをかけることは少なっており、かける場合でも電動式のモノが使われることが多くなっています。
向こうが透けるぐらい薄く削られたカンナクズは大工さんの腕の証明でもあると思います。
木に鉄製の刃がついたカンナは台鉋(だいがんな)と呼ばれるモノで室町時代ぐらいから使われ始めました。
では室町時代以前にはどんなカンナが使われていたかというと槍鉇(ヤリガンナ)というモノになります。
電動カンナは簡単に綺麗に仕上がりますが、台鉋に比べ表面の艶がないと台鉋を今でも使う大工は言います。
槍鉇は、法隆寺の昭和大修理をした西岡常一氏の元で副棟梁を務めた小川三夫氏は木のもつ艶を損なわないという面で、台鉋より槍鉇の方が格段に優れた道具だと言っています。
AD