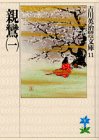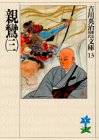ここ最近、白州の話になる事が多く、そんな中、蒸溜所へ赴いたと言う報告をうけ、すっかり白州が気になって仕方なくなってしまった。
どちらかと言うと、インパクトに欠け、どうと言う事もない、そんな印象を初めて飲んできた時から持ち続けていたが、もしかしたらもっと別の顔があるのかもしれないと、どっしりと腰を据えて向き合って見た。
ノーマル白州
色がまず薄い。
匂い
新鮮な香気。軽度の森林浴をしているよう。
口の中でふわっとほのかに感じるのはフルーツとバターのような甘さ。だが、まったりもったりとはしていない。丸くて、それでいて後味のキレが抜群に良い。
シングルモルトは比較的穀物の燻したりした匂いが前面に出てきているが、もっと生っぽい。新緑、若葉、みずみずしさ。
春の若葉を集めて水に浸したらこんな味になるんじゃないかなと思わせる。
白州10年
今年の何月かに生産中止となり、あとは残ってるだけ。
それを知って急いで買ったが、意外とおいてる事が後ほど判明。
匂い
甘みが強く若葉の量が増えている感じ。ノーマル白州が散歩し始めだとしたら、少し緑の深いところに足を踏み入れた感じ。
全体の印象はさほどノーマルと変わらないが、確実に濃さが増してる。
林道の養分になった葉の土臭さが、歩を進めるたび、口に含むたびに立ち上ってくる。
ノーマルよりも林道全体の風景を感じられる。
チーズを食べてしまったのでそのせいかもしれないが、メロンっぽい甘さが加わった。
ノーマルだとやや物足りなさを感じる部分もあるが、10年になるとその物足りなさが洗練と感じるようになった。
余市は練磨、竹鶴は熟達、日本酒だったかお酒の用語で「磨く」と言う工程があったような気がするが、それとは全く別物だが、日本のウイスキーはそれぞれの磨き方に個性があるような気がする。
白州12年
どんどん香りが深くなる。
奥入瀬渓谷の風景が浮かぶ。
森と川。朽ちて倒れている大木に、苔がむし、見上げれば、深く、爽やかな新緑に囲まれている。
けれど、清潔さ、洗練さは変わらない。熟して益々若々しい。
いや、美しさに近いかもしれない。
ウイスキー界の吉永小百合。そんなイメージ。笑。
さて、ここで、残りに水を加えて見る。
ウイスキーを調合?配合?する職人をブレンダーと言うらしいが、彼らは味を見る為に一滴ずつ垂らして飲んでみたりもするらしい。
さらには、ウイスキーの香りが1番開くと言う事で、トワイスアップと言う1:1で割る飲み方もあるそうだ。
加水すると味が薄まると思って基本はストレートで飲むのだが、そう聞いたらやらずにいられない。どう化けるかなと期待しつつ……。
加水しました。
ガラリとまでは行かないけれど、木陰で休んでいたところに日が差し込んできたような感じ。
グラスから立ち上ってくる香りこそ薄くなれど、味わいはまた違った一面。
水をいれた状態で、ノーマル白州のみずみずしさを感じる。
こういう飲み方もやってみないとわからない。
アルコール度数が強い方がウイスキーを飲んでる!!と言う感じがするが、度数が強いだけにすぐに揮発してしまう。もっとゆっくりと味わうにはものによって多少の加水は充分「あり」なんだと思った。
白州なるウイスキーを飲み比べてみて、12年ともなると素直に美味しいと思える。
ここまできてようやく、白州の個性に触れたような気がする。
初めは、個性がないのが個性と思っていたが、そうじゃなかった。
こんなウイスキー他にないと言えるほど個性的。
振り返ってみるとウイスキーの好みは味の好み云々にかかわらず、飲み手の性格が出てるかもしれない。
その辺の話はもう少し語れるようになってからにしよう。
今度はハイボールで飲み比べするのも面白そうだ。少しもったいな気もするが10年、12年のハイボールがどうなるか楽しみだ。
うだるような暑い夜に、キンキンに冷やしたグラスで作るハイボール。
三杯ともなるとかなり時間が必要なので下手をすると夕方からウイスキーと向き合う事になるのかもしれない。
iPhoneからの投稿