漸く、読了。
殆どと言って歴史小説は読まないできたが、大河とはこういうものかと思った。
今までの親鸞のイメージが薄れて行く中、確固たる親鸞像がそこに息衝く。
歴史は流れるが親鸞は流れない。
ただ、岩のごとく、そこにある。
「そこにある」という言葉で思い出すのが、「まはさてあらん」。
臨終だったか、晩年床に伏せている時かは忘れたが、何を思ったか、
「まあ、そんなもんだろう」と呟いたのだ。
そこにある温度は、極めて平坦だ。
苛烈と言えば苛烈な人生を歩み、迫害すらされて、一仏教者として、一つの結論に達した彼をして、人生そんなもんだろうと。
いや、ここで、その呟きが何に向かって吐かれた言葉なのかは不明だが、この小説を読むと、素直に人生で良いのではないかと思う。
この小説では自分が気にしていた親鸞の念義や悪人正機について親鸞の口から語られる事は無かった。
読み始めて、弟の恋人が山賊に攫われるくだりがある。
が、攫われて終わり。親鸞がその山賊に対して抱いたであろう気持ちは語られない。
なんと、薄情なと吉川親鸞に魅力を見出せずにいた。
物語はたんたんと進む。
たまにその山賊が顔を出し、幼少から嫌がらせをして来た人間が憎悪むき出しに親鸞に向かってくる程度だ。
まぁ、親鸞の人生に激動を見出したいとは思わなかったが、主軸となる親鸞の生身に触れている気が全くしなかった。
ここで話は少しずれる。
昨日、一つの出会いが一つの形になった。円環とは言えないが、それでも、形にはなった。
小さな頃に遊んだ番号のついた黒丸を番号順に線をつなげて行くと何らかの絵になるものの様なものだと思う。
ヒントが書かれていて、そこには大好きな人とする事とでも書いてあったのだろう。
当然、大人の私はあたりをつける。
その間、邪魔が入ったり、霞目で次の番号がなかなか見つけられなかったりと、多少の紆余曲折はあったものの、何とか形になって来た。
しかし、何かが違う。
まぁ、それを表現する絵など、多数ある。
番号だけを見て、線だけをつないで行く。
すると最後の方の番号が見当たらない。
探しても見つからない。
未完成。
すると、裏面にいつの間にか書いてあった、同じテーマのものが殆どできかかっている。が、それもまた、いまいちピンとくる様な絵にはならない。
もしかして?と、その紙を日にかざす。
すると、裏と表が重なり合って一つの絵になった。
少しだけキョトンとする。
その絵が望み通りかと言われればそうではないけれど、まぁ、そんなもんだろうと思う。
ここで、改めて親鸞の平熱を考え直す。
仏に帰依するものでありながら、妻帯し、死別したのちに再婚。子も何人かもうけた。
そんな親鸞が平熱であるはずがない。思い返せば、最初の伴侶、玉日の事を思う若き日の親鸞は熱に浮かされていた。
ならば、平熱とはふさわしくない。
恐らく、内在している熱量が高すぎるのではないだろうか。
そのすべてを、人に念仏を伝える事に費やし,
瞬間瞬間で全てを出し切ろうとするような、しかし、それはとても静かで、穏やかな作業だ。
もしかすると、出し切ろうとすらしていないのかもしれない。
今日を精いっぱい生きようとか思っていないのかもしれない。
いや、恐らく思っていないだろう。
全ては仏の御心のままに。
つまりは『他力』
そこには我というものは存在しない。
だから生き死にすらも預けてしまっている。
それゆえの平静。
ならば、内在している熱量の行きどころはどこなのか?
おそらくそれが、親鸞が若い時から悩んでいた事なのだろう。
妻帯することで初めて我を捨てる事が出来たのではないだろうかとすら思える。
一見これは矛盾をはらんでいるように思える。
しかし、そうではない。これは断言できる。
自分ではどうしようもない我を突き通す事で彼は我を捨てたのだ。
禁じられている事、あり得ない事、あってはならない事。
そういった事を超えたからこそ、我が抜け落ちたのだ。
話は戻るが、
会話らしい会話をしたのは去年の事だ。
それからはメール。
そして、メールも尽きて、何がしかが起こり、そして、時間だけが過ぎて行った。
互いに我を突き通す力がなかったと思えない事もない。
突き通そうとして半端に終わり、それはどこにも届かない。
相手は落ちて行くその言葉達を受け止める事も出来ず、ただ、見つめるだけ。
けれど、それはそうでしかなりえなかったし、そういう類の行為だったのだと思う。
だから、我は抜け落ちない。
むしろ、届かない歯がゆさに同じことを繰り返す。
そして、さらに歯がゆさが増し、我が残り、歯がゆさが消え、行為も消えて、我だけが残った。
ここで『なむあみだぶつ』と唱えても、それは何にもならない。
なぜならば、残ってしまってだけいるその『我』の存在理由がないのだから。
吉川親鸞では良く周り、取り巻きの場面が描かれる。
それが自分には不満の一つでもあったのだけれど、
最後の最後でこれが利く。
調子の良い、お定まりの物語。
とある夫婦の物語。
そんなにうまくいくはずがないと鼻で笑うもよし。
その場に居合わせたように、かみしめるもよし。
兎に角、素晴らしい終わり方だった。
終わって初めて、この全三巻に綴られた物語が素晴らしいものだと
わかった。
つまり、親鸞の物語は市井の物語なのだと。
五木寛之の親鸞にも悪役が出てきたが、吉川親鸞の悪人っぷりはしつこかった。
どうせ最後は改心するのだろうと高をくくりながら読んでもなかなかそうはならない。
それにひねくれ者の読者としては、改心しない悪役でいてほしいとも思っていた。
親鸞が凶刃に倒れることは歴史的にない事なので、そういうどきどき感は全くないが、
親鸞の立ち振る舞いには痺れてしまった。
そして、それが腑に落ちる。
書かれない事で親鸞という人物を描きだし、そして、教義を表現したといっても過言ではないだろう。
さて、まだまだ、書き足りないが今日はこの辺で。
せめて、ここ位は『書きたい』という我を通していきます。
iPhoneからの投稿親鸞(一) (吉川英治歴史時代文庫)/講談社
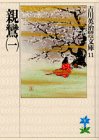
¥777
Amazon.co.jp
親鸞(二) (吉川英治歴史時代文庫)/講談社

¥840
Amazon.co.jp
親鸞(三) (吉川英治歴史時代文庫)/講談社
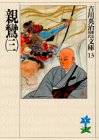
¥777
Amazon.co.jp
殆どと言って歴史小説は読まないできたが、大河とはこういうものかと思った。
今までの親鸞のイメージが薄れて行く中、確固たる親鸞像がそこに息衝く。
歴史は流れるが親鸞は流れない。
ただ、岩のごとく、そこにある。
「そこにある」という言葉で思い出すのが、「まはさてあらん」。
臨終だったか、晩年床に伏せている時かは忘れたが、何を思ったか、
「まあ、そんなもんだろう」と呟いたのだ。
そこにある温度は、極めて平坦だ。
苛烈と言えば苛烈な人生を歩み、迫害すらされて、一仏教者として、一つの結論に達した彼をして、人生そんなもんだろうと。
いや、ここで、その呟きが何に向かって吐かれた言葉なのかは不明だが、この小説を読むと、素直に人生で良いのではないかと思う。
この小説では自分が気にしていた親鸞の念義や悪人正機について親鸞の口から語られる事は無かった。
読み始めて、弟の恋人が山賊に攫われるくだりがある。
が、攫われて終わり。親鸞がその山賊に対して抱いたであろう気持ちは語られない。
なんと、薄情なと吉川親鸞に魅力を見出せずにいた。
物語はたんたんと進む。
たまにその山賊が顔を出し、幼少から嫌がらせをして来た人間が憎悪むき出しに親鸞に向かってくる程度だ。
まぁ、親鸞の人生に激動を見出したいとは思わなかったが、主軸となる親鸞の生身に触れている気が全くしなかった。
ここで話は少しずれる。
昨日、一つの出会いが一つの形になった。円環とは言えないが、それでも、形にはなった。
小さな頃に遊んだ番号のついた黒丸を番号順に線をつなげて行くと何らかの絵になるものの様なものだと思う。
ヒントが書かれていて、そこには大好きな人とする事とでも書いてあったのだろう。
当然、大人の私はあたりをつける。
その間、邪魔が入ったり、霞目で次の番号がなかなか見つけられなかったりと、多少の紆余曲折はあったものの、何とか形になって来た。
しかし、何かが違う。
まぁ、それを表現する絵など、多数ある。
番号だけを見て、線だけをつないで行く。
すると最後の方の番号が見当たらない。
探しても見つからない。
未完成。
すると、裏面にいつの間にか書いてあった、同じテーマのものが殆どできかかっている。が、それもまた、いまいちピンとくる様な絵にはならない。
もしかして?と、その紙を日にかざす。
すると、裏と表が重なり合って一つの絵になった。
少しだけキョトンとする。
その絵が望み通りかと言われればそうではないけれど、まぁ、そんなもんだろうと思う。
ここで、改めて親鸞の平熱を考え直す。
仏に帰依するものでありながら、妻帯し、死別したのちに再婚。子も何人かもうけた。
そんな親鸞が平熱であるはずがない。思い返せば、最初の伴侶、玉日の事を思う若き日の親鸞は熱に浮かされていた。
ならば、平熱とはふさわしくない。
恐らく、内在している熱量が高すぎるのではないだろうか。
そのすべてを、人に念仏を伝える事に費やし,
瞬間瞬間で全てを出し切ろうとするような、しかし、それはとても静かで、穏やかな作業だ。
もしかすると、出し切ろうとすらしていないのかもしれない。
今日を精いっぱい生きようとか思っていないのかもしれない。
いや、恐らく思っていないだろう。
全ては仏の御心のままに。
つまりは『他力』
そこには我というものは存在しない。
だから生き死にすらも預けてしまっている。
それゆえの平静。
ならば、内在している熱量の行きどころはどこなのか?
おそらくそれが、親鸞が若い時から悩んでいた事なのだろう。
妻帯することで初めて我を捨てる事が出来たのではないだろうかとすら思える。
一見これは矛盾をはらんでいるように思える。
しかし、そうではない。これは断言できる。
自分ではどうしようもない我を突き通す事で彼は我を捨てたのだ。
禁じられている事、あり得ない事、あってはならない事。
そういった事を超えたからこそ、我が抜け落ちたのだ。
話は戻るが、
会話らしい会話をしたのは去年の事だ。
それからはメール。
そして、メールも尽きて、何がしかが起こり、そして、時間だけが過ぎて行った。
互いに我を突き通す力がなかったと思えない事もない。
突き通そうとして半端に終わり、それはどこにも届かない。
相手は落ちて行くその言葉達を受け止める事も出来ず、ただ、見つめるだけ。
けれど、それはそうでしかなりえなかったし、そういう類の行為だったのだと思う。
だから、我は抜け落ちない。
むしろ、届かない歯がゆさに同じことを繰り返す。
そして、さらに歯がゆさが増し、我が残り、歯がゆさが消え、行為も消えて、我だけが残った。
ここで『なむあみだぶつ』と唱えても、それは何にもならない。
なぜならば、残ってしまってだけいるその『我』の存在理由がないのだから。
吉川親鸞では良く周り、取り巻きの場面が描かれる。
それが自分には不満の一つでもあったのだけれど、
最後の最後でこれが利く。
調子の良い、お定まりの物語。
とある夫婦の物語。
そんなにうまくいくはずがないと鼻で笑うもよし。
その場に居合わせたように、かみしめるもよし。
兎に角、素晴らしい終わり方だった。
終わって初めて、この全三巻に綴られた物語が素晴らしいものだと
わかった。
つまり、親鸞の物語は市井の物語なのだと。
五木寛之の親鸞にも悪役が出てきたが、吉川親鸞の悪人っぷりはしつこかった。
どうせ最後は改心するのだろうと高をくくりながら読んでもなかなかそうはならない。
それにひねくれ者の読者としては、改心しない悪役でいてほしいとも思っていた。
親鸞が凶刃に倒れることは歴史的にない事なので、そういうどきどき感は全くないが、
親鸞の立ち振る舞いには痺れてしまった。
そして、それが腑に落ちる。
書かれない事で親鸞という人物を描きだし、そして、教義を表現したといっても過言ではないだろう。
さて、まだまだ、書き足りないが今日はこの辺で。
せめて、ここ位は『書きたい』という我を通していきます。
iPhoneからの投稿親鸞(一) (吉川英治歴史時代文庫)/講談社
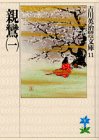
¥777
Amazon.co.jp
親鸞(二) (吉川英治歴史時代文庫)/講談社

¥840
Amazon.co.jp
親鸞(三) (吉川英治歴史時代文庫)/講談社
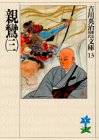
¥777
Amazon.co.jp