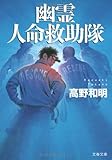昨日は待ちに待った白州デー。
と言っても、決まったのは二日前くらいだったか。
引越し祝いに送った白州のシェリーカスクを開けるからとお呼ばれし、どうせならと揃えられる白州を飲もうと言う事になった。半強制的に。
左からノーマル、12年、10年、そして、主役?のシェリーカスク。
普段、二杯くらいでかなり酔っ払う身としては身も心も引き締めねばなるまいと、約束の時間を押すのを覚悟で整体へ。
マッサージなどにいくとすごく喉が乾く事からはじめの一杯目は白州のハイボール以外考えられなくなっていた。
整体の話は余談になるのでまとめてしまうが、
通りすがりに入った整体で些か怪しい外国人のお姉さんが登場。
まさか、そっち系の整体なのか?と緊張を隠せなかったが、無事強すぎるほどの指圧で次の日は揉み返しで動けなくなるほどだった。
さて、友人の家に着くと、何と無く緊張してしまう。
前日の打ち合わせ?通りピザがそろそろくるらしい。
お腹も空いて、喉もからから。
とりあえず、決めいた通り白州のハイボールを。
ただ、量が多かったので、10年から。
驚いた事にグラスもその日に買ってきたらしく、なんだか、ウイスキー一杯飲むのにとても気を遣わしてしまったと感じるも、その後で、旦那のほうが、今日あるおつまみ何があるか全て教えてくれと妻に問う。
なぜなら、私が後で
それがあったのかぁ!と言わせないようにする為らしい。
そんな事をされたら王様にでもなったように錯覚してしまうのは誰であっても仕方のない事だろう。かくして、先ほどまでの恐縮は何処かへ飛んで行ってしまった。
そうして、傲岸不遜に他人の家で気持ちよく酒が飲めると言うのはなんとも言えない贅沢だ。
やがて、ピザがきて、二杯目のハイボールを飲む。
因みに、どどいたピザは何気に食べた事のないドミノピザだった。
早く飲みたい!と言う気持ちとは裏腹に、ドミノピザってこんな感じなんだーと感慨ぶかげに思案していると、隣ではグラスを空け、ストレートへ突入しようかと言う輩を発見した。
旦那だ。
ペースが自分の1.5倍は早い。
必然的に、眠くなるまでの時間が短くなる。
ここからは、
「倍返しだ」と言わんばかりの鋭い視線を向け、自分もストレートへ。
と言う事で、ここからが本題。
まずは、
ノーマル白州
香り。
爽やか。
この爽やかさと言うのはなかなか他では出会えない爽やかさ。青臭いをちょっとすぎたくらい。
味
白州はストレートで飲むにはパンチが足りなく、ハイボール用として割り切っていたので久々のストレート。
結論から言えば、
軽く扱ってごめんなさい。だ。
確かに、スモーキーでもなく、ウイスキーとして?と確固たる主張もないが、久々に飲むノーマルは全くそんな事はなかった。
むしろ、ウイスキーの新しい個性と言っても過言ではない。
口当たりは優しく、香り高く、若さゆえの爽やかさが際立つ。
自分はスモーカーが故にウイスキーの持つ繊細さに気がつかなかっただけかもしれない。
煙草と合わないウイスキーはウイスキーですらないと思っていた節もある。
が、心地よい空間で飲む白州ノーマルはこれまで感じた事がないほどうまかった。
さて、次に飲むのは白州10年。
終売されていることもあり、これは700mlを購入。
ノーマルよりも12に近く、ノーマルよりもずっと熟している。
香り。
爽やかさが、若干押しのけられ、若さから熟した果実の芳醇な匂いがする。
味
口に含めば、その香りが口いっぱいに拡がり、適度な余韻を持って消えて行く。
若さから来るキレがなくなり、その代わりに丸みがまし、味わいが深くなる。
果実の香りに続いて、穀物の持つもつコクが感じられるようになる。
だからと言って、煙草に合うかと言われれば、そうではなく、あくまで淡さはがあり煙草の煙は邪魔になる。
この淡さが白州のもつ一番の魅力なのかもしれない。
そして、12年。
香りは更に円熟味を増し、旨味がまし、一派的に美味いと評される様なウイスキーの足がかりを感じる。
だが、それは淡さを奥に潜め、ノーマルよりも美味いと言うよりも白州の12年は美味いと言うちょっとした感想の違いを産む。
ただ、ここにきて、香りは爽やかさが濃くなるような気がする。
けれど、味となると話はまったくちがう。
今まで白州だと思っていた部分は個性ではなかったのではないかと思わされるほどに白州らしい。
言い換えれば、今までフォーカスしていた白州の個性は全くの見当違いで、スモーキーさ、樽の香り、年数によって際立ってきた甘さこそが白州だとおもわせるほどそれぞれが際立ち、丸く収まっている。
が、それ故に角が取れしまつまた様な気がして少し寂しい気もする。
そして、本命のシェリーカスク。
ここだけの話だが、本当は自分用にもう一本買おうと思っていた。
が、買わなかった。
それはやはり、買ったら先に飲まない自信は無いし、その年のものを味わってもらい、その感想をまつ楽しみがあるからだ。
この他人の感想と言うのはとても参考になる。
良く語彙が少ないからとか言葉にするのが下手だとか言う人がいるが、如何に伝えられるかが焦点であり、そこに伴う表情や間、仕草全てで伝わればそれは夏目漱石に説明されるよりも参考になる。
私は夏目漱石を知らないが説明しようとしてくれる人物は知っている。
だから、飲みたいは飲みたいが聞きたい方が強いと言えば強いのだ。
今回に当てはめれば、引っ越し祝いのシェリーカスクは小瓶にも拘らずそれを分けてくれると言うだけでもありがたい。
だから、もう飲む前から美味いのだ。
とは、言いながらも、総評としては、
白州ではないと言う結論に落ち着く。
旦那は
マッカランにすごく似ていると言っていたが、私はシェリー樽のマッカランを未だ知らない。
ほうほう。とうなづきながら香りを嗜む。
甘く、その甘さが煮詰められ、重厚になっている。カラメルの焦げた匂いから、強く樽を感じる。
味は白州ではない。
これは断言しても良い。もっと舌が肥えたら撤回するかもしれないが、白州とは別次元のウイスキーだ。一般的に次元の上下で優劣がある様な気もするが、そうではなく、白州と言うブランドに相応しいとは思えないが、間違いなく美味い。
白州と思って飲めば期待を悪い意味で裏切られるが、割り切ってしまえば、こういったウイスキーには出会ったことはなく。12年で感じていた甘さは引き締まり、余韻はスッキリとしている。
渋みの様なものも感じ、赤ワインの様な印象も受ける。
樽が違えばこれだけ味が、風味が違うと言うとてもわかりやすく示してくれた良例と言えるだろう。
と、書いたものの本当に書きたかったのは次のウイスキーだ。
既に全て飲んだ風に書いているが、シェリーの前にサプライズがあった。
白州のシングルカスクだ。
これには本当に驚いた。
料理はたんと用意してもらってたから酒は自分が用意しようと思っていたからこそ驚いた。
なんと、その日に買っていたというのだ。
しかも、シングルカスクを。
あまりこのブログではでてこないが、出てこないからこそそれなりのものだと推し量っていただきたい。
大げさに言えば、
いわば、今までのものを貨幣価値で置き換えれば小銭だったものが、一気に二桁三桁増えたようなものだ。
シングルカスクとシェリーカスクどちらを先に飲むか。
これはいきなり突きつけられた今年一番の難題と言っても過言ではない。
シングルカスクは間違いなく美味い。
シェリーカスクはこの時点ではまだ未知の存在。
当たり前だが、飲めばそれだけ酔う。酔えば味がわからなくなる。
シングルカスクは60度近く、飲めば間違いなく酔いが回る。
が、シェリーカスクは瓶を通しても色が濃い。つまり、味が濃いのでは無いかと思われる。
味が濃ければ後に引き、シングルカスクがわからなくなるかもしれない。
こんな悩みならいつまででも悩んでいたいが、そうもいかない。
飲まねばならぬ。
決めてとなったのは、
美味いものを美味いと味わえる状態で飲みたかったと言う所だろう。
シングルカスクを飲むことにした。
これはもう。美味い。
うますぎてすぐに飲んでしまう。
分析だとか味わいだとか、小賢しいと思ってしまう、理性を飛ばすほど美味いのだ。
勿論、今までのウイスキーが暇つぶしに味を分析しているわけでは無いが、まだ、分析しようとする理性は残る。
だが、美味いからこそ言葉にするのが煩わしい。
この味を体感している今が全てだと、すっかりアル中の様にウイスキーに浸ってしまう。
そうした中、飲まない者がそこにいた。
旦那の妻だ。
ここで彼女は救い。
アル中が言葉に出来ない部分を言葉にしてくれる。
メイプルシロップ。
この言葉がきっかけとなり理性を取り戻す。
そして、被せる様に旦那が、
山崎に似ている。
と、呟く。
ほほー。と感心。
確かに山崎に近くなっている気がする。
いや、なら山崎の方がうまいってことじゃん。となりかねないが、そこはさすがのシングルカスク。
ちゃんと白州として美味い。
果実っぽさ、渋み、それらを自分は、干しぶどうの甘みと香り、そして、梅干しの持つえぐみ、そこから引き出される木の強い香りを感じることができた。
やはり、自分の言葉だけでは正確に表せないものだなと痛感した。
ここに来て、複雑系と言う言葉を思い出す。
精妙にブレンドされたそれぞれのウイスキーにはそれぞれの個性がある。
が、熟成されていくとその円熟味からにている様な印象を受ける。
だが、きっぱりとそれは違うと言える。
言えるが美味すぎて感想がまだ、追いつかない。
1998と言えば、旦那の方と出会った時期に近い。
それだけの年月を重ね、白州はここまで成熟する。
だが、自分はどうだ?と自問した方が今後の為には良いかもしれないが、そうはいかない。
まずはこの酒が美味いのだから。振り返ってる暇などない。
蒸発する前に、飲み切らねば。
こうなってしまうと、誰にも望まれていない使命感が顔を出し、如何に美味く飲むかと言うことしか考えられなくなる。
一口すする度に、巨峰を食べ、口直しをする。
この巨峰が今回のクリティカルだったかもしれない。
何せ、口直しにうってつけなのだ。
甘み酸味、皮のちょっとした渋みが程よく口の中をクリアにしてくれる。
一粒食べた後は味が明瞭になる。
本当に色々つまみを用意してもらったが、そのおかけでどういうものがウイスキーのあてとしてふさわしいか見えてきた気がする。
が、そこも優劣ではなく、程度の問題でしかない。
アーモンドやくるみはどのタイミングでも合うが、一番ではない。
チェイサーもやはり、なければならないがそれはウイスキーの種類によるだろう。
ツウはチェイサーが一番というかもしれないが、そこに落ち着くには世の中には食材が多すぎる。
確かに、チェイサーはトップ3に入るだろうが、後はそのウイスキーとの相性。
チェイサーは喧嘩しない。
が、合うというほどではない。
あくまで、口直し。
だから、一番合うものと飲めば世界が変わる。
生牡蠣とボウモアの様に、奇跡の様な組み合わせがある様な気がしてならない。
今回の巨峰はその可能性を示してくれた有難い例と言って良いだろう。
まだ、25年ものなどは残っているが、殆どの白州は飲んだと言って良いだろう。
しかも、量も結構飲んだ。
が、これほどのみやすく、バラエティ豊かで、万人受けしやすそうなウイスキーも珍しいのでは無いだろうか。
結論から言えば、どれも美味い。
何より煙草と合わせないからこそ美味いウイスキー。
と言いながらも、シングルカスクを思い出して涎が溢れる。
色んな銘柄を楽しむのも変化が顕著で楽しいが、同じ銘柄の年数違いをこうして楽しむことができるというのは、なんとも贅沢極まりない。
恐らく、今年一番の贅沢になるだろう。
なんにせよ、美味い酒を飲む秘訣というのはそういった場も、酒も、人もいなければ成り立たない。
一人飲む酒も好きだが、こういう飲み方ができるというのはとても恵まれている事だろう。
酒は美味い。
けれど、
美味い酒を美味いままに飲める相手と言うのはなかなかいない。
つまりは、かなりわがままな飲み方をしているということなのだろう。笑。
ご馳走様でした。
iPhoneからの投稿