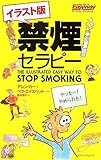ここ60日、禁煙している。
吸いたいかと言われば、Yesですし、
はてまた、
吸わなくても気にならないかと言われてもYesです。
備忘録的にきっかけと自分なりに気が付いたことを書き留めておきます。
まず、きっかけはというと、
・・・・一つには絞れません。
私はタバコが大好きで、数年前の値上がりでやめるやめないと周りが盛り上がる中、全くやめる気も起きませんでした。
多少の値上がりごときでタバコを切り離した生活というものを考えることができなかったし、考えられなくても良いとすら思っていました。
そんな自分が煙草を吸わなくなるようになったことは正直今でも自分が一番驚いていると思います。
何故やめるまでに意志が固まったのかといえば、
小さなひっかかりが積み重なって、うっかりトリガーを引いてしまった。そんな感じで禁煙するようになりました。
その小さな引っ掛かりはというと、
一つに、超ヘビースモーカーだった知り合いが、いつの間にか禁煙してその結果、
タバコを持っていなければならないストレスからの解放は凄いぞ!と言っていたこと。
一つに、ウイスキーを飲む際に最初はつまみとしてのタバコというポジションがありましが、ハイランドやスペイサイドと言った華やかな香りのウイスキーを飲む時にタバコの匂いが邪魔して味わえなかったこと。
一つに一度一年くらい禁煙していた事もあり、いつでもやめられると思っていたところ、やめた人と話している時に一番やめられない人は、いつでもやめられると思っている人と言っていたこと。
一つにタバコをやめると冷え性が治ると聞いたこと。
一つにタバコとコーヒーの組み合わせは最高!と思っていたが、コーヒー単品でも美味しいよと言われたこと。
一つに会社で自殺者が出て以来、10年以上タバコをやめていた社長が吸うようになったこと。
要はストレスで吸ってしまうのは当然だ。でも、自分に少しでも非を感じるなら吸わないことの方が辛いのではないだろうか?と疑問に思ったこと。
そして、トリガーは、
ブックオフでなんとはなしに手に取った、
「禁煙セラピー イラスト版」に軽く、恐らく1、2分でしょう、パラパラと目を通したことです。
当たり前のことすぎて、改めて書くと恥ずかしいのですが、
タバコでストレス解消してるというけれど、吸ってない人は吸わないでもストレス解消できている。
そんな内容がしばらく頭から離れませんでした。
次の日何と無く本数を減らして見ました。
いつもは1時間に一本程度。
それを徐々に吸わない時間を伸ばしていって、吸ったいつかの一本に衝撃を受けました。
初めてタバコを吸った時の様な感覚です。
が、その時よりも血管にハリはなくなり、細胞自体の活動も衰えているからでしょうか、
初めて吸ったときよりも一層、朦朧とし、頭に行くはずの血液が途中で留まり、循環してるように感じられず、ギューっと孫悟空の頭の輪がしまってくるような感じを受けました。
そこで、こんなにも血液の循環を妨げていた、これほど体にストレスを与える行為を習慣的に行っていた自分自身の無茶ぶりに恐ろしくなりました。
とは言うものの、これだけ世間から忌み嫌われているタバコです。
その悪影響が耳に入っていなかったとは言いません。
好きで吸っているから肺がんになるのは自己責任だし、寿命が縮まるという考え方も、人間の死ぬときは決まっている。だから、吸おうが吸うまいが、死ぬ日は同じであると運命論に寄っていました。
だから、いまさらタバコがもたらす悪影響を実感したところで、
吸った時のふわーっとする感覚をやめたいと思うまでには行きません。
こんな体験はタバコでしか得られない感覚です。
けれど、ふと、
『好きだ好きだというけれど、この感覚のどこがどのくらい好きなんだろう』と思うようになりました。
冷静に考えると美味しさもあるし、くつろいだ感じもするし、コーヒーと一緒だと美味しいけれど、焼いた葉っぱを吸って体を汚して、無ければイライラしてしまうタバコから得られるものってたいしたことないんじゃないだろうか?と思うようにもなりました。
とはいっても、何かあるごとに吸いたくはなります。
そして、吸います。
そして、上記の質問、『タバコを吸っている理由はなんだろう?』と吸う度に自問するようになりました。
減煙し始めてから、最初の休みにブックオフで禁煙セラピーを購入しました。
本当はイラスト版が欲しかったのですが、どこにも置いてませんでした。仕方なく買ったのは、通常版のものです。
読んでみると、
いきなり、本を読みながら吸って良い。と書いてありました。
(この時、フライングして減煙していた事をほんの少しだけ後悔しました。笑。)
そして、
読み終わった後に吸いたくなくなってるはず。
と書いてありました。
また、吸いたい気持ちはそれ程長続きしない。少し我慢してみるみたいなことも書いてありました。
いやいや、こんな風に何となく抜き出すと分かりにくいので要約してしまえば、
喫煙者のタバコを吸う理由は幻影だ。突き詰めて考えて行くと、いかに考えなしに吸っているかがわかる。
わざわざ中毒になって、お金を消費して、体を悪くして、ストレスも解消できていないものを吸うとは如何に?
著者は超が何個も付くほどのヘビースモーカーだったそうです。
そんな彼がやめたし、誰にでも出来る方法だと豪語する。
ならば、私は本を読み、読み終えたころ、吸いたくなくなっているからきっと禁煙はつらくないだろう。と思ってましたし、
そんなにやめたい!何が何でもやめよう!とは思っていませんでした。
ただ、タバコを吸わない日が長くなるという感じに近いです。その感覚は今でも同じです。
まぁ、この体でタバコの煙を吸いこみ、ニコチンにどっぷりつかり、いつの日か吸ってしまうかもしれないことを考えるとこれから先、一生禁煙しているとしか言えないのかもしれません。
やめるに当たり、懸念があります。
タバコをやめるとイライラします。
落ち着かず、些細な事に反応してしまう。
結果周りに予期せずあたってしまうような事があるのではないかと心配になってしまいます。
以前勤めていた会社の上司も突然禁煙し、毎日イライラしていました。
たちが悪いことに、イライラしていることを認めないので、回りとしても対処のしようがありませんでした。
禁煙している時ほど、タバコについて考えているときは無いように思えます。
吸いたくなったから考える、考えるから吸いたくなる。でも吸えない。そしてストレスになる。
結果、根性で1週間。その後は自分との戦い。そして、一本くらいならいいかと周りの人間から貰って、貰う本数が増え、貰いっぱなしじゃ悪いからと一箱だけ購入し、結果もとに戻ってしまいました。
そんな姿を見ていたものですから、周りにあたるようになるのは避けたいな。避けたいがために吸ってしまうことはやめよう。と思っていました。
それにはタバコのことを考えないかタバコのことを真正面から考えるのがいいと思いました。
タバコのことを考えないようにするといつの間にか吸いたかった気持ちを忘れてしまうこともありましたし、タバコのこと、悪影響だとか、ここで吸わなきゃ二日やめているとか、美味しいけれどそうでもないよなとか等を考えているといつの間にか波が去っていきました。
それでもダメな時は吸い。
次はもう少しだけ間隔を空けようとか、
今でも、タバコの匂いを嗅ぐと吸いたくなることもありますが、でも、吸ったところで何も変わらないし、また頭が締め付けられるだけだと思うと吸いたくなくなります。
さて、
本格的にタバコをやめてから、自分が吸っているタバコの新作が出ました。
うわっ!これは吸いたい!!
なんか、かっこいいし、どんな味がするんだろう!!気になるなぁ。
…まぁ、吸いたくて吸いたくて死んじゃう!って思ったら吸えばいいか。
そんな感じにタバコを吸いたくなった時には吸ったらどうなるか?なんで吸いたいのか?どのくらい吸いたいのか?を考えるようになりました。
私はこれまでタバコが大好きで大好きで吸っていた。
そう思っていましたが、実はそうではなく、暇つぶしに吸っていた感が強いことに気がつきました。
だから、ふとバルコニーを見たときに柔らかな日が差し込んでいたりすると、タバコを吸ってみたくなります。
待ち合わせに早めに着いて、ふと持て余した時間にタバコを吸いたくなることがあります。
寒い日は煙と吐く息の白さが混ざり合い真っ白くてやわらかい煙が吐き出せます。
吸ってない人にはぴんと来ないかもしれませんが、こんなどうしようもない造形がほんの少し楽しかったりします。こうして書いてしまうとなんともくだらないと思います。笑。
そんな時は毎回、
おおー!こういう時に吸いたいんだ!!と気がついていなかった自分の時間の過ごし方に驚いたりします。
タバコをやめて良かったかというと際立ってよかったことはあまり無いような気がします。
まあ、悪くない程度。
でも、確かにたばこを持っていなくても気にならなくなったことと喫煙席を探し周らなくてもよくなったので、どんな喫茶店でも気兼ねなく入れるようになりました。
体感的に、月二万位は浮くし、使える時間も長くなった気がします。
単純計算すると大体月に一日分の時間は浮いた計算になります。
これも趣味として考えれば一日くらいの時間はとって当たり前でしょうし、無駄なものと見てしまえば貴重な一日を浪費していたと考えられるでしょう。
私自身、まだまだ、いつ吸ってしまうかはわかりませんが、今のところ吸わなければならないような事は起こっていませんし、きっとそうそう吸わなければ乗り越えられないようなことは起こらないと思っています。
長かったタバコ人生を振り返ると、周りには意外とタバコをやめたいけれどやめられないという人は多い気がします。
それはきっと自分に合ったやめ方に出会っていないからだと思います。
正しい知識をもって正しく対処すれば、それほどの苦も無くやめられます。
外来に行ってやめられる人もいれば、こうして本を読んでやめられることもある。
何もなしに自分の意志だけでやめてしまう意志の強い人間もいることでしょう。
私などは意志も弱く頭も悪いしだらしない。一貫しない論理などざらだし、根性も努力も嫌い…というか、持ち合わせていない。
一般的に本当に駄目な大人だと思っています。
けれど、だからこそ、私がやめられるのならきっと誰でもやめられると思っている。
もしも禁煙しようという人がここにたどり着いたら、一言言いたい。
絶対にやめられます!と。
後ほど参考にしたサイトと本を上げることにします。
【追記】
まずは禁煙セラピー
読むだけで絶対やめられる禁煙セラピー [セラピーシリーズ] (ムックセレクト)/ロングセラーズ

¥945
Amazon.co.jp
そしてイラスト版
禁煙セラピー イラスト版 [セラピーシリーズ] (ムックの本 820)/ロングセラーズ
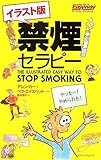
¥950
Amazon.co.jp
そして、仕事の合間(!?)に見ていたのが
禁煙先生のブログ。
http://blogs.yahoo.co.jp/kusamac99
書いてある事はほぼ禁煙セラピーと同じです。
吸いたくなったり、吸っちゃおっかなと思ったり、タバコを吸う言い訳を
し始めた時に開いてました。
あと、禁煙セラピーでは減煙も代替品のガムなども進めていません。
減煙は根本的な解決ではないし、代替品も口が寂しいというのをごまかしているだけなので、
口が寂しいという感覚はそのまま残ってまうからです。
しかし、自分は読む前から減煙し、ガムやら強烈ミントのタブレットやらを買い込んで口寂しさに備えてました。
けれど、減煙は減煙でニコチンの悪影響を実感できましたし、ガムも思ったほど食べませんでした。けれど、濃い目のコーヒーは良く飲むようになりましたが、それも今では普通のコーヒーに戻りました。
タバコを吸わなくなって、何かなくしたものがあるのか?
何もありません。
今年は色々と整理していきたいと思っているので、
灰皿もライターもいらない生活は少し自由になれた気がします。
あ、それから、アプリで評判の良さそうなものが一つ。
禁煙ヨーガ呼吸というアプリです。まぁ、本ですね。
外来にかかるよりもずっと安いし、普段ヨーガをしていることからも興味があって購入してみました。
で、実際やってみたらいい感じでした。
ただ、自分がやったのは一日だけ。
こういう呼吸って結構真剣にやらないといけない気がして、
そうすると落ち着いて出来る場所というのがほとんどないんです。
だから、そのままこのアプリは使わなくなりました。
タバコを吸いたくなったら、数分呼吸をする為に場所を移動し、何しているのか訝しがられないところで静かに呼吸できる人、もしくは上手に立ち回れる人にはいいかも知れません。