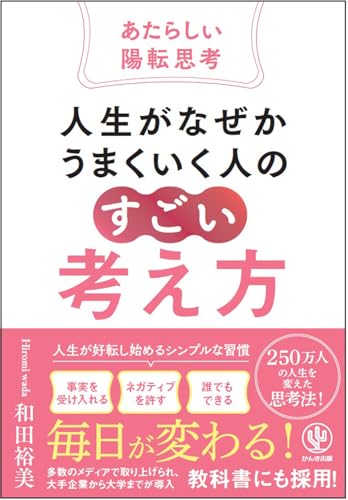先日、60代の患者様が来られました。
「転んだのがショックで……」とおっしゃるのです。
外傷もなく、検査でも異常はありません。
けれど、その方にとって“転んだ”という出来事が心に大きな衝撃を残していたのです。
しかも、それはもう1か月も前のこと。
何がショックだったのか?
詳しく伺ってみると、
何もないところで転んだこと、
つまり、つまずくような段差もなく、自分の足がもつれて転んだことがショックだったと言います。
「筋力が衰えたのだ」
「年をとったのだ」
「もう使い物にならないのかもしれない」
そんな思いが一瞬で心をよぎったそうです。
「老い」への恐怖
けれど、何もないところで転ぶことは、若い人にもよくあること。
老いたからといって、人生が終わるわけではありません。
今も現役で働いている方はたくさんいます。
それでも、人は“老いること”に、どこか恐れを抱くものです。
仏教の言葉に「生老病死(しょうろうびょうし)」という言葉があります。
生まれた者は、必ず老い、病を得て、いずれ死を迎える。
これは誰もが避けて通れない道です。
「老い」は終わりではなく、成熟の始まり
人生100年時代。
それは“老いている時間”が長くなったということでもあります。
だからこそ、心も身体も元気でいることが大切です。
確かに、老いることで体力は落ち、 耳は聞こえにくくなり、目も見えづらくなり、歩ける距離も短くなるかもしれません。
それでも、 心まで老いる必要はありません。
人生の経験を通して得た知恵や、 人の痛みに寄り添える優しさは、若い頃には持てなかった宝物です。
老いの時間を「豊かさ」に変える
老いとは、終わりではなく、成熟の始まり。
自分の内側を見つめ、感謝を育て、次の世代へと教えを伝える時間です。
転ぶことも、時には気づきのサイン。
「これからどう生きたいか」を考えるきっかけになります。
私も、老いを恐れるのではなく、 心豊かに年を重ねていきたい。
そして次の世代へ、健康と生きる知恵を伝えていきたいと思います。