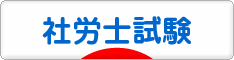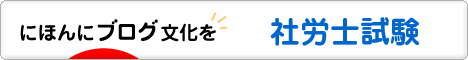
↑私の99%は、皆さまの愛と応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>
本試験で直接問われないことであっても、「一体どういうことなのか?」と疑問を抱えたまま、どうにもスッキリしない規定ってありますよね?
そこで今日から不定期で、多くの方が疑問に思う規定について、制度趣旨なども踏まえてできるだけ分かりやすく解説を行ってみたいと思います。
なお、科目、規定も順不同となりますし、中には「私なりの解釈」であって、立法時の背景とは多少異なる部分もあるかもしれませんが、学習上のボトルネックの解消に役立つことができれば幸いです。
第1回は、健康保険法の「特例退職被保険者」です。
・
・
・
この制度は、主に「法附則3条(特定健康保険組合)」に規定されています。
条文を一部抜粋しますと、「厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(以下この条において「特定健康保険組合」という。)の組合員である被保険者であった者であって、改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「特例退職被保険者」という。)となることができる。」とあります。
最も疑問に感じるのは、「特例退職被保険者と、国民健康保険法の退職被保険者とはどのような関係があるのか?」という点ではないでしょうか?中には、この「特例退職被保険者」を、国民健康保険の被保険者であると勘違いしている方もいらっしゃるかもしれませんね。
結論から申しますと、特定健康保険組合とは、「自前で」退職者医療制度を行うことができる健康保険組合のことであり、この被保険者を「特例退職被保険者」というのです。
先ず、「特例退職被保険者」は、あくまでも健康保険(特定健康保険組合)の被保険者である点を押さえましょう。つまり、国民健康保険の被保険者ではないのです。
次に、「国民健康保険の退職被保険者」を押さえましょう。一般的に、適用事業所を退職すると、「市町村が運営する国民健康保険(以下、「市町村国保」といいます)」の被保険者となります。しかし、定年等により高齢期になってから企業を退職した者が、大量に市町村国保の被保険者となると、「市町村国保の財政が悪化」することになります。理由は、非常に心苦しい言い方になりますが、一般的に、これらの方は保険料(税)収入は少ないが給付の機会は多いためです。
そして、企業を退職した市町村国保の被保険者のうち、老齢又は退職の支給事由とする年金給付の受給権者であるなど、一定の要件を満たした者を「退職被保険者」といいます。また、このような「退職被保険者」に係る市町村国保の医療費を、各保険者が拠出金(退職者給付拠出金)という形で支えるのが国民健康保険の「退職者医療制度」なのです。
しかし、一方で、財政状態が優良な一定の組合については、「自前で」退職者医療制度を行うことが認められているのです。このような健康保険組合を、「特定健康保険組合」といいます。そして、特定健康保険組合が行う退職者医療制度の被保険者を「特例退職被保険者」といいます。
つまり、①市町村国保の退職被保険者に係る医療費を「拠出金」という形で支えるのが「国民健康保険の退職者医療制度」であり、②退職OB対して、「自前で」退職者医療制度を行うのが「特定健康保険組合(特例退職被保険者)」ということになります。
なお、最後に、①「国民健康保険の退職者医療制度」は65歳未満の者に限られますが、「特例退職被保険者」については特に年齢制限はない(=後期高齢者医療の被保険者となるまで)、②国民健康保険の退職者医療制度は、「平成26年度末」をもって廃止される点を付け加えておきます(廃止される理由は、現在では、前期高齢者に係る財政調整の仕組みがあるからです。)。
なお、本試験では、このような「背景や制度趣旨」は問われません。特例退職被保険者となるための要件や届出、資格の得喪などが問われる点にご注意ください。
#反響があれば、このテーマを継続したいと思います。
#応援クリックもよろしくお願いします<(_ _)>
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成23年度 雇用保険法 第1問E>
個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労災保険法第34条第1項の規定に基づき労災保険に特別加入した中小事業の事業主は、雇用保険についても被保険者となる。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労災保険法第34条第1項の規定に基づき労災保険に特別加入した中小事業の事業主は、雇用保険についても被保険者となる。
個人事業主や法人の代表者は、労災保険に特別加入した場合であっても、雇用保険の被保険者とはなりません。
なお、これに対して、代表者等ではない取締役や役員であって、工場長や支店長など従業員の身分を有し、労働の対償として賃金が支払われている者は被保険者となります。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
択一式試験で点数を伸ばすコツ(目次)はコチラ!
ご質問方法の詳細はコチラ!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆