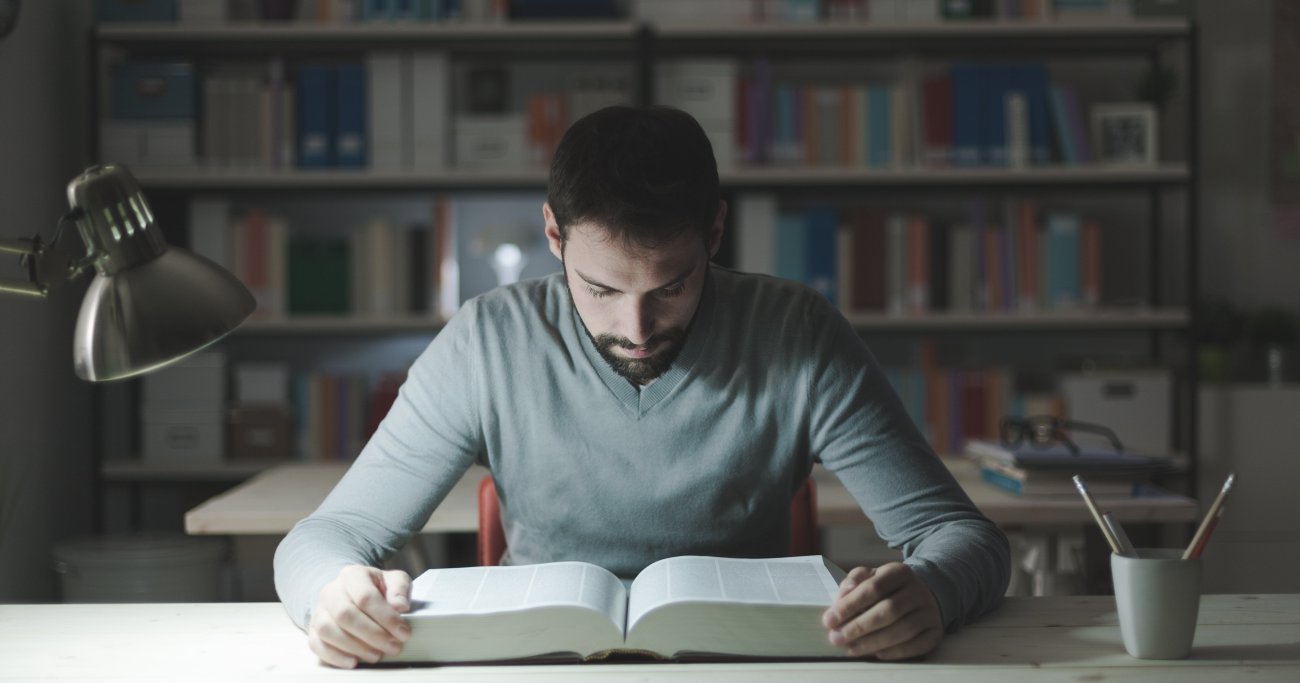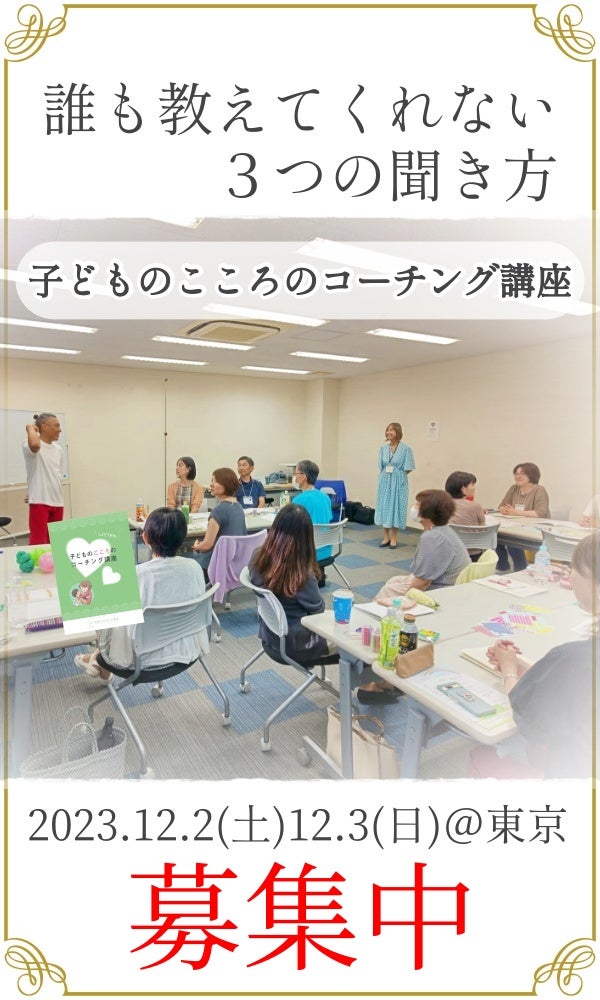こんにちは、18年生ベテラン学童保育支援員さとさんです。
宿題に関する悩み事もありますよね?
・そもそも宿題をさせた方がいいの?
・宿題をすると遊ぶ時間も無くなってしまう
・宿題が全然終わらない子どもがいます
・宿題をさせてほしいと保護者から要望がある
さとさんは、宿題をさせる児童クラブと宿題は親子で「する・しない」を決めてもらう児童クラブと両方経験しています。
どちらでもいいかなって考えています。
重要なのは、保護者さんと共通理解を持てているか。
児童クラブを訪問する中で、「させている」「保護者に任す」と両方ありました。
ちょっと、視点を変えてみるね。
親子の1日の生活
朝、学校に行って一日の大半を過ごします。下校して児童クラブに来ます。
普段だと早くて15時、遅い子どもは16時半以降に児童クラブに来ることもあります。
だいたい17時半前後にお迎えのピーク。地域差があると思います。
そこから、買い物をして、帰って、ご飯作って、お風呂に入れて、ゲームやyoutube見て寝る。
割と寝るのが遅くなりがちなのも、児童クラブの子どもたちの傾向かなと思っています。
お母さん・お父さんも仕事終わってから、寝るまでの時間帯は忙しい。特にお母さんかな。
この忙しい時間帯に、「宿題をさせる」はかなりの難関なはずです。
特に、宿題がうまく進まない子どもは大変。
泣きながらやっているという話も聞いたりしませんか?
親子ともにストレスがかかる。
だったら、児童クラブで宿題ができちゃった方がよさそうな気がします。
宿題をさせる技術
児童クラブ支援員は教員ではないので、勉強を教えることは基本できません。
宿題に付き合ってあげることはできます。親の立場と変わりはありません。
そこで、さとさんからの提案。
宿題の時間もコミュケーションの時間と捉える。
宿題をして帰れば、保護者は安心。
宿題が終われば、次の日学校に行く子どもも安心。
学校に宿題という制度があるので、宿題をしなきゃいけない。個人的には宿題必要か?っては思ってるんだけどね。
じゃ、宿題に付き添う・寄り添うことで、子どもとの信頼関係を作っていけばいいじゃないか!
さとさんは考えます。
こんな記事もあるので、参考までに。
なぜ、宿題が進まないかを整理してみましょう。
1.読んでない
2.分からない
3.遊びたい
長年宿題に付き合うと、だいたいつまづくポイントは同じ。例えば…「位」「割り算」「文章題」「国語の長い文章を読む問題」とかね。
宿題ができる子は、放っておいても宿題をするので、あまり気にしなくてもいいでしょう。
問題を読ませる
「わからーん」と持ってくる子どもに、「問題読んで」と読ませると、半分以上解けたりします(笑)
問題読んでない問題
読むのが苦手な子、ひらがな・漢字が読めない子は、指や棒で文字を追ったり、物差しで読むところをあてたり、一文字ずつ読み方を伝えたりして、とにかく問題を読むことをしてもらう。
問題が読めるようになったら(…って、児童クラブに在籍している間くらいの長いスパンで…)ほとんど、解決と言っていいくらいです。
躓きポイントは?
それでも分からない場合でも、まずは一人でやらせてみます。
で、どこでつまづいているかを観察します。
色々ありますね。そもそも、文字を読むのが大変な子もいます。問題の量にやられている子も。
そのつまづいているポイントを確認出来たら、それを解決する手立てを考えます。
文章ではイメージしにくい部分を実際のものとか状況を使って説明します。登場人物を、その子の名前にして読むのも、意外と効果あります。
1年生の足し算引き算なら、そろばん使ったりもしてますよ。
オセロとか使うこともあるかな。
どうしても理解できない場合は、無理に解かせる必要はなくて、「学校の先生に、もう一度教えてもらってね。」とできない問題を残すこともします。
なかには答えを見てやっている子もいますよ。
ちなみにこんな記事もある。
まずはやってみて分からない時は、答えや教科書を見て書いてもいいと思っています。
漢字は辞書調べたらいいしね。
こんなポスターも使ってます。プラ段ボールに貼り付けて、いつでも出せるようにしてますよ。
遊びたい問題
周りが気になって宿題が進まないとか、遊びたくてイライラしてしまっている子もいますよね。
一人になった方が落ち着く場合は、できる限りその環境を用意します。横に座って、一緒に取り組むだけでも進む場合もあります。
宿題をやらないと遊べません。
という言い方はやめてあげましょう。
宿題して、遊ぼうよ。
と、肯定的に伝えてあげてくださいね。ただでさえ、イライラソワソワしているのに、否定的な伝え方をすると火に油です。
量が多くてキャパを超えていると判断できる場合は、全部するのではなく、「ここまでしようか」と区切ることもあります。家でやる部分を残すことになりますね。保護者さんに伝える場合もあります。
できたところは「がんばったね」と伝えて、できたことを承認します。
それから、皆でやるという時間なら、ある程度「場」の力が発生して、宿題をしやすくなる子もいます。
一人でするより、皆でやった方がいいこともあるもんね。
で、さとさん的重要ポイント
宿題も楽しむ
宿題ができない子は、宿題が苦痛でたまらない。
そんな時、宿題はきちんと座ってやりなさい!なんて、怒ってませんか?
必要ないから大丈夫。
座れずにソワソワしながらでも、宿題に取り組んでいるんだったら、「頑張ってるね」と声をかけてあげてね。
机に突っ伏して今にも溶けそうになっていたら、「溶けちゃってるじゃん!」とツッコミ入れてあげてください。
「めんどくさーい」と叫んでいる子がいたら、「めんでけくせー」と一緒に叫びましょう。
支援員全員で厳しく指導する必要はなくて、注意する支援員もいれば、子どもに寄り添う支援員もいていいし、多少ふざけても宿題が進むのなら楽しくやってもいい。
さとさんは横で一緒に勉強したり、時にはウクレレの練習したりしています。
面白いワードを見つけたら、あえて言ったりします。
漢字ドリルの文章を並べて読むと、壮大な世界観になったりして笑えるんですよ。
仲のいい子どもたちの宿題を見ていると、学校であったことを話しながら、時にはふざけ合いながら、笑ってやっている。
それでいいんです。
ある程度のかじ取り(宿題をする)だけ支援員が担って、子どもと宿題も楽しめるのなら、それは子どもとのコミュケーションです。
苦痛な時間で覚えるより、楽しい時間で覚えた方が効率がいい。
そして、これが重要。
10分でも遊べるのなら、遊びます。
そして、宿題のサポートの仕方はこの本が最高です。
お疲れ様です。 学童保育生活向上研究所SAT所長のさとさんです。
【登録無料のメルマガ】
【お役立ちまとめ記事】