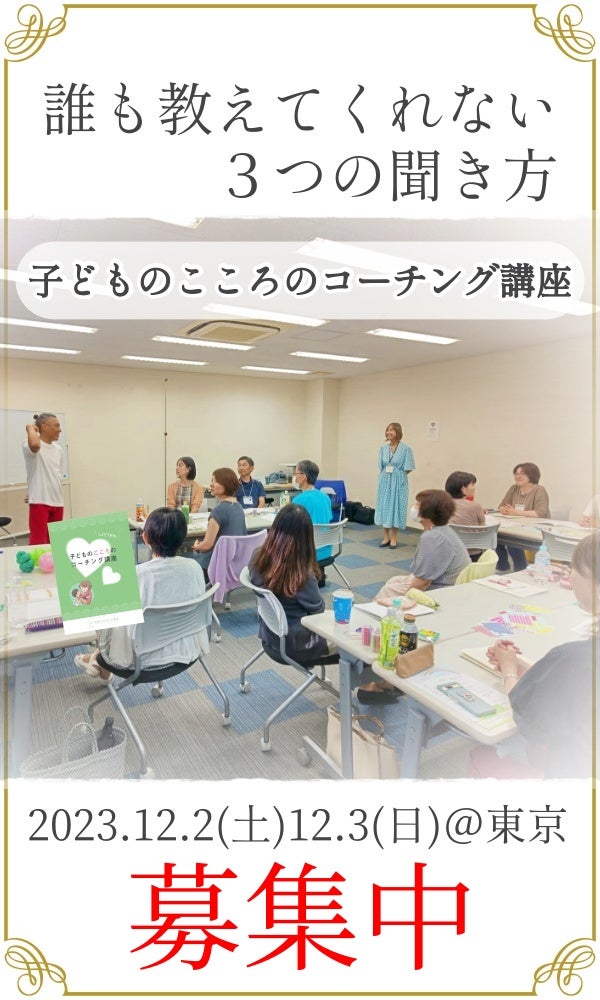お疲れ様です。 学童保育生活向上研究所SAT所長のさとさんです。
その道の途中に、子どもから見えないところに支援員さんが立っている。
子どもが通りかかると、支援員が突然子どもたちの前に出てきて全員を止めた。
そして、「列が乱れてるでしょ!」と怒り始めた。
これはフィクションではなく、ある児童クラブでの目撃したことです。
目的は何?
怒る快感!?
経験的・感覚的には分かっていたことだけど、実際にそうなんだなって思ったな。
怒るために、怒る状況を作り出す。
わざわざ怒ることで、ドーパミンを出し続けている可能性が否定できない。
怒られやすい子
どの児童クラブにも、怒られやすい子がいますよね。
4つのタイプから言うと、黄タイプ・青タイプは怒られがちです。
4タイプ(コミュニケーションカラー)についての個別の説明はこちらをご覧くださいね。
黄タイプは興味がわくと、ルールからはみ出してしまう。
青タイプは、納得してから動くので、全体に合わせて行動することが苦手。
ここで書いていることは「怒ってはいけない」というつもりはありません。
怒らざる得ない時もある。
感情的になってしまうときもある。
何度言っても伝わらない時は、ついつい怒ることも分かる。
だけど、わざわざ怒るシチュエーションの罠を作ることがは必要だろうか?
子育てコーチング協会では、伝えるとか教えるは「叱る」のカテゴリーになる。
ここにも書いたけど、さとさん的には「怒られたと思ったら、それはもう叱るではなく怒る」なんです。
伝えることがあるとき、怒っても伝わらないんだな。
自分が受け手だったら、そうでしょ?
最初の列の例でいえば、罠を作ることに力を注ぐくらいなら、まっすぐ列を作るための工夫に力を入れた方がいいよね。
タイプを知るということは
ここで書いた4つのタイプ。
これを知ると何がいいのか?
行動の原理が違うことが分かる。
自分の価値観とは違うことで、行動していることが分かる。
困らせているのではなく、違うと分かる。
怒らなくても、よくなるよ。
相手を尊重できる
ツール
そのうえで、どう伝えると伝わりやすいかを選べるようになりますよ。
【登録無料のメルマガ】
【お役立ちまとめ記事】