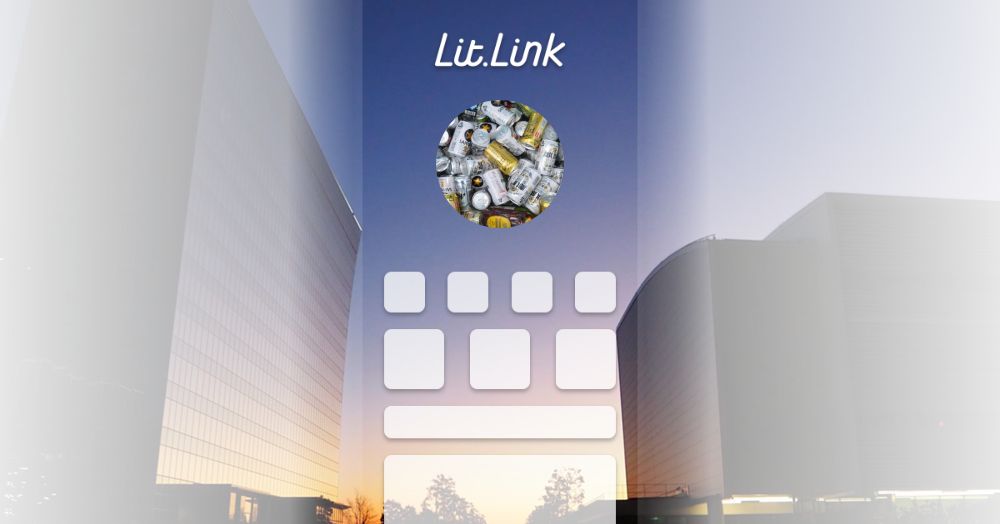
学び with 生成AI
須々木です。
年度が変わり、現在、サークル的にガッツリ学ぶターンに入っております。
RWは集団でいろいろやっているわけなので、何かを学ぶとき、いくつかパターンがあります。
大きく分ければ3つくらい。
① はじめからみんな結構わかっているパターン
この場合は、そこからさらに学びを深めたい状況なので、ディスカッションっぽい展開になりやすいです。
いろいろ意見をぶつけ合いながら、知識を深化させていく感じ。
みんな最低限の知識をもち、自分の言葉で語れる状況でスタートするので、わりとやりやすいです。
② 誰かがわかっていて、他の人はあまりわかっていないパターン
ある分野に関し、メンバー間で理解度に差があるパターンです。
たいていは、誰か一人が比較的よくわかっていて、それを他のメンバーに広げていく感じです。
サブカル界隈で言うところの「布教」っぽい展開になりやすいです。
理解度の差はあまり問題になりませんが、興味のレベルに差があるときは、うまくやる必要があったりします。
③ 誰もあまりわかっていないパターン
学ぶ必要があるという認識は共有しているけれど、みんな揃ってよくわかっていないパターンです。
当然、これが一番厄介です。
基本的には、教材を確保して、読み合わせみたいな感じですかね。
大学のゼミで論文を読み合わせするようなノリ。
そこまで固くはありませんが。
そして、今回の学びは、③のパターン。
みんな「わからんね!」というところからのスタートです。
本当に誰も教えようがないので、ひたすら調べるしかないわけですが、ここで記事タイトルにもあるとおり生成AI(ChatGPT)を活用しています。
もともと積極活用の方針ではなかったのですが、ちょっと試してみたら「結構活用できるな」となりました。
ChatGPTもかなり進化してきていますが、それでも全幅の信頼をおいて教えを乞うことはできません。
その前提で個人的に一番活用しやすいと感じているのが、到達目標(何を達成するために学びたいか)を明確にしたうえで、「どのあたりを学べばよいのか」というあたりをつける部分。
全然知らないものだと、どこら辺から手を付ければよいのかわかってくるまでに、そもそも一定程度のインプットが求められたりします。
学生など教師を頼れる状況だと、ここの部分をうまく導いてくれるわけですが、自学自習の場合はそうもいきません。
しかし、この「一定程度のインプット」は、タイパという意味ではなかなか微妙。
最小のコスト、時間で最大の効果を得たいのです。
その点、ChatGPTは、個別の情報の信頼性に多少難があっても、ざっくりどのあたりを学ぶと良いかはうまく教えてくれます。
言語化はさすがのレベルなので、学びの最初の方向付けにはもってこいです。
いろいろ関連する質問をぶつけていくと、よく吐き出すワードというのもありますし、徐々に学ぶべき対象のアウトラインが見えてきます。
普通に、要望に沿った良い感じのシラバスも出してくれますし。
アウトラインが見えれば、あとはさくさく調べて学べばよいだけ。
あと、まだそれほどやっているわけではありませんが、こちらが提示したものを批評してもらうという使い方には可能性を感じます。
創造的な思考は厳しくても、王道的な思考はなかなかハイレベルで、しかも言語化も得意。
添削にはもってこいです。
というわけで、生成AIに関しては、効率化をはかりうまく活用していこうとしています。
結局なんでも使い方ですよね。
sho
ネトフリで映画。
どうもこんばんは霧島です。
今月分の仕事が一段落して束の間のインターバルです。
先日ネトフリで「ティアメイカー」を観ました。
同じ養護施設で育った2人が同じ家に引き取られていつしか惹かれ
序盤から少女漫画的…と思いながら観ていたのですが、
これは二人の横顔が美しかったところ。
カテリーナ・
始終ミステリアスなリゲルは序盤ヒロインに対してあたりがめちゃ
こちらも少女漫画あるあるというか、
2人が抱える闇の部分はこの雰囲気なら個人的にはもっと重くても
ネトフリでは基本的にドラマを観ることが多く映画はノータッチだ
こういう、観たことある…けどちょっと違う!
今月ネトフリで観たものだと、「ライフリスト」も楽しめました。
亡くなったあとにも愛が残っている系の作品は否応なく好きなので
さて、明日は1日なのでなにか映画観に行けたらいいな〜
したらば!
rin
1~3月の活動報告
どうも遊木です。
一ヶ月が秒で過ぎて宇宙猫みたいになってますが、まぁまぁ元気に生きてます。
といっても、3月末から4月上旬にかけては、気候にぐるんぐるん振り回されて心身共に白目を剝いてましたが……。
今日は、すっかりご無沙汰だった活動報告のまとめをしたいと思います。
1~3月分を一気に載せるので、ほぼ列挙するだけ。
<1月>
■初日の出
横浜に来てから10年以上経ちますが、初めて初日の出を見ました。
想像以上に人が多かったです。
場所は臨港パーク。
■ヨルノヨ 謎解きスタンプラリー
スタンプラリー自体は以前からありましたが、2024年度は謎解き要素も追加され、コンプリートが極めて難しい仕様になっていました。
ちなみに私は71/72個取った……筈です。(Barに行かなきゃ取れない奴だけ逃しました)
ヨルノヨ本家の景品は(多分)落選しましたが、連携していたみなとみらい線+アメリカ山イルミネーションのSNS企画には当たりました。
■「デジタルでアナログ作品に画竜点睛」ミーティング
詳細は別記事でまとめてあります。
久しぶりに、サークルメンバー全員で一つの制作企画に取り組みました。
■春節
〇市役所の獅子舞
確か春節祭のオープニングセレモニー…だったと思います。
平日真昼間なのに、結構な人が見に来ていました。
〇春節スタンプラリー
今年は新しいランタンが増え、見応えがありました。
春節のスタンプラリーは、集めたら必ず紅包クジが引けるのでやりがいがあります。
ただ今年は神戸と連携していたので……まぁコンプリートは無理ゲーでしたね。
来年は、長崎とも連携すると踏んでいます。
〇1/28 春節
初めて行きました。
山下町公園でカウントダウンして、獅子舞などを見ました。
深夜に爆竹が鳴りまくってるのが面白かったです。
■山手資料館
実は一度も入ったことがなかったのですが、今年になってようやく見学できました。
開港以降、横浜がどのような雰囲気だったか、その一端が感じられます。
そして、こういう所にしれっとあるのが宮川香山の作品。
■YOXO FESTIVAL 2025
詳細は別記事でまとめてあります。
横浜で行われる技術の文化祭です。
<2月>
■横浜サイン展
今年は市役所で開催されていました。
小規模の展覧会ですが、コンセプトが面白くて何度か見に行ってます。
■吉田町イベント
〇横浜ジビエフェスタin吉田町
どれも美味しそうで、酒飲みが嵌りそうなイベントです。
〇骨董市
この裏路地でやってる雰囲気が良い。
〇獅子舞
春節との連携でやってました。
■BankART KAIKO 「絹が生まれる場所」展
養蚕業は、横浜の歴史を語る上で重要なポイントです。
スタッフの方が簡単な説明をしてくれたり、実物に触らしてくれたり、なかなか興味深い展覧会でした。
■JICA 「サンノゼ・ジャパンタウン」展
かつては沢山あったアメリカのジャパンタウン。
現在はロサンゼルス、サンフランシスコ、サンノゼの3つだけです。
その中でも、移民文化の面影が色濃く残るサンノゼについて、歴史や文書、写真、インタビューなどが展示されていました。
確か6月まで開催されている筈なので、気になる方は是非。
■そごう美術館 「ブラック・ジャック」展
テーマごとに分類されたパネル展示が主な内容でしたが、個人的には手塚治虫のご家族や当時の編集などのインタビュー動画が印象に残っています。
現在では“漫画の神さま”と呼ばれる人が、かつてはどのような境遇にあり、周囲からどう思われていたのか、とても興味深い内容でした。
■伊勢旅行
詳細は別記事にあげています。
もう鳥羽水が恋しい……。
<3月>
■横浜税関庁舎公開
普段は公開されていない旧特別会議室や応接室、税関長室を見てきました。
接収されたときは、ここにマッカーサーがいたのか……など、なんだか不思議な気持ちになります。
■横浜都市発展記念館 「運河で生きる」展
現在はその多くが埋められていますが、かつての横浜には沢山の運河がありました。
横浜の運河文化はどのように興り、そこで生きていた人達が築いた独自の文化や生活、抱えていた問題、彼らが横浜にとってどのような存在だったのか、それらのことにスポットをあてた展覧会です。
今まで知らなかった内容が沢山あった展示だったので、改めて調べ直したい。
■横浜美術館 「おかえり、ヨコハマ」展
ようやく正式にリニューアルオープンした横浜美術館一発目の展覧会です。
開港、敗戦という大きな出来事を経験し、特異な発展を遂げた横浜の歴史を、新しい視点で読み解いた展覧会です。
6月まで開催しています。
■みなとみらいイベント系
〇さくらフェスタ2025
さくら通りで開催されているイベントです。
行ったときはまだ桜は咲いていませんでしたが。
何で綱引きをやるのかだけ、誰か教えて欲しい。
〇BAY WALK MARKET
恒例のイベントです。すっかり定着しましたね。
今回は歩き回るだけじゃなくてカレーパンを買いました!
〇赤レンガでわんさんぽ
ライブドローイングがあるということで見に行きました。
■BankART Station 「アライブ!」展
BankART Station最後の展覧会です。
郵船の頃から何度かお邪魔していますが、特に新高島に来てから様々な展覧会を楽しませて貰いました。
今後、どのような形で活動し、横浜と関わっていくのかはわかりませんが、BankARTが新たなステージに進み、ますます横浜のアートを盛り上げてくれればと思っています。
■第13回横浜創作オフ会
最後の定期開催でした。
毎回、沢山の興味深いお話を聞ける有意義な会ですが、今後は条件を設けての開催になります。
今後についての詳細は幹事が記事をあげているので、そちらをどうぞ。
↑↑の関連写真はインスタに更新しています。
あと、久しぶりにpixivにらくがき等のまとめも更新しました。
漫画や絵の練習、関連資料のまとめなど、制作関係は相変わらずてんやわんやですが、それとは別に今年に入ってから皮膚関連の治療が続いているので、ちょっとそれが憂鬱です。
2月末に瞼の腫瘍を切除し、現在は足裏に出来たウィルス性のイボを治療中。
コイツがやっかいで、本来イボに痛みはないそうですが、体重がかかる足の裏の場合、神経を圧迫して強い痛みが出るらしい。
歩けない程ではないとはいえ、痛いは痛いので、普段通りに行動出来ず、それがかなりのストレスです。
げふー。
ただ、メダリストをようやく読めたし、アニメも見れたのは満足です。
メダリスト、話が面白いのはもちろんなんだけど、とにかく漫画表現がめちゃめちゃ上手い。
余談ですが、私、司と夜鷹のことを「失敗した勇利とヴィクトル」って呼んでるんだけど、誰かわかる人いません???
ではでは
aki
2025年度ですね。
須々木です。
RWは年度区切りで回っているので、年末より年度末の方が重要です。
年度末のミーティングではがっつり「年度末のまとめ」(通称:ガチ会議)を発表、共有していきます。
昨年度末に共有された活動計画にてらして、できたこと、できなかったこと、想定外だったこと、その原因など振り返っていきます。
さらに次の年度の活動計画も発表、共有します。
RWは、サークルが具体的な到達目標を掲げ、それに応じて各メンバーに役割を振っていく・・・みたいな集団ではないので、
各メンバーが何をやりたいのか、何をやるつもりなのか、それが他のメンバーにどう影響するのか、など定期的に主張してもらってすり合わせる必要があります。
ちなみに、面白そうなものは「プロジェクト/企画」と称してパッケージングしてみんなで取り組むことにする場合もあります。
とは言うものの、毎年大きなネタがあるわけではないので、単純に前年度できなかったことが引き継がれていくことも多いです。
それで、今回のガチ会議は、「前年度からの継続がメインで、あまり大きなネタは出てこないかなー」と思っていましたが・・・
結局、最終的にはいろいろ面白そうなネタが並んでいきました。
どれも「やらないとどうなるかわからない」という感じなので、具体的な進展が見られたら徐々に表に出していく感じになると思います。
先行して情報を出しているのが、前回のブログで触れた「横浜創作オフ会×COMITIA」です。
まさに「やらないとわからん」の最たるものですね。
過去に横浜創作オフ会に参加したことがある人は、できれば把握して、もし興味があれば連絡してくれると大変ありがたいです。
他にも個人的に頑張りたいものとかあったりするので、さっさと進めていきたいと思います。
というわけで、今年度もよろしくお願いします!
もう4月終わりそうですが・・・早い!
sho
映画『ウィキッド ~ふたりの魔女~』を見てきました。
4日連続の過去最高気温を更新し、初夏のような陽気に「なんか頭と体がめっちゃフワフワする~ッ!ヤメロ~ッ!(恒例の季節の変わり目体調不良」て悶えながら仕事してたら、また冬の気温に叩き戻されて「もうこれ以上動くな~ッ!!!!!!!!(気圧と気温のグラフを見てブチ切れ」という緒不安定な日々を過ごしてる米原です。今日1日寒かったけど気温変動が少なくてやっと回復してきた…ハァ…ハァ…。
そんな感じで発狂していた私ですが、先日すご~~~く楽しみにしていた待望の映画を鑑賞。
『 ウィキッド ふたりの魔女 』 part1
緑とピンクって馴染のある組み合わせだなと思ってたけど、そういえば桜カラーじゃん!てなりました。春にピッタリだね。(今日の気温はずっと8℃だったけど…。
今作は2部構成の前編。アメリカでは今年11月に後編公開予定だそうです。
みなさん!安心してください!撮影・制作は終わってますよ!
さて、今回は感想を書こうと思ったのですが、やぁ~~~~~~~、正直、
めっちゃ良かったから!見て!!
としか言えないです。はい。元が大人気ミュージカルなだけあって歌も音楽も物語も良し。歌って踊るミュージカル映画に嫌悪感が無いのなら、是非見て欲しい作品です。私の願いはそれだけです。はい。
あえて書くなら、世界観の構築というか、舞台美術全般に異常なまでの情熱を感じました。監督のこだわりというか、フェチズムを感じるというか、とにかく歌と音楽と映像と合わせて始終圧倒されました。すごい(IQ2)。
世界観の構築という意味で、ミュージカル映画ということもあり比べるのもアレですが、私の中では映画『ロードオブ・ザ・リング』や映画『ハリー・ポッター』と並ぶというか…むしろ…一番好きまである…それくらい好みドストライクでした…。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
折角の大好きな児童文学『 オズの魔法使い 』に関する話題なので自分語りもしますね。はい。
ざっくりまとめると、アメリカ児童文学の代表作のひとつライマン・フランク・ボーム著『オズの魔法使い(1900)』、名曲『Over the Rainbow』でも有名な映画『オズの魔法使い(1939)』がありますが、映画『 ウィキッド ふたりの魔女 』の原作にあたるのは外伝として出版されたグレゴリー・マグワイア著『ウィキッド 誰も知らない、もう一つのオズの物語(1995)』。その小説を舞台脚本に構成し直し、そのミュージカル『ウィキッド』を映画化したのが今作、らしいです。(オズは昔から好きだけどウィキッドに関してはにわかファン。
オズは私がまだ小学校低学年だった頃、母に連れられ今は無き新宿コマ劇場でミュージカル『オズの魔法使い』を見に行ったのを切っ掛けに大好きになった作品です。
その後、劇団四季の「ウィキッド」大阪公演CMを見た時「劇団四季の舞台CMかぁ~⇒ん?オズの魔法使い?でもメインパーティーキャラが誰もいなくない?⇒悪い魔女が主人公なの!?」と衝撃を受けたのを今でも思い出します。
関東生まれ関東育ち関東住みだったのもあり、さすがにチケット代と大阪までの交通費を親に強請ることはできず、その後もずっと頭の隅に残り続けました。
で、そんな中、ミュージカル『ウィキッド』映画化か!?というニュースを見かけ、「やった!舞台に行けなくても映画になれば内容だけでも知ることができるぞ!」と喜んだんですが………。
あれから…どれくらい経ったんだろ…正直わらかん…少なくとも10年は経った気がする…。
ネタバレを見たくなかったのでウィキッドについて極力調べないようにしていたら、その所為で、舞台版の原作小説が、あることにも、気付けないまま、ココまで、来てしまった…。どうせなら原作小説読みながら10年待ちたかった…な………。
やぁ、しかし、今回の映画は、10年以上待った甲斐があった、と思わせてくれるクオリティに仕上がってたのは、本当にすごいことだと思います。感謝しかない。完成させてくれてありがとうございますとしか言えない。
この作品に出会えて本当に幸せです。本当にありがとうございます。生きる元気が湧いてくる。その内ガンにも効くようになると思います。はい。
これは映画見た後に撮った浮かれポンチ写真。生まれてはじめてルームフレグランスなるものを買った。あと映えのために去年買った映画「オズの魔法使い」Tシャツを引っ張り出して来た。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
去年の2024年に劇団四季で再公演されたのですが、ざっと調べた所、東京で約10年ぶり、大阪で約15年ぶりだそうで(違ったらすみません)。
四季のCMを見てはじめてウィキッドを知ってから約15年???………ココまで長かったな。
劇団四季の公演、私も行きたかったのですが、劇団四季のファンクラブ会員でもない、そもそもチケット予約にも慣れてない私が争奪戦に挑もうなんておこがましかったですね…はい…観劇素人が…すみませんでした………。(一瞬で完売。
ついでに言うと制作元がユニバーサルスタジオなので、今USJでウィキッドのグッズ売ってるんですよね………。
私が石油王だったら四季のチケットも取れたしUSJにも行ってグッズも買えるし…というか本場のブロードウェイミュージカルのウィキッドも見れるのに………しく…しく…。
まぁ、悲しいことや悔しいこともありますが、それでもまだ幸せな気持ちの方が圧倒的に勝っているので、新年度も仕事に散歩に創作に娯楽に取り組んで行きたいと思います。大嫌いな春の陽気には負けないぞ。
それではまた次回!
noz

























































