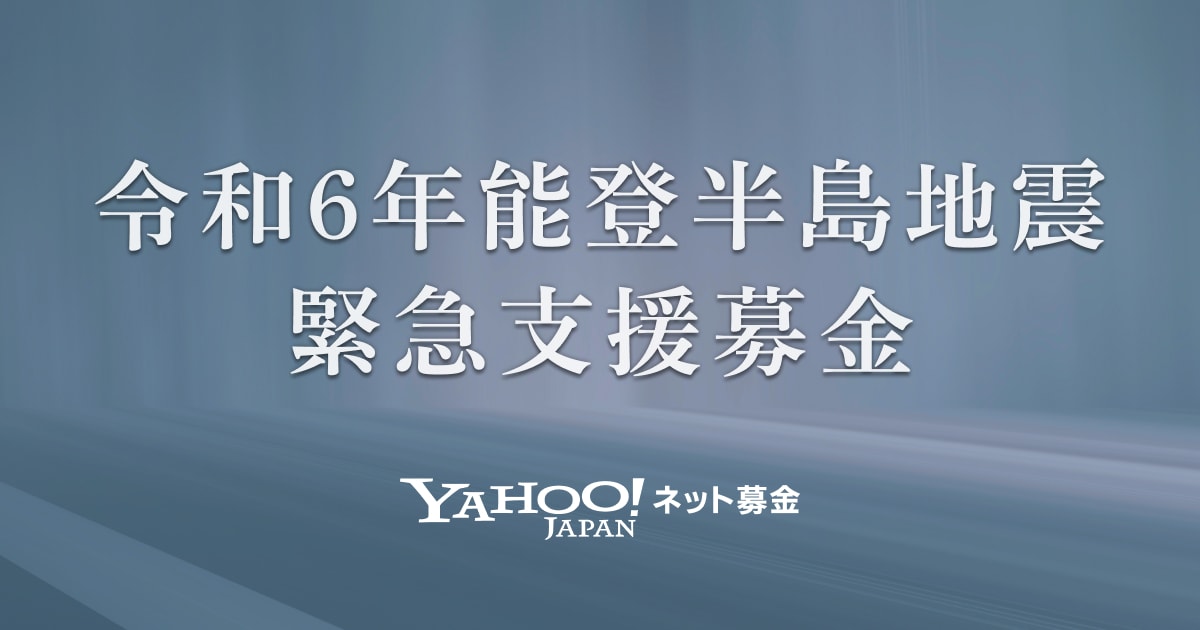2012年3月4日に敢行した、春の煉瓦祭りで訪ねた、もしかして拙ブログで過去イチにメジャーかもしれない物件をご紹介。タイトルだけで映像が浮かぶ方も多いと思われる。
まあ、あんまメジャー物件ってやった記憶がないんだけども、たぶん天城山隧道よりも断然メジャーよね?
この日のネタで以前に記事にしてるのは馬場丁川橋梁と円妙寺橋梁だが、本日のネタの後にこれを見つけた、いわば我が仁丹看板ハントの始まりの日(場所)でもあったりするので、その意味でも思い出深い。
まずはこれ。
現在地はこのあたり。琵琶湖疎水の疎水分線に沿って歩いている。
ここは誰でも普通に歩けるところ(たぶん現在も)だが、人はそう多くない。
これをずっと辿っていくと、このように封鎖に行き当たる。
もちろん、これが水路閣(通称:南禅寺水路閣)である。
水路閣といえば、ほぼお決まりの撮影アングルがあるんだが、この上部からの写真はとんと見ない。試しにYahoo!で水路閣と入力して画像検索してみても、ほぼほぼ絶無。上からは上からで、それなりにバエるのになあ。
足元の歩廊部分も、
煉瓦敷き。
この水路閣の脇から南禅寺境内へと降りることができ、お決まりのアングルで撮れるのだが、その前に!
そこはアナタ、ウチがやるからには、マニアックなオプションをご用意しておりますよ(笑)。
疎水分線が水路閣へと至る、その数十m手前部分。実はそこにも
ええモンありまんのや!(なんでいきなり関西弁
疎水分線、もとは谷筋だったと思われるところを桟橋状に渡っていて、
足場も見通しも悪いながらも、五連(たぶん)の煉瓦アーチ橋となっている。
これはもう、一般の観光客には興味も関係もない話(笑)で、逆に同業者各位にはぜひご覧いただきたいところ。時間帯により人目は気になるかもだけど。
ちなみに当日の訪問時間は朝の7時半ごろである。ご参考に(笑)。
さて、改めて水路閣。
このアングルとか、
バエるんだけどね~。
まあもちろん訪問当時、インスタなんてなかったけども。
こういうのも
間近で見られますしね~。
いや~この芸術点の高さ。
小一時間くらい見てたって飽きませんぞ(弊社基準による)。
あとは下へ降りて鑑賞。コメント控えめで。
そしてこれね。
これはもう、ここを訪ねた者全員が撮ってしまう恐怖のアングルと呼んでも過言ではない(笑)。
ここへきて、水路閣の解説。
お察しの通り、各自、お目通しを。
それにしても、
東京遷都により衰微した京都が近代都市として再生するための重大事業(琵琶湖疎水)とはいえ、よくぞこんなものを古刹・南禅寺境内にぶっ通すことが許されたもんだなあと、今さらながらに驚嘆する。
1885(明治18)年着工時までには反対もあったとされているが、どの程度のものだったんだろうか。
現在に置き換えて考えてみれば、とても認められるとは思えないレベルよなあ。この素晴らしい水路橋を見ながら、不埒にもそんな感想が出てきたのを覚えている。
現代でこそ、ここになくてはならない景観と呼べるほどに周囲とマッチしており、そういう意図を込めて設計した田邊朔郎博士の目的はしっかりと達成されていて、これにも改めて感心させられる。
意外にも(笑)【次回】に続く。