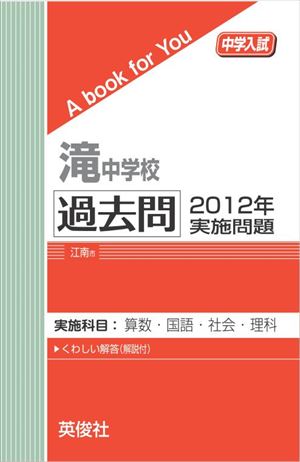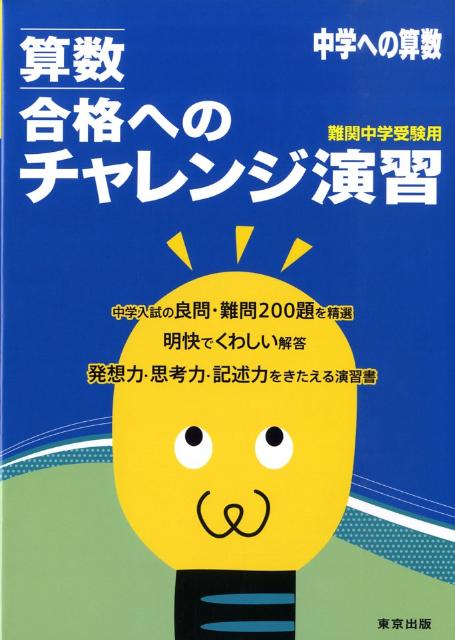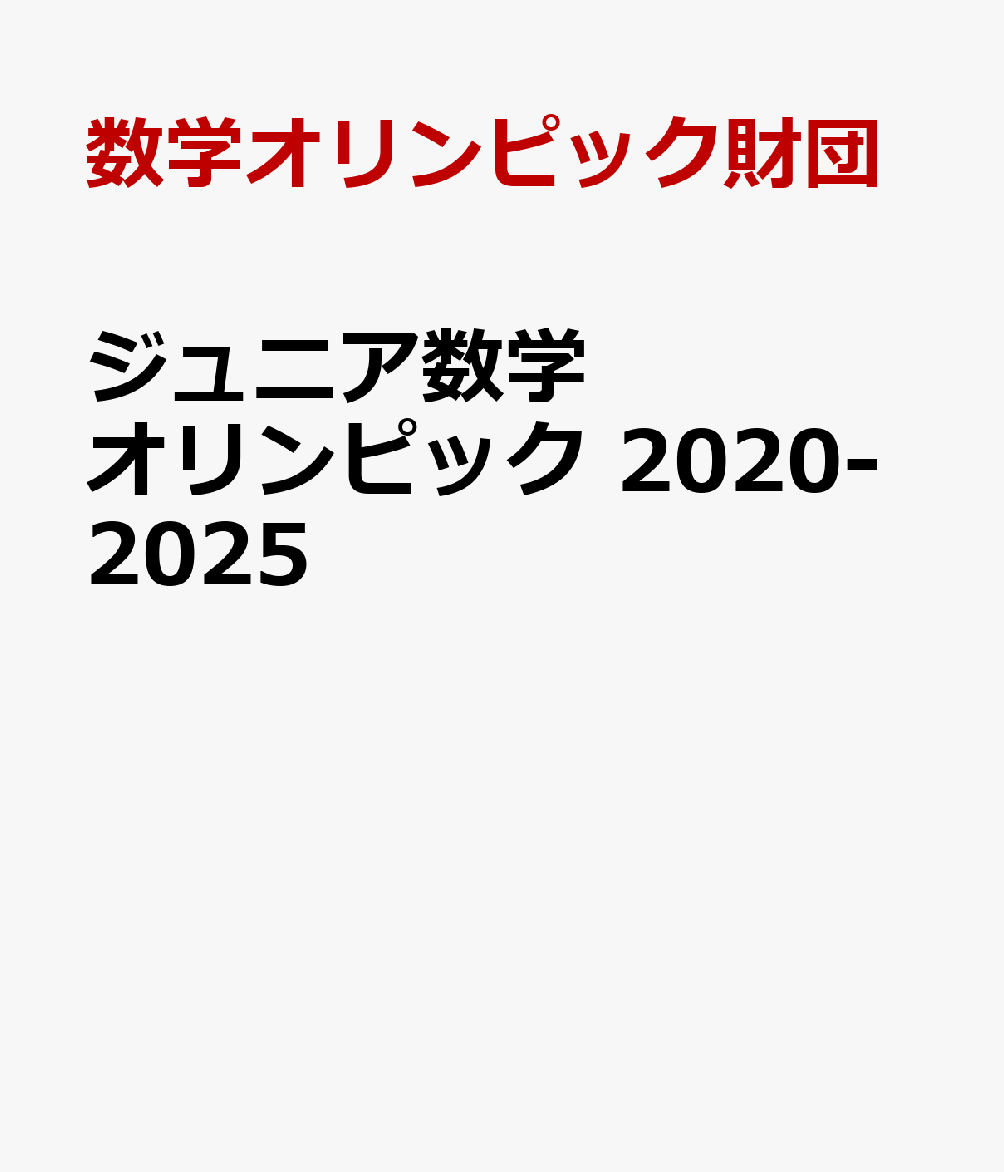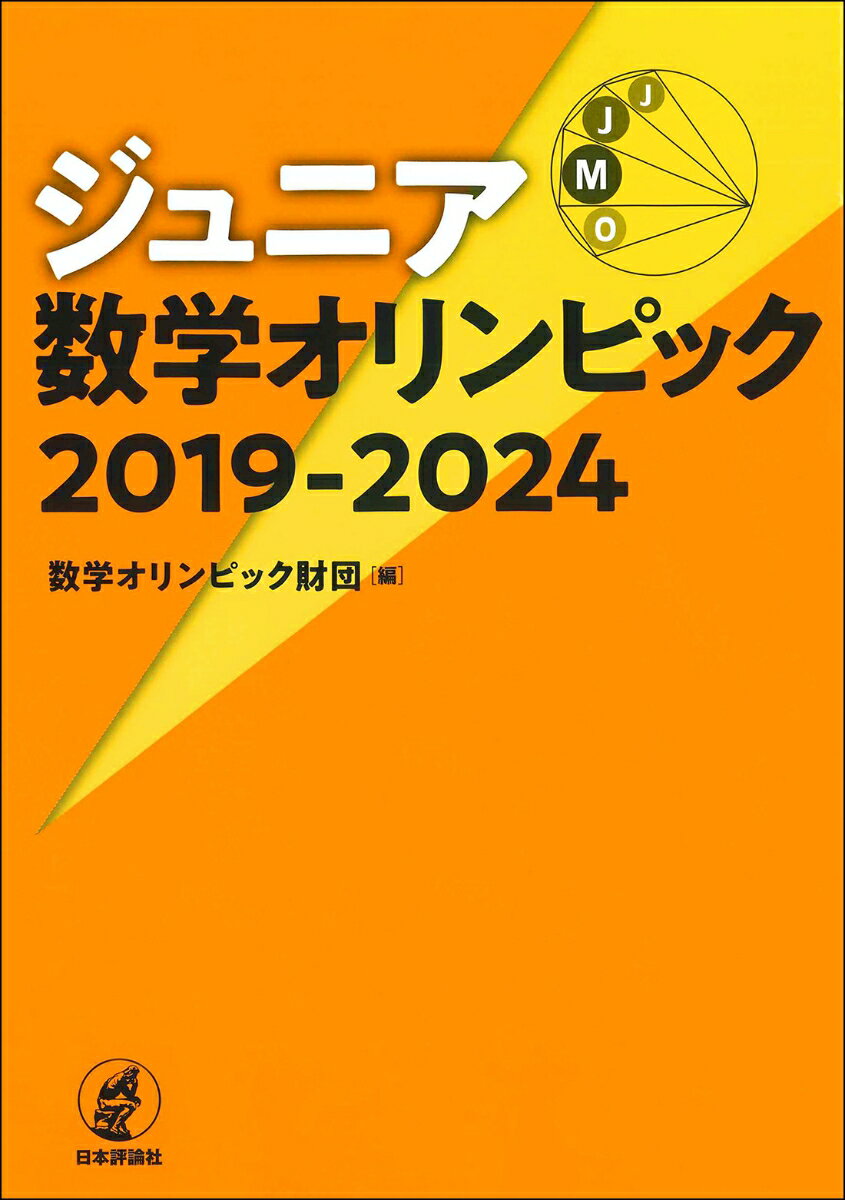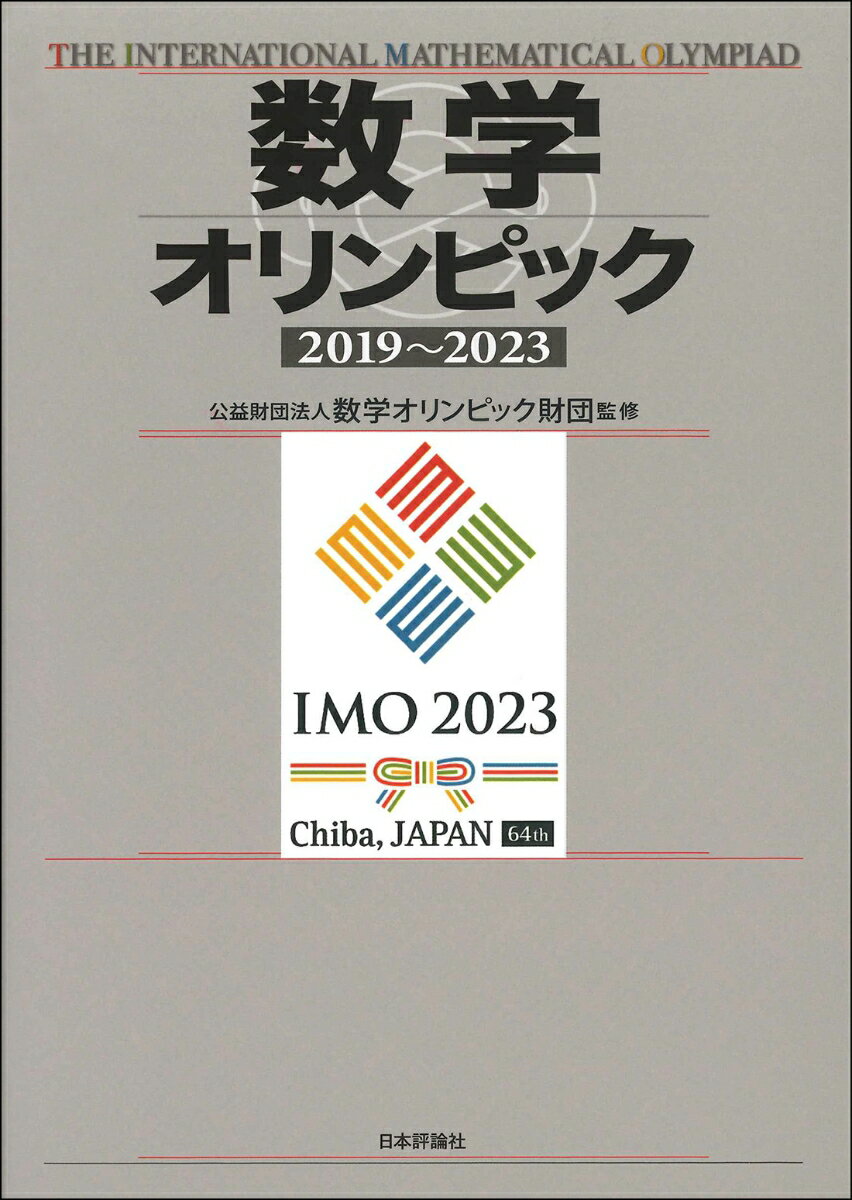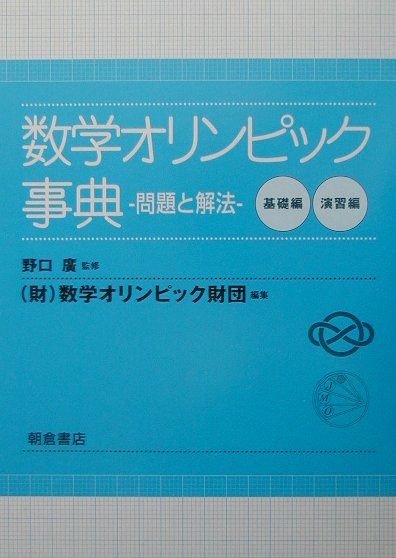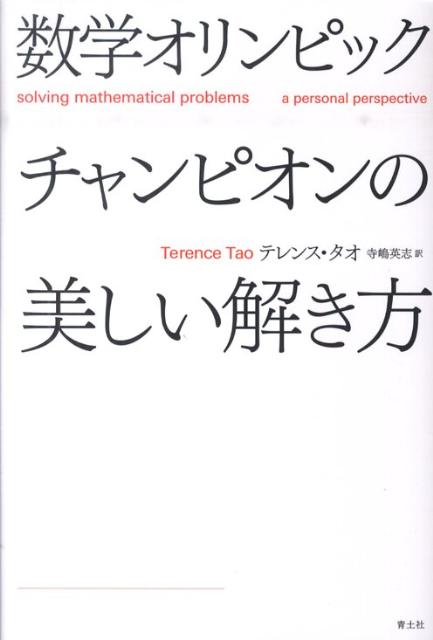日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)2016年予選の問題
今回は日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)2016年予選第8問を取り上げます。
同じような問題は中学入試でも出されています(999の倍数判定法の問題(灘中学校2003年1日目第7問、大阪星光学院中学校2005年第1問(1))、9999の倍数判定法の問題(洛南附属高等学校中学校2023年算数第3問)、1001の倍数判定法の問題(灘中学校2002年算数1日目第2問))。
37×3=111、111×9=999であることを利用します。
各桁の数字が異なる整数は10桁以下であり、最大のものを求めるのだから、とりあえず10桁の場合を考えます。
10桁の整数をABCDEFGHIJ(A~Jは各桁の数で、異なる整数(ただし、Aは0以外の整数)とします。
10桁の整数ABCDEFGHIJは
A×1000000000+BCD×1000000+EFG×1000+HIJ
=A×999999999+A+BCD×999999+BCD+EFG×999+EFG+HIJ
=A+BCD+EFG+HIJ+999の倍数(当然37の倍数ですね)
となるから、10桁の整数ABCDEFGHIJが37の倍数となるのは、A+BCD+EFG+HIJが37の倍数となるときになります。
最大のものを求めるから、とりあえずABCDEFG=9876543(H、I、Jは0、1、2のいずれか)の場合について考えます(区切りのいいところで固定して考えます)。
9+876+543+HIJ
=1428+HIJ
=999+333+96+HIJ
となり、999と333は37の倍数だから、HIJ+96が37の倍数となるものを考えることになります。
HIJ+96は3の倍数(H、I、Jの各位の数の和が3の倍数で96が3の倍数だからです)だから、37×3=111の倍数となるものを考えることになります(問題文には3の倍数という条件はどこにも書いてありませんが、各桁に使う数字に着目して3の倍数判定法を使うのがポイントで、これを使えないと調べる量が激増します。第31回算数オリンピックトライアル問題5(算数オリンピック2022年トライアル問題5)で、問題文には9の倍数(9で割った余り)という条件はどこにも書いていないにもかかわらず、各桁に使う数字に着目して9の倍数判定法(9で割った余りの判定法)を使うのがポイントだったのと同じですね)。
HIJ+96は12+96=108以上210+96=306以下だから、HIJ+96=111つまりHIJ=15またはHIJ+96=222つまりHIJ=126となりますが、いずれの場合も条件を満たしませんね。
以下、同様の作業となるので、説明を多少端折ります。
FとGの4と3を入れ替えると、HIJ+87=111または222より、HIJ=24または135となりますが、いずれの場合も条件を満たしませんね。
ABCDEFG=9876453(H、I、Jは0、1、2のいずれか)の場合について考えます。
9+876+453+HIJ
=1338+HIJ
=999+333+6+HIJ
HIJ+6=111より、HIJ=105となりますが、条件を満たしません。
FとGの5と3を入れかえる(999+222+99+HIJを考えることになりますね)と、HIJ+99=111または222より、HIJ=12(012)または123となり、HIJ=012のときに条件を満たします。
したがって、答えは9876435012となります。
なお、10桁の整数の各桁に使われる数字の和が45で9の倍数であることから、最初の段階で10桁の整数が9×37=333の倍数であることを使うと、次のようにすることができます(こちらの解法のほうが上の解法より調べる場合がさらに減ります)。
10桁の整数をABCDEFGHIJ(A~Jは各桁の数で、異なる整数(ただし、Aは0以外の整数)とします。
10桁の整数ABCDEFGHIJは
A×1000000000+BCD×1000000+EFG×1000+HIJ
=A×999999999+A+BCD×999999+BCD+EFG×999+EFG+HIJ
=A+BCD+EFG+HIJ+999の倍数(当然333の倍数ですね)
となるから、10桁の整数ABCDEFGHIJが333の倍数となるのは、A+BCD+EFG+HIJが333の倍数となるときになります。
最大のものを求めるから、とりあえずABCDEFG=9876543(H、I、Jは0、1、2のいずれか)の場合について考えます(区切りのいいところで固定して考えます)。
9+876+543+HIJ
=1428+HIJ
=999+333+96+HIJ
となり、999と333は333の倍数だから、HIJ+96が333の倍数となるものを考えることになります。
HIJ+96は12+96=108以上210+96=306以下だから333の倍数となることはありえませんね。
以下、同様の作業となるので、説明を多少端折ります。
FとGの4と3を入れ替えると、HIJ+87が333の倍数となるものを考えることになりますが、この場合もありえませんね。
ABCDEFG=9876453(H、I、Jは0、1、2のいずれか)の場合について考えます。
9+876+453+HIJ
=1338+HIJ
=999+333+6+HIJ
HIJ+6が333の倍数となるものを考えることになりますが、この場合もありえませんね。
FとGの5と3を入れかえる(999+333-12+HIJを考えることになりますね)と、HIJー12が333の倍数(0も含みます)となるものを考えることになりますが、HIJ-12=0つまり、HIJ=012のときに条件を満たします。
したがって、答えは9876435012となります。
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策ならプロ家庭教師のPTへ
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策のお申込み・ご相談