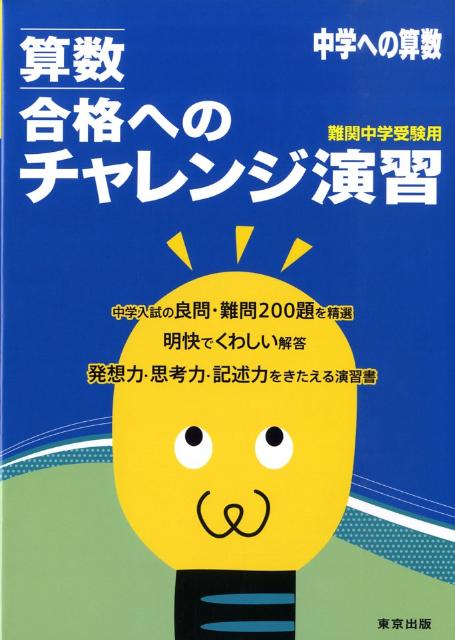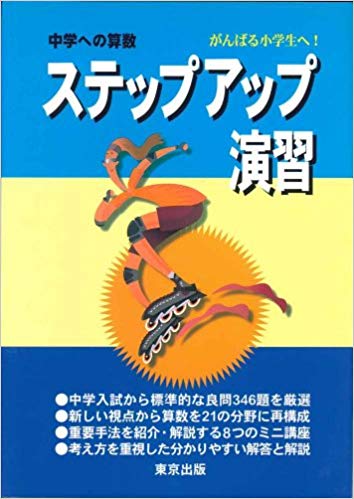みかん、りんご、ももの1個あたりの値段はそれぞれ100円、150円、173円です。これらの果物を3403円分おつりがないように買います。個数の合計が最も多くなるように買うには、みかん、りんご、ももをそれぞれ何個ずつ買えばよいですか。ただし、どの果物も1個以上は買うものとします。
条件不足のつるかめ算(いもづる算)の問題です。
まず、みかん、りんご、ももを1個ずつ買うと考えます(絶対に必要なものをまず買うのは当然のことですね)。
100+150+173
=423円
かかるので、残りの
3403-423
=2980円
で、果物ができるだけ多くなるように買うことを考えます。
一番高いももをなるべく買わないようにしたいのですが、100円も150円も50の倍数だから、代金総額は50の倍数となります。
ところが、2980は50で割ると30余るので、173円のももを何個か買って30を作り出す必要があります。
2980も100も150も10の倍数で、173は10の倍数でないから、ももは10の倍数個買う必要があります。
ももはなるべく買わないようにしないといけないから、10個買うことにします。
2980-173×10
=1250円
で、果物ができるだけ多くなるように買うことになりますが、1250÷100=12.5だから、果物は最大でも12個数までしか買うことができません。
みかんを12個買うことができないことは明らかですね。
みかんを11個買うと、りんごを1個買えばちょうど買うことができ、条件を満たします。
したがって、みかん、りんご、ももをそれぞれ11+1=12個、1+1=2個、10+1=11個買えばいいことになります。
下の問題もぜひ解いてみましょう。
見た目は変わっても、基本的に解き方は変わりません。