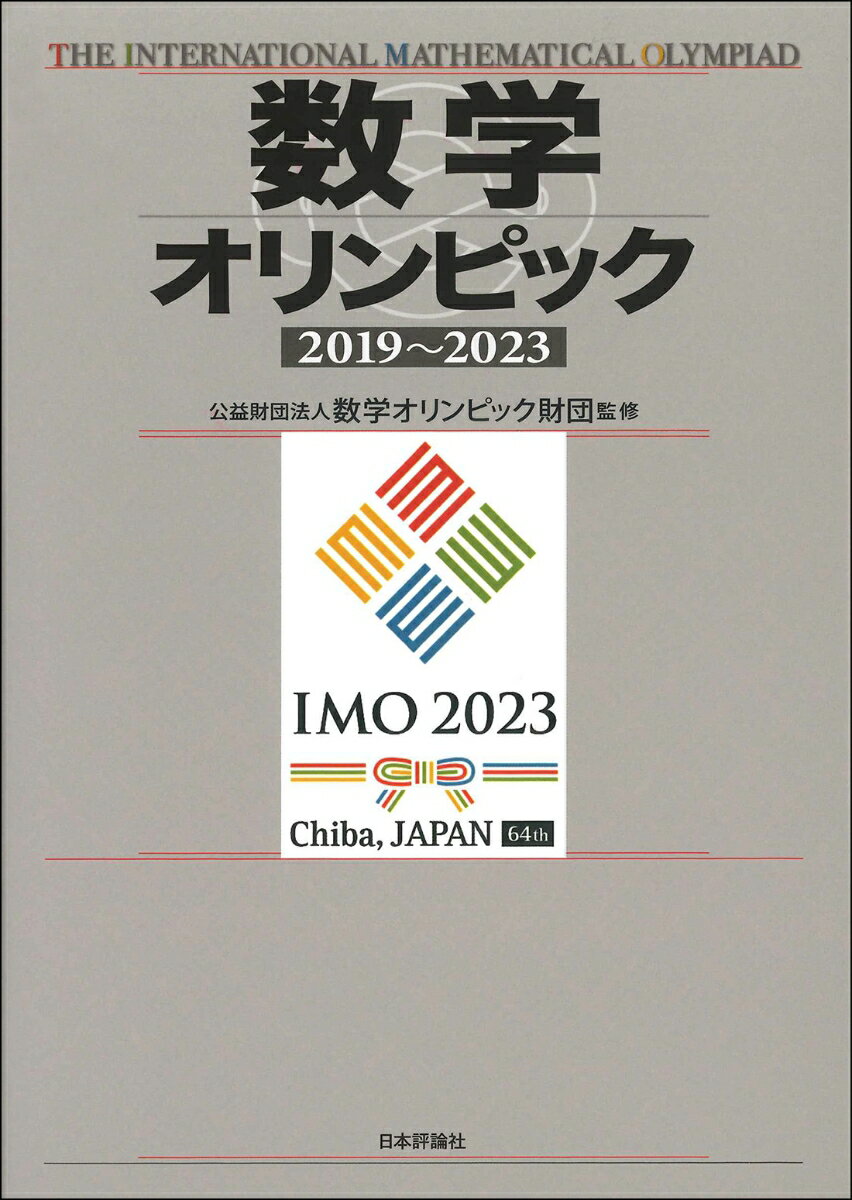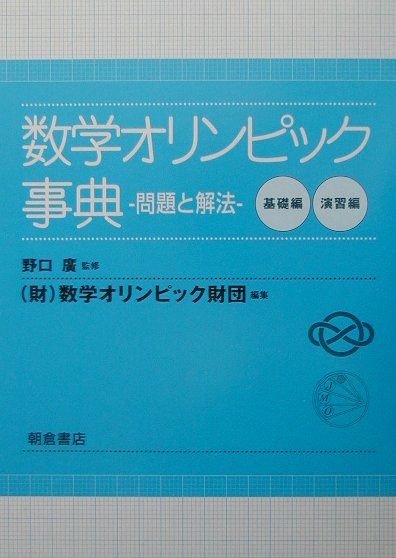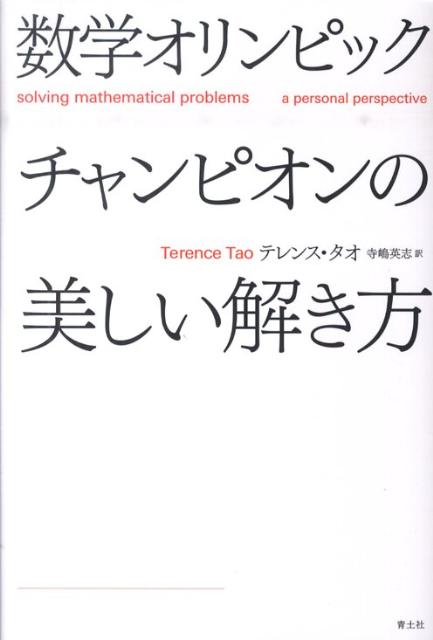今回は2018年のJMOの予選第5問を取り上げます。
「小さな例で実験→観察→規則性の把握→一般化」という規則性の問題の基本的な考え方(麻布中学校1999年算数第5問、筑波大学附属駒場中学校2008年算数第2問、四天王寺中学校2018年算数第4問の解答・解説を参照)をしっかりマスターしていれば、小学生でも難なく解けるでしょう。
いきなり11個のオセロの石を考えるのは厄介なので、とりあえず少ない個数の石で考えます。
(a)において、両端が●で、●と〇が交互に並んでいることに着目して、奇数個の石が(a)と同じように並んでいる場合を考えます。
1個の場合は与えられた作業ができないので、3個の場合から考えます。
●〇●
両端の石を裏返しにすることはできませんね(以下同様)。
左から2番目の石を裏返しにすると、●●●となります。
結局、3個の場合の石の裏返し方は1通りあります。
この1というのは、両端の石を裏返しにすることはできないことから、3-2ということですね。
次に、5個の場合について考えます。
●〇●〇●
左から2番目の石を裏返しにすると、●●●〇●となります。
[●●●]〇●の[●●●]の部分は以後同じ動きをする(この場合は裏返すことはできません)ので、[●●●]の部分を1つの●と考えることができ、3個の場合の石の裏返し方を考えればいいですね。
左から3番目の石を裏返しにすると、●〇〇〇●となります。
●[〇〇〇]●の[〇〇〇]の部分は以後同じ動きをするので、[〇〇〇]の部分を1つの〇と考えることができ、3個の場合の石の裏返し方を考えればいいですね。
左から4番目の石を裏返しにした場合は、対称性を考慮すると、左から2番目の石を裏返しにした場合と同様に考えられますね。
結局、5個の場合の石の裏返し方はは3×1=3通りあります。
この3というのは、両端の石を裏返しにすることはできないことから、5-2ということですね。
もう決まりが分かりましたね。
11個の石の裏返し方は
(11-2)×(9-2)×(7-2)×(5-2)×(3-2)
=9×7×5×3×1
=945通り
あります。
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策ならプロ家庭教師のPTへ
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策のお申込み・ご相談