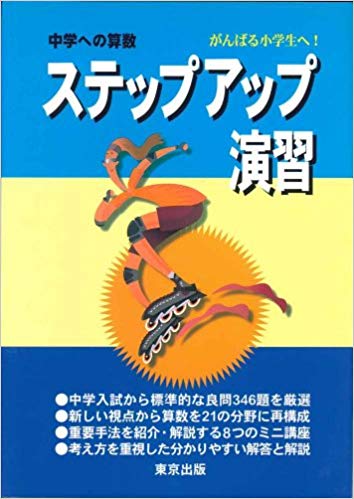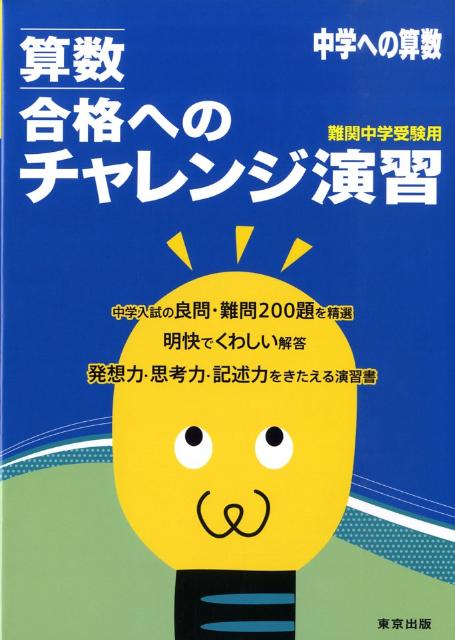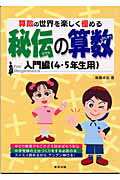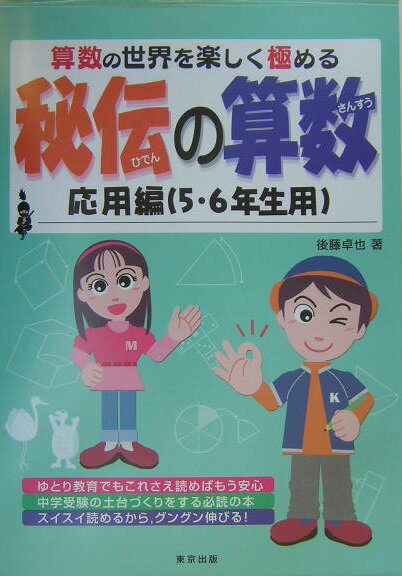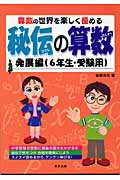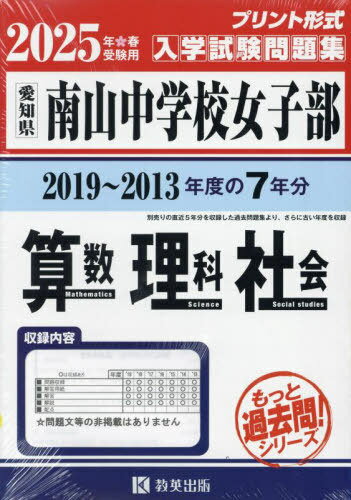A地点からB地点までのハイキングコースは、平らな道、上り坂、下り坂の順に7.5kmの道のりがあります。Cさんは、平らな道は4km/時、坂を上るときは2km/時、坂を下るときは5km/時の速さで歩いて、このコースを往復しました。行きは2時間24分、帰りは2時間15分かかりました。
それぞれ一定の速さで歩いたものとし、休憩時間は考えないこととします。
(1)ハイキングコース全ての道のりを、4km/時の速さで移動したとすると、往復するのに何時間何分かかりますか。
(2)平らな道のりは何kmですか。
同志社中学校で頻出の峠と速さの問題です(近年だけでも、2025年、2023年、2020年などに出題されています)。
下の問題のように、片道を移動したときの上りと下りの道のりの差を問う誘導がついていることが多いですが、今回は別の誘導がついていますね。
解説では、速さと比を利用した解法と速さのつるかめ算の解法を紹介しています。
いずれの場合も平均の速さを利用しています。
詳しくは、下記ページで。