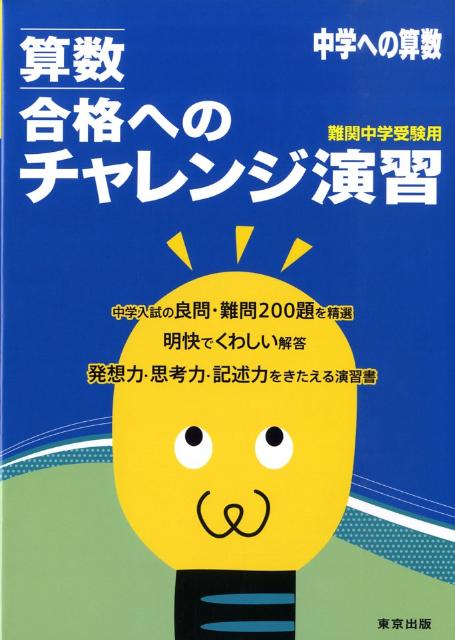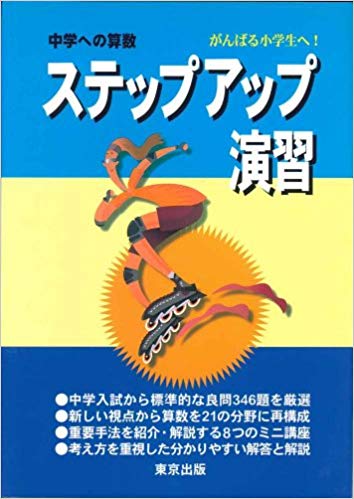次の計算をし、約分できない分数で答えなさい。
5/(2×3)+11/(3×4)+19/(4×5)+29/(5×6)
分母が積の形になっているので、部分分数分解を利用すればよいことがすぐにわかるでしょう(分母が積の形になっていなくても解けるようにしておくべきでしょう(計算の工夫(部分分数分解)の問題を参照))。
また、分子が分母の計算結果より1小さく、分数全体の値はほぼ1であることもすぐにわかりますね。
与えられた式
=1-1/(2×3)+1-1/(3×4)+1-1/(4×5)+1-1/(5×6)
=4-{1/(2×3)+1/(3×4)+1/(4×5)+1/(5×6)}
=4-(1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6)
=4-(1/2-1/6)
=4-2/6
=4-1/3
=3・2/3(表記の都合上、3と2/3をこのように書いています。)
丁寧に書くと、上のようになりますが、実際には暗算で解けるでしょう。
分子が異なるタイプの部分分数分解の問題で、今回取り上げた問題とは少し系統の異なる問題を紹介しておくので、ぜひ解いてみましょう。