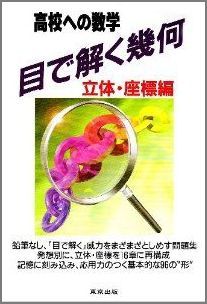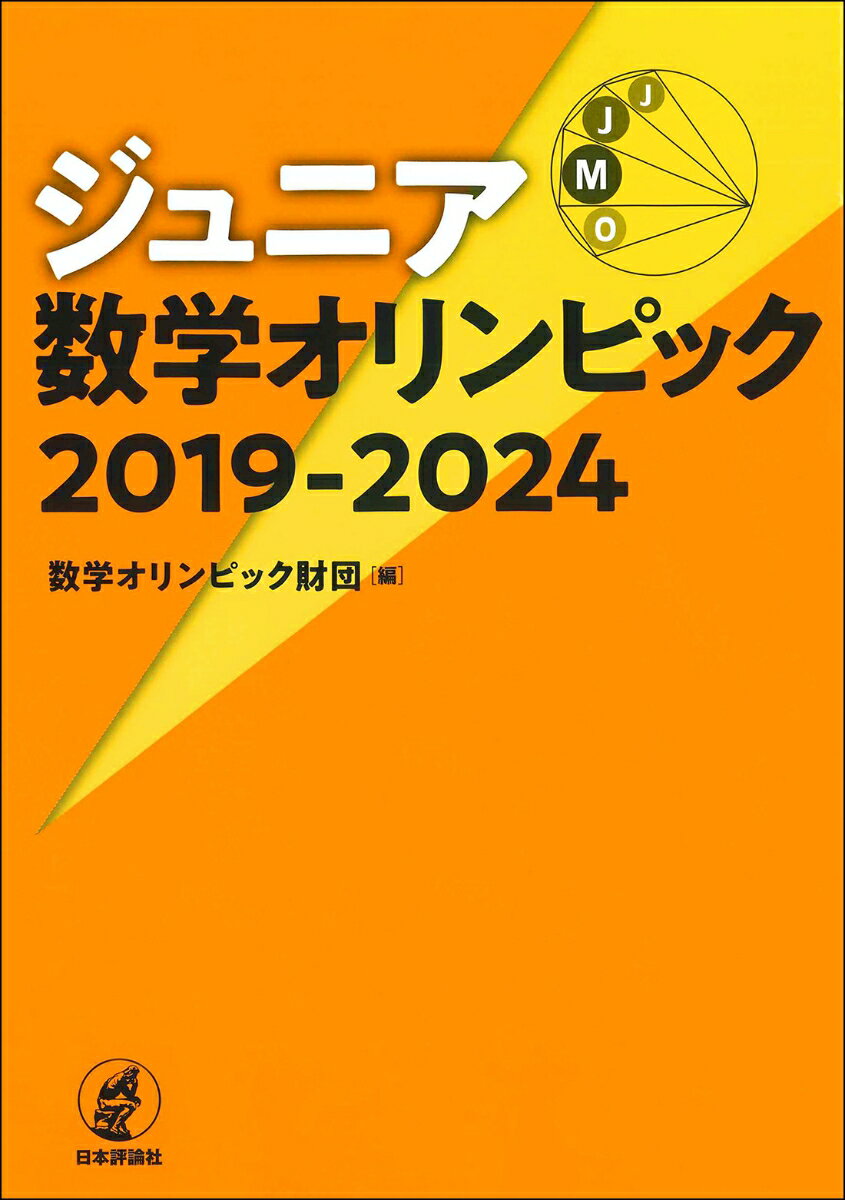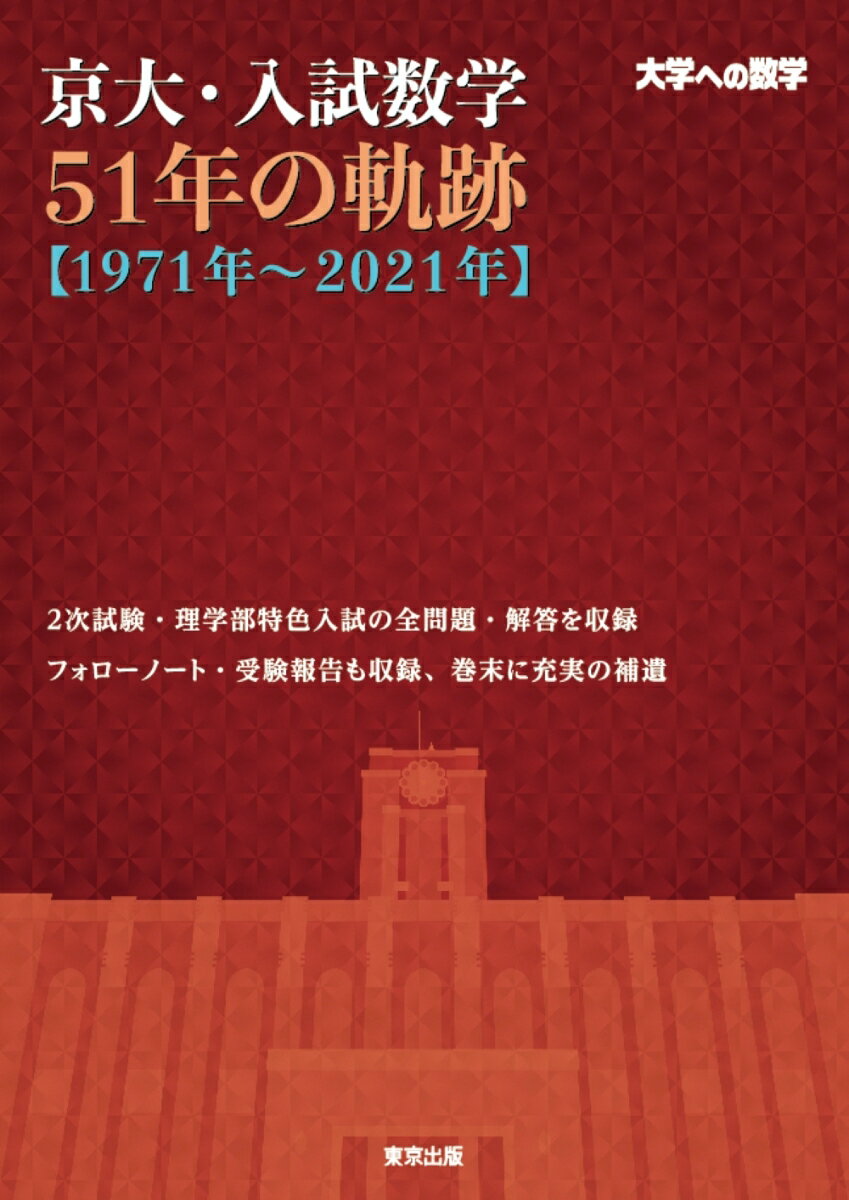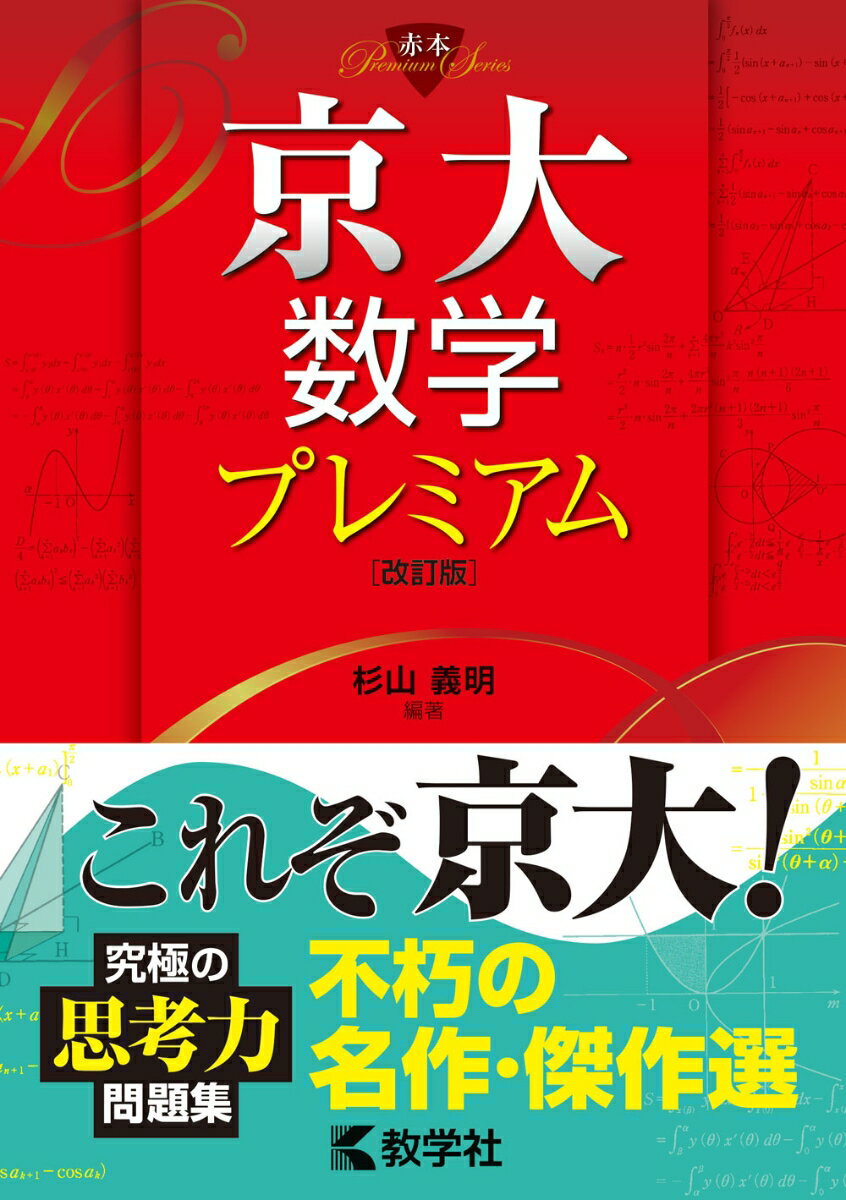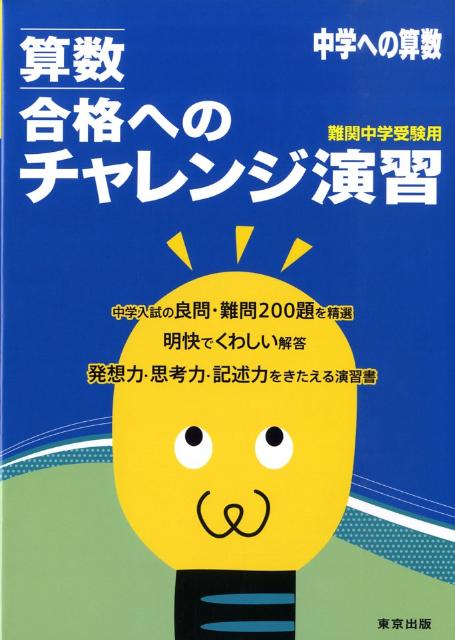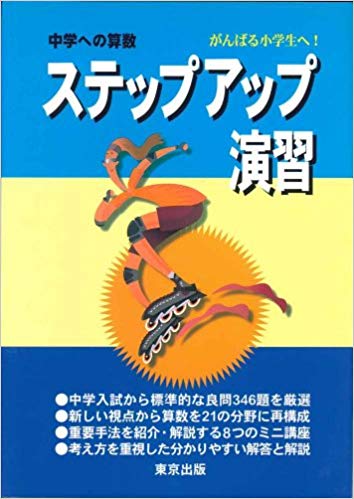AB=4、BC2、CA=5である△ABCがある。半直線CB上にBD=4となるように点Dをとる。また、辺CA上に点Eをとり、2直線ABとDEの交点をFとする。
△AFEの面積と△FDBの面積が等しいとき、以下の問いに答えよ。
(1)省略
(2)点Bを通り、四角形BCEFの面積を二等分する直線と直線ACとの交点をGとする。このとき、線分AGの長さを求めよ。

(1)はルートが絡むので省略しています。
メインの(2)を解くにあたって(1)は不要で、(2)だけ解くのであれば、AB=4という条件は不要です。
この(2)は灘中入試の1日目で出されても標準的な問題でしょう。
さて、問題を解いていきましょう。
実質的には、長さの比(AG:GC)を求める問題です。
長さの比を求める主な手法は、面積比の利用と相似の利用です。
(解法1)
面積比だけで解きます。
三角形AFEの面積と三角形FDBの面積が等しいから、それぞれに四角形BCEFの面積をつけ足した三角形ABCと三角形DCEの面積も等しくなります。
三角形ABCと三角形DCEは、底辺の比がBC:DC=2:(2+4)=1:3だから、高さの比(AC:ECと一致)は、その逆比の3:1となり、AE:EC=(3-1):1=2:1となります。

2点C、Eを直線で結び、三角形CEFの面積を①とすると、高さの等しい三角形の面積比は底辺の比と一致するから、三角形AFEの面積は①×2=②となり、与えられた条件から、三角形FDBの面積も②となります。
再び、いわゆる等高図形の面積比の知識を利用すると、三角形FBCの面積は②×2/4=①となります。
結局、四角形BCEFの面積は①+①=②となるから、面積を二等分する直線BGを引くと、三角形BCGの面積は②×1/2=①となります。
三角形ABCの面積は②+①+①=④となるから、再び、いわゆる等高図形の面積比の知識を利用すると、AC:GC=④:①=4:1となります。
したがって、AGの長さは5×(4-1)/4=15/4となります。
(解法2)
面積比と相似を利用して解きます。
この問題では、(解法1)のほうが若干楽な感じですが、問題によっては、この解法のほうが楽なこともあります(例えば東海中学校2019年算数第4問など)。
2点A、Dと2点B、Eをそれぞれ直線で結びます。

三角形AFEと三角形FDBの面積が等しいから、それぞれの三角形に三角形ADFの面積を加えても等しくなります。
三角形ADEと三角形ADBは、底辺(AD)が等しく、面積が等しいから、高さも等しくなり、ADとBEは平行になります。
三角形CEBと三角形CADのピラミッド相似(相似比は、CB:CD=1:3)に着目すると、EB:AD=1:3となります。
また、三角形BEFと三角形ADFのちょうちょ相似(相似比は、EB:DA=1:3)に着目すると、FE:FD=1:3となります。
三角形BEFの面積を①とし、いわゆる等高図形の面積比の知識を利用すると、三角形FDBの面積(三角形AFEの面積)は①×3=③となり、再び、いわゆる等高図形の面積比の知識を利用すると、三角形BCEの面積は(①+③)×2/4=②となります。
四角形BCEFの面積を2等分する直線BGを引くと、三角形BCGの面積は(①+②)×1/2=①×3/2となります。
三角形ABCの面積は③+①+②=⑥となるから、再び、いわゆる等高図形の面積比の知識を利用すると、AC:GC=⑥:(①×3/2)=4:1となります。
したがって、AGの長さは5×(4-1)/4=15/4となります。
中学受験算数プロ家庭教師の生徒募集について
中学受験算数プロ家庭教師のお申込み・ご相談