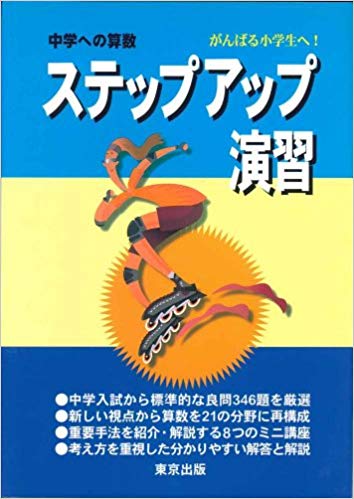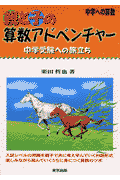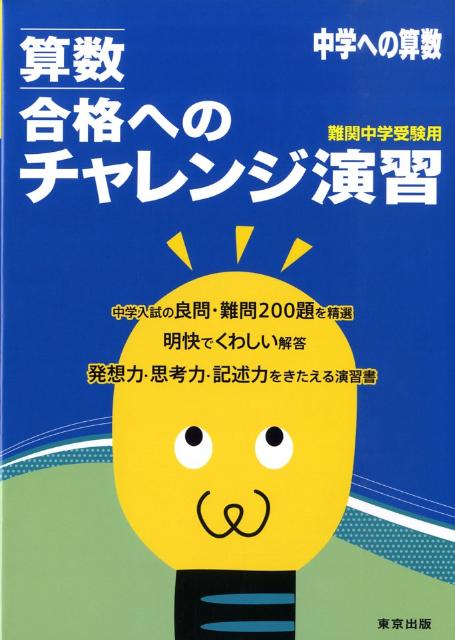濃さが6%の食塩水200gと、濃さが12%の食塩水300gを同じ容器に入れました。ただし、食塩水の濃さとは、食塩水の重さをもとにした食塩の重さの割合のことをいいます。
①この容器に入っている食塩水の濃さは何%ですか。
②この容器から水を蒸発させました。ここに、濃さが15%の食塩水を、蒸発させた水の重さと同じだけ加えました。さらに水を加えたところ、食塩水の濃さは水を蒸発させる前と同じになりました。
この容器に加えた、濃さが15%の食塩水の重さと水の重さの比を、最も簡単な整数の比で求めなさい。
①は食塩水の濃度の基本問題です。
数値がきれいなので、実際には暗算で答えが求められるでしょう。
②はやや難しい問題で、以前紹介した今年の灘中の食塩水の問題(灘中学校2025年算数1日目第2問)より難しいでしょう。
結局のところ、15%の食塩水に水(最後に加えた水から蒸発させた水と同じ量の水を取り除いたもの)を混ぜ合わせると①で求めた濃度になるだけのことで、このことさえ見抜ければ暗算で解けますが、若干厳しいかもしれませんね。
問題としては、以前紹介した今年の洛南の食塩水の問題(洛南高校附属中学校2025年算数第2問)と同じ系統のものです。
詳しくは、下記ページで。