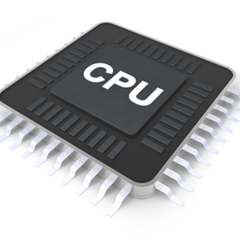たまに人に聞かれ、ネット上でも疑問に感じてる人が結構いると感じたので書いてみる
パソコンのメモリーはどれほど乗せた方がいいのか
結論は下の方で書いてます
■これに関しては人によって意見が異なるので
絶対にこうすべきだというわけではありません。
初めに書いておくと、自分の用途に合わせて容量を考えたときに
余りにも過剰すぎる容量は必要ないという意見です。
【メモリー容量大体の目安】
ソフトを多重起動しない重いソフトが入っていない、officeソフトやネット閲覧程度なら4GB~8GBで十分。
ゲーム単体、ソフト同時起動でも16GB
それ以外の特に重いソフトなら32GBや更に増量という感じ、用途次第
※記事を書いた時点での感覚から。
【注意点】
ゲームや作業などメモリー必要容量は年々徐々に増えていくのでそこは注意。
時代とともに必要容量は増えていきます。
メモリーというのは今現在不足していない、足りているなら増やす必要はない(RAMディスクを除く)
自分のPCでソフトを起動して、タスクマネージャーで確認して使用率が高くない場合は増やしても意味は全くない
むしろ増やすことでデメリットが出てくる。
ただし大容量を必要とするソフトの場合は増やせば早くなる。
【パソコンでメモリーが不足してるかの確認】
パソコンで重いと思う作業、これだとメモリーが不足するだろうと思う作業中に
タスクマネージャーを表示させ、パフォーマンスタブのメモリー項目で使用率が見れる。
そのときメモリーの使用率に余裕があれば、そのままでも問題ない。
誤解しがちなこと
早くなるという表現で誤解がありそうなので一応追記
早くなるというより 「重く、遅くならない」 という方が正しい表現
メモリーは増やすほど早くなるわけではない、動作を低下させないため
極端な状況を除き、メモリーの変更はパーツの中で一番変化を感じにくいパーツです。
●大容量メモリーのデメリット
ハイバネーション、(休止状態機能(hiber.sys)にメモリの70%の容量がHDDやSSDから削られる
(システムドライブから)
要するにSSDやHDD(システムドライブ)の容量がメモリの70%減ることになる
デフォルトではON状態だが無効にすることも出来る
しかしノートパソコンで休止状態は無効にするべきではない。
windows8~10ではハイバネーションを無効にすると高速スタートアップが使用できなくなる
PC起動時にhiber.sysに格納されているドライバ情報をハードからではなく、直接読み込むことで高速化する
ハイバネーション無効はhiber.sysがなくなるので格納されているドライバ情報もなくなる
●仮想メモリがストレージに影響する
ページングファイル(仮想メモリ)によってストレージの容量が削られる
メモリ容量と約同じだけSSDやHDDの容量が減る(システムドライブから)
ページファイルは物理メモリが足りなくなった場合ストレージの一部をメモリとして使い、そこに書き出すシステム。
これも無効に出来るが、仮想メモリ(ページングファイル)は無効にするべきではないと私は思う。
無効化にするとどこかでトラブルが起きる場合があります。
大容量の物理メモリーを乗せていても仮想メモリは無効にしない方がいい。
仮想メモリは自動割り当てにしておくことを強く勧めます。
●
メモリーを4枚挿しなど増やせばその分メモリーの不具合の可能性が上がる
枚数を増やせばメモリ同士が熱し合い発熱が高くなる、高負荷では結構な高温になる
他にメモリーの枚数が増える分、消費電力が増える
これはデスクトップだと電源容量を増やせばいいので、そこまで気にする必要はないが
ノートではGBの容量が増えるごとにバッテリー消費に影響するだろう
●
64bitのOS上で32bitのアプリケーションを起動させる場合、WOW64というエミュレータ機能により
32bitアプリケーションが使用できるメモリ量は制限され2GBまでで、多くても4GBまでしか使えない
そしてパソコン上で使うアプリケーションは現在の64bit OSでも32bitアプリケーションが意外とある
※2020年追記、近年はさすがに減ってきた(64bitに対応したりで)
これはもう気にしなくてもいい時代になったと思う。
つまりどういうことか、64bit OSだからといってメモリを大容量にしても
インストールされているアプリケーションが32bitのものが多い場合
起動していアプリケーションが32bitだったら2GB~多くて4GBしか使っていないので
残りは眠ったまま、どころかパソコンのお荷物にしかなっていないという悲しい現実
なのでソフトを起動し自分のパソコンのメモリ使用率をチェックして、メモリ使用量のパーセンテージが高くない場合
メモリーを増やす必要は全くないということ
メモリーというのは不足したとき初めて増やすもの
要するに使いもしないのに無駄に大容量にする必要はない、容量は用途で考えよう。
●理屈だけで言えばメモリーというのは、メモリーの動作の仕組み上
メモリーは増やすほどパソコンは遅くなる(PC業界人談)
メモリーは処理をするときいったん容量満タンまで溜めてから動作をする
容量が多いと溜まるまで時間がかかり、一度溜まるまで待ってから処理を高速で繰り返すので
毎回いちいち溜める量が多く遅くなるというイメージ、容量が少ないと1回1回溜まるのが早く動作が早くなる。
※ちょっと訂正、おそらく体感ではそれは感じないと思う。
あくまでも理屈ではという話で。
ただインストールしているソフトによってはメモリーを馬鹿みたいに消費するのもあるので
容量に関しては完全に用途次第ということになる
8GB程度で十分な人もいれば、64GBでも足りないという人も中にはいるだろう
結論
メモリーは余裕があるに越したことはない。
余裕はあった方が絶対にいい、これは間違いないのだけれど
あまりにも過剰には乗せる必要はないと思います。
たまにメモリーを誤解してる人がいますが
その人の用途でここまでの容量は絶対に必要ないという基準はあります。
過剰に増やしてもパソコンの動作に変化はないですから、無駄になり意味はないのです。
他人がこれだけの容量が必要と言っても、その人に不要であれば無意味です。
例えば8GBで十分足りる用途に32GB乗せたり
16GBで十分足りるのに64GB乗せるとか、過剰すぎる容量に私は意味を感じないです。
どれくらいの容量だと過剰になるのかは、使う人が自分で調べて判断してください。
●メモリー周波数の違い
DDR3だと1333、1600が平均的
DDR4だと2133、2400、2666、さらに上の3000以上
表示だと12800とか19200という表示だけれど、それを8で割ると1600や2400になる
19200 ÷ 8 といった感じに
高い物はオーバークロック用メモリで、CPUをオーバークロックした際にどこまでクロック数が上がるかという影響と
CPU内蔵のiGPU(オンボードグラフィック)の性能が上がるという部分に影響してくる
現時点のintel CPUでは周波数を上げてもオンボードグラフィック以外では体感で変化はない。
intelでグラボを乗せるならメモリークロックを上げる意味は薄く気にする必要はないと言える。
メモリークロックの関連性
RYZENだとCPUとメモリの周波数と関連が強く
メモリクロックを上げることでCPUパフォーマンスが伸びるようだ
※ただしRYZENの場合は4枚挿しより2枚挿しの方がメモリークロックが高くなるので
2枚での使用がベストということになる
人に聞かれたので一応追記