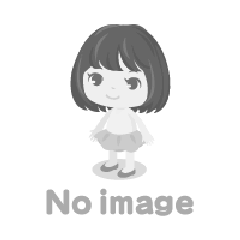【神道つれづれ 113】
※R5.4発行 「社報」256号より
実家の故母の部屋の片づけをしていたら、昭和58年3月発行の皇學館大學の「神道学会会報」が出てきました。そのトップ記事が「神道者の道」國學院大學教授上田賢治とあり、驚いてしまいました。先生は、私の院生時代の恩師、後に國學院大學の学長を務められました。宗教心理学が専門で、疑問を持てば一途に考え追求される誠実な方でした。今回は、この皇學館大學神道学会の会報の記事より紹介いたします。
以下、「神道者の道」國學院大學教授 上田賢治より紹介したい部分のみ抜粋。
※途中の・・は、以下省略になります。m(__)m
「私は神道の信仰を持ち、その信仰にいききる人格を神道者と考え、このような人と、職業的に或いは職業上の必要から何らかの形で神道に関わる人との区別をしている。前者にとって神道の信仰は人生の目的であり、人生そのものであるが、後者にとっては、それが単なる手段に過ぎないと考えられるからである。
今日の神道にとって、神道者の育成が如何に大変な課題であるかは、贅言を必要としないだろう。日本文化の基底に予想される価値態勢、日本人の伝統的な生活への構え、いわゆる日本の心を次の世代へと伝承し発展させるのは、神道者に他ならないからである。
そのような神道者は、一体どのようにして育成されるのだろうか。
その最も大きな過程枠組みを考えてみることが、ここでの課題である。・・・
宗教的人格(神道者も含む)の成立には、三つの重要な年齢期がある。第一は幼少期、誕生から五歳に至る時期である。・・
この時期の人間にとって必要なのは宗教に関する概念ではなく、情緒の安定による自我の成長である。それを可能ならしめる要因は(父母による存在受容)・・・である。
第二期は青年期、特にかつて思春期と呼ばれた十六・七歳を頂点とする前後の時期である。・・この時期に最も必要なのは、ごまかしのない言葉での存在の意味の徹底的な追求であろう。良き指導者、よき人間の壁が求められる時期である。
第三の時期が、成熟期。・・暦年齢との関係で相即せず、大人子供が沢山いる。・・
心理学的な大人には、三つの条件がある。
第一は、人間問題への関心を失うことなく、常に自我の営みのあらゆる分野に、自己の人間として生きる事の意味が関わってあることを自覚し、これに何らかの参与を怠らない姿勢をとることである。
第二に、笑いを失わないこと。特に自己自身を、常に関係性の中で見る目を持ち、これを笑うことが出来る能力を備えていること。かくして人は自己を受容し、成長することが可能になるからである。
第三に、成熟人格は、自己の人生態度に一貫した姿勢を持っていなければならない。当然、生活は簡素化され、一つのスタイルを示すことになる。知的表現の可能性を超えて、このような人格は必ずある意味での哲人だと言ってよいだろう。信仰は決して、慰安や豊かさへの手段ではない。それは時に、進んで苦しみを荷い、価値的な生を成就する、人間の決断と行為なのである。・・
この会報には、妹 悟子の皇學館大學神道学科四年「神道学科女子学生のつどい」の記事が掲載されていました。偶然にもこの度、目にすることが出来たようです。不思議なご縁にも、感謝・感謝です。有難うございました。