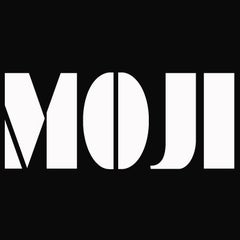PLAN 75(2022 日本、フランス、フィリピン、カタール)
監督/脚本:早川千絵
製作:水野詠子、ジェイソン・グレイ、フレデリック・コルヴェズ、マエヴァ・サヴィニエン
撮影:浦田秀穂
編集:アン・クロッツ
音楽:レミ・ブーバル
出演:倍賞千恵子、磯村勇斗、ステファニー・アリアン、たかお鷹、河合優実、大方斐紗子、串田和美
①想像力の欠如が生み出すディストピア
ディストピアは、想像力の欠如から起こる。
…という気がしています。現世の様々なイヤなことの原因は、だいたいが想像力の欠如ではないかと、最近つとに思います。
冒頭。どこかの施設の廊下を捉えた、ピントの合わない画面。
画面手前に現れる、血まみれの手で猟銃を持った男。
彼は「高齢化問題を告発するために」「老人ホームを襲撃して老人たちを殺害」したようです。ありましたね、似たような事件。
自殺する犯人の見ていた窓の外の(ピントの合わない)景色に、「75歳以上の高齢者の安楽死を認めるPLAN75法案が可決された」というニュースが流れます。
似たような老人襲撃事件が続発していて、高齢者問題の解決を求める世論が高まっていた…ということも。
この一連のシークエンスには、見えていない場面があるわけです。ピントが合っていなくて、映画に映っていないシーンが存在する。
それは、例えば猟銃犯人が怯える老人たちを次々と射殺して血や臓物を撒き散らす、無惨で残酷で醜悪な光景であるはずだし。
一方的な考えに突き動かされて短絡的な犯行に走った犯人の、成熟していない幼稚で醜い顔であったりするはずです。
でも、それは見えない。テレビのニュースには映らないし、データとして残されることもない。
それはただ、「深刻化する高齢者問題」という漠然とした主題に置き換えられてしまいます。
でもそれは、想像できるはずだと思うのです。
それを想像しさえすれば、こんな事件に一部の理があるなんて考えるはずもない。
殺される老人たちの絶望や恐怖を自分のこととして想像することができたなら、まだ健康な老人を死に追いやる法律なんてものに賛成できるはずがない。
でもね。通っちゃうんですよね。
高齢者の死を、ただ数値上の効率化としか捉えず、その先にある人の死が想像できない人たちがいる。
自分もいずれ年老いて、自分がただ生きていることが「問題」と見做されるということが、想像できない人たちがいる。
そんなふうに、民主的に効率的に、ディストピアは作られていくわけです。
②真面目に生きた人が報われない世界
75歳以上の高齢者が自ら死を選ぶことのできる制度「プラン75」が導入された日本。78歳の角谷ミチ(倍賞千恵子)はホテル清掃の仕事をしていたが失職し、新たな仕事も見つからず、やむなくプラン75を申請します。市役所のプラン75申請窓口で働く岡部ヒロム(磯村勇斗)は、申請に来た叔父の幸夫(たかお鷹)と再会します。介護職のマリア(ステファニー・アリアン)は幼い娘の手術費用を稼ぐため、プラン75の施設に転職します。ミチはプラン75のサポートセンターでオペレーターを務める瑶子(河合優実)と交流します…。
映画は、プラン75のある世界で生きる人々それぞれの様子を、スケッチするように描いていきます。
本作で描かれる人々は、普通の人々。
制度を作った人ではなく、制度の是非を問う人でもない。
ただ、制度が既にある世界で生きる人々です。
そして、本作で描かれる高齢者たちがプラン75を選ぶ理由は、結局のところお金です。
生きるためのお金に余裕があれば、誰も好き好んで自分の死なんて選ばない。
貯えもなく仕事もなく、この先に希望を見出せない。だから、死を選ぶしかない。それって本当に自分の意思で選んだと言えるのか?ってことですね。
また、「やめたくなったらいつでもやめられる」と本人の自由意志が強調されていますが、しかしそもそも困窮してそれしか選べなくなっているわけだから、やめたくなってもやめられない…のが大半じゃないでしょうか。
事前に10万円貰えるというのも、罠として機能してますね。それを使っちゃったら、多くの人は今さらやめられないと思ってしまうでしょう。
こういう問題に対して、声高に自己責任を叫ぶ人たちがいます。
でもね。やっぱり何かが変だと思うのです。
映画に出てきたミチのように、真面目にコツコツと働いて丁寧に生きてきた人が、人生の終わり近くになってその日暮らしのような生活を強いられ、ただ生きるというだけのことさえ、許されない贅沢とされてしまうというのは。
これは、プラン75のある世界だけのことではないですね。
「わたしは、ダニエル・ブレイク」がそんな映画でした。現代のイギリスの話でしたが。
プラン75によって死を選ぶ人たちは、生きていることが辛い、厳しい境遇に置かれた人たちです。
金持ちや権力者たちは、誰もプラン75を利用したりしないでしょうね。
彼らには役職があるからね。「必要とされているのだから死ぬわけにはいかん」という理屈でもって、政治家や大企業の経営者などのいわゆる「上級国民」たちはのうのうと生き続けることでしょう。
だから、これは結局公平ではない。金のない人を切り捨てて、金を持ってる人を優遇するシステム。今あるいろんな仕組みと同じです。
貧乏人が死ぬことで浮いた財政は、彼らに回るでしょうね。若者じゃなく。
そして、制度を決めるのは彼らです。かくして、ディストピアは安泰になっていくのです。
③老人を殺す仕事を若者がする世界
若者のため、子供たちの未来のために…と「子供の笑顔」のポスターで宣伝されるプラン75。
しかし、その実態は見えないようにされています。
何となくのきれいごとだけが前に出て、「健康な老人に毒物を与えて死に至らせる」という本質の部分は誰の目にも触れないところに隠されています。
でも、誰かがそれをやらされることになるわけですよね。
皮肉なことに、末端でしんどい思いをして、制度を支える役割を担うことになるのは若者たちです。
市役所で、笑顔で老人たちをプラン75へと誘導するヒロム。
申し込んだ老人が心変わりしないように、会話を通して「ケア」する役目の瑤子。
安楽死を遂げた老人たちの遺体から、遺品を回収し、遺体を次の「処置」に送る役割のマリア。
結局のところ、しんどい役割ほど外国人などの「持たざる人々」に押しつけられていく。
だってね。介護とか医療だって、従事する人たちの精神的なキツさは大きいわけですよ。
でも、それらが「救う仕事」であるのに対して、これは「殺す仕事」ですからね。
精神的なしんどさは比べものにならないだろうと思えます。
中でもいちばんキツいであろう、実際に老人にガスを吸入させて、死んだことを確認する人は、映画ではさらっと「顔も見えないくらいに」描かれているだけで、故意にピントを合わされていません。
この人の内面に踏み込んだら、映画は更にずっしりと重いものになっただろうと思います。ここも、想像力。
老人を殺して数を減らす制度が、若者を幸せにしているのかといえば、していない。
毎日大勢の老人が殺され、殺す仕事を若者たちにさせる社会。そんな社会が幸せであるはずないと思えるのだけど。
でもそれは、巧妙に見えなくされていて、表面に出てくるのは「高齢者が何人減った」という数字だけなんですよね。
④俳優が支える、人の生きる姿
ずっと制度の話ばかりしてますが、本作の制度と社会の描写は本当に上手いと思います。リアリティの凄みがある。
それを支えてるのはやはり人間、役者の力。
特に倍賞千恵子さんのパワーは素晴らしいですね。
特別なことは起こらない。感情を高ぶらせることもない。
ただ毎日を淡々と、慎ましく、丁寧に生きている78歳のミチさんの姿が描かれていきます。
でもそれによって、単なる漠然とした「高齢者」ではない、一人の人間としてのミチさんを我々は知り、好きになっていきます。
観る人が、自然とミチさんを好きになる。そうさせる倍賞千恵子さんの人間力が、やはり凄いですね。
瑤子が気持ちをガツンと持っていかれてしまうことも、説得力がある。それだけの人間的魅力が、ただ淡々と生きる姿を通して伝わってくる。
だから観ていると自然に、ミチさんに死なないで欲しい、生きて欲しいと思うし。
そんな人を機械的に呑み込んでしまうプラン75という制度のある社会が、何かおかしい、間違っているということも、理屈じゃなく気持ちで実感することができます。
ベテラン女優のそんな魅力を引き出した、早川千絵監督の力量も感じます。なんでもない生活スケッチのようだけど、切り取り方がやはり巧みなんですね。
全体を通して、もしも架空の制度が導入されたら…という社会シミュレータみたいになりがちだけど、しっかりと血の通った、人間味のある映画になってると感じました。
冒頭から書いてる、焦点の合わない画面を再三使って、「何かが見えなくされている社会」を表現していく手法が、実に映画的で。
論文とかレポートのようじゃなく、ちゃんと映画としての魅力がある。
本作を観ずに情報だけ聞いて、プラン75の概要だけ聞いてしまうと、短絡的に賛成する人も出てくると思うんですよ。だからこそ、リアリティがあるわけだけど。
でも実際に映画を観ると、まさかそんな感じ方にはならない。
非人間的な制度を否定し、生きることそれ自体を肯定する、確固たる意志のある映画になっていたと思います。
⑤映画が描かなかったもの
最後に、映画にはあえて描かれていない側面がありました。
映画でプラン75を選ぶのは、身寄りのない孤独な老人ばかりなんだけど。
もし実際にこの制度があったら、表面化してくるのは「家族に忖度して死を選ぶ人たち」だろうと思います。
一人であれば、生きるための費用は自分だけが頼りだけれど。
家族がいれば、その負担は当然家族に課せられることになります。
高齢者の介護や医療、認知症などに伴う負担があまりにも過大なものになって、家族に重くのしかかる…というのは、既にずっと前から問題になっていることです。
そして高齢者の側では、家族にそんな負担をかけるわけにはいかないという心理が強く働きます。
というか、これは確実に同調圧力になっていくでしょうね。
生きていることが身勝手なわがままであるような、そんな空気が醸成されていくでしょう。
本心では生きたいと思っていても、そんなことは口にできない。半ば強制的に、死を選ばざるを得なくなっていく。
そして、自分の親にそんな選択をさせた以上、若い世代もいずれは同じ選択をしなくちゃならない。
かくして、本人の自由意志などそっちのけで、ある年齢になれば自動的に死ななければならない暗い社会が出来上がります。
作りたかったのは「自分の死を選べる社会」であるはずなのにね。巡り巡って、選べない世界になってしまう。
もしここまで踏み込んでいたら、映画は更にしんどいものになっていたと思います。
自分の親に、やんわりとプラン75を勧める。おじいちゃんおばあちゃんが、早くプラン75に申し込めばいいのにと願う。
おじいちゃんおばあちゃんがプラン75を選んで、みんなで明るく笑って送り出す家族…。
早川監督はこの辺りも当然考えたでしょうが、観やすさを考えてそこまでの地獄を描くことは避けたのかなと思います。
ちなみに!「アイデアSFのネタ、大概は藤子・F・不二雄が描いているの法則」で、本作も連想した作品があります。
1973年の短編「定年退食」。「定年法」が定められ、73歳以上の老人が食糧その他国家による一切の保障を打ち切られる世界を描きます。
これは人口爆発による食糧危機が叫ばれた時代の作品ですが、50年経って世界も進歩してるはずなのに、同じようなディストピアがリアルな世界になってるのは皮肉ですね。
短編なので気軽に読めます。実比べてみるのも一興です。
テレビ演説してるのは首相。この時代は長髪が真面目の証で、反抗的な若者は坊主頭にしてるという設定。それだけ取っても凄いよね!
「定年退食」収録。
倍賞千恵子さんの前作。これも老いと死にまつわるSF。
‥といえばさくら。その記憶も大きく作用している気がします。
河合優実の前作。よく出てますね。