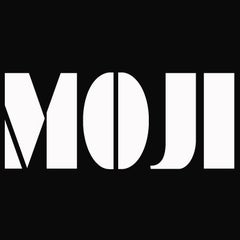哀愁しんでれら(2021 日本)
監督/脚本:渡部亮平
製作:浅野由香、涌田秀幸
撮影:吉田明義
編集:岩間徳裕
音楽:フジモトヨシタカ
出演:土屋太鳳、田中圭、COCO、山田杏奈、ティーチャ、安藤輪子、金澤美穂、中村靖日、正名僕蔵、銀粉蝶、石橋凌
①挑戦心あふれる「気の悪い映画」
なかなかタイミングが合わなくて、大阪で映画館のレイトショーが解禁されたところで、ようやく観ることができました。レイトショーはやっぱりありがたい…。
本作に関しては、期待と不安が入り混じるところがあって。
予告編のムードや漏れ聞こえる感想などから、すごく好みの映画かもしれない…という期待がある一方で。
でも、場合によるとただ不快に感じるだけかもしれない…という不安もあったんですよね。
で、結果なんですが。良い方でした! 非常に好みの映画。どストライクの作品でした。
いわゆる、「気の悪い映画」の系譜。
古くは「未来世紀ブラジル」とか「セブン」とか、「ミスト」とか、「ダンサー・イン・ザ・ダーク」とか。
最近ではやっぱり「ヘレディタリー」とか「ミッドサマー」、「パラサイト 半地下の家族」とか。
鬱展開、バッドエンドの映画。見終わった後でスカッとしない、イヤ〜な気持ちが渦巻いてしまう映画。
でも、そんな映画に限って意欲作が多いし、後々まで記憶に残る、印象に残る作品だったりするんですよね。
本作は、そんな作品群に連なる、挑戦的な作品だと思います。
「TSUTAYA CREATORS' PROGRAM FILM 2016」でグランプリを獲得した企画の映画化。渡辺亮平監督は33歳、これがメジャーでは初監督の若手です。
当時にグランプリを競った作品には、「ブルーアワーにぶっ飛ばす」(2019)や「ゴーストマスター」(2019)がある模様。
本作が企画から実現まで時間がかかったのは、大手からのオファーはあったものの、ハッピーエンドに変えろとか、誰でも泣けていい気分になるラストに変えろとか、様々な制約があったそうで、それを跳ね除けて初志を貫徹したのは偉い!
本作が「いい気分のラスト」になっちゃったら、もう作る意味ないもんね。さすが、「100日後に死ぬワニ」を「100日間生きたワニ」に変える大手の考えることは違う!
とにかく本作はそんな阿呆な圧力も跳ね除け、初心の通りに「気の悪い、後味最悪の映画」として完成したわけです。
いやほんとに、よくやった!と言いたい。今の時代に、日本で、よくこのラストを押し通したと思います。
②「ポップ」に寄り過ぎない地に足ついた演出
市役所に勤め、児童虐待に目を光らせる正義感の強い小春(土屋太鳳)。ある日祖父が倒れ、病院に駆けつける間に家が火事で全焼。駆け込んだ彼氏は職場の先輩と浮気中。怒涛の不幸に見舞われた小春は、泥酔して踏切で横たわっていた大悟(田中圭)と出会います。大悟は大金持ちの開業医で、幼い娘ヒカリ(COCO)と暮らしていました。小春は大悟と結婚し、一気に幸せを掴むことになりますが…。
タイトル通り、童話「シンデレラ」をモチーフとした作品。
不幸で貧しい境遇から、王子様との出会いで運命を一転させる小春ですが、実際童話でもシンデレラは王子様のことを何も知らない。王子様もシンデレラの「足のサイズしか知らない」のですよね。
結婚して初めて、相手の様々な素顔が見えてくる。そして、せっかく掴んだ幸せに固執すればするほど、日常は歪んで、崩れていく…。
序盤の怒涛の不幸が連鎖する展開はテンポよく、コミカルな描かれ方になってはいるんですが、例えば中島哲也監督のような広告っぽい過剰なポップさではなくて、抑制された描き方になっている。また別の資質を感じさせます。
映画の虚構性をことさらに誇張し過ぎない。地に足のついた堅実な演出を感じました。
シンデレラをモチーフにした寓話なんだけど、基本的なタッチはシリアスでクール。
それだけに、要所に配置されたユーモアや、キレのいい毒の印象が強くなっている。上手いなあと思いました。
魅力的なのは、幸せの絶頂にある小春と大悟、ヒカリの3人が海辺で踊るミュージカル・シーン。土屋太鳳さんを上手いこと生かしてますね。
ミュージカルっぽいシーンなんだけど、非現実のミュージカルまでにはしていなくて、浮かれた家族がちょっとふざけて踊ったりクルクル回ったり、あるよね…という描き方になっていて、結構「リアル」なんですよね。
ありそうなんだけど、土屋太鳳だから完成度が高くて目に楽しいという。そういう絶妙なダンスシーンを、海辺の美しい光の中で1カットで見せる。
序盤の不幸から中盤の幸福へ、ジェットコースターのように展開しつつ、主人公たちの過去を自然に見せていくのも上手かったですね。
それによって、キャラクターの掘り下げができていて、中盤以降、彼らへの「疑い」が顕在化していくときに、十分な厚みになっている。
一面的でない、多層的な存在である人間というものを、感じさせる描写になっていたと思います。
③大悟の素顔の絶妙なバランス
結婚して「日常の生活」が新たに始まると、それまで見えなかった一面が少しずつ見えてくる。誰でも、よくあることでしょうね。
大悟は秘密の部屋を持っていて、そこには子供の頃に飼っていたウサギの剥製が飾られていて、彼が描いた「裸の自画像」が飾られている。
三十年に渡って、自分の成長を自分で描き続けていて、その絵をズラリと壁に並べて飾っていく。それを目にした小春は、「引く」ことになります。
そういう大悟の異常性は、母親との関係にその原因があったことがやがてわかってきます…。
…という大悟の異常性なんだけど、まあ確かに「引く」素顔ではあるけれど、本気で見限ってしまうような、そこまでの異常でもない。というのがポイントですね。
あんまり人に言えない趣味があるとか、性癖があるとか、誰でも大なり小なりあるもので。
優しくて人当たりのいい反面、変なところでキレるとか、思わぬことが許せないとか。
そういうのも含めて、人それぞれの個性なのでしょう。
大悟は、妻に「完璧な母親」であることを求めてしまう。それは彼自身の子供時代の体験が影響したものであるわけですが。
それによって小春は追い詰められていくわけで、見てると「お前ら冷静に話し合えよ!」とか言いたくなりますけどね。
でも、小春は小春で真面目で、いっぱいいっぱいなんですよね。
家族ぐるみで大悟の経済力に依存してしまっていて、もう戻れない…という引け目もあるし。
また、彼女自身、自分の母親を反面教師として「ああはなりたくない」と思って生きてきたから、完璧な母親になるべきと考えてしまう。それでますます、自分を追い込んでいくことになります。
経済的に夫に依存してしまって「籠の鳥」になった女性が、抑圧で我を失っていく…という構造は「Swallow/スワロウ」とも共通するテーマでした。
そこには、「Swallow/スワロウ」で追求された、女性の社会的立場の問題も背景にあるわけで。
「Swallow/スワロウ」の場合は、夫やその家族の側が無理解で無神経な「悪役」に設定されていたけど、本作の大悟はそこまで悪というわけでもないんですよね。彼なりに真面目で、真面目ゆえにおかしなことになっていく。
④ヒカリという少女の多面性
そんな不穏さを引き起こすきっかけになるのが、娘であるヒカリ。演じているCOCOさんは達者ですね。
最初、結婚するまではいかにも天真爛漫な純真少女みたいに振る舞っていたヒカリが、実はそうじゃなかったかもしれない…というのが、少しずつ見えてくる。
欲しいものを手に入れるためには手段を選ばない、平気で嘘をつき約束を裏切る、いわば「悪魔っ子」だったかもしれない…という疑惑。
ヒカリを愛したい、母親にならなくちゃ…というプレッシャーと、拭えない疑惑の間で、小春が混乱し疲弊していく。
クラスの好きな男の子の気をひきたいために、筆箱を盗まれたと濡れ衣を着せる。そのために筆箱はトイレに捨てる。
関心を引くために弁当を持たせてもらっていないふりをする。
クラスメートの葬式にも心を動かさず、赤い靴を履いていくと言って聞かない。
小春がウサギの剥製を壊すと嬉しそうに囃し立てる。
それで小春に殴られると、大悟には言わないと約束したのに速攻で破って、平然と言いつける。
そういう様々な疑惑の中で、「ヒカリはクラスメートの女の子を突き落として殺したのか?」というのが最大の焦点になるんですが。
しかし、その肝心なところは描かれていないんですよね。あくまでも疑惑にとどまる描かれ方になっています。
そして、「殺人」という大ごとが混じるのでいかにも異常な少女のように見えてしまうんだけど、それを取り除いて冷静に見れば、それは大悟の「異常性」とあまり変わらない程度の、子供ならあり得る程度のおかしさに過ぎないかもしれない…という見え方もしてきます。
映画の中でのヒカリの行動は、よく見ると常に、お手本になる行動をした誰かが存在しています。
ヒカリは好きな子の気をひくために、弁当がないとか、筆箱を盗まれたとか嘘をつくんだけど、その前にはその好きな子も「嘘をついてる」のですよね。いかにもなホラ話を女の子にして、気をひいている。つまり、ヒカリは「嘘をつくことで気を引くことができる」と彼から学んでる。
小春に殴られたことを「言わない」と約束しながら大悟に言いつけるのは性悪に見えますが、これ実は小春もその前に同じことをしています。
ヒカリがおねしょしたのを「言わない」と約束しながら、大悟に伝えている。だからヒカリにしてみれば、「されたことをやり返しただけ」という感覚でしょう。
でも、結果だけ見ればそこは見えない。小春も、自分が同じことをしていたなんてことには思いは及ばない。
先入観を除いて見れば、子供が嘘をついたり、やられたことをやり返したり、大人のように空気を読んで気を使うことができなかったりするのは「当たり前」のこととも思えるんですよね。その程度の悪さは、誰でもすることだったりする。でも、思い込みがあるとそう見えない。
で、この思い込みは、映画自体に仕込まれたところでもあるんですよね。
「こういう映画だろう」って思って観るから、邪悪な子に見えてしまう。
でも、小春に「行かないで」と泣くヒカリの悲しみは、やはり本当に見えて。
ということは、小春が母親に「行かないで」と泣いた時も、母親には違うふうに見えていたのかもしれない…。
いろんなことが怪しく思えてくる。このバランスが絶妙だと思いました。
⑤衝撃のラストが納得できる理由
で、「衝撃のラスト」に向かっていくわけですが。ここはかなり「飛躍がある」という意見が多いですね。ある種の比喩表現として捉える方も多い。
確かに、現実的にあれを誰にも止められず実行できるかと言えば、ちょっと無理があるだろう…とは思いますが。
ですが、そこへ向かってしまった登場人物の心理は、確かにそうなるしかないだろうと、しっかりと伝わるものがありました。共感はしないけどね。
ヒカリを殴ったことで大悟に「出て行け」と言われ、一旦家を出て行って、踏切で死にかけて死なず、戻ってきたシーンで、小春は「生まれ変わる」ことになります。
今度こそ、「完璧な母親」になることを小春は決心する。
完璧な母親。つまり、どんなことがあっても子供を信じ、無条件で守る母親。
大悟がいつも言っていた、「たとえ世界中を敵に回しても、我が子を守る。それが親ってもんじゃないの!」ってやつですね。それを、実践しようとする。
ヒカリが靴を盗まれたと訴えて、二人で学校へ乗り込んでいく。ここまで小春はヒカリの嘘をかなり見てきてますからね。ここでも疑いの念はあったはずだけど、それは一切出さない。ヒカリを100%信じて、大悟と二人でモンペ丸出しで学校へ怒鳴り込んでいく。それが小春の決意ですね。
これはつまり、ヒカリが本当のことを言っていようが嘘をついていようが関係ない。どっちであろうとも、親だから子供の味方をするんだという、そういう行動原理を二人は選んでいるということですね。
しかしこれは、ヒカリが「突き落としたのはヒカリちゃんだ」と告発されることで、かえって二人を窮地に追い込むことになります。
靴の件で「事実がどうだろうと」という立場に立ってしまった以上、ことが殺人であっても同じ態度をとらなくちゃならない…ということになってしまうからです。
ヒカリがそんなことをするはずがないと、本当に思っていたならば、小春と大悟はヒカリの無実を訴え、なんとかしてそれを証明する方向に発想が向かうはずだと思います。
しかし二人は、靴の件で既にヒカリを信じていない。ヒカリが嘘をついているかも…と薄々思いつつ、それでも100%ヒカリの味方をするんだ…という立場に自らを追い込んでしまっている。
そうなると、もう殺人の件でも、ヒカリを信じるという立場には立てなくなってしまうわけです。ヒカリがやったかもしれない、いやたぶんやっただろう…と思いつつ、それでも味方をする、と。
そう決意したならば、これはもう自分たちもヒカリと同じ立場になるしかない。
殺人犯になるしかない。それも、ヒカリより遥かに罪の重い、大量無差別殺人犯になるしかない…というところにつながるわけですね。
そこで、「世界中を敵に回してもヒカリを守る」というところに図らずもつながってしまう。
最後の、どう見てもめちゃくちゃな、飛躍したやり過ぎの行動が、彼ら二人の中ではきれいにつながってしまうわけです。そこが、怖い。
そして、ここであまりにも皮肉なのは、ヒカリは本当に無実なんじゃないかということが匂わされる…というところですね。
ヒカリを告発した男の子は、「ヒカリが突き落とすところを見た」と言っていましたが、彼はその時教室でなく地上にいたはずです。近くでは見ていない。また、本当に見たなら直後に告発するはずで、今頃言い出すのはおかしい。
彼は死んだ女の子を好きで、ヒカリがじゃましてくるのに気づいていたから、ヒカリを逆恨みのように憎むのも考えられることです。
それに、筆箱の件でヒカリに濡れ衣を着せられてもいますね。靴を盗んだのは彼で、筆箱の件の仕返し。そのことで両親が怒鳴り込んできたから、慌ててヒカリの罪を告発して、靴の件をごまかそうとしたんじゃないでしょうか。
気をひくために嘘を使うというのは、彼がそれまでも何度も行なっていたことです。
そして、教室にいた第三者であるメガネの女の子。彼女は、小春に「ヒカリちゃんはやってないよ、みんな信じてるよ」という手紙を渡します。
小春はその手紙を信じずに捨ててしまうのだけれど、でもなぜ小春が信じないかというと、彼女が間近で現場を見ていたことを知らないからですね。小春は、何も知らない生徒の一人が、口だけでかばうようなことを書いていると思ったのでしょう。
しかし、彼女はあれだけ間近にいたのだから、彼女がやってないと言ったということは、ヒカリは本当にやってない可能性が高いわけです。
それなのに…それをきちんと、伝えられているのに。
それは既に、小春が最悪の決断をしてしまった後なんですね。せっかくの証言者を、小春は皆と同じように殺してしまう。
そんなふうに、本作は事実がどうなのか曖昧なところが各所に作ってあって、あえて観る者に考えることを促す作りになっています。
小春と大悟の出会いである、踏切のシーンにしても、小春が大悟を助けるシーンはないんですよね。
あの時、不幸の連鎖でむしゃくしゃしていた小春は、大悟を見殺しにしようとしていたのかもしれない。
大悟は自力で踏切から這い出たけど、泥酔していたので助けてもらったと勘違いしただけかもしれない。
渡辺亮平監督はインタビューで「自分が理解できないという側の視点に立ってみることは重要」と言ってますね。
実際、小学生に対する大量無差別殺人なんて、本当にあったらそれこそ問答無用で死刑にしろ!で終わりだろうし、理解する気にさえならないでしょうね。
でも、そんな対象に対してさえも「視点に立ってみる」想像力を発揮できることが、映画の強みであって。
一定の不快感を感じさせるリスクも引き受けた上で、あえてそこまで想像力を届けようとしている。意欲的な映画だと思いました。渡辺亮平監督、注目だと思います。
渡辺亮平監督の自主制作によるデビュー作。
今作のオファーを3度断り、4度目で引き受けた土屋太鳳さんの前作。気になったけど見なかったな…