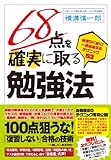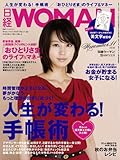横溝慎一郎行政書士合格ブログ
行政書士試験対策ブログ
プロフィール
最新の記事
テーマ
このブログのフォロワー
ブックマーク
お気に入りブログ
試験はあなたが知ってることを聞いてくれるとは限らない
テーマ:行政書士試験戦略的学習法諸法令はこれ
昨年から出題が復活した行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法。
これらをまとめて「諸法令」なんて呼んだりします。
昨年は2問出題(行政書士法と住民基本台帳法のみ)でした。
今年何問出されるかはわかりませんが、「諸法令」は得点源にしておきたいもの。
そこで、3時間で「諸法令」をしっかり学べる道場を作りました。
過去問中心の一問一答形式の問題とまとめのレジュメでゼロから一気戦える知識をみにつけていきましょう!

重箱の隅
長野県大町市などで震度5弱の地震が昨夜発生しました。
長野市も震度4だったとのこと。
その後も余震とみられる揺れが続いているようです。
付近にお住まいの方は十分ご注意ください。
さて今回はこんな話を、
重箱の隅をつつくような、という言葉があります。
私がもし使うのであれば「ここまでは知らなくて良い知識」という意味です。講義中にこのフレーズを使ったことはないですけど。
合格するためには、合格者なら間違えない問題をあなたも間違えないようにすることが大切です。
そのために必要とされる知識をきちんと押さえることで十分です。
テキストを隅々まで全て解らないといけないというのは、ウソです。
きちんとしたテキストであれば、その70〜80パーセント理解できていたらよいのです。
例えばこちらの本に書いてあるAランクテーマがわかっていれば、得点力は格段に上がります。
そこをおざなりにして、ランクCの瑣末な論点をありがたがって学ぶのは、時間の無駄です。
ちなみに、さきほどの「重箱の云々」は、受験生が使う場合、別の意味で使ってしまっている場合がありえます。
それは「自分がよくわかっていなかったことを正当化しようとしている」というものです。
以前、行政事件訴訟法14条3項を模試でだしたら、「こんな条文だすのはおかしい!」と抗議してきた方がいたことをふと思い出しました。模試だけ受けた方だったようでした。
その時点ですでに何度か本試験で出されていたこともあり、「それはあなたが知らなかっただけですよ」と優しく諭したのですが、その後どうされたのかな。
とにかくこういう発想をし始めたら要注意です。
試験はあなたが知っていることを聞いてくれるわけではありません。
あなたが知っているかどうかに関係なく、出題者が聞きたいことを聞いてくるのです。
そこを履き違えてはいけません。
おまけ
そういえば、2024年度試験では、民法において「組合」が、商法では「匿名組合」がそれぞれ出されました。
ともに、昨年の出題予想論点として「あと50日の過ごし方」で紹介していたテーマです。
合格講座や横溝プレミアム合格塾の講義でも取り上げていましたので、私の講義を受けていた方はできた人が多かったようです。
ついでに「監査委員会等設置会社」も推してました。
昨年は「設立」が選択肢ひとつしか出ませんでしたが、商法会社法は、それでも2問はとれる出題内容になっていたということです。
「匿名組合」や「監査委員会等設置会社」を「重箱の隅をつつく」という講師はいないと思いますが、独学の方からするとそうでもなかったかもしれません。
今日の東京は27度の予報です。
まだ先かなと思ってはいたのですが、25度を超えてきたので、シアサッカーのジャケットを出しました。
4月でここまで気温が上がるって、やっぱり地球がおかしくなっているとしか思えないですね。