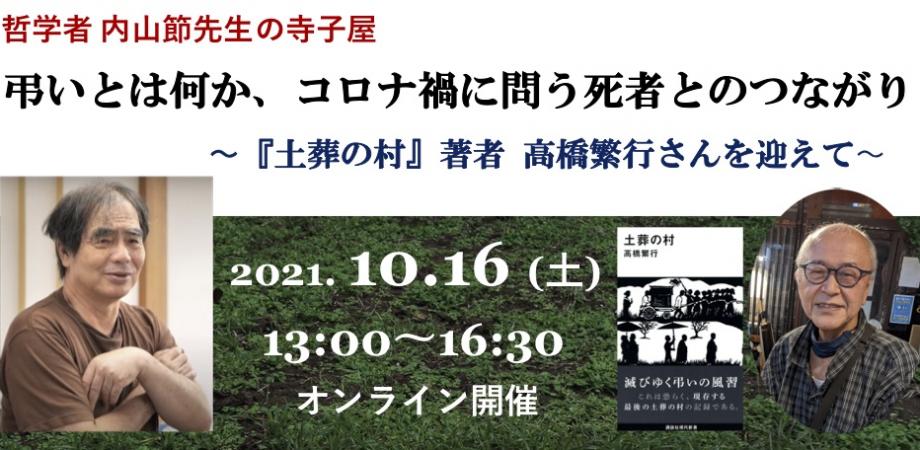小説の「作法」以前に、「小説とは何か」を問う。その問い自体が、小説を書くプロセスには欠かせないのだ、と著者は言う。
小説を書くことは人生そのものであり、彼にとっての小説観は、彼自身の人生観と不可分である。その意味で、彼の小説論を教科書的に一般化することはできないし、するべきでもない。保坂さん自身が「この本を鵜呑みにするな」と注意を促す所以であろう。けれども、ぼく自身は彼の小説論はとても「まっとう」だと思った。
面白い点を上げればきりがないけれど、ここでは思わず考えさえられた次の文章を取り上げてみたい。
「小説の次の行に書くべきことは、事前に用意されたものではなく、小説の〝運動〟によって決まるーーこの、書く人間と書かれつつある作品の力関係の一種の逆転は、小説を書くときに絶対に忘れてはいけない」
この「小説の〝運動〟」は、「人生の〝運動〟」と言ってもそのまま通じるだろう。けれども同時に、「これは疎外の構造ではないのか?」とも思った。
「疎外」はいろんな意味で使われるが、哲学的な用語としては、「人間が作り出したものによって、逆に人間が支配される」という、転倒した構造を指すことが多い。だから「貨幣の疎外」と言えば、「人間が作り出した貨幣によって、逆に人間が支配される」ことだし、「宗教の疎外」は、「人間が生み出した宗教によって、逆に人間が支配される」ことである。ちなみに「貨幣の疎外」は社会主義者であるモーゼス・ヘスが主張し、「宗教の疎外」はフォイエルバッハという哲学者が主張したことで知られる。
数ある疎外論のなかでも有名なのは、マルクスが展開した「労働の疎外=労働疎外論」だろう。資本主義社会においては、労働者が労働によって作り出した商品が労働者のものにならず、資本家の資本に転じる。その資本によって、労働者が逆に支配されてしまう。さらには、労働の内容自体も労働者にとって疎遠なものとなり、人間は人間性を喪失してしまう、とマルクスは主張する。
さて、ここで保坂さんの小説論に立ち返ってみる。
彼によれば、「小説の次の行に書くべきことは、事前に用意されたものではなく、小説の〝運動〟によって決まる」。そしてそれを、「書く人間と書かれつつある作品の力関係の一種の逆転」と表現している。これは一面において、「作家によって書かれつつある作品によって、作家が支配される」という疎外の構造として見ることもできる。
ところが保坂さんは、小説を書くためにはぜひともこの運動が必要なのだ、と言うのである。ぼくもそう思う。文章が本当に面白くなるのは、書き手の事前の構想を超えて、文章自体が自己展開するときだと思う。そのとき、文章は〝生きもの〟としての生命力を獲得する。これを、ここでは仮に「小説の疎外」と呼んでおこう。
それに対して、ヘス、フォイエルバッハ、マルクスらが主張した「貨幣の疎外」「宗教の疎外」「労働の疎外」は、人間本来の生命力を喪失させるものとして展開する。この違いは一体何なのか。それがわかれば、現代人が縛られている「疎外の構造」を克服するヒントになるかもしれない。
これについてはいろんな分析ができると思うけれども、大きいのは、その対象が、人間の生命活動と具体的に結びついているかどうか、ということのような気がする。
保坂さんが言うような「小説の自己運動」を生み出すのは、書き手と世界との関係がその作品に反映される時であり、別の言い方をすれば、「小説の自己運動」とは書き手の生命活動の反映でもある。このとき、書き手と作品は相互に影響し合う、具体的関係の内にある。「小説の自己運動」は「作者の生命活動」と一体である。
それに対して「貨幣の疎外」では、貨幣は、人間同士の類的交流が外化したものである。それは市場経済の中で人間から疎遠なものになり、個人と貨幣との関係は抽象的なものへと変換されている。要するに、「人間同士の具体的な交流」が、「貨幣を介した抽象的な交流」に置き換えられてしまっている。言わば「交流なき交流」である。人間の生命活動の根源は他者との交流の中にある。とすれば、ここでは主体としての人間の生命活動が失われてしまっている。
「宗教の疎外」における宗教とはキリスト教のことだが、フォイエルバッハによれば、キリスト教の神は、人間の本質である「愛」が外化したものであり、人間が生み出したものである。ところが、この人間が生み出した神によって、人間の生き方が規定される。ここでは「神と自己との関係」こそが重要なのであって、「自己と他者(人間)との関係」は二次的なものにすぎない。しかし「神」が人間が作り出した「概念」である以上、神との関係は抽象的なものにならざるを得ない。ここでの主体は人間ではなく「神」なのである(とフォイエルバッハは言っているのだと思う)。
「労働の疎外」においては、労働者が生み出した商品は資本家の資本に転じ、労働者にとって疎遠なものとなる。それだけでなく、より商品を効率的に生産するために、労働は「分業」という形をとるようになる。それまでは、まさに作者と小説との関係のように、自身の生命活動の反映でもあったはずの労働が、生産活動の「一部分」だけに関わるようになり、労働自体が抽象的なものへと変えられてしまう。こうした労働をしているうちに、人間自身もまた自己を抽象的な存在として感じるようになる。それは人間の生命力の喪失につながる。
……ごちゃごちゃとわかりにくいことを書いてしまったが、要するにこういうことではないかと思う。
疎外とは、「人間が作り出したものによって人間が支配される」構造だが、「人間が作り出したもの」との具体的な相互関係がそこに維持されていれば、それは人間疎外を生み出すのではなく、むしろ人間の生命活動の発現を促す。それは疎外の運動のプロセスにおける「外化の程度」の問題なのかもしれない。その対象と「顔の見える関係」を結べている限り、その運動は人間から自立したものではなく、自己と対象との一体的運動として成立している。
しかし、いわゆる人間疎外を生み出す「疎外」では、人間が生み出した対象が人間と相互関係を結ばず、自立した自己運動を開始する。その自己運動は、もはや人間の生命活動を反映していない。人間から完全に外化・対象化し、システムとして固定化することによって、むしろ人間を振り回す。
保坂さんの小説論は、このような疎外、すなわち「自己の生命活動のシステム化」の罠に捉えられないための作法なのではないだろうか。保坂さんにとって小説は生きることそのものであり、生命活動そのものである。それがシステム化されてしまった時点で、もはや小説ではあり得ない。
保坂さんの言葉を借りれば、「事前に用意されたもの」に固執して小説を書くことこそが、本来的な意味での「小説の疎外」を生むのであって、そうなると小説と自己との関係は運動性を喪失し、閉じてしまう。そのような「閉じた小説」を書くことは、小説家にとって「閉じた人生」を生きることにほかならないはずである。
小説も、人生も、システム化された時点で、その醍醐味を失う。保坂さんの小説論は、この「システム化」への抵抗の論理なのだと思う。そう考えれば、保坂さんがいわゆる「プー太郎」に対して親近感を感じているもうなずける。保坂さんは別の著書で次のように書いている。
「規則正しく労働することに本質的に向いていない人が、世の中には必ずいるものなのだ。プー太郎まで労働に駆り出されるような社会は最悪の社会ではないか」(『「三十歳までなんか生きるな」と思っていた』草思社)
ぼくはこの言葉が大好きなのだが(笑)、要するにプー太郎とは、この資本主義社会のシステムに抗う存在なのである。もちろんほとんどの場合、当人にそんなつもりはないだろうけれども。
だから、本書は小説論としてだけでなく、人生論としても読むことができる。ほんの小さな出来事が、その人の人生を大きく変えてしまうことがあるように、小説も、主人公の小さな心の変化が、その後の展開に大きな影響を与える。
「小説は〝細部〟が全体を動かすという独特の力学を持っている表現形態なのだ」
彼の小説観は、人生のままならなさと同時に、希望のない人生などないのだ、ということも教えてくれているような気がする。