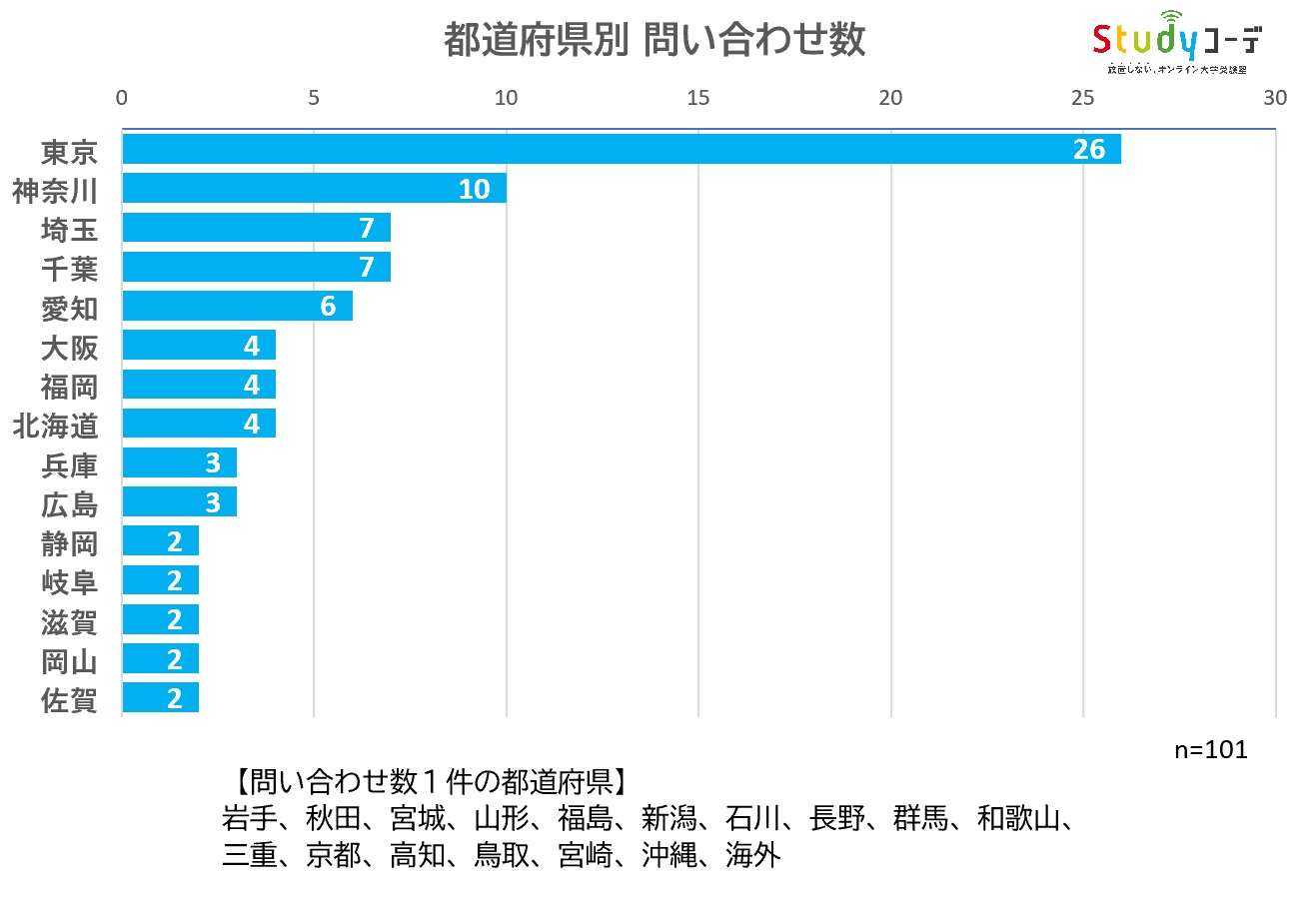「大学っていくつ受ければいいんですかー?」
たまに生徒から聞かれる質問です。
人それぞれ受験戦略があるわけですから、
一概に何校受ければ良いということは言い切れません。
ただそれだと答えになっていないので、
まずは一般的に言われている志望校の考え方についてお話をしています。
上の図の通り、志望校は基本的に3ランクに分けて考えます。
・「難易度が高いけど絶対に行きたい」と思える第一志望群(チャレンジ)
・「まー自分の実力的にはここかな」という第二志望群(実力相応)
・「ここは流石に受かるだろう」という第三志望群(滑り止め)
そして、上から順に1~2校、2~3校、3~4校程度とピラミッド型に考えておくと良い。と言われています。
例えば、浪人はしたくないけど日程が許す限り受験をして早慶を目指したいという学生は
・第一志望群⇨2校(早慶上理レベル)
・第二志望群⇨3校(GMARCHレベル)
・第三志望群⇨4校(日東駒専レベル)
といった志望校戦略になります。
ただし、受験校を増やしすぎると対策することも多くなる+お金も多くかかってきます。
そのため、浪人覚悟で第一志望校1校のみ(特に、東大など難関国公立に多いパターンです)という学生も一定数います。
ここの判断は
・自分の学力
・受験にかけられるお金
・浪人OKかNGか
・どれだけ第一志望にいきたいか
など変数が多くなってくるため、正解はありません。
後悔のない受験をすればそれで良いのだと思います。
ちなみに私の場合は、早慶以上でないと浪人をするという意志でしたので、
・第一志望群⇨1校(東大)
・第二志望群⇨2校(慶應、早稲田⇨受験票はとったが未受験)
・第三志望群⇨なし
という戦略で行きました。
感覚的に、第一志望群が国公立の生徒の場合は受ける大学数は少なく、私立の場合は6~10校程度受けているように感じます。