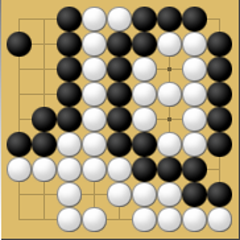囲碁の1手目は黒から打ち始める。という意味の先手ではなく、対局の途中で、
「この手は先手だ」
というように使われる、先手、後手についての話です。
先手であるとは、自分が打った手に相手は必ず受けてくれる、という意味です。
なぜそんなことが言えるのかというと、
もし受けなかったら、勝敗を決するような次の良い手があるから、です。
人間の碁打ちとしてはこの説明で十分理解できますが、プログラムを作るのにはあまりに不十分です。
もう少し、定量的に、数学的に表現できないと、とてもプログラムにはできません。
順を追って説明しますね。
囲碁には普遍的な考え方があります。
それは、大きいところから順に打つ、というものです。
大きいとは、一体何が大きいことなのか。
1手の価値です。
(以下は、ちょっと暴論っぽいですがイメージですのでご容赦)
例えば、黒が初手を隅の星(じゃなくても良いですが)に打ち、白が投了したとします。
結果は、黒の360目勝ち(コミは無視)ですので、黒が打った1手の価値は、360目になります。
2手目に白が反対側隅の星に打ったとします。局面は均衡に戻りました。
つまり、白の2手目によって、黒白1手ずつの価値は180目(正確には179.5目)になりました。
以降、1手打つ毎に1手の価値はだんだん下がっていきます。
最後に、1手が1目の手を打ち、それ以上打っても地が増えないかさらには損になる手(価値がマイナスの手)しか残らなくなったらお互いにパスをして終局です。
さて、先手になる、ということは、この1手の価値と密接に関係しています。
ある時点で打った1手の価値がm目だったとき、そこを手抜きした結果、次の相手の1手の価値がm目より大きくなるなら手抜きが出来ない、つまり先手である、ということです。
なぜなら、大きいところから順に打つのが原則なのですから、手抜きして他を打って、相手にそれより大きい手を打たれたら明らかに損だからです。
あ~、もう理屈っぽいですねえ。笑
でも、これはつまり、1線ハネツギみたいに当然先手だろう、と思うような手でも、他にもっと大きい手があれば手抜きして良い、ということでもあります。
プロなどが、「これは単にヨセの手。まだ早い」と説明することがありますが、実はヨセだからまだ打たないのではなく、そのヨセの手より価値の大きい手が他にあるからまだ打たない、ということなのです。
「この手は先手だ」
というように使われる、先手、後手についての話です。
先手であるとは、自分が打った手に相手は必ず受けてくれる、という意味です。
なぜそんなことが言えるのかというと、
もし受けなかったら、勝敗を決するような次の良い手があるから、です。
人間の碁打ちとしてはこの説明で十分理解できますが、プログラムを作るのにはあまりに不十分です。
もう少し、定量的に、数学的に表現できないと、とてもプログラムにはできません。
順を追って説明しますね。
囲碁には普遍的な考え方があります。
それは、大きいところから順に打つ、というものです。
大きいとは、一体何が大きいことなのか。
1手の価値です。
(以下は、ちょっと暴論っぽいですがイメージですのでご容赦)
例えば、黒が初手を隅の星(じゃなくても良いですが)に打ち、白が投了したとします。
結果は、黒の360目勝ち(コミは無視)ですので、黒が打った1手の価値は、360目になります。
2手目に白が反対側隅の星に打ったとします。局面は均衡に戻りました。
つまり、白の2手目によって、黒白1手ずつの価値は180目(正確には179.5目)になりました。
以降、1手打つ毎に1手の価値はだんだん下がっていきます。
最後に、1手が1目の手を打ち、それ以上打っても地が増えないかさらには損になる手(価値がマイナスの手)しか残らなくなったらお互いにパスをして終局です。
さて、先手になる、ということは、この1手の価値と密接に関係しています。
ある時点で打った1手の価値がm目だったとき、そこを手抜きした結果、次の相手の1手の価値がm目より大きくなるなら手抜きが出来ない、つまり先手である、ということです。
なぜなら、大きいところから順に打つのが原則なのですから、手抜きして他を打って、相手にそれより大きい手を打たれたら明らかに損だからです。
あ~、もう理屈っぽいですねえ。笑
でも、これはつまり、1線ハネツギみたいに当然先手だろう、と思うような手でも、他にもっと大きい手があれば手抜きして良い、ということでもあります。
プロなどが、「これは単にヨセの手。まだ早い」と説明することがありますが、実はヨセだからまだ打たないのではなく、そのヨセの手より価値の大きい手が他にあるからまだ打たない、ということなのです。