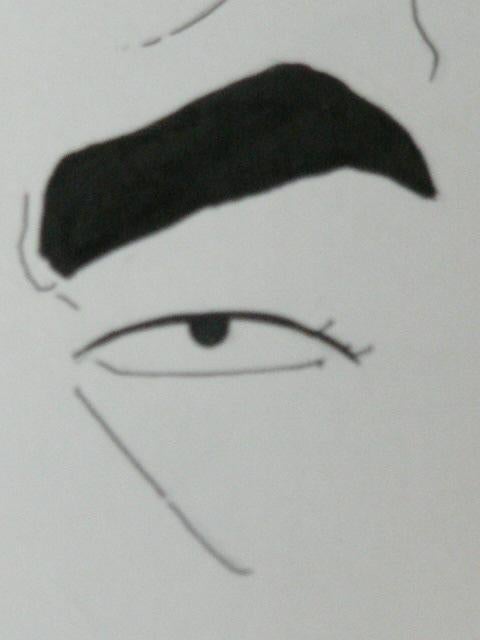星ヶ嶺、斬られて候
城の探訪記、相撲、歴史等の雑文を掲載しています
プロフィール
テーマ
月別
最新の記事
お気に入りブログ
このブログのフォロワー
ブログ内検索
ブックマーク
2025-04-09 15:18:14
羽茂城(新潟県佐渡市)
テーマ:北陸の城
新潟県中越地方の西方30kmほどの所に浮かぶ佐渡島。
その面積は850平米に及び、北方領土を除く日本の離島の中では沖縄本島に次ぐ広さを誇ります。
近世以前は一島をもって佐渡国であり、時は流れて今日では全島が佐渡市の範囲。
但し平成の大合併以前は両津市を中心に7町2村の10の自治体からなっており、このことをもってしても佐渡の広さが実感できようというもの。
昨年(令和6年)には「佐渡島の金山」が世界遺産に登録され、注目を集めているエリアでもあります。
かくの如く佐渡といえば金山とトキというのが多くの人が持つイメージではないかと思ひますが、その金山が多く開発されるのは江戸時代以降のことであり、それ以前の中世においては三川砂金山、鶴子銀山が知られているくらいで、なおゴールドラッシュが訪れてはいませんでした。
そのせいもあってか、島内には有力な大名といふ存在が育つことはなく、中小の国人が割拠する状態に―。
中でも守護代の地位を得て佐渡中原に覇を唱えた本間氏が有力な国人でしたが、その本間氏も庶子家が分立して独立性を強めたためについに一島全域に号令するやうな勢力は現れませんでした。
雑太、河原田、久知、多田、吉岡、潟上、沢根、吉住、宮浦といった諸家が分立した本間氏の中で、島の南東を中心に島内でも一、二を争う勢力を有したのが羽茂本間氏でした。
本間氏は元は相模の豪族で、武蔵七党のうちの横山党・海老名氏の流れですが、佐渡国内に分立した本間諸家の中にはこの系統に属さない家もあり、どちらかというと血縁よりも地縁が重視された党のような存在だったのかも―。
数多の本間家の中でも惣領家であったのが雑太(さわだ)本間氏であり、羽茂家はその分家の河原田本間氏より出たらしいが必ずしも分明ではありません(吉岡本間家の分家とも)。
大永年間(1521~28)には羽茂本間氏が雑太本間氏を攻めて「前代未聞の弓矢」と称される戦乱となり、これにより惣領家の力が減退、羽茂本間家台頭のきっかけとなった。
羽茂本間氏の領域は概ね佐渡の南東部であり、これに対し中部に勢力を展開したのが河原田本間氏で、佐渡の戦国はこの両家を軸に展開してゆきます。
羽茂本間氏が本拠としたのはその名の通り羽茂本郷であり、居城を羽茂城といいました。
本郷の集落の東方、比高80mほどの山上に築かれた城は殿屋敷と呼ばれる平場を中心としたエリアと北東の北ノ城、その南で殿屋敷ブロックとは谷を挟んで向かい合う厩・馬場エリアに三分され、さらに殿屋敷―厩エリアに挟まれた谷間も城内として屋敷などが置かれたのでせう。
‹主郭の五社城に建つ五所神社(十王堂)›
殿屋敷エリアは北の殿屋敷に対して南に奥方屋敷、南東に元屋敷が一段低くあり、殿屋敷内の北西が壇上の高まりとなって五社城と呼ばれ、平場を挟み南に南ノ城、その西方に三の城、二の城が続き、殿屋敷と元屋敷の北には荒神城が北ノ城と対峙するやうに高く屹立して北縁に土塁を巡らせる厳重ぶり。
また西麓には平時の居館と城下が開かれるなど、小規模の城館の多い佐渡では破格に大きい規模の城でした。
‹荒神城と北ノ城の間を隔てる堀切。切通し道となっており、T字路となっている所に東門があった›
羽茂本間氏の領域内には羽茂本郷から南に2kmほどの羽茂港、さらに西方には小木港、宿根木港、東方には赤泊港といった港湾を擁し、その地勢的な要因もあって越後守護の上杉氏とは緩やかな従属関係を結び、その後ろ盾を利してなお勢力を伸ばすやうな勢い。
これに先立つ永正6年(1509)には越後守護職の上杉家当主の座を巡る混乱から関東管領の上杉顕定と対立して越中に逃れていた越後守護代・長尾為景を佐渡に迎え入れ、翌7年の越後への反転攻勢に助力、この功により羽茂本間家は越後国内に所領を得たばかりか、越後の実験を握った為景とは強い紐帯で結ばれることとなり、その縁は為景の子の上杉謙信に引き継がれていたのです。
羽茂本間氏はこうした上杉氏との関係を名目にして佐渡における勢力拡大を図って河原田本間家らと構想を繰り返している状態でしたから、上杉謙信や景勝による佐渡の戦乱の調停も中々上手くいかない。
最終的には豊臣秀吉の内諾もあって天正17年(1589)に上杉景勝が軍勢を率いて真野より佐渡に入り、自らの軍事力によって佐渡平定に乗り出し、とりわけ頑強に抵抗した羽茂本間氏であったがあえなく羽茂城も落城し、当主・高茂(高貞)は越後へ逃れるも捕えられて処刑されました。
これにより佐渡を掌握した上杉景勝は同地を直轄領として羽茂、沢根、小木の三か所に城将を配置、すでに開発されていた金銀山を管理下に収めます。
残置された羽茂城の城将となったのは富永長綱、ついで黒金尚信で、慶長3年(1598)に上杉氏が越後から会津に移った後も佐渡は上杉氏領として残されましたが、関ケ原の敗戦により佐渡は江戸幕府の直轄領となり、羽茂城も廃城となりました。
この際、建物の一部は小木港を統括する陣屋である御役屋に移築され、また伝承では羽茂本間氏の菩提寺である大蓮寺にも東門が移築されたとのことで、この門は現存しています。
現在の羽茂城は北ノ城に民家がある他は山林となっており、過去の戦乱の歴史を忘れたやうに今はひっそりと佇んでいます。
島内の公共交通機関は基本的に路線バスであり、羽茂を経由する路線はいくつかありますが、小木と佐和田バスステーションを結ぶ新潟交通小木線が最も一般的なアクセス手段。
城址へは羽茂高校前の停留所が最寄です。
‹杉林となっている殿屋敷内›
‹五社城東面の切岸›
‹元屋敷東の虎口。右の高まりが荒神城›
‹腰曲輪状の二ノ城›
‹奥方屋敷南方の不開門址›
‹城域東の厩跡。南に伸びる馬場は藪になっている›
‹羽茂城址略図(現地案内板より)›
‹東門と伝承される大蓮寺山門。但し棟札によれば貞享3年(1686)の築で、門扉が古い材に見える›
2025-03-26 16:37:43
大相撲の東西論(下編)
テーマ:相撲史考今回も始まりはトザイ、トーザイ。
相撲における東と西にまつわる話の3回目です。
前回の中編では番付の話にて終わりまして、その記載法においても東が優位である、と述べました。
ところが少し視点を変えてみるとやや様相が変わってきます。
例えば色。
現在の土俵では上に吊るされた屋根の四隅に四色の房が垂れていますが、これは元々、屋根を支える柱を意味しており、同時に結界として内外を分けるものでした。
この中で東(北東角)の房の色は青(緑)であり、西(南西角)は白房。
つまり色の点では東が陰、西が陽となってしまうのです。
さらにこの房は季節や五行を表わしてもいるのですが、東は木、西は金であり、五行の相克関係でいえば金の方が勝ちとなる。
尤もこの点は四本柱の中で親柱と定められていた北(北西角)の柱の色が黒であり、陰。
対峙する南が赤で陽となるのですが、五行では北が水、南が火であり、相克関係でいえば当然、水が強い訳ですからここでは色とは逆の結果となります。
ちなみに今日の感覚だと白→勝ち、黒→負けとなってしまいそうなんですが、元は勝ちは●で表現されて単に星と称していたのを明治に入って新聞紙面で勝ちを〇、負けを●で表わすようになったから白星、黒星の名称も生まれたという次第で、四股名などを見渡してみても黒を忌諱するような傾向は見られません。
但し黒に対してはマイナスイメージが全くなかったという訳ではなく、死の穢れを黒不浄と称する例もありました。
同じく北に関しても敗北に通じるなどとしてこれを忌諱する動きもなきにしもあらず―でしたが、土俵上に関する限りは正面がどちらであれ北が優位であり、決して敗北―勝南という関係性にはなりませんでした。
あくまで北を主体(チュチェ)とする思想が一貫して揺るがなかったのです。
かたや東と西の関係性はより流動的。
建前として東を陽、上位としながら、太陽の軌道と同じく、東西における陰陽は絶えず変化するものであり、実際の勝負においても時として東が勝ち、時として西が勝つというように東西のいずれもが陽にも陰にもなり得たからです。
ただ、ところ変われば東西(ドンシー=もの)が変わるやうに制度もいささか変わってくる。
近世、江戸相撲を頂点とする角界の中では異端ともいふべき存在として、現在の岩手県から青森県東部及び秋田県鹿角地方―すなわち南部藩領を地盤とした南部相撲というのがあり、いわばメジャーリーグに対する独立リーグの気風がありました。
この南部相撲では江戸流とは異なり、西を重んじる風潮があったやうで、その理由をたどれば南部流の開祖・長瀬越後が京都相撲(西国)の行司であったからださうです。
行司が力士を呼び上げる際も東は「東方相撲」というのに対し、西は「西方御相撲」と露骨だったようで、あえて吉田司家に対抗する意図があったからだとも―。
とはいえ基本的な順序としては東が陽なのであり、番付においても東が上と見做されていました。
すでに述べたように寄せ相撲では寄方が東となる慣例があったやうですが、これは元方が賓客である寄方に敬意を表して上座に置いたとも解釈できる。
江戸相撲では寄方といえば上方の相撲集団でしたが、その集団が西日本から来ていたとしても番付では東に配分されるのが常でした。
ただし東が上だからといって東大関が西大関より上であるというような個別の番付における東西を跨ぐ比較には意味はありません。
それはいかに好成績を挙げようとも元々の方屋が西ならば序列は西のみで完結されて、原則として東になることが出来ないからです(東西の均衡を図るために東西が変わることはある)。
当代最強をうたわれた横綱免許の谷風や大関の雷電も番付は常に西でした。
余談ながら江戸時代には様々なものを格付けして番付に仕立てる‘見立番付‘が盛んに作られましたが、これらの中でも名所や名店などでは実際の所在地に基づいて東と西に振り分ける事例が見受けられます(そうでない場合の方が多い)。
例えば温泉の番付ならば東大関が上州草津、西大関が摂州有馬といった具合。
見立番付においても東西は使い勝手のよい区分方法である一方、東西の序列が曖昧であるという点はかえって都合が良かったのでせう。
閑話休題―。
こうしたいわゆる東西の固定が崩れるきっかけとなったのがやはり明治42年の国技館の開館でした。
この場所より東西優勝制度が導入され、東西それぞれの幕内力士の勝ち星の合計が多い方が優勝となり、翌場所の番付で東に回るという一大エポックが実現したのです。
それでもこの制度においてなお番付の序列は東西の中で完結するために東大関が西大関の半枚上とはなってこない。
個人の成績がいかに良くてもと東西対抗で優勝できなければ西となってしまう訳で、ここにおいてもあくまで東は東、西は西なのである。
皮肉なことだが東大関>西大関>東関脇のような東西における半枚の差は東西対抗性という秩序が崩れ、一門系統別の取組編成が実現してより有効となる。
そのきっかけとなったのが昭和7年の天竜事件で、この時、同一陣営の力士の大量離脱が起きたために東西の均衡を保つことが出来なくなり、いよいよ番付の上で東西を分けていた壁が崩壊し、力士が東西を自由に行き来するようになったのです(昭和15年~22年の間は東西制が復活)。
ベルリンの壁の崩壊に先立つこと、実に60年近くも前のことでした。
これによりそれまで同陣営にあったために実現しなかった好取組がより多く組めるようになったというメリットをもたらし、さらに時代は部屋別総当たり制(昭和40年~)へと推移しました。
今日における東西は番付の格付けと力士の立ち位置及び使用する支度部屋をわける以上の意味はなく、力士の中にも東西の意識は希薄になっていると言えるでせう。
実は、こうした東西に対する意識の低下は相撲会場における東西の位置関係にも通底するやうで、両国国技館では正面を木戸のある西としたために東が実際の方位では北、西が南となってしまっている。
他の地方場所でも会場のメインゲート側を正面とするのが原則で、大阪、名古屋(~令和6年)では国技館同様に西が正面、九州場所の福岡国際センターに至っては南が正面のため実際の方位の西が東になるといふチバニアン的逆転現象を生む事態に―(蔵前国技館は正面が南東で、福岡に近い)。
この辺りはムリ偏にゲンコツの頑なさと、状況に応じて柔軟に対応するしなやかさが同居する大相撲特有の硬軟を併せ呑むしたたかさを見るようです。
今日、東西が強く意識されることがあるとすれば最高位たる横綱の中でも最上位となる東正横綱を誰が占めるかどうか、あるいは東であれば勝ち越せばまず十両への昇進が約束される幕下筆頭の地位くらいではないでしょうか。
最後に大阪における大相撲の維持員組織である東西会にもふれておきませう。
大阪で開催される3月の春場所で土俵周りにジンドル、あの海老茶のちゃんちゃんこのお歴々といえばわかりやすいでしょうか。
いわば大阪における溜会で、この会員は溜席に座ることが出来ます。
会の発足は昭和12年といいますから昭和2年に大阪相撲が実質的に東京相撲に併呑されてより10年後のこと。
浪花のタニマチ筋の心意気を感じますが、ここで東西の名を組織名に冠したのは、東西制から一門系統別の取り組体系となって東西の意義が薄れてなおこの語が相撲を象徴していると見做されていたからと言えるかもしれません。
以上、長くなりましたが相撲における東西問題に関する古今東西(あれやこれや)を集めてみました。
締めとしてこんな川柳を一句―。
東西はあれど裸のすまふとり
これにて本論の打ち止めと致します。
2025-03-13 16:32:24
大相撲の東西論(中編)
テーマ:相撲史考さて、改めましてトザイ、トーザイ。
大相撲の東西を巡る2回目でございます。
前回は東西が陣営(方屋)として意味を持っていた、といふ所から余談などを差しはさんで終わりました。
相撲における陣営という点ではもう一つ、元方(勧進方・本方)と寄方(よりかた/よかた)という区分がありまして今回はここよりお話しいたしませう。
相撲興行はかつて寄せ相撲といって勧進元となる団体が他の団体を招待して挙行されるパターンが多かったのですが、この時、招待される側のことを寄方といいました。
当然、この場合は双方の陣営の対抗戦となる訳で、番付もそれぞれの陣営で編成して取組における実力の均衡化を図ることで熱戦を増やそうという思惑。
今日の神事角力でも集落や組に分かれての対抗戦となるものがありますが、これなどはかつての寄せ相撲に近い形を維持していると言えそうです。
江戸時代の大相撲では江戸、大坂、京都が三大メジャー団体として並立しており、それぞれに江戸と上方を行き来して興行する寄せ相撲のスタイルが続いていました。
18世紀前半の江戸の番付を見ていると東に上方の力士が配される傾向が見出されますが、これはまさに寄方としての立場が維持されていたからでせう。
この時の東西は実際の力士の所属母体の位置関係、すなわち上方が西という訳ではなく、寄方が東という慣例があったやうです(当初は勧進方が東であったとも)。
ところが次第に江戸相撲が一強化し、上方相撲が江戸のマイナーリーグ(3A相当)へと変じてゆくと当然、従来の寄せ相撲のスタイルは維持が出来なくなってくる。
変わって東西の陣営を分ける上で重視されるようになったのがお抱え藩で、こうなってくると個々の藩の力士の勝敗こそが重視され、従来の東西対抗という側面は薄れてしまいました。
同時に番付の編成システムも同一団体=江戸の相撲会所の中だけで完結できるようになり、その権を握った筆頭、筆脇及び番付版元の三河屋の専権事項としてブラックボックス化していくのですが、そのあたりはまた別の機会に…。
では、番付面における東西はいずれが上位せでう。
結論を先に申しますと答えは東。
何故かといえば言えば東が陽であるからで、例えば『古今相撲大全』(1763年・木村政勝著)には「左方を陽とし、右方を陰となす」とあります。
太陽自体は日本では南東から南西へと動いているのですが(実際は地球が動いている)、東は太陽が昇る方位であり、まさに旭日昇天。
地名でも東は常陸であるし、西は日向、古くは聖徳太子が「日いずる処の天子、書を日の没する処の天子に致す」としたためて隋の煬帝の不興を買ったのは皆さんもご存じでせう(但し中国の皇帝にとって唯一無二である天子を用い、さも同等の如き書きぶりが癇に障ったとも)。
土俵開きにおける方屋開口でも「清く明かなるもの陽にして上にあり、これを勝ちと名づく」とあり、東の優位性は明らかです。
<番付に見る東の文字。意外と小さい・・・>
歴史を紐解けば奈良・平安の頃の相撲節会時代は左方、右方に分かれており、この場合は左方が上位。
この辺りは官位などの発想と同じで、左大臣と右大臣であれば左大臣の方が上です。
では、左の基準とは何か―というと相撲節会の場合は主賓は天皇であり、その天皇の御座候所を正面としてその左手が左方となります。
余談ながら寺社の金剛力士や狛犬には阿吽の別がありますが、これも本堂や拝殿から見て左が阿形、右が吽形とするパターンが多い。
これも物事の始まりたる「阿」が日の出に通じ陽、終わりに当たる「吽」を日没に通じる陰としている故なれば―。
同様に今日の大相撲でも正面である北を基準に左が東、右が西となっています。
ただ、この正面というのが実は厄介。
というのは今日でこそ正面は北ですが、元々は南が正面であったからです。
南が正面といふことは今日とは反対に行司が立つのが北側であり、この北から見た時の左が東、右が西であるということ。
南を正面とする発想は元々、相撲が野外で行われていたからと思われ、北を正面とすると逆光となり、横綱の土俵入りなどでは観客が陰翳の濃いシルエットを見ることになってしまいます(観念的には北が南に対して上位であるという考えもあったのでしょう)。
こうした南正面の考え方はやはり野外興行である芝居などでも適用されたようです。
同時に左右の思想も芝居には適用されていて、正面に対し左(客席から見て右)を上手、右を下手と言って、上手を優位としています。
ところが明治42年、相撲の殿堂である国技館が落成すると、まず天気の問題が解消され、さらに順光・逆光の問題もある程度、解消されます。
同時にこの国技館では天皇等の来臨を仰ぐべく貴賓席を新設、その位置は「天子、南面す」という中国の教えに基づいて北側に配置され、これが新たに正面の基準となったのです。
この時、本来の正面の座を明け渡したのが行司であり、以後、向正面と呼ばれるようになった南側に立つようになります。
そして横綱土俵入りも北側を向いて行われるやうになったのです。
ここで印刷された番付表をご覧下さい。
中央に「蒙御免」と大書され、右に東、左に西の力士が並んでいるのが確認できたかと思ひます。
この右に東が来る形は北を上とする現代の地図を見慣れた身には違和感なく受け入れられるのですが、この番付においても基準となっているのが中央の「蒙御免」であり、ここを北として行司の名が配され右が東、左を西と割り振っているのです。
同時に東を右に配置した時点で、東の優位性が補強されることにもなる。
それは日本語の縦書きが右→左と流れてゆくからで、番付も右が横綱もしくは大関で、以下、左に流れて関脇、小結、前頭と続きます。
この並びである以上、右手の東が当然の如く左の西に対し優越的地位を得ることとなる訳です(古い番付では上下に東西を配し、東を上段とするものもある)。
以上、番付における東上位の謎について論じた所でまた次回へ続きます。
2025-02-28 13:41:15
大相撲の東西論(上編)
テーマ:相撲史考トザイ、トーザイ。
さて、今回は相撲における東西の謎を取り上げたいと思います。
相撲の東西と申しますと単に方位を表わす言葉ではなく、取組上、または番付上で重要な意味を持つ言葉です。
取り上げますのは、
何故、東と西なのか―
何故、東が上位とされるのか―
・・・などの疑問、質問、オブジェクション。
ちなみに冒頭のトザイ、トーザイ(東西東西)とは、「東西の皆さま、お静まり下さい」という意味の口上の前置きで、相撲の他でも芝居などで使われる言葉ですが、あえて東西という方位を入れていることに相撲との親和性を感じさせる。
大相撲では結びの一番の呼び上げで、行司の口上の前に呼出しが柝を鳴らしつつ発声することでおなじみです。
そもそも大相撲における東西とは何でしょう?
まず押さえておきたいのは取組における力士の立ち位置で、即ち正面(概念上の北)より見て左手が東、右手が西ということになります。
これはボクシングやプロレスにおける赤コーナー、青コーナー、野球でいえば一塁ベンチ、三塁ベンチに相当するもので、行司の軍配もあらかじめ定められた力士の東西に基づいて挙げられます。
さらにいえば本来の相撲の東西は単一の取組における力士の立ち位置を定めるだけではなく、力士が属する陣営(方屋)としての意味を持つものでした。
東西の区分は番付にも存在していて今日でこそ東と東の番付同士の力士でも対戦がありますが、かつては東の番付の力士は西の番付の力士としか対戦しない(但し近代以降は幕内以上のみ)という時代が長く続いてきた訳でして・・・。
本来の相撲は個人の競技というばかりではなく、東と西の対抗戦という意味も帯びていたのです。
では、東西の区分がいつ頃からあったのか―というとこれが分明ではない。
平安王朝の宮廷行事であった相撲節会では左方、右方という陣営に分かれていて、おそらくこの形が後年の東西になっていくのではあるのでせう。
『相撲隠雲解』(1793年・式守蝸牛著)には「朝廷節会ノ礼、東西ト云コトナク、左右ト唱フ、左方ハ元方、右方ハ寄方ト見エタリ」とあります。
一説には天正8年(1580)、安土城下において行われた竹の両端を持って引っ張りあうといふ竹相撲に由来するともされていて、この際、いずれ劣らぬ剛力を発揮してついに引き分けとなった二人に対し、織田信長がそれぞれ東、西を名乗らせたのが始まりであるとも―。
この東家、西家の末裔は今でも健在であり、関連する古文書も伝存しているので信憑性が高そうですが、そもそも相撲においては東と西の陣営に分かれるならいがあり、信長もそれに準拠したとも考えられます。
古文書も一時史料ではないながら東と西の使用例としては最も古い部類のものとして注目されてもよいのでしょう。
相撲節会時代にはすでに力士たちの出身地―即ち今日でいう所の東日本・西日本である東国・西国といった生国ごとに左方・右方に召集されたとも言いますが、はっきりと東西に分かれていると言えるのは実は番付面での記載であり、その確実な事例としては享保年間(1716~36)まで待たなければなりません。
なお、延宝年間(1673~81)の成立とされる『相撲強弱理合書』(木村孫六著)には土俵成立以前の事情を述べて「古例は勝負の場所五六間を明け、其余に東西を分けて並居たり」とあります。
これが何故、東と西で、北や南ではないのか―というと日本の内でかつては海内の範囲であった本州・四国・九州の範囲が東西に長い構造であり、これを二分するとすれば当然、東と西になる訳です。
あるいは元々は出身地に基づく陣営配分をしていたのかもしれませんが、後に形骸化して東と西といふ名だけが残ったのかもしれません。
さて、東西にはもう一つ意味がありまして、それが陰陽、すなわち太陽の通り道としての側面です。
私は以前、カンボジアのアンコール遺跡を訪ねたことがあるのですが、所々に点在する寺院遺跡はその多くが東を正面とする構造であり、アンコール・ワットなど一部が西を正面としていました。
その所以はやはり東西が太陽の通り道であるからで、南北を正面とすることはない。
アンコールの都市プランは古代インドの思想に基づいており、その思想は仏教の経典などを通じて日本にも流入していました。
日本の寺社の配置は立地上での制約はありますが、南を正面とするパターンが多い一方で、東西を正面とすることを決して忌諱してはいない。
ところが北を正面とする事例はグッと減ってきて、あえてそうする場合は‘北向観音‘などと断りを入れるくらいです。
ちなみに角界では‘北向き‘といえば‘変わり者‘の意味となり、それほどに北向きというのは一般的ではなかった。
当然、相撲にもこの太陽の道という考え方が早い段階で流入している可能性はありますが、どちらかといえば陰陽道の影響が大きかったのではないかと思はれます。
余談ながら相撲場の意味で‘辻‘といふ言葉が使われることがあるのですが、これはかつて路上で偶発的に相撲が行われていた時分の名残とされています。
一方でこの陰陽の示す如く、土俵とは東西より進み出でた力士が出会う場所であり、かつ南北方向にも出入り口(徳俵・二字口)が切られていてまさに土俵とは十字路=辻を体現した舞台といえるかもしれません。
長くなりますのでこれにて一旦打ち止めと致しまして、また次回へ―(全3回)。
2025-02-14 14:50:56
土俵の上の吊り人たち(後編)
テーマ:相撲史談前編では主に昭和の吊り名人を取り上げましたが、時代は平成、そして令和へ―。
平成以降の土俵で先陣を切るのが大関の霧島です。
ウェイトトレーニングを取り入れた筋骨隆々たる鋼の肉体は人呼んで「和製へラクレス」。
こちらも上手く腹に乗せながら上体を後ろに反りつつ強い引き付けで相手の体を持ち上げるのですが、呼吸を捉えて一息に吊り上げるといった感で、さほど力みを感じさせない技巧を見せてくれました。
同じく大関で平成の一ケタから10年代に活躍した貴ノ浪はまた違った吊りを見せる力士。
身長はおよそ2mという長身で、相手を引っ張り込むと閂に極めあげて寄っていくというセオリーを無視した規格外の相撲を貫き、2度の優勝をも手にしました。
この人のは全くの極め出しで、長身故に相手の両腕をロックして後ろに少し反ればもう相手は浮足立ってしまう。
それこそそのまま持ち上げて土俵外まで運ぶこともあり、仮にこれを吊り出しの一類型と見るならば‘極め吊り‘ということになりますでせうか。
俗に「UFOキャッチャー」と呼ばれることもありました。
渋い所では琴龍(前頭筆頭)の吊りも印象的です。
色黒で肩幅広く、細い目で渋面を作る辺りは「野武士」を自称(?)するだけのことがありましたが、この琴龍も大きく胸を反らせて相手を腹に乗せる豪快な吊りを時折見せてくれました。
近年に入ると外国人力士が用いる例が増えてきた。
横綱の朝青龍などは中に入って吊り上げるとそそのまま捻りを加えて土俵中央に叩きつける吊り落としの荒業を見せて物議をかもすことがありました。
最近ではエストニア出身の怪人・把瑠都とジョージア出身の栃ノ心が記憶に残ります。
把瑠都(大関)は身長197cmに体重177kgと体格も規格外。
膂力も一頭地抜いており、肩越しの上手から片手で相手を持ちあげてつかみ投げや波離間投げを見せる剛腕ぶりを発揮しました。
そんな把瑠都の吊りは外四つだろうがなんだろうが相手をがっちり捕まえたら根こそぎ持ち上げるという吊りで、こうなっては相手も不可抗力。
吊られた時の対処法としてよく足をバタバタと泳がせるというのがありますが、これは両者の体の重心が吊り手のへその下に来て安定しているのを少しでも逸らせるのが狙い。
吊りというのは二つの体の重心がピタリと決まっていればさほど重さも感じないといいますが、それが外れれば忽ちに負荷がかかって吊り続けることができなくなります。
ところが把瑠都の吊りはそもそも自重も重く、しかもそこまで大きく上体を反らさずとも腕力で吊り上げてしまうので体勢が非常に安定している。
こうなっては相手ももはやジタバタしても無駄といったところで、まさにまな板の鯉ならぬ鮭状態。
クレーンと呼ぶにふさわしい吊りでした。
霧島の「アラン・ドロン」に対し「ニコラス・ケイジ」と呼ばれたカスカフのヘラクレスこと栃ノ心(大関)の吊りもかなり腕力に頼る所がありましたが、もう少し上体を反らせて腹に乗せるタイプの吊り。
身長も192㎝と高く、引き付けの強さも抜群である一方で、呼吸を捉えて軽々と、かつ力強い印象が残ります。
以上、吊り名人を列挙してまいりましたが、名人といわずとも昭和の頃までは比較的見かける頻度の高い決まり手。
力士名鑑の得意手の欄を見てもつり出しとある力士が散見されます。
ところが平成以降になると力士の大型化が進んでつり出しが次第に珍しい決まり手へと推移して、十両以上では1場所に1、2回出るや否やというレベルになっていきます。
平成の中期以降は大型化も頭打ちとなってややスリム化するのですが、それでも昭和に比べると断然に重量級で、吊りの復権には至っていません。
ごく最近では現役の霧島(大関)の吊りが師匠譲りと話題になったものの多用するには至らず、かえって令和6年の11月場所では後輩大関の豊昇龍に吊られてしまいました。
この時の吊りは豊昇龍がもろ差しになってから大きくのけ反り、胸に乗せる感じで豪快に持ち上げた。
元々、花形の決まり手ではあるが昨今は中々お目にかかれないとあって館内は大きくどよめきました。
この度、横綱に昇進した豊昇龍は、初場所で懐に入ってから軽く腰に乗せるように吊り気味に寄る相撲を何番か見せており、どこか新境地を拓いた感もあります。
ちなみに吊りを得意とする力士は足腰のしぶとい力士が多く、うっちゃりを併用する場合も少なからず―。
このうっちゃりも相撲の花形ではあるが、近年はめっきり減ってしまった決まり手のひとつです。
吊りの場合も相手の攻撃をしのいで腰の伸びた所で吊り上げるといった攻守が逆転する妙味のある展開が見られたもので、見ていて力の入る面白い相撲でした。
今年は是非、そんな相撲を一番でも多く見てみたいという思いから、令和の起重機の出現を期待する次第です。