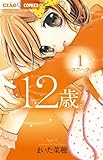夢をカタチに インターネット活用コーチの福田浩です(^_^)v
今から、この本を読みます。
新刊はAmazonでは買わないと決めているんです。
地元の本屋さんを大事にしたいんでね。
今まではネットからジュンク堂に取り置きを頼んでいたのですが、ネット販売の統合と言うことでその仕組みが無くなってしまいました。
普通の「通販」になってね。本屋さんに行かなくて済むので便利ではあるのですが、Amazonと比べるとトロいんですよ。
便利なら便利に、不便なら不便にして欲しいよね。僕は不便でも良いって思っているんだから。
で、近くの本屋さんに届けてもらえる仕組みがあると言うことで、それを使ったんです。
届いたと言うことで本屋さんに行ってみると、手違いでその場で発注になってしまったようで。
出たときにサイン本を読めると思っていたのに、ちょっと待ちになってしまいました。
本を受け取ったのですがサインが無いと言うことで間違いに気付き、サイン本と交換しました。

慣れてなかったんでしょうね。
取り置きをしてでも、お店の人とやりとりをして買いたいなぁと思うんです。
地元から本屋さんが無くなるのはイヤだし、そこは消費者にも責任があると思う。
Amazonって手軽すぎて怖いと思うことがあるしね。
この本、すごく分かりやすいです。お薦めします。
さて、「話し方の心理学」の続きです。
今日のお題は、「コミュニケーションとは与えること」としました。
コミュニケーション(communication)の語源を調べると、コムニカチオ(communicatio)、 「分かちあうこと、共有すること」、communicare(コムニカーレ)「共有する」などが出てきます。
人間関係は、このように「分かち合う」「共有する」ことで成り立っています。
自分では満たせない欲求が誰にでもあります。
人は満たしてくれる相手を求め、その求めを拒絶するものは同じ目に遭います。
人が人に求めているもの、愛情、承認、励まし、賞賛、理解、同情、共感・・・こうした欲求の大半は、会話を通じて満たすことが出来ます。
そのため、特に意図しなくても、ごく自然のうちに会話の中にはこのような欲求が侵入して来ます。
そのとき、相手の要求を満たしてあげることが出来れば、会話は実のあるものになります。
会話の中には、このようなGive&Takeがひっきりなしに行われ、こうしたお互い様の連続で人間関係は維持されます。
会話は金銭に換えられない素晴らしいもの-注目、関心、興味、共感、知恵-を相手に与えることが出来ます。
物質的なもので満たされることの無い深い飢えを、会話は満たしてくれます。
「話すことによって与えるもの」として、次の三つが挙げられます。
- 教育する
- 楽しませる
- 感情面の欲求を満たす
「教育する」とは、事実や情報を与える、建設的な批判をする、個人的な経験を共有する、役に立つ情報を与える、といった幅広い意味を表します。
「楽しませる」とは、ジョークや愉快な話、エキサイティングな話などを通じて、相手に元気を与えることです。
「感情面の欲求を満たす」とは、相手を賞賛したり、認めたり、同情したり、自慢に思っていそうなことを話題にしたりすることです。
会話は同時に複数の働きをします。
例えば自分の感情を相手に打ち明けるとき、相手に気持ちを伝えるとともに、私はあなたに自分のことをさらけ出します、それだけあなたのことを信頼していますと言うことを伝えることになります。
愉快な話をして聞かせることは、相手を楽しませるとともに、相手を楽しませるために自分の時間も労力も使っていること、それだけあなたのことを気遣っていると言うことを知らせています。
言葉は贈り物です。物質的な贈り物に負けないほどの喜びをリアルに伝えることが出来ます。
「聞くことによって与えるもの」もあります。
自分の考えや感情を吐きだしてしまいたいとき、耳を傾けてくれる人が居るのはありがたいことです。
聞き手がいることで思考が整理でき、感情を解放することが出来ます。
つまり、聞くことそのものが贈り物になります。
考えると言う行為は、非常に無秩序なプロセスです。頭の中には雑多な欲求がひしめき合ってそれぞれが主張しています。
それを押しのけるように「考え」が形成されます。このような混沌としたプロセスが頭の中で行われています。
このように頭の中につぎつぎに「考え」が浮かぶと、それを解放したいという感情に駆られます。
それが建設的なもので無くても、話すことで楽しい思いをして、多少でも緊張が和らぐだけで本人は至って満足なのです。
そこに聞き手という存在が居ると、相手に分かるように秩序立てて話そうとします。
聞き手が居るから明確な思考が出来ると言うことはよくあることです。
たとえて言うなら、自分の考えを相手に試着させ、すこし後ろに下がって見栄えを点検するようなものです。
聞き手が熱心に聞けば聞くほど、話し手は考えをまとめて結論を出そうとします。
そのお返しとして、自分も相手の話を聞こうとします。話を聞いてくれたことの感謝の証しです。
話し手にとって聞き手とは感情の放出を促す媒体です。
感情が鬱積して居るとき、とりあえず話をするのが一番であり、話す限りは聞き手が必要です。
これとは別に、勢いは無いけれどもどうしても吐き出したいという感情があります。
こういう感情は、放出しても安心、共感してくれる、力づけてくれると確信できる聞き手を待っています。
聞くという行為は、相手を癒やすことに繋がります。相手の緊張を解きほぐし、相手は楽に感情を吐き出すことが出来ます。
情報交換という意味ではプラスでは無いかもしれませんが、相手との関係は豊かなものになります。
「話すことで得る」ことは、聞くことで与えることの逆です。
鬱積した感情を話すことで相手の時間と労力を使って気持ちを楽にしようとしています。
相手の感情を受けとめることで得られるものはなんでしょうか。
話し手は聞き手に対して、あなたを信頼しているからここまで自分をさらせるのだというサイン、つまり有る特別な地位を与えています。
感情を発散して大満足な話し手は、自分にとって楽しいことは、相手にもきっと楽しいはずと思いがちです。
感情を長々と放出し、聞き手の時間を消費すればするほど、聞き手はうんざりし、自分の問題に関心が移ってしまいます。
視界を曇らせていた感情の暗雲が消えて、相手を「耳」では無く「人」としてみることが出来るようになったら、すぐに相手を会話に巻き込み、感想を尋ねるなどして、ぞんぶんに話してもらいましょう。
「聞くことで得ること」は、話すことで与えることの逆です。
聞き手は役に立つ情報と心地よい気分を手に入れています。
ただ、聞き手が聞くことに徹し、何も返さないとなると話し手は不快感を覚えます。
良い聞き手はありがたいものですが、全てを吐きだしたと思った瞬間、聞き手の存在はさほど有り難くなくなります。
お返しが何も無いのでは、相手に都合良く利用されたのではと、話し手はうんざりします。
役に立つ情報、励ましの言葉を貰ったら、相手に敬意を示すことを忘れないようにしましょう。
会話は宝の山です。私たちは、貴重な時間と集中力を会話に注ぎ、さらに情報を提供し、相手を力づけるためのエネルギーを提供します。会話は素晴らしい資源です。
会話とは互いにその資源を分け合うことです。問題はどちらがどれだけ手に入れるかです。
往々にして、会話は激しいぶんどり合戦になります。
相手の話を遮り、会話の主導権を握ろうとし、自分の持ち分を相手に奪われたような気持ちになります。
少しでも自分の持ち分を増やそうとすると相手の言葉に耳を貸すことが出来なくなります。
これは不毛な戦いです。そんな戦いに勝ったとしても得られるものは有りません。
初めから相手に資源を提供するつもりで会話をする方がはるかに実りはあります。
会話は共有するものである。目的を果たすためにはそれが一番の近道です。
私たちはつい、相手は当然聞いているものとだと思い込んでしまいます。
会話で何を話そうか、どのように話そうかと私たちは知恵を絞りますが、相手に聞いてもらうための工夫というと、ほとんど何もしていません。
話したいと言う欲求があると、聞く力はガクンと落ちます。
どういうときに聞き手は話したいと思うでしょうか。
- いま聞いたことに疑問がある。同意できないので質問したい
- 意味が理解できないからもっと詳しく話して欲しい
- あなたの意見に賛成だという意思表示とその理由を話したい
- 本題とは関係は無いがどうしても言いたいことが有る
どんな場合でも、話したいと言う気持ちが起きると、聞き手は話し手に集中できなくなります。
このような事態を避けるには、「話したい」という欲求を発散させる方向に持っていくことです。
聞き手が自分から話そうとしないなら、合間合間で上手く誘導して言いたいことを引き出しましょう。たとえ本題と関係の無いことでも話してもらった方が良いです。
ものごとを効率的に進めていくためには、論理的思考と感情の両面で人を納得させなければなりません。相手の発言が論理的で無くてもキチンと対応するべきです。
感情は論理をかき乱そうとします。だから自分は論理的に話しているつもりでも、相手には非論理的に聞こえることもあれば、相手は分かったつもりでもこちらはサッパリ分からないということも起きます。
論理的な意見であろうと、理屈では説明のつかない気持ちであろうと、相手が伝えようとするからにはそれを受けとめるところから始めなくては、人間関係を築き発展させていくことは出来ません。
会話とは「共有すること・分かち合うこと」です。
相手に時間を与えて、考えて居ることや気持ちを語ってもらいましょう。
それを習慣にすることが、良好な人間関係と質の高いコミュニケーションを手に入れる近道です。