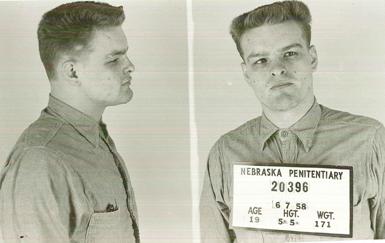突然降って湧いたように過去の傷が浮上する。
それは自分の人生だけでは無く、自分が胎内で育んだ生命の人生にも関わるのだ。
その傷は、自分の体面を保つために秘密にし、秘密にするがゆえに
それを糊塗するために嘘で塗り固めたものでもある。
この「秘密と嘘」は1996年カンヌ映画祭で最高賞パルムドールと
ブレンダ・ブレッシンが主演女優賞を受賞、ジャン=バプティストが
助演女優賞にノミネートされた。
このような評価を得たことを理解するためにいくつか考えてみる。
イギリスは国王を頂点とする階級社会で、貴族、中産階級・ブルジョワ
労働者階級に区分される。勿論中産階級と労働者階級とは教育などによる
階級間移動もある。労働党党首はサーの称号を持つが労働者階級の出身で、
オクスフォードを出た後、法曹界で検察局長官を務めた事による称号だろう。
労働者階級の下はわれわれ東洋の黄色人種や旧植民地出身の大抵は黒人。
偏見と差別に晒されている者たちだ。
メーガン妃に対するバッシングの凄さを考えてみるとそれがわかる。
幼くして母親を亡くしたシンシアはすぐ父親や弟の世話をする羽目になり、
ずっと独身だが婚外子の娘ロクサーヌと同居し、父親の死後工場に勤めている。
ロクサーヌはもうすぐ21才だが市の清掃員で、恋人は足場作業員。
弟のモーリスは写真館の経営者で結婚式の写真を主な柱に裕福な暮らしをしている。
子供は無く、実は妻モニカは不妊治療を受けているが夫婦以外には秘密である。
シンシアにはロクサーヌに隠している大きな秘密があった。
それは16歳の時最初の婚外子を出産し、その子を抱くことも無く養子に出したこと。
一方その子は中産階級の中で成人し、大学教育を受けて検眼師になっているが、
養父母の死後、遺品の中から実の母親と養父母との間に交わした約定を発見する。
その娘ホーテンス・カンバービッチはシンシアの住所を確認し、電話をする。
驚いたシンシアは取り乱すが、会いたいというホーテンスに断り切れずに会うことを承知。
地下鉄の駅で待ち合わせする。
が、目の前に黒人の娘がうろうろするが眼中に無い。
ホーテンスのファミリーネームは由緒ある白人の名前だから、シンシアはてっきり
白人とばかり思い込んでいたのだ。
もう一つは、出産時に嬰児をろくに見ていなかったことがある。
ふたりは会うようになり、シンシアの心境は変化し、むしろホーテンスを誇りに思う。
一方ロクサーヌの21才の誕生日パーティを弟モーリスが主催することが決まり、
ホーテンスにそれに出席しないか、と誘い、モーリスの許可を得る。
無論シンシアはホーテンスが自分の最初の婚外子であることを皆には隠しており、
ホーテンスが玄関に立ったとき黒人であることに皆が驚く。
ロクサーヌはホーテンスを含めて皆からプレゼントを受け取り、日頃に似合わず素直に
楽しんでいる。ホーテンスは自分の事が秘密にされたままの状態に気分が落ち込んで行く、
母親のシンシアもホーテンスの心中を察し追い込まれてゆく。
そしてホーテンスとシンシアの二人の心の共鳴が深まり、シンシアの感情が爆発し、
過去の真実が明るみに出される。
われわれは私秘性(プライバシー)をもち、それが尊重される。
私秘性は個人の尊厳にかかわり、それを他人に暴露されることを好まない。
その秘密は国家が握ると、個人に対する脅迫手段ともなり得る(マイナーカード)
しかし、今ここでの会話の中で、秘密が隠されていることで、
真のコミュニケーションが阻害されることもある。気まずくなり場に入り込めないのだ。
その秘密を明るみに出し、共有することで、関係が深まり親密度が増すこともある。
このプロセスの中で、ロクサーヌの父親についてシンシアから明かされる。
そしてホーテンスが「私の父親はどんな人だった」とシンシアに尋ねたとき、
シンシアは泣きながら、それだけは勘弁して、とホーテンスに謝罪する。
私秘性で全てが明るみにされない。しかし賢いホーテンスはそのことを
受け入れた上で、シンシア、自分、ロクサーヌの関係を新しく作り上げて行く。
「それだけは勘弁して」というシンシアに言わしめたものは、私秘性と、
イギリス社会に潜む黒人に対する偏見や差別である。
偏見や差別は明るみに出さなければ闇から闇に葬られ、問題は潜行し持続する。
この映画はその偏見を明るみに出し、可視化しようとした。
しかし可視化することで即解決に直結するほど簡単な問題では無い。
たとえばアメリカのオバマ大統領の8年で、黒人に対する偏見差別が解消したわけではない。
むしろそのことが白人至上主義者を刺激し活性化した面があり、トランプがそれを利用した。
アメリカ社会では黒人が自由に息を吸えるのはスポーツと芸能の社会である。
バイデンもオバマの築いた礎石の上に何とか2歩目を、と懸命の努力をしている。
そこに異国ながら希望を見いだすことが出来る。
さて映画に戻る。
ここに至るまで、シンシアは究極的に自分しか出来ないことを為し、
弟のモーリスも自分が役割を果たすべき時に果たす。
モーリスはホーテンスに向かい「あなたの勇気をたたえる」とリスペクトし
それを機に皆はホーテンスを受け入れる。
何事にも為すべき時に、為すべき事があるのだ。
(追記2参照:旧約コヘレトの言葉3章、新共同約1036-7)
映画としてシンシアの真情が出来事を大きく動かして行くが、
その真情の奥底は何だろうか?
哺乳類の雌は雄の精子で受精し、数ヶ月胎内でその子を宿して命を育む。
胎内で確かに生命が動いている実感。
出産すれば授乳してさらに生命が力強く育って行く。
そうした実感がその真情の奥底にあるのではないか、
それに通底してシンシアには、嬰児のホーテンスを胸に抱き授乳しなかった
悔いが真情の奥底に一層強くあるのだろう。
と雄の私は確証の得られない想像をするのである。
追記1:英国の現首相スナクはヒンズー教徒で、インド由来である。
両親はインド洋に面した東アフリカ(現ケニア)でイギリスの現地黒人の支配を
黒人を以てする、という植民地経営から、イギリス人の代理支配層としてインドから渡った
ものの後裔なのだろう。スナクはオクスフォードで哲学・政治・経済を学び米国のフルブライト
奨学金でスタンフォードでMBAを取得し、そこでインドの大実業家の娘と出会い結婚。
まあバリバリのエリートと言ってよい。
ボリス・ジョンソンのもとでナンバーツーの財務大臣を勤め最後はジョンソン政権崩壊の
引き金を引いた。その後2022年の保守党党首選挙で白人女性リズ・トラスと争い敗戦。
そのトラスの辞任を受けた党首選挙で対立候補がなく無競争で党首に就任した。
トラスとの選挙期間中、スナクが黒人である事で抵抗があったことが度々報道された。
いまも黒人に対する偏見は根強くあるとおもう。
しかしその彼も今の英国民の今の苦境を救うことが出来れば、評価は変わってくるだろう。
インフレやNHS(ナショナルホスピタリティシステム)などハードルは高い。
しかし偏見はなくなって欲しいものだ。
追記2:参考のためにコヘレトの言葉を抜粋する。
何事にも時があり、 天の下の出来事にはすべて定められた時がある。
生まれるとき、死ぬとき。
殺すとき、癒やすとき。
破壊するとき、建てるとき。
泣くとき 笑うとき。
嘆くとき、踊るとき。
求めるとき、失うとき。
黙するとき、語るとき。
愛するとき、憎むとき。
戦いのとき、平和のとき。
名声は香油にまさる。
死ぬ日は生まれる日にまさる。
悩みは笑いにまさる。
顔が曇るにつれて心は安らぐ。
この空しい人生の日々に、
わたしはすべてを見極めた。
善人がその善ゆえに滅びることもあり
悪人がその悪ゆえに長らえることもある。
善のみ行って罪を犯さないような人間は
この地上にはいない。
追記3:Filmosophy Daniel Frampton 2006 Wallflower press より。
映画「秘密と嘘」は上記の最終章「Conclusion」において取り上げられている。
Film Phylosophy は既に定着して久しい用語だが、映画のテーマ、状況設定、
対話やナレーション、あるいは結末などを、たとえばハイデッガーやメルロ=ポンティ、
ウイトゲンシュタイン、映画論を書いたカベルやJドゥルーズなどを活用して分析する。
フランプトンは、われわれの眼前に広がる画面の中の世界を、われわれの世界の鏡として
ではなく、それ自身独自の世界として思考する。それをFilmosophy と名付けている
と理解しているが、「秘密と嘘」が、キャラクターが座れば映画も座り、同じように動く。
場面の展開も、急なクローズアップやジャンプカットなどをせず、見る我々の心に添って
動く。その共鳴がわれわれの知ー思考を深める。と概略主張する。
これに関して付け加えれば、各キャラクターの演技に誇張やムリが無いことが、
見終ったあとのすがすがしさに繋がっているとおもう。貴重な体験だ。
参考:同じマイク・リー監督とティモシー・スポールによる映画「ターナー」
のブログを以下に貼ります。
このターナーの姿勢、モーリスが記念写真などを撮るときに似ていますね。