中将姫と二上の具縁さん ―前篇― 聖衆来迎練供養会式のはじまり ~ 【葛城のむかしばなし】より
葛城市のマスコットガール(ゆるきゃら )蓮花ちゃん
)蓮花ちゃん

そのモデルとなったのが中将姫です。

「女性の味方 血の道の人 中将姫」では中将姫のラストについて触れませんでした。
まずはそこから語りたいと思います。
不思議な尼が一夜の内に、織り上げた曼荼羅。
その後、姫は来る日も来る日も祈りつづけ、曼荼羅に描かれた世界、極楽浄土のすばらしさを人びとにかたってきかせました。
姫が29才になったときです。
清らかな調べとともにくもの彼方から二十五菩薩がお迎えにあらわれて、姫を極楽浄土へと導いたのでした。
・・・
毎年5月14日、二上山に陽が傾くころ、當麻寺では「聖衆来迎練供養会式」(しょうじゅらいごうねりくようえしき)がとりおこなわれます。

聖衆来迎練供養会式は、中将姫のラストシーンである生きたまま成仏したという伝承を再現しているのです。
二十五菩薩に扮した人々が、人間の俗世界にみたてた東側の娑婆堂(しゃばどう)と、極楽浄土にみたてた西側の曼荼羅堂(まんだらどう)を結ぶ約110メートルの永い来迎橋を練り歩く儀式です。
いわゆる菩薩様のコスプレ行列ですね。
だけど菩薩様のお面は、新しいもので350年前の仕立てになります。
差し込む日差しが、練供養の神々しさを引き立て、見る人々に、西方浄土を連想させます。
この聖衆来迎練供養会式がとりおこなわれたきっかけとなった不思議なおはなしがあります。
後編へ続きます
ランキングに参加しています。
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓

 )蓮花ちゃん
)蓮花ちゃん

そのモデルとなったのが中将姫です。

「女性の味方 血の道の人 中将姫」では中将姫のラストについて触れませんでした。
まずはそこから語りたいと思います。
不思議な尼が一夜の内に、織り上げた曼荼羅。
その後、姫は来る日も来る日も祈りつづけ、曼荼羅に描かれた世界、極楽浄土のすばらしさを人びとにかたってきかせました。
姫が29才になったときです。
清らかな調べとともにくもの彼方から二十五菩薩がお迎えにあらわれて、姫を極楽浄土へと導いたのでした。
・・・
毎年5月14日、二上山に陽が傾くころ、當麻寺では「聖衆来迎練供養会式」(しょうじゅらいごうねりくようえしき)がとりおこなわれます。

聖衆来迎練供養会式は、中将姫のラストシーンである生きたまま成仏したという伝承を再現しているのです。
二十五菩薩に扮した人々が、人間の俗世界にみたてた東側の娑婆堂(しゃばどう)と、極楽浄土にみたてた西側の曼荼羅堂(まんだらどう)を結ぶ約110メートルの永い来迎橋を練り歩く儀式です。
いわゆる菩薩様のコスプレ行列ですね。
だけど菩薩様のお面は、新しいもので350年前の仕立てになります。
差し込む日差しが、練供養の神々しさを引き立て、見る人々に、西方浄土を連想させます。
この聖衆来迎練供養会式がとりおこなわれたきっかけとなった不思議なおはなしがあります。
後編へ続きます
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓
女性の味方 血の道の人 中将姫 ~算命学と奈良歴史 (再掲載)
連動企画【算命学で見た、奈良・歴史上の人物とミステリー】
中将姫
・・・再掲載です。
(=⌒▽⌒=)
゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
家なき子・中将姫
「むかし、むかし、あるところに、それは美しい、娘がおったそうな・・・」
このような出だしではじまる奈良県葛城の昔話があります。
聖武天皇の時代。
天平19年(747)8月18日のことでした。
なかなか子に恵まれなかった夫婦は、長谷寺の観音様に参篭して祈願しました。
そうして、生まれたのが中将姫でした。
ところが不幸なことに、中将姫が幼いころ、母親を亡くします。
その後、やってきた後妻は、中将姫をひどくうとく思います。
評判高い美貌と才能あふれる中将姫に、自分の子が、ないがしろにされるのを恐れたからです。
ある日、父親が不在の時、家臣に雲雀山へ連れ出し殺すようにと命じます。
家臣は、娘があまりにも哀れに思い、ともとなり後妻の手から逃れて寺を、山中を逃亡します。
しかし、中将姫は、逃亡中の疲労と冷え込みのため、重い婦人病にかかります。
病に効くとうわさを聞き、中将姫は、美濃の願成寺を訪れます。
観音菩薩に病気平癒を祈り、果たして回復します。
中将姫は、お礼に観音菩薩の守護を祈願し、桜を植えます。
(これが有名な「中将姫誓願桜」です。)
そして、中将姫は、自らの病から、女人だけの苦しみ、病を知り、あらゆる女性特有の災いから救おうと観音菩薩に誓うのでした。
血の道・婦人病と中将湯
バスクリンなど薬用入浴剤や婦人病薬で有名な津村順天堂(現・ツムラライフサイエンス)。
創始者の津村重舎の母方の実家・藤村家は、逃亡中の中将姫をかくまったお礼に、婦人病の薬の製法を教わったと伝えられています。
それが、この中将湯でした。
- ★婦人薬中将湯24包入り(24日分)【第2類医薬品】

- ¥2,948 楽天 ※モバイル非対応
明治26年創業の津村順天堂では、中将姫の中将湯を看板商品にしたのでした。
藤村家があった奈良県宇陀郡では、薬の材料となる薬草や鉱物が豊富で、もともと薬の製造が盛んでした。
また藤村家は、中将姫と縁がある雲雀山青蓮寺(日張山青蓮寺:ひばりやませいれんじ)の檀家でした。
中将姫とは遠からず縁がある家系でした。
當麻曼荼羅・伝説
果たして雲雀山に隠れた中将姫は、狩りに訪れた父親と再会し、再び、都にもどることができました。
現世の浄土を願い、出家をし當麻寺(たいまでら)に入ります。
ある夜のことでした。亡き母を想い嘆く中将姫の前に、年老いた尼が現れます。
蓮の華を手に尼は、浄土をお見せしましょうというと、するすると蓮から糸を紡ぎだします。
もう一人の尼が現れ、その糸を使い、一夜の内に、4メートル四方ものの大きな曼荼羅を織り上げていくのでした。
老いた尼が中将姫に、
「これが浄土です。こちらに、あなたの母君がおわしますよ。」
と、示した先に、忘れもしない愛しい母の姿が、曼荼羅に織り込まれていたのでした。
當麻寺(たいまてら)
推古天皇の時代。
聖徳太子の教えによって、麻呂子親王が創建。
大和と河内の境となる二上山の東麓にあります。

白鳳時代の梵鐘、石灯籠でも有名です。


日本最古の石灯籠。重要文化財に指定されています。
中将姫・伝説
中将姫は、父親は、奈良時代の右大臣、藤原豊成公の娘です。
しかし、中将姫の伝説には、諸説あります。

今回紹介したお話の主軸には、葛城の民話から引用しました。
時を経ることに、中将姫の物語は凄惨に脚色されていきます。
今回のお話では、曼荼羅を織るのは、謎の尼としていましたが、當麻寺で紹介されている内容とは異なります。
百駄の蓮の茎より蓮糸を繰り、これを井戸に浸すと五色に染まった。
これを用い、中将姫本人が曼荼羅を一夜にして織り上げたとあります。
継母のイジメによるものは室町時代にでてきたと伝えられています。
また、弟がいて、姉弟は、継母に雲雀山に捨てられ、弟が死んでしまう話もあります。
更に、メロドラマがかったお話になると、天皇の后に見染められたが、継母の策略により、不義の疑いをかけられるものもあります。
女性ならではの受難を、てんこ盛りに脚色されていきましたね。
「血の道」。
女性特有の病「婦人病」を、そう呼ばれた経緯には、子宮や卵巣の疾患、月経や妊娠、出産に関するトラブルが、忌避されるもの、マイナスなイメージに与えられたことにありました。
そのため、穢れたこと、通俗的に女性の中で隠されることとなり、苦しまれていたことだったのでしょうね。
中将姫は、そんな悩みを抱えた女性たちを救うのヒロインであったのではないでしょうか。
苦難を与えられても仏の道を貫き、そして、女性たちを救う医師であり、薬剤師であった。
また、カウンセラー、セラピストであったのではないでしょうかね。
 算命学カウンセラー紅星くれないぼし先生の鑑定結果は、こちら。
算命学カウンセラー紅星くれないぼし先生の鑑定結果は、こちら。
連動企画【算命学で見た、奈良・歴史上の人物とミステリー】
「中将姫 」
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓
*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:
関連情報:
![]() 紅星先生との連動企画で紹介した歴史上の人物はこちら。
紅星先生との連動企画で紹介した歴史上の人物はこちら。
第一弾、豊臣秀長 。
第二弾、筒井順慶 。
第四弾、菅原道真 。![]() 算命学カウンセラー紅星(くれないぼし)先生のブログは、こちら。
算命学カウンセラー紅星(くれないぼし)先生のブログは、こちら。
- 日本〈聖女〉論序説 斎宮・女神・中将姫 (講談社学術文庫)/田中 貴子
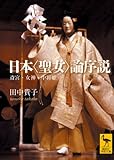
- ¥966
- Amazon.co.jp
- 葛城と古代国家 (講談社学術文庫)/門脇 禎二

- ¥945
- Amazon.co.jp
キツネのタロさん ― 葛城きつね(4) ~ 【葛城のむかしばなし】より
狐、狸、狢が人にイタズラするお話は枚挙に暇がありません。
ですが、狐はイタズラするものばかりではなく、お稲荷様の使いとして祀られていますね。
キツネのタロさんは、そんなキツネの神様です。
ただし、このお話は民話ではなく、ちょっと昔まで本当にあったことだそうです。
二月の第一回目の午の日を初午(はつうま)といいます。
昔、初午の日に、京都の伏見稲荷神社に祭神が降り、それ以後、稲荷社のお祭りとなりました。
葛城の竹内では、どこの家でも神棚に山海のもの、お神酒や洗い米、旗飴などをお供えしました。
ときに「お台さん」と呼ばれる不思議な力をもつ人が「稲荷下げ」を行われることがありました。
稲荷下げとは、お台さんに狐がのりうつって、いろんなことを教えてくれるのです。
竹内のお地蔵さんの横に住むキツネのタロさんは、お台さんをつとめる長尾のおばあさんによくのりうつったそうです。
ある年の初午の日のことです。
長尾のおばあさんが、竹内のある家に招かれて稲荷下げをしました。
お台さんが祝詞をあげると、キツネのタロさんがのりうつって言いました。
「わしは四つ辻のお地蔵さんの横に住んでいるキツネで、タロさんというんや。
聞きたいことがあったら、何でも遠慮せんと言うてみ」
そこで主が、
「息子が戦争に行ったまま、何の連絡もないんですわ。どうしているのやら、心配でたまらんのですわ。」
「あんたの息子は、かわいそうにサイパンで弾にあたって死んでもうた。胸にあたってどうにも助からんかったんや」
それからしばらくして息子さんの戦死の知らせがあったそうです。
その様子は、長尾のおばあさんが話したこととぴったり合っていたということでした。
ほかにも、なくしたものや病気のことなど、何でもびっくりするほどよく当たりました。
その後、この長尾のおばあさんが亡くなってからは、ほかにお台さんになれる人が見つかりませんでした。
初午の日の稲荷下げも、お台さんがいなくなってからというものの、いつの間にやら稲荷下げを知る人もいなくなりつつあります。
けれども今でも竹内の人びとは、狐のタロさんのために、お稲荷さんにお供えをしているとのことでした。
ランキングに参加しています。
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓

ですが、狐はイタズラするものばかりではなく、お稲荷様の使いとして祀られていますね。
キツネのタロさんは、そんなキツネの神様です。
ただし、このお話は民話ではなく、ちょっと昔まで本当にあったことだそうです。
二月の第一回目の午の日を初午(はつうま)といいます。
昔、初午の日に、京都の伏見稲荷神社に祭神が降り、それ以後、稲荷社のお祭りとなりました。
葛城の竹内では、どこの家でも神棚に山海のもの、お神酒や洗い米、旗飴などをお供えしました。
ときに「お台さん」と呼ばれる不思議な力をもつ人が「稲荷下げ」を行われることがありました。
稲荷下げとは、お台さんに狐がのりうつって、いろんなことを教えてくれるのです。
竹内のお地蔵さんの横に住むキツネのタロさんは、お台さんをつとめる長尾のおばあさんによくのりうつったそうです。
ある年の初午の日のことです。
長尾のおばあさんが、竹内のある家に招かれて稲荷下げをしました。
お台さんが祝詞をあげると、キツネのタロさんがのりうつって言いました。
「わしは四つ辻のお地蔵さんの横に住んでいるキツネで、タロさんというんや。
聞きたいことがあったら、何でも遠慮せんと言うてみ」
そこで主が、
「息子が戦争に行ったまま、何の連絡もないんですわ。どうしているのやら、心配でたまらんのですわ。」
「あんたの息子は、かわいそうにサイパンで弾にあたって死んでもうた。胸にあたってどうにも助からんかったんや」
それからしばらくして息子さんの戦死の知らせがあったそうです。
その様子は、長尾のおばあさんが話したこととぴったり合っていたということでした。
ほかにも、なくしたものや病気のことなど、何でもびっくりするほどよく当たりました。
その後、この長尾のおばあさんが亡くなってからは、ほかにお台さんになれる人が見つかりませんでした。
初午の日の稲荷下げも、お台さんがいなくなってからというものの、いつの間にやら稲荷下げを知る人もいなくなりつつあります。
けれども今でも竹内の人びとは、狐のタロさんのために、お稲荷さんにお供えをしているとのことでした。
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓
- 日本の昔話 9 (お風呂で読む日本昔話 9)/楠山 正雄

- ¥1,050
- Amazon.co.jp
- 狐―陰陽五行と稲荷信仰 (ものと人間の文化史 39)/吉野 裕子

- ¥3,150
- Amazon.co.jp