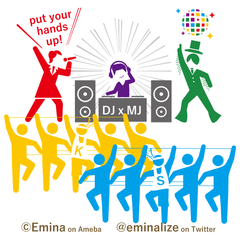【8/14ロケ地写真など更新しました】
【7/15、8/3ロケ地情報更新しました】
ついに全国放送になりました、
「永遠のニㇱパ ~北海道と名付けた男 松浦武四郎~」
待ちに待った全国放送なので、
皆さんがどのような感想をお持ちになるのか、先行放送組としても楽しみにしてました。
やっと話せるーーー!!!
武四郎が北海道にかけた時間に比べて、
80分というのはとても短い時間で、北海道での先行放送後は連ドラでやってほしい!
などの感想も多く見かけました。
たぶんそれは、大石静さんが時代劇の奥ゆかしさを醸すために、
現代劇のように言葉を多用しなかった、つまり…視聴者の想像力に託した、
というところにもあるんじゃないかな、と私は思います。
潤くんが雑誌で言っているような「よくまとめたな!」と感じるには、
もしかすると、想像の源になる知識を必要とする人もいるかもしれない、
とこの一ヶ月考えていました。
そこで出会ったのが、
更科源蔵「北海道と名付けた男 松浦武四郎の生涯」という本です。
この本は、ドラマのシーンとシーンの間の出来事を理解するのにとても役立ちました。
ドラマの冒頭、こんな言葉が映し出されましたね。
「このドラマは、「北海道」の命名を提言した松浦武四郎を主人公としたフィクションです」
普通のドラマなら、最後に持ってくるものをあえて最初に持ってくる。
ここさらっと流しがちですけど、結構大事だなと思いました。
例えば、深田恭子さん演じる「リセ」は架空の人物です。
でも、実際に様々なアイヌの身に起きたことを「リセ」や周りの存在に集約しています。
詳しくは後ほど、ですが、存在はフィクションでも、表現されていることはだいたいこの本に書いてあることと合致することが多かったので、このブログを読んでより興味を持たれた方は、ぜひ読んでみていただけたらと思います。
今日はその中からドラマの補足になりそうな部分と、自称地学オタクとしての興味で、どんな場所で撮影されたのか、ということも私の分かる範囲で紹介できたら良いな、と思います!
シーン1 武四郎、雪原を進む
ロケ地:鹿追町瓜幕
角度的に火山展望地あたりかなぁ…歩いているところは多分農地かなと。
奥に見える山は、右が東ヌプカウシヌプリ、中央が西ヌプカウシヌプリ、だと思います。
(地元では夫婦山、と呼んでいるとか…?)
※ヌプカウシ・ヌプリ=「野の上にある山」
この山の向こうには「然別湖」という、火山活動によってせき止められた湖があります。
(私のどうでもいい興味…武四郎が手にとった方位磁針は「正針」ですね。江戸時代末期は東西が逆になっている「逆針」のほうが多いと聞いていたので、ここは武四郎の遺したものも正針だったのか、興味あります)
シーン2 武四郎、海岸を進む
ロケ地:ひだか町百人浜あたり?
右側に見えるのは日高山脈、左の陸の果てがえりも岬だと思います。
この先の海岸のシーンはだいたい同じ場所かと。
シーン3 箱館・1845年
「この地にロシア船が度々出没する話」とあるように、北海道のすぐそばにあるのは中国でも朝鮮半島でもなく、ロシアなんですよね。うん。本州の人からしたらロシアはすごく遠く感じると思いますし、道民も…だから北方領土問題も他人事に(自粛
1700年代から千島列島、根室、釧路などに来て測量をしたり、交易を迫ったりしていたようです。
長崎から蝦夷地まで船で向かったかのようにわたしは理解したんですが、更科によると、長崎→京都→大坂→近江(滋賀)→越前(福井)→加賀(石川)→越中(富山)→越後(新潟)→会津(福島)→酒田(山形)→能代(秋田)→黒石→弘前→鰺ヶ沢(青森)などなどと登山も挟みながらひたすら歩いて行ったにもかかわらず、天気や季節などの都合で一度仙台に引き返し、さらには江戸まで戻って旧知を訪れたり、資金調達をして、もう一度奥州街道を抜けて青森までの鰺ヶ沢へ向かっているというので、読むだけで卒倒しそうになりました…笑
更科は、「北方の危機と取り組むとは思われない、彼本来の悠々とした遊山的な傾向が見られる」(「松浦武四郎の生涯」P42)といいますが、そういう部分はここではカットのようです。
「蝦夷測量図」は、伊能忠敬が書いたやつですねきっと。
「船旅で濡れてしまった」というのはたぶん、津軽海峡の荒波でやられたのかなぁ。
新堂屋は架空かもしれませんが、最初は場所請負人である松前商人を頼ったというところは本当のようです。
シーン4 関所~ウテルクとの出会い
ロケ地:(流石に分からんけど七条大滝に進む道かなぁ?)
ドラマではアイヌの「ウテルク」が登場しますが、案内人をアイヌにしたのは、実際は2回目に松前藩医・西川春庵の雑用係として蝦夷地から樺太まで行って再び戻るときのことで、武四郎はアイヌと同じ雑用係をしているうちにある程度アイヌ語ができるようになったそうです。(同 P54-58)
シーン5 山道~滝
ロケ地:苫小牧市 七条大滝
事前番組で最初のロケ地になったのはこのあたりでしょうか。まさにアドベンチャー。
ドラマで野帳を開くシーンがありますが、「シコツ沼」(支笏湖)とあり、チトセ(千歳)川が左側にあるので、下が北になっていますね。のちに武四郎が描いた北海道の地図も下が北になっているので、何か当時の習慣とか理由があるんでしょうね。
野帳の左奥はヲサツ沼と読めるので、現在の千歳市長都(おさつ)のことだと思います。
ウテルクが滝に向かって祈りを捧げていたのも、アイヌがあらゆるものに魂が宿っていると考えていることの象徴のように思いました。
シーン6 巨岩に挟まれた川
ロケ地:(どこなのか猛烈に知りたい)
→2019/7/15追記、ちいすけさんに教えていただきました!樽前ガローだそうです!行く!絶対行く!
→2019/8/14追記、行ってきました!
Emina👑@em1nalize
#永遠のニㇱパ ロケ地2枚目、これがやばかった… #樽前ガロー 小雨が降ってて、いい感じでモヤが。 序盤で武四郎がこの崖の間の川を歩いていました。 https://t.co/cvS6NT160f
2019年08月12日 16:51
Emina👑@em1nalize
#松本潤 主演 #永遠のニㇱパ ロケ地 #樽前ガロー 動画でもどうぞ。 https://t.co/5lMUwdJG0J
2019年08月12日 16:53
シーン7 「ウテルク、あれはどこだ?」
ロケ地:恵山(函館市)→リンク
岩だらけの山を登って、武四郎が対岸を指差すシーン。
「ヌプリ…ポロチケウェ」
ポロチケウェとは、室蘭にある「チキウ(地球)岬」の断崖のことです。
対岸の奥に見える一番大きな山は”蝦夷富士”とも呼ばれる、羊蹄山かと。
この角度・距離で羊蹄山が見えるのは…森町の駒ケ岳とか砂原岳だと思うけど…え…山登ったの?岩ゴロゴロな感じ火山じゃん…
2019/8/3追記
函館の恵山(えさん)でした!!函館からでも、羊蹄山が見えるなんて知らなかった…!!
はぁぁぁジオみがすごい…
(地学オタクという別の血が騒ぐ)
いつか必ず
ピリカー!ピーリカー!!
って叫んでやる!!
Emina👑@em1nalize
実は道南の北海道駒ヶ岳の方まで行ったのですが、雨と霧で全然ポロチケウエ(室蘭の地球岬)すら見えず…天気がよかったらピリカー!と叫んだ恵山まで足を伸ばそうと思ってただけに、こちらは次回へ持ち越しです。
2019年08月12日 17:13
シーン8 北蝦夷地(樺太)、アイヌの現実①
アイヌが無理やり連れてこられ、強制労働をさせられるシーン。
各地の漁場で商人から搾取される現実を目の当たりにし、武四郎の真っ直ぐな面と、自己を正当化する商人(和人)を象徴する場面でもある。
→2019/7/14追記 これまたちいすけさん情報!北海道開拓の村、旧青山家漁家住宅(ストリートビューへ)
シーン9 ウテルクとヒグマとの格闘
ロケ地:(七条大滝近辺?後ろの崖がなんとなく)
このシーンでウテルクはなぜヒグマと戦ったのか、と疑問を持った方もいるかもしれません。
アイヌの方々は、神々がヒグマに宿ってアイヌへ贈り物(熊肉)をとどけに来ると信じています。狩猟で獲ったヒグマは、神送りの儀式を行い、丁重に扱ってから食していました。
ですが、人を襲うなど暴れるようなヒグマは、「神に見放された存在」とみなし、懲罰の意味で処分します。このときは、丁重に扱うようなこともなく、地域によっては殺したヒグマをズタズタにする地域もあったようです。
シーン10 リセとの出会い、アイヌの現実②
ロケ地:二風谷アイヌ文化博物館、洞爺湖畔(壮瞥町)
ウテルクの妹、リセとの出会いが武四郎を変えていく。
コタン(集落)の男性は北蝦夷地で武四郎が見たように、漁場でボロボロになるまで働かされ、女性は和人の妾にされたという。更科によると、武四郎の書いた「西蝦夷日誌」には、
「請負人より非道の遣方厳しく、夫婦たりとも其夫は遠き場所に遺し、婦を己が妾として別場所に置、孕むときは水蝋樹(イボタ)にトウガラシを加て是を努て呑し脱胎させ候間」(同、P94)
とあり、その酷さを糾弾した。
イ、イボタにトウガラシ…
途中、武四郎が何かを彫っているシーンがあるが、これは篆刻(てんこく)で、つまりはハンコですね。武四郎は北海道に来るまで諸国を旅しながら、篆刻の技術を身につけて、各地の有力者や文化人に売り資金集めをしていた。これが後のリセへの形見にもなるという…
2019/7/17追記:アイヌが結婚をするときや交際を申し込むときには、男性は女性に自分で彫ったメノコマキリという小刀を、女性は男性に自分が織った衣服を贈るんだそうです。武四郎はメノコマキリとまではいかないまでも、篆刻の技術を持っていたので、それをリセに贈ったんですね。
ちなみにわたくし、潤くんのロケの数日前に偶然洞爺湖にいまして…いいですよね、洞爺湖。
追記 2019/8/14、ロケ地に行ってきました。
Emina👑@em1nalize
#永遠のニㇱパ のロケ地を少しだけ。1枚目 #洞爺湖畔 実際にロケした場所は別の場所なのですが、角度的にはだいたい合ってるはず。リセの住むコタンからは洞爺湖の中島が見えていました。 https://t.co/JwcoUoYa9U
2019年08月12日 16:49
(アイヌの踊り、歌、楽器は不思議な響きがあります。和人と全く違う文化だということの象徴のシーンですね。どんな踊り、歌なのかは正直わたしはまだ不勉強ですし、詳しい方がいらっしゃると思うので…後日わかるものを見つけたら追記します)
それにしても、「イチニカが大人になったら、私も死ぬ」とはどういうことなんだろう。
シーン11 リセとの別れ
ロケ地:洞爺湖畔(壮瞥町)
すこし、大石静さんらしいシーンですよね。リセはようやく信じられる人に出会った。もしかするとそれは、神からの贈り物だと感じていたのかもしれない。
一方の武四郎は、アイヌへの思いや商人たちに対する義憤の念から、江戸に帰ることを決めるという…。
更科さんの本によると、武四郎自身、四男坊に生まれ、若い頃から気ままに放浪して暮らしてきて、ようやく世の役に立てるものを見つけたと感じ決意をもって蝦夷地に渡っているので、このシーンは武四郎の意思の強さを表す場面でもあるのかな、と個人的には思います。
リセの「わたしは”ここに住む人”」という言葉が、鍵になっていきますね。
シーン12 松前藩家老と新堂屋・湊屋
西村まさ彦さんのふてぶてしさがすごい。
新堂屋が「熊に食われて死んだのでは!!」ということは、お付きの七之助は帰ってこれたということですかね…
新堂屋が最初、武四郎の旅の手配をした時は、ロシアから攻め入られては自分の商売が成り立たないと考えたのかもしれませんが、まさか武四郎がこのような行動に出るとは思わず、逆に自分の身を危うくしたことに気がついたんでしょうね…。
シーン13 身の危険
武四郎は幕府の屋敷に出向き、出雲守を通して伊勢守に蝦夷地の現状を直訴しようとした。
しかし、証がないと戻され、その帰路で松前家から放たれた刺客の追跡襲撃にあう。
これも、武四郎が実際に経験したことで、実際には6年も隠居せざるを得なかったとか…。更科さんは常に歩き回っていた武四郎にとって、これは辛かっただろうと。
次からが、幕府の役人としての武四郎の旅になるのですが…今日はここまで!
 北海道と名づけた男 松浦武四郎の生涯
北海道と名づけた男 松浦武四郎の生涯