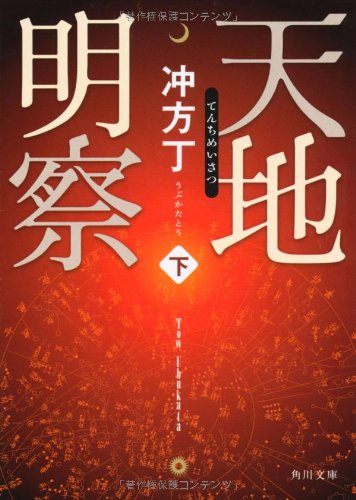三浦しをん『舟を編む』(光文社文庫)は、2012年本屋大賞受賞のベストセラー小説。
2年ほど前にこの小説を読んだとき、ほんとうに “映画を観ているみたいに” 物語世界に没入し、楽しむことができた。
しかも、私のイメージの中で、主人公馬締光也は松田龍平、彼が恋する香具矢は宮崎あおい、国語辞典『大渡海』編集主幹の松本先生は加藤剛の姿で生き生きと展開した。
もちろん、例によって “予告編を観てから小説を読む”という裏技を使ったためである。
さらにこのときは、1、2分で終わってしまうふつうの予告編ではなく、7分あまりもある「特別映像」をYouTubeで見つけて観た。
それでイメージの材料が記憶に豊富にストックされたので、ほんとうに“映画を観ているみたいに”、楽しんで読むことができたのである。
その結果、映画はまだ観ていないのに、すっかり観たような気分でいた。
もちろんそれは錯覚なのだが、実際、Amazon Prime Videoで映画『舟を編む』(2013年石井裕也監督)を見つけたときも、「観たことある」という満足感があって、食指が動かなかった。
それから数か月……
いつのまにか、映画『舟を編む』がAmazon Prime の見放題から外れていた!
いつでも観られると思ったのに観られないとわかると、今まで観ないでいたことを激しく後悔した(身勝手なものである)。
しかし、さいわいNETFLIXで見つけて、観ることができた。
そんなわけで、“読んでから観る” この映画に、まったく違和感はない。
地味な辞書作りに費やす年月が、映画の中でしっかりと流れていく。
大きな盛り上がりはない物語だが、馬締と香具矢の恋の行方はやきもきするし、松本先生には何とか『大渡海』の完成を見せたいと願う気持ちが募る。
見終えてみて、素直にいい映画だと思った。
ただ、ひとつ残念に感じたのは、主人公馬締の内面がほとんどわからない点である。
馬締光也は、他人とのコミュニケーションが極端に苦手で、興味のある対象には徹底したこだわりと抜群の集中力を発揮する。
ASD(自閉スペクトラム症)の典型的な特性を持つ主人公像である。
彼がその特性を生かす「辞書編纂」という天職に出会い、香具矢という女性を一途に愛する。
この小説は、場面ごとに視点人物が代わり、その人物の感想も交えて出来事が描写される。
中には馬締が視点人物の場面もあり、そこでは彼の内心の声も語られる。
例えば……
「最近のジェットコースターは、大きさもひねりも、たいそうなものなんですね。恐そうだな」
「おばあちゃん、私たちに気をつかったみたいだと思わない?」
嚙み合わない。馬締は香具矢を見た。香具矢も馬締を見上げていた。黒い目が、意志と何らかの感情を宿して輝いている。馬締は胸が苦しくなり、なにか言わねばと思ったけれど、どんな大きな辞書を調べても、ふさわしい言葉には行きあえそうもなかった。 (光文社文庫版 P87)
映画では馬締の言動を外から撮るだけなので、こうした彼の内面は見えない。
香具矢への恋も、辞書編纂にかける思いも、表情に乏しい馬締の外面からは読みにくい。
映画を観ている人には最後まで、馬締光也は「変な人」なのである。
同じASD特性を持つ私には、そこが気になった。
香具矢が笑顔で「変だけどおもしろい」と言ってくれるのだけが、救いである。