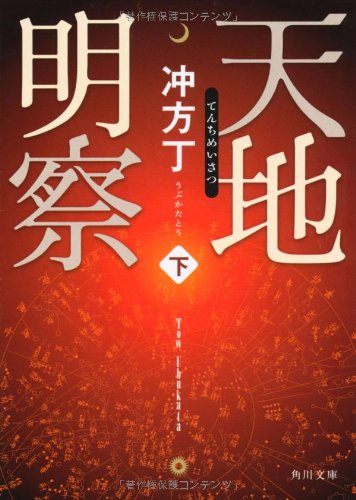2011年本屋大賞受賞作、冲方丁『天地明察』は、数年前に読んだ。
まず、作家の名前の読み方が難しい。
冲方丁(うぶかたとう)は、ライトノベルの作家として知られていたが、初めて挑んだ時代小説で、各賞を総なめにした。
江戸時代初期、天体観測と算術計算を積み重ねて、日本独自の暦を打ち立てた、暦法学者渋川春海の生涯を描く。
上下巻文庫本の帯にあった映画の写真をイメージの手がかりにして読み始めた。
主演は岡田准一だが、自分の中では違う気がして、北村匠海をイメージしたら、しっくりいったので、そのイメージで読み始めた記憶がある。
映画『きみの膵臓をたべたい』を見たばかりだったからかもしれない。
とはいえ、読み進めるうちにイメージは変化し、自分なりの主人公像ができていったのは、いつものことである。
春海の妻となる“えん”は、映画の写真通り、宮崎あおいのイメージで安定して読み進めることができた。
春海は碁打ちの名門家の跡継ぎだが、算術と天文が大好きで、算術の問題が書かれた神社の絵馬を見て、関孝和(和算を確立した天才的数学者)の存在を知り、同時にえんとも知り合う。
1年以上かけて日本全国を歩き北極星の位置を観測するプロジェクト、そして、長年の間に誤差が生じ、正確でなくなっていた日本の暦を正確なものに直そうとする「改暦」に向けた探究、それを実現するための朝廷との闘い。
観測と数理を駆使した自然の真理の探究と、それに基づく新たな暦の創設は、地味な作業の積み重ねだが、それをロマンあふれる挑戦の物語として、みごとに描き出した。
伝記ふうの文章も格調高く、かつ読みやすくて、ありありと場面が浮かんでくる。
文庫本上下2冊を飽きることなく読み終えた。
それから何年か経ってしまった。
ふと思いついて、Amazon Prime Videoで『天地明察』(2012年 滝田洋二郎監督)を観ることにした。
映画は2時間20分。
観始めると、岡田准一の春海にも違和感なく楽しむことができた。
(ちなみに、私は別に岡田准一が嫌いなわけではない。大河ドラマの『軍師官兵衛』はカッコよくて大好きだった)。
映画の前半は、本因坊道策との碁の勝負、関孝和の存在を知るきっかけとえんとの出会い、天文・数理オタクの大先輩二人(建部伝内、伊藤重孝)とともに歩く北極星観測の旅、そして「改暦」の命と、小説通りの展開で楽しめた。
観測儀などの大道具、小道具もみごとで、それらの形を見るだけでワクワクする。
いつもながらジムで走りながら観るので、前半1時間10分余りを観て、いったん中断。
続きは、翌日観た。
すると、後半は小説とは少し違う。
派手な場面も挿入されている。
そこは映画ならではの演出として楽しむことができた。
観終えて、原作小説のよさを生かして、みごとにビジュアル化した映画だと感じた。
飽きさせない展開ののち、達成感、爽快感を味わえる。
さあ、この小説、“観てから読む”か、“読んでから観る”か。
原作は伝記ふうの格調高さとともにイメージを喚起する巧みな文章なので、飽きることがないのは保証する。
しかし、時代劇や天文・数理の話をとっつきにくい、イメージしにくいと感じる向きには、いつもながら、“映画を観ながら読む”のをお勧めしたい。
前半1時間くらい映画を観てから小説を読む。
小説を読み終えてから、映画の後半を見ると、脚色の工夫も見えて、より楽しめると思う。