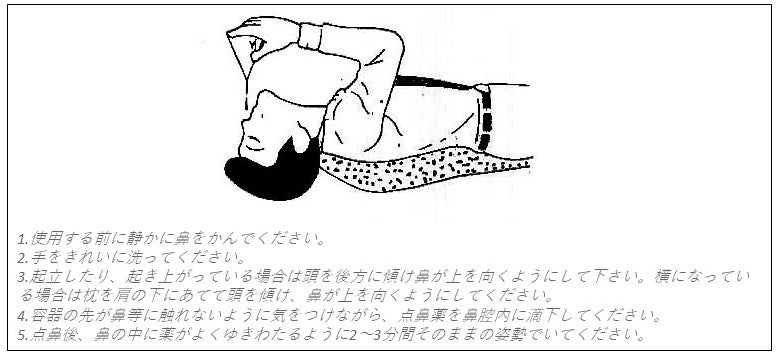毎年、この季節になると”特定医療費(指定難病)受給者証”の更新用の書類の束が送られてきて、またわざわざ病院に行って診断書を貰らって役所に行かなければ(私の場合は、それを家内に頼まなければ)、と思っただけでうんざりします。
それは、以前に「特定医療費支給認定更新」のブログにも書いた通りで、家内は診断書を貰うためだけに病院への往復を含めて7時間以上を費やしました。
そのブログに「皆で、毎年更新制度の反対署名を集めて、厚労省に直訴しましょうか?」と書いたところ、大勢の方から「賛同します」の声が届き、神経難病”安心予後”プロジェクト(SAY-プロジェクト)事務局で種々検討結果、オンライン署名を立ち上げることとなりました。
ご興味を持っていただける方は、下のバナーをクリックしてみてください。
署名を募る理由やその背景、署名方法などが書かれています。
署名にはお金はかかりませんが、運営会社より寄付を求める画面が出ます。これは当署名活動への寄付ではなく、署名サイトへの寄付ですので何もせずページを閉じてください。
書かれている署名方法に従ってスマホやPCで署名に賛同すると、入力したメールアドレスに確認メールが送られてきます。
「認証ボタン」を押して最後のページまでで行くと署名が完了します。
この署名は難病患者やその関係者のみならず、一般の方々の賛同も大歓迎です。
「数は力」ですから、できるだけ多くの方々に情報を流して(シェアして)いただきご賛同をいただければ幸いです。
コメント欄もありますので忌憚のないご意見をいただけると、今後の改善に役立ちます。
この署名が効果を発揮して、特定医療費(指定難病)の手続きが少しでも簡素化されることを願っています。
ご協力の程、よろしくお願いいたします。
スマホでこのバーコードを読み込むことでも署名サイトにアクセスできます。(👇)