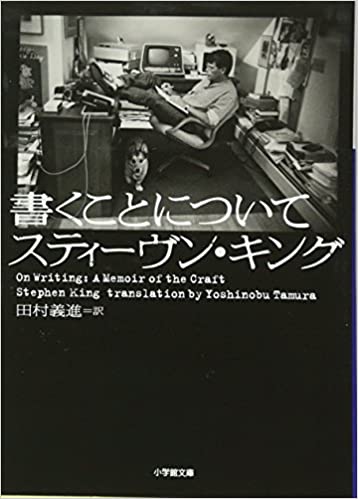★★★☆☆
国民を危険な目に遭わせるのが趣味な王族一家の話。かつての日本なら土井たか子が黙っていなかったね!
国を混乱に陥れる統治者
「未知の旅へ〜〜」と、またしても二人が旅立つわけなんですけどね。全国民が被災者となる災害の直後に国をあけがちですよね、この姉妹は。
↓てっきり「道 の旅へ〜」だと思っていて、どういう語順やねんと悪態をついておりました。すんません。まあイントネーションが悪いからなんだけど。「みち⤴︎(道)」か「みち⤵︎(未知)」か。
VIDEO
私は前作の感想で「ハンス王子は実はよい統治者であった」論 を展開するほど、この姉妹の統治者としての姿勢を疑問視している。国民はいつだってこの二人のせいで生活を脅かされ命の危険すら被っているのに、当の本人たちは気持ちよく歌いながらさっさと旅に出て行きがちなのである。
前回は「ずーっと真冬」という危機的状況に国を陥れた雪の女王であるが(その間ハンス王子が国民に毛布を配るなどの善後策を施していた)、今回は国民を山の高台に避難させたまま 全国民がまだ山の上
よくこれで国民から革命が起きないものである。世襲の国だからそういう概念自体がないのかもしれない。
しかも、護衛も連れない王族たちの旅 の果てに、フタを開けてみれば、アナとエルサのじいちゃんが諸悪の根源という圧倒的なまでに絶望的な真相があったにも関わらず、めっちゃ前向きに——もとい、全然気にせず
アナとエルサのじいちゃんのせいで30年以上も霧の中に閉じ込められていた人たちがいるのだが、他人の30年なんてあまり気にならない のか、エルサは「私があなたたちと国との架け橋よ〜」と愉快に歌って終わっていた。30年以上といったら日本における無期懲役刑の仮釈放が認められるまでの平均的な期間 と同じである。
これくらい「広い心」と「前向きな心」とをもって日本と近隣諸外国も外交問題に取り組めれば、戦後から現在にいたるまでの様々な諸問題もきっとすぐに解決することだろう。もちろん無理
なぜ大人になるとこんなにも素直に映画を観られなくなるのかな〜と悲しみに暮れながら鑑賞したすっかり荒んだ大人となったアタシ。
ちなみに劇場にいた子供達はオラフの一挙手一投足にもちろん大興奮の様子でございました。それが人間としてあるべき姿だと思いました。はい。
記憶のみであらすじを辿ると、エルサが「何か声がする」といって旅に出るという100万回は観たことがあるパターンで旅に出て、オラフがボケて、じいちゃんのせいで対立した部族と会って、オラフがボケて、エルサが徒歩で 愛の力 で全てが解決するというストーリーである(オラフ復活含む)。
総評としては、ストーリーはイマイチですが、オラフの愉快さがとても心に染みるハートウォーミングな作品です。
オラフの声問題
で、そのオラフさんだが、周知のとおり我らがピエール瀧は雪だるまの声を降板してしまった。まったくもって当然の処置であるが、そこで問題となるのが「新オラフの声を受け入れられるかな?」という不安である。
まったく無問題
でありました。
ここまで問題ないと、逆に寂しさすら漂ってくる。つまり、ピエール瀧でなくても良かったんじゃないかという問題——ひいては、「あなたがやっている仕事は、きっとあなたでなくても良い」 という誰もに当てはまる問題へと繋がってくる。
ナンバーワンにならなくてもよい、元々特別なオンリーワン——そう歌った方達がナンバーワンの座から転落したら、5人中3人ほどはオンリーワンの存在を発揮する機会を失ってしまったように、オンリーワンであることはとても難しいことである。たとえ自分はオンリーワンであると思ってやっていても、転勤や配置換えがあっても何事もなかったかのように回り始める仕事の仕組みに、「ナンバーワンになることの方が実は簡単なんじゃないか……?」とすら思えてくる。
組織の中でナンバーワンは必然的に誰かがなるわけであるが、オンリーワンがいなくても組織は成り立つ。むしろオンリーワンの存在が組織にいて、もしその人に頼りきっていることがあるのなら、それは危険信号であるとすらいえる。その人がいなくなったら回らなくなる仕事があるのなら、それは組織の脆弱性に直結するからだ。やはりシステムはもっと冗長化しなければいけない。
ということで、ピエール瀧の不在は大勢にまったく影響がなかった という話でした。むしろどんな声だったかもはや思い出せない。寂しい。
実は続編があるディズニー作品
私は正直『アナと雪の女王』自体あまり面白くなかったので、本作もイマイチであった。続編はなお面白くなかったという印象である。1作目を超えられないのは大ヒット作の続編のあるいみでは宿命的なことであるのかもしれない。
で、続編の話。
有名どころのディズニー作品であっても、実は人知れず続編が制作されていることがある。人知れずというのは、要するに劇場公開されていない「ビデオスルー」というやつだからである。
劇場公開されていないといっても、そのクオリティは本編(1作目)とほどんど変わらないところが、アニメ作品の良さであり、難しさでもある 。続編のクオリティに満足する一方で、劇場でアニメ作品を観る意義というものがなんとなくモヤモヤするのである。この感じ、伝わりますかね?
しかし何はともあれあの有名作品にも実は続編があるんだよ〜ということお伝え&オススメしたい。
シンデレラ
シンデレラⅡの感想
シンデレラⅢの感想
いきなり最もオススメの続編を紹介してしまう。
私はディズニープリンセスで間違いなくこのシンデレラが一番好きである。その想いを抱くに至ったのは、何を隠そうこの続編を観たからに他ならない。
「Ⅱ」は、サザエさんのように三本立て構成で、特に1話目はシンデレラの強靭な精神力と肝の据わり方が描かれていてる。王子様との結婚後、新参者(シンデレラ)が己の権力を利用して次々と城のしきたりを自分の都合よく改変していく様は、内閣が叫ぶ大改革よりもよほど大きな変革の渦を生んでいた。最後に自身の教育係に放つ名言「あなたとは仲良くやっていけそうね」は新しく赴任してきた上司の辣腕パワハラに怯える社員たちには胸にグサッとくる一撃となりそうである。
また3話目では、義理姉アナスタシアとパン屋の主人との恋が描かれ、その恋を成就させようとここでもシンデレラが縦横無尽に活躍する。この恋は「Ⅲ」で無かったことのようになっている が、「Ⅲ」ではアナスタシアはかなりトーンダウンしていて、「Ⅱ」を受けての制作陣の「どうしよう」感が伝わってくるようである。
「Ⅲ」では、継母の極悪非道っぷりが一線を超えてもう笑えてくる 継母無双が始まる のである。ここまで清々しい悪役ぶりも、昨今ではすっかり珍しいのではないだろうか。こんなやつと再婚したシンデレラの亡き父親が諸悪の根源 であるとしか思えなくなってくる次第である。
↓3作セットなんてのもあるのね〜
アラジン
ジャファーの逆襲の感想
盗賊王の伝説の感想
私はアラジンという男をクズ だと思っているのだが、この続編はそうした私の想いに同意してくれる作品である。1作目をきちんと鑑賞していただければわかることだが、アラジンは本当にどうしようもない奴で、お姫様のジャスミンはダメ男に熱を入れてしまう典型的なダメ女である。一度の優しさで「彼は本当はいい人なの〜」というタイプだね!
「Ⅱ」は悪役ジャファーの復讐譚である。ランプの精となってランプに封印されてしまったジャファーが復讐しにきて、ランプから解放されたジーニーでは対抗できずどうしよ〜となる。しかしそんなことはどうでもよく、大切なのはアラジンが王宮でめちゃ嫌われている という点である。素晴らしい。衛兵から「このどぶねずみが!」などと叫ばれる。素晴らしい。
「Ⅲ」はアラジンの父親にまつわる話である。まあつまりは盗賊王で、アラジンとジャスミンの結婚式を台無しにした張本人なわけなのだが、そんな事実が判明しても一国の王女はアラジンと結婚する。盗賊の息子で、本人の経歴もロクでもない人間と。これくらい国家に寛容さがあれば、相手が留学したまま延期だか中止だかよくわからないままになっている某国のプリンセスの婚約騒動もあっさり片付くことであろう。小さき島国の国民はここまで寛容ではないようである。
↓こちらも3巻セットがあったのね〜
ライオン・キング
ライオン・キング2の感想
ライオン・キング3の感想
あの『ライオン・キング」にも続編があったのだ!
しかも、『2』の出来はかなり良く、ぶっちゃけ『アナ雪2』なんかを劇場公開にするなら(トゲのある言い方)、十分劇場公開しても良かったのではないかと思うくらいの完成度である。
『2』は前作の主人公「シンバ」の娘(なんとラストシーンで生まれたライオンはメスだったのだ!)が主人公となり、前作の悪役「スカー」とロミオとジュリエット的な絆を育みながら大冒険をする話である。こんな簡単なあらすじでもなかなか良さげじゃね?
一方『3』は結構余計な話を作っちゃったな〜という印象の内容で、あのイノシシとミーアキャットがどのようにして『1』のストーリーに関わることになったかを描く「『1』の舞台裏」的な作品となっている。それが余計なのである。
たとえば、シンバの父親がスカーに殺されるシーンは結構シリアスな場面であるべき だと思うのだが、実はあの2匹もその場にいてドタバタしてました〜テへ、みたいなことが描かれるのである。
というわけで、『2』が好きで『3』が嫌い、という個人的な感想。
↓やっぱりあった3巻セット。
リトルマーメイド
リトル・マーメイドⅡの感想
リトル・マーメイドⅢの感想
「Ⅱ」はアリエルと王子様の間に生まれた子供の話である。上記『ライオン・キング』と同じ構成である。というか、ストーリーラインもほとんど同じである といっても過言ではない。
ディズニー作品に出てくる「親」という存在は、やたらと子供に説明を端折る というダメな子育ての典型をするのだが、あれほど父親の姿勢に反発していたアリエルも、自分の子供には父親とまったく同じ姿勢で 上から押し付けるような物言いをするので、子供はかつての自分のように反発し、どっかいっちゃうのである。「親の背中を見て子は育つ」の負の方面のスパイラルを描く作品であるともいえる。
「Ⅲ」は一作目の前日譚で、海の中の物語である。独裁者(アリエルの父)に音楽を禁止された世界で、夜な夜な開かれる音楽パーティーに「あんだーざ・し〜」で有名なあのセバスチャンが参加していたことが発覚したため大騒動へと発展する。
まあいつの時代も「禁止された物で反社会的勢力は潤う」という構図は同じなのである。禁酒法時代には酒が売れ、現在では大麻や覚せい剤が暴力団の資金源になっているのと同じように。
↓もちろんあった3巻セット
ターザン
ターザン2の感想
ターザン&ジェーンの感想
私はターザンが嫌いである。なぜなら、自分の責任に無自覚 たターザンの無責任っぷりは幼少期から形成されていた ということが丁寧に描かれる。こいつ、マジでクソだと思うのである。こういう奴が職場にいると非常に迷惑なのだが、こういう奴に限って周りの迷惑を考えずに自分いい仕事してる〜感を出すので、迷惑を被った点を大人の気遣いを含ませながらゆる〜く指摘すると、キョトン顔をされていっそう腹立つ パータンなのである。
『&ジェーン』の方が正当な続編というか後日談で、ターザンが住む島が近代化していて、ジェーンのかつての友達が平気でたくさん遊びに来たり観光ガイドがあったりする。『1』のラストでジェーンは迷った末にジャングルに残ってターザンと共に暮らすことを選んだのだが、これなら嫌になったらいつでも帰れる 勢いであるので、そんなに悩まなくても良かったねという後日談でもある。
↓ついに3巻セットがない作品が……。「1」&「2」のセット。
わんわん物語
わんわん物語Ⅱの感想
『Ⅱ』は『Ⅰ』の完全なる続編で、王道パターンである「前作の主人公カップルの子供」が主人公である。『Ⅰ』の主人公は野良犬だったが、無事室内犬と愛を育んだ のでその子供は見かけは主人公にそっくりでも室内犬として育った。そのため「外の世界が知りたい!」と言いだし、例によってディズニー作品伝統のダメ親 となった前作主人公が頭ごなしにダメダメ言うもんだから外の世界に飛び出した——という話である。『1』での悪役は子供を預かるには人間性に問題があった 飼い主の伯母であったのだが、『2』で主人公が飛び出すきっかけとなったことを起こしたのは飼い主の息子であり、2作続けて観ると「この家系にはロクでもない奴らしかしない」と思う次第である。
↓2巻セットありました。『わんわん物語』という邦名がどうかと思う原題がわかるパッケージ。
アトランティス
アトランティス 帝国最後の謎の感想
『アトランティス』といえば『ふしぎの海のナディア』のパクリで有名な作品である(ガイナックス社長の逮捕!)。1作目は『失われた帝国』というサブタイトルが付いており、ラストシーンで主人公はその失われた帝国であるアトランティスに残る選択をする。作品としては全然面白くない のだが、それでも続編が作られるあたりにディズニーの言葉にならない意地を感じる。
で、続編である『帝国最後の謎』はアトランティスに残った主人公の後日談となるわけだが、主人公たちが雑なんだか出てくる敵がバカなんだかわからないが、とにかく大味な展開でドッタンバッタンする話である。まああまり面白くはない。
美女と野獣
美女と野獣 ベルの素敵なプレゼントの感想
今までの作品群は「続編」か「前日譚」かのパターンであったのだが、名作『美女と野獣』の場合は少し毛色が異なる。
『ベルの素敵なプレゼント』は、あの有名な二人のダンスシーンに至るまでを挿話として描いている。が、いろいろとつじつまが合わないところもあるのでパラレルワールド的な描かれ方をしているといえる。「細かいことはいーんだよ、うっせーな!」というディズニーの心意気を感じる作品である。
本筋の作品では「オオカミに襲われたベルを野獣が助ける」という過程を経て二人の心が溶け合ってゆく(淫靡な表現)わけだが、この作品は「その後もいろいろピンチがあって二人は溶け合ったのです(淫靡な表現)ということを描く。オオカミに襲われたこととかもはや石につまずいた程度のことだったと思えるようなことが二人を襲うのである。
『ベルのファンタジーワールド』は実は未見であるので何も述べることはできないが、4話構成のショートストーリーであるらしい。
ピーター・パン
ピーター・パン2の感想 ネバーランドの秘密の感想
フック船長はワニが苦手なのだが、その理由をみなさんはご存知だろうか?
「ワニに腕を食われたから」
は間違いである。答えは
「ピーター・パンに腕を切り落とされて ワニに食われたから」
である。ドラえもんが居眠りしてて耳を齧られたせいでネズミが苦手となったこととは明確に異なる線引きがここにはある。私だったらワニよりもピーター・パンが苦手になる
このように『ピーター・パン』という作品は、世間が抱くイメージと反して、決して生易しい物語ではない。
『2』の冒頭にもそれは如実に表れている。主人公はディズニー続編シリーズの定番である前作の主人公ウェンディの娘であるのだが、まずこの娘の父(ウェンディの夫)が戦争に徴兵される 当然の怒り
そんな中、ふて寝をしてしまった主人公の元に、戦闘機の合間をかいくぐって フ ック船長がやってくきて——というのがストーリーである。
この他、ピーター・パンの性格が悪すぎて、ピーター・パン症候群ではダメだな、ということが暗にわかる話となっております。
以上、『実はあのディズニーの名作には続編があった!』まとめでした〜