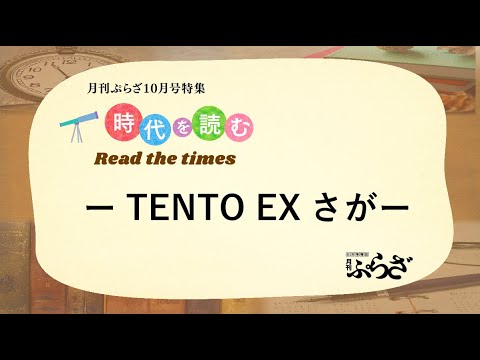こんにちわ。
佐賀市で「ICT教育×eスポーツ×遊び場」を運営しているDigitalStudyです。
子供向けプログラミング+パソコン教室や大人向けパソコン教室など各種デジタル教育の教室を運営しています。
先日FORTNITEという小学生に大人気のゲームの小学生限定の大会を開催した際に、大会中のマナーに関して説明した際に面白い反応がありました。
「ゲームマナーとして、死体撃ち、煽り屈伸はマナー違反だから禁止です」と説明した際、保護者の方から「え、そうなの?」というリアクションがあり、子供たちからも「え?そうなんだ!?」という声がありました。
リアルでもマナーに関しては様々な観点から、時として揉め事の種になります。
今回は保護者の方が一番気にしているであろう子供たちの罵詈雑言に関する記事です。
罵詈雑言の原因は味方に対して
これ、結構意外に取られます。
エビデンスやデータがあるわけではないですが、ゲーセンに20年勤めていた私が勤務中に大声で切れる人をずっと見てきましたが、体感として敵にキレるのではなく味方にキレるケースが圧倒的に多いです。
これはゲームに限った話ではなく、集団行動を是とする日本人として、「足を引っ張られる行為」というのを嫌いますよね。
敵が強くて負けたというのは単に自分が弱いからという理由があって納得できます。
例えそれが理不尽なものであったとしても、対策できなかった自分が悪いという事で納得できる部分があるからです。
しかし、ゲームセンターのゲームはチームとして全国各地のゲームセンターから無作為で選んだプレイヤーでチームを組み、チーム単位で対戦するゲームが主流になるにつれ、足を引っ張った味方への罵詈雑言が増えて来るわけです。
つまり、遊ぶゲームの種類によって言葉遣いが悪くなるかどうかがわかるわけですね。
罵詈雑言の象徴、League of Legends
ゲーム好きなコアゲーマーでもプレイを躊躇してしまうゲームがLOLと呼ばれるLeague of Legendsです。
eスポーツタイトルの中でも最大規模を誇るユーザー数で、世界で一番スタンダードなゲームです。
日本にはあまり馴染みがないですが、全国のeスポーツ部がある高校ではこのゲームがほとんどと言っていいほど採択されています。
チームの連携がものすごく重要であるがゆえに、初心者が足を引っ張るとチームの仲間から袋叩きにあいやすいという事でも有名です。
連携が重要なのでボイスチャット等を通じてコミュニケーションを取りながらプレイする必要があるのですが、自分のミスで負けてなじられようなら、もうこのゲームしたくない…と思ってしまいます。
逆に言えばチームの絆が重要視されるゲームですので、連携を取って勝利した日にはこれ以上に絆を感じる事はないです。
このタイトルをメインにしているeスポーツチームは衣食住を共にするゲーミングハウスと呼ばれるシェアハウスを活用していたりするほど、チームのコミュニケーションを重要視します。
さすがにこれは究極系の話だと思いますが、大なり小なりチームを組んで遊ぶゲームはこの世に多数存在します。
味方への罵詈雑言はゲームに限った話ではない
世の中にはチームで戦うスポーツがごまんとあります。
サッカー、バスケ、野球、バレー…etc
部活の中で足を引っ張る選手がいれば、それがいじめに直結したりと問題になるのはゲームに限った話ではありません。
ではなぜゲームだけピックアップされてそういうイメージがあるんでしょうか?
それは「監督」の存在です。
部活には顧問、監督という大人が存在し、チーム連携における問題点に対して監督がフォローアップします。
しかし、ゲームのチームプレイはeスポーツ部でない限り、それらをコントロール、フォローする人がいません。
ですので無法地帯になりやすいという事になります。
逆に言えば、大人が介在しない場所でサッカーなどをやれば、ゲームと同じく味方に対する罵詈雑言やいじめの嵐になる可能性は高いです。
この問題をどうフォローアップしていくか?は、ゲームをeスポーツ部に限定するか、保護者が監督としてコントロールする以外ないと思います。
マナーの捉え方、考え方の違いが罵詈雑言を生む
ゲームセンターで人気の、鉄拳と呼ばれる大人気の格闘ゲームがあります。
このゲームは他の格闘ゲームと違って、相手に勝利した後数秒間自由に動けるタイミングがあり、その後次の試合に進むという仕様になっています。
自由に動けるタイミングがありますので、この時間を使って倒れた相手にさらに追い打ち攻撃が可能となっています。
この追い打ちにゲーム的な意味はありません。
次の試合に有利になるわけでもなく、ただ自由な時間です。
これを俗称「死体蹴り」と呼びます。
ですので、負けた側からすれば、「負けが確定しているのにさらに攻撃を続ける煽り行為だ」と捉えて怒る人がいます。
一方で、これがマナー違反という常識であるなら、それができる時間を作ったメーカーがおかしい。
何年も新しい新作ができているのに、この仕組みがなくならないのはマナー違反ではないからだ。
と捉える人もいるわけです。
鉄拳はゲームセンターで大人気商品でしたので、この死体蹴りをめぐってプレイヤーがしょっちゅう揉め事を起こしては仲裁に入るという事をしていました。
私としては「どっちでもいい」が感想です。
自分が嫌ならやらなければいいだけですし、マナー違反でないと考える人の理屈も正しいと思いますので、自分はやらないだけで人に強制するものでもないと思います。
明確な悪意を持ってやったらマナー違反だと思います。
こういったマナー違反に対する認識がズレると、それが悪という捉え方になるので、文句を言ってしまうという事になります。
なので我々は公式の大会ではマナー違反の考え方に関する説明を事前に行う事が多いです。
しかしながら、これもゲームに限った話ではなく、近年では「挨拶を強要するのはマナー違反だ!!挨拶を禁止しろ!!」というマンション組合の中で一部の方で意見があって、そのマンション自体が挨拶禁止になったというニュースがあるくらい、ゲーム以外でもよくある話です。
ゲームだから口が悪くなるという事には直結しないんですよね。
ゲーム特有の内弁慶の環境
ゲーム独特の環境というのがこれで、ネットも同じですが、ケンカ相手が目の前にいないという事が罵詈雑言の原因とも言えます。
ゲームセンターのゲームもオンラインで繋がっており、全国各地のゲームセンターにいる人が対戦相手になります。
目の前に対戦相手がいないので、調子に乗って煽ったりするわけですね。
ですが、稀に煽られて本気でブチ切れて、遠い所からわざわざ煽られた相手の所までやってきてケンカになるケースがありました。
もしくは店に電話で「今お前の所の〇〇というゲームの所に〇〇というプレイヤーがおるやろ!!電話に出せコノヤロー!!」というブチ切れ電話が定期的にかかってきます。
そうなると調子に乗っていた人が急激におとなしくなるわけです。
ケンカがしたいから煽ってるわけではなく、ケンカにならない事がわかってるから煽るわけですね。
実際乗り込んできた人から煽ったプレイヤーを守らざるを得ない状態になったりするケースもあり、相手をなだめつつ煽ったプレイヤーに謝ってもらって場を収めるケースもありました。
我が家でも子供が煽ったりしていたら、「直接そいつの所に行って煽ってやろうぜ。ほら行こう」「目の前にいないからケンカ売ってるだけってダサくね?」「ケンカしに行こうぜ」と誘い続けたら、煽らなくなりました。
安全なエリアで相手をバカにすることがいかに恥ずかしい事か?という事を、学ばせる必要はあると思います。
但し、これについてはSNSで芸能人を攻撃する人たちと変わらないわけで、ゲームだからというのも違いますよね。
現実に起きている事をゲームのせいと押し付けるのは簡単
逆にこうは考えられませんか?
ゲームが原因で発覚したので、ゲームを通してそれらを学ぶきっかけができた。
だから現実でもそこに気を付けるようになった。
「口が悪くなるからゲームは禁止」と対応する事よりも、それをうまく使って子供の成長に繋げられたらなぁ…と思います。