こんにちわ。 佐賀市で「ICT教育×eスポーツ×遊び場」を運営しているDigitalStudyです。 子供向けプログラミング+パソコン教室や大人向けパソコン教室など各種デジタル教育の教室を運営しています。 https://stat.ameba.jp/user_images/20240605/00/digitalstudy/43/c6/p/o1366059615447565748.png"> alt="" height="183" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20240605/00/digitalstudy/43/c6/p/o1366059615447565748.png" width="420"> プログラミングを何歳から学べば適切なのか? その答えは「早ければ早いほど」です。 幼児からパソコンスキルに触れることでより子供の未来が広がります。 今回はその理由を3つのご紹介いたします。 1.タッチタイピングの入力速度には年齢の壁がある https://stat.ameba.jp/user_images/20240605/00/digitalstudy/0e/dd/j/o0511034015447565796.jpg"> alt="" height="279" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20240605/00/digitalstudy/0e/dd/j/o0511034015447565796.jpg" width="420"> ブラインドタッチができない大人が多い中、タイピングの訓練期間と結果を分析した結果があるのですが、パソコンが得意な方で一般的に「早い」と思える速度が5分間で400字と言われています。 これは手書きの約2倍くらいの速度という事で、手で書くより効率的だという事が言えますね。 では、5分間でその倍の800文字の速度で入力できるようになるのは、ほとんどが小学生の低学年から始めた方なんです。 絶対音感も幼児のうちに育てておかねば失われるという言われているように、このタイピングスキルも年齢が上がると共に向上の壁が出てきます。 入力が早いほど効率も上がり、それによりPCを使った全体的な作業でその効果を発します。 例えば仕事で報告書をWordで作成するにしても、そのスキルは生かされますし、「しゃべる」とほぼ同じように「入力する」は毎日当たり前のように行われているスキルです。 幼児から始めるにはまだ早いんじゃないか?と悩まれている保護者の方も多いかと思いますが、むしろ今から学ぶ方がいいのです。 2.情報を調べる基礎力が身に着く https://stat.ameba.jp/user_images/20240605/00/digitalstudy/20/aa/j/o0640042715447565924.jpg"> alt="" height="280" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20240605/00/digitalstudy/20/aa/j/o0640042715447565924.jpg" width="420"> よくプログラミングに関するサイトで子供に役に立つ能力として ・論理的思考 ・問題解決能力 ・創造性 などが取り上げられますが、結局具体的に見えないですよね? そこでわかりやすい例を出していきたいと思います。 プログラミングは構文の順番が一つ違うだけで全く違う結果になります。 一つの構文の位置ミスで今まで動いていたものが動かなったり、永久に動き続けたりします。 その時に「なぜうまく行かないのか?」を試行錯誤します。 学校の教育現場においては基本的に生徒は「教えられる」という一方向になりがちですが、プログラミングの授業は常に自分が発信する側に回ります。 この繰り返しが自ら思考して問題を解決する習慣が身につけさせます。 普通の人はわからない事が出ると人に聞きますが、問題解決能力が高い子供は、わからない事がでるとGoogle検索や辞書等で自分で調べる事を優先し、自分で解決するようになります。 「ggrks」(ググレカス)という言葉をご存知でしょうか? ちょっと汚い言葉ですが、昔のPCスキルが高い人は、人から何か聞かれるとすぐこの言葉をいいました。 「PCスキルが高い=自分で調べる力がある」に直結していると言えます。 そして、プログラミングで何かを作る際は、文字だけでなく動かすキャラクターも作る必要があります。 作ったゲームに音楽をつけるかもしれませんし、難易度や面白さを調整する事で、遊びながら想像力が培われていくわけです。 これが子供からプログラミングを子供から学ぶべき理由その2です。 佐賀市のとある大人向けパソコン教室のHPに面白い事が書いてありました。 「パソコン教室」という検索をした時点で独学に向いていない。 全く同じ意見です。 私も独学でほとんどの事を学びましたが、スクールを検索するのではなくもっとピンポイントで情報を調べます。 例えば今回私は脱サラして起業したのですが、起業スクールを検索したわけではなく起業テクニックをYouTubeなどでダイレクトに検索して学びました。 特に創業融資を獲得するにあたっては、YouTubeをフル活用して創業融資を成功に導くテクニック系の税理士や中小企業診断士の動画を探しては勉強しました。 結果個人事業主としてはかなり条件が厳しかったはずの融資を満額審査が通るという事になりました。 情報を調べる力が身に着けば、余計なお金を支払うことなく無料で学びを得る事もできるようになります。 特に現代は情報にあふれていますし、芸能人のフワちゃんも言ってましたが、「YouTubeで学べないものはない」という言葉のごとく、学べる素材はネットに溢れているとも言えます。 これらを活用できる検索スキル、探索スキルは将来において大きく役に立つ事でしょう。 3.学びの時間が確保しやすい https://stat.ameba.jp/user_images/20240605/00/digitalstudy/c4/d0/j/o0454034015447566058.jpg"> alt="" height="315" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20240605/00/digitalstudy/c4/d0/j/o0454034015447566058.jpg" width="420"> 特段プログラミングに限った話ではないのですが、答えは「時間」です。 大人と違って子供は学ぶ時間が存在しますが、大人になってから学習の時間を確保するのは非常に困難です。 当店では大人向けのパソコン教室も運営しておりますが、大人の入会に至らない最大の理由は「時間が噛み合わない」です。 通常学習において簿記や宅建などは、今までの社会経験の知識が基礎として役に立つことが多いですが、デジタル系の学びはそもそも基礎知識がない所からスタートします。 私はよく昔からパソコンに関して教えて下さいと頼まれるケースが多いのですが、まだ人に教える事に慣れてない時は「何語をしゃべってるのかわからない」と言われてました。 そもそもデジタル系の用語は英語が基本であり、言葉の意味から勉強する必要が出てきます。 多くの大人たちがデジタルに対して距離感を置くのは、この「用語がわからない」につきるのではないでしょうか? ある一つの事を調べるのに、わからない用語に引っかかり、まずその用語を調べる。 しかしその用語に書いてある別の用語の意味がわからない。 自学で進めるのには時間との闘いが大きいです。 もし少しでもデジタルに対する基礎知識があれば、自分で調べる事もできますが、その基礎知識を得る事ですらそこまで時間が割けないというのが大人のパソコン学習の難しい所だと思います。 プログラマーのような専門家にならなくても、自分で起業する、会社で管理者側になるなどすればデジタル化は避けられません。 そうなる前に子供のころからデジタルの基礎知識を学ぶ事が重要かと思います。 この3つの理由により、「大人になってから学ぶ」というのはなかなか現実的に難しいという所です。 お子様にプログラミングを学ばせたいと思った時に引っかかるプログラミング教室の違いについてはコチラ https://ameblo.jp/digitalstudy/entry-12853488784.html" rel="bookmark">プログラミング教室、何が違うの?
こんにちわ。
佐賀市で「ICT教育×eスポーツ×遊び場」を運営しているDigitalStudyです。
子供向けプログラミング+パソコン教室や大人向けパソコン教室など各種デジタル教育の教室を運営しています。
今日は「プログラミング教室の具体的な内容ってどんなもの?」について記事にしたいと思います。
とは言っても他社の授業の内容まで全て把握しているわけではありませんので、当教室の授業の流れを今回はご紹介いたします。
まず最初にヒアリングからスタート
無料体験の時にも行いますが、まず最初に行うのはヒアリングからスタートします。
・今までPCを触ったことがあるか?
・PCでゲームをしているか?
・学校でPCを使った授業を受けたか?
各質問の中でどこまでできて、どこからできないのか?を見極め、子供のスキルに合わせて初期の授業を構築します。
以降は初めてのパソコンという前提で進めていきます。
タッチタイピング
タイピングがどこまでできるか?にもよりますが、初めてPCを触る子供に対しては第一歩として「ローマ字」を理解できるか?です。
まずこのローマ字が理解できていないと入力のしようがありません。
かな入力でも入力できない事はないですが、かな入力で一度覚えてしまうとクセがついて矯正が非常に難しくなります。
ですので、ローマ字がわからない場合は、まず英語のABCからスタートして一文字ずつタイピングを入力する訓練を行います。
タイピングのホームポジションの位置を覚え、「GGG、JJJ、FFF」などキーボードの下から二段目だけで指先を使って入力する訓練です。
ここからスタートして様々な段の入力を行って行きます。
その際、当教室は「ナレッジタイピング」というシステムを使って指導します。
こちらはよくあるタイピングゲームのような構成になっていて、入力の正確さやスピード等をスコア化して、子供たちのやる気を引き出す仕組みになっています。
タイピングのレベルに応じて難易度が設定されており、ローマ字を知らない子もタイピングゲームを通してローマ字を覚えていく流れになっています。
初日はこのタイピングを30分ほどやって、初級の別のアプリを使う授業に以降します。
ある程度慣れて来ると、タイピングは15分程度で終わらせるようになり、できるようになると、10分程度の毎回全国ランキングに挑戦できるスコアアタックに挑戦して終了という流れになります。
ワード、エクセル、パワポの基礎授業
無料体験でスクラッチを体験しますので、スクラッチの授業がと思いきや、最初の3か月程度はワード、パワポ、エクセルの基礎的な操作を勉強します。
これは、いきなりプログラミングだけやっても総合的な力がつかないので、まずはアプリの操作が基本的に共通である事。
クリックやダブルクリック、ドラッグなどの基本操作や、コピー&ペースト、アンドゥ、リドゥなどを覚える事にあります。
これら基礎知識が備わると、スクラッチの理解がより深まっていきます。
3種類の基礎授業の進め方は生徒にお任せ
同じアプリだけをひたすら進めてしまうと生徒にも飽きが来ますし、一つのアプリの深度だけを掘り下げると総合的な力が養いにくいので、今日はエクセル、明日はパワポ、その次はワードという形で覚えるアプリを切り替えて行きます。
色んなアプリをバラバラで教えて混乱しないか?という心配があるかと思いますが、アプリは違えど操作の基本はほぼ同じです。
ワードで覚えた事がパワポで使えたり、パワポで覚えたことがエクセルで使えるので、逆に生徒達はアプリは違っても基本は同じなんだという事を学びます。
アプリごとにミッションが細かく区切られており、最初のうちは1つのミッションを2回分の授業時間を使ってクリアしていくイメージです。
大人も同じですが、エクセルを覚えてもワードが使えないと思いがちですが、基本的な仕組みは一緒なのでなんとなしで使えるようになります。
1つのミッションをクリアすると、生徒に「次はどれにする?」とアプリを決めてもらって進めていくので、自主的に選択した授業へのモチベーションは基本的に高いです。
ある程度の基礎ができてからプログラミング授業へ移行
基礎的な力がついてきたら、タイピング、ワード、エクセル、パワポに続いてスクラッチが追加されます。
スクラッチもミッション式になっており、他のアプリと同様に生徒の自主性においてミッションを進めて行く流れです。
プログラミングは考える時間が必要になって来るので、1ミッションで3~4回分の授業時間のイメージです。
定期的に資格取得の為のテストを行う
ある程度の力がついたと判断したら、色んな試験に挑戦します。
「毎日パソコン入力コンクール」や「ジュニアプログラミング検定」など様々な検定試験を受け、節目と目標を作成していきます。
定期的に情報リテラシーの為の講義やプレゼンの訓練
嘘の情報を見抜く話や、SNSでの住所が特定される原因の話などの講義をイベントとして任意参加で実施します。
こちらは教室の生徒だけでなく外からも参加を募りますが、生徒優先で行います。
それ以外にパワポを使ってプレゼン資料を作成し、発表する授業なども定期的に挟んで行きます。
当プログラミング教室の平均継続率は4年の為、長くしっかりと姿形を変えて幅広く教えていく
という形になります。
また、バレッドキッズの中でも当教室はeスポーツに特化している所もあり、教室以外の所でフォートナイトの小学生限定大会
であったり、学び以外の部分での楽しいイベントに参加できるというのもウリになります。
今回は初めてのパソコン+プログラミング教室という形でのご紹介となりましたが、すでに上級者になっている生徒などに対しては、スキルに合わせて一気に授業をすっ飛ばして、濃い内容の授業に切り替えて行きます。
最後までご覧いただきありがとうございます。
当バレッドキッズは無料体験を常に実施しておりますので、「体験してみたい!!」と思われたらお気軽にご応募下さい。
こんにちわ。
佐賀市で「ICT教育×eスポーツ×遊び場」を運営しているDigitalStudyです。
子供向けプログラミング+パソコン教室や大人向けパソコン教室など各種デジタル教育の教室を運営しています。
今日は「プログラミング教室のオンラインとオフライン どっちがいいの?」について記事にしたいと思います。
最近ネット広告で子供向けプログラミングの広告が活況になって来ていると思います。
それも、2025年大学共通テストで「情報Ⅰ」がスタートし、国語算数理科社会の主要科目に情報が仲間入りするという事で、情報教育、プログラミング教室に関しての興味関心が高くなってきているからという背景があります。
私もやはりその波を狙って事業を立ち上げたという事もあります。
さて、数あるプログラミング教室で、プログラミング教室の違いについてはプログラミング教室、何が違うの?で記事にしてますのでこちらをご覧下さい。
本日の本質は「オンラインスクール」と「オフライン教室」のメリット、デメリットを解説します。
というのも実は、当教室は子供向けはオフライン教室、大人向けは自学教室スタイル、専門的なスキル獲得や資格獲得は当教室からのオンライン教室と、サービスごとに学ぶスタイルが変わるハイブリッド教室なんですね。
オンラインスクールの授業ってどんなもの?
オンラインスクールの授業は基本ZOOMなどを通して行う授業スタイルとなっており、先生と生徒が1対1または1対5などのマンツーマン、少数個別指導のスタイルか、一気にまとめて多人数がZOOM上に存在し、わからない時に先生にヘルプを求める自学スタイルなどがあります。
先生の講義をパブリックビューイングのように見るというパターンもあります。
オンラインスクールのメリット
なんといっても自宅で受けられるという利便性ですね。
送り迎えなし。
子どもも自宅なのでリラックスして受けられる。
全国を対象にしているので、先生も専門的な先生が多くスキルレベルがとにかく高い。
自分生活スタイルに合わせて教室を選べるので時間の調整がしやすい。
オフラインよりも授業料が安い傾向がある。
オンラインスクールのデメリット
他の生徒との交流がもてないので、モチベーションの維持が難しい。
兄弟一緒、友達と一緒になどがやりづらい。
オンライン授業を受ける為の環境整備が必要。
先生と生徒の授業以外のコミュニケーションが取りづらい。
子どもの場合はしつけの部分で統制が取りづらい。
子供の些細な変化を見抜けづらい
親がセッティングしないといけないので、親のスキルが必要。
オンラインスクールの総評
専門的に学ぶという意識があるなら、オンラインの選択肢が強いと思います。
目的が明確なので、オンラインスクールを受ける為の環境整備の費用であったり、授業を受ける為のセッティングに対してしっかりとできると思います。
もちろん子供の学ぶ意欲が高い前提ですので、モチベーションの維持も目的があれば保てます。
専門的な講師も多いのでより専門的な学びを得られるでしょう。
しかし、初心者や明確なプログラマーなどの目的が明確でない場合、スクールの学ぶ以外の重要な点として、立派な人間として成長するという点において、仲間であったりしつけであったり、悩みなどの人間部分の育成には向いているとは言い難いです。
授業料の安さに目を奪われがちですが、重要なのは費用対効果。
長く続いて子供が吸収しなければ、結局今まで学んだことはなんだったのか?という形になります。
個人的な見解としては、明確な目的とモチベ維持ができる大人がオンラインの方が向いていると感じます。
オフラインスクールの授業ってどんなもの?
基本的に先生1人に対して生徒1~5人の少数個別指導の形が多いかと思います。
1対1のマンツーマンも佐賀には存在します。
マンツーマン以外の場合でも、先生が講義をして生徒がそれを見る集団講義方式ではなく、それぞれの理解度やペースに合わせて、テキストや動画を進めて、わからない所があると先生に聞く自学スタイルに近いものがあります。
とはいえ大人と違い子供はほとんどの事がわからないので、ほぼほぼつきっきりで教えている状態になり、1人で5人同時を回せる先生というのは非常にすごい先生です。
私はまだ教室開業したてという事もあり、二人で今は限界です。
オフラインスクールのメリット
講師と生徒が直接触れ合うので信頼性が生まれ、人間形成に影響を与える。
仲間がいる事によるモチベーションの維持。
わからないが発生した際に、実際にやってみせて教えたり、場所を指さしたりなどのわかりやすさがある。
テキスト、動画をベースとした自学スタイルの場合、問題を読み、マニュアルを見てやってみて、わからない所を自分で調べるクセがつくようになり、「自分で学ぶ」というスタイルが構築できる。
オフラインスクールのデメリット
送り迎えが大変。
近くに教室がないと不便。
時間が決まっており融通が利きにくい。
授業料が比較的高くなりやすい。
教室の先生の数が決まっており、先生の質の当たりハズレが大きい。
知らない所で学ぶので、子供が馴染むかどうかにかかっている。
オフラインスクールの総評
一般的な習い事の延長線ですのでイメージもしやすく、その場所で営業しているので地域への信頼性で教室を選ぶ事で、教室の質はある程度カバーできるかと思います。
初めてのプログラミング教室であるならオフラインの方をオススメします。
デジタルアレルギーはわからないが放置される事で苦手意識に直結して発生します。
わからないが発生した瞬間、リアルタイムでフォローできるのがオフライン教室の最大のメリットです。
我々バレッドキッズでは、特に低学年の子供たちの入学から3か月は、メインがしつけと言われています。
大人たちが触っているパソコンを自由に触れるという興奮や、ゲーム感覚で楽しく学べることから興奮してしまい、脱線してしまう事が多々あります。
逆にわからなくなってしまって止まってしまう子が、他の生徒に見入ってしまったりしてしまった場合に、すぐさまフォローに入ったりします。
また、義務教育においての受け身の集団講義方式から、自学スタイルの自分で学ぶ授業方式に慣れていく為の準備期間でもあります。
オフラインの教室はまさにここに特化していると言えます。
専門的に学びたい!!
目標はプログラマーやシステムエンジニア!!
など明確な目標がある方はオンライン
とにかくパソコンを学びたい!!
長く続けたい!!
友達が欲しい!!
というとにかく情報教育の入口から入りたいという方はオフライン
私はこのようにまとめたいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございます。
Digital Studyの各種教室の情報はコチラ
こんにちわ。
佐賀市で「ICT教育×eスポーツ×遊び場」を運営しているDigitalStudyです。
子供向けプログラミング+パソコン教室や大人向けパソコン教室など各種デジタル教育の教室を運営しています。
今日は「デジタルアレルギー」について記事にしたいと思います。
デジタルアレルギーの定義は、デジタルが苦手というだけでなく、デジタル機器、ICT端末、システム、DXやアプリ、ソフトなどに対して極端に苦手意識が強く、恐らくこの単語を並べただけで「もうお腹いっぱい!!」という状態を指します。
一般的な会社で…
Aさん「部長!!広告を打つ際のメディア選定において、マスを取る為のTVやラジオ、新聞やポスティングなどもあると思いますが、WEB広告の場合はインプレッション数やコンバーション数が明確に数値化できるうえに、こちらの狙ったターゲットに直接アドセンス広告が設置できるので、費用対効果が非常に高く効率的にリーチできると思います!!」
部長「は?」
Aさん「主戦のSNSはZ世代をターゲットとしているのでインスタグラムが妥当かと思いますが、インフルエンサーに出稿してプロモーションをかけてもらうのが確実かと思います。TikTokもありだと思います。」
部長「は?」
Aさん「まずはインスタの広告でABテストを行い、リアクションが高かった方を採用していくのですが、うまくいけばそこからLPに誘導して自社商品のECサイトに誘導を行う事をコンバージョンとしたいと思いますが、いかがでしょうか?」
部長「は?」
部長「…………新聞でよくない?」
Aさん「えっ!?」
部長「えっ!?」
これ、現実に起きてる事象です。
というよりこの記事に辿り着いた方であればデジタルの事を調べていると思いますので、すでに上記の例え話がわからないかもしれません。
何がわからないかと言うと、まず「単語がわからない」につきると思います。
ECサイト ⇒ ショッピングサイト
コンバージョン ⇒ 目標に対してゴールしたかどうか?
インプレッション数 ⇒ ユーザーがネットを使っている時に広告を見た数
などなどの横文字が大量に連なるわけですが、横文字を日本語にした所とて、結局「わからん」につきるわけです。
これってそもそもネットの仕組みを知らないから、単語を聞いてもイメージがわかないせいなんですよね。
インターネットでは全てのユーザーの行動が記録されていて、誰がどこで、何を何秒見たか?が記録されています。
そのデータを使ってどんな性別で年齢がわかって、どういう単語を使って何を調べようとしたのか?を分析できると、今の需要がわかるという事になります。
このブログを始めた理由も、プログラミング教室を事業としてやる以上、プログラミングや情報教育、デジタルに意識を向いた方がどんな情報を求めているのか?の仮設を立てて話題を決め、記事を書いているわけです。
そこで興味を持って頂いた方に当教室の事を知ってもらい、入会してもらうという算段があるわけです。
ここら辺の話はマーケティングに繋がる話ではあるんですが、そもそもデジタルリテラシーが高くないと、マーケティングに繋げる事ができません。
現代の40代以上の方はそこまでデジタルに強くなくてもアナログの仕事でやっていけました。
しかし、コロナ禍を経験し、人手不足が社会問題化するにあたり、世の中はDXに向けて一気に加速していってます。
DXとはデジタルトランスフォーメーションの略称で、簡単に言うとアナログの仕事をデジタルにしていきましょうという事です。
このDX化で一番みんながイメージしやすいのがセルフレジですね。
それ以外の所でもDX化の波は凄まじく、今では事務職の「ワード、エクセルが使える方」という基準は「入力ができる」ではなく「初歩的な関数が組める」という基準に上がってます。
「計算式の所に数値を打つな!」「数値を全角で打つとデータが集計できない」が理解できないと事務職にはつけなくなっています。
今後もこのDX化の波は止まらず、5人でやっていた作業をDX化で2人に減らすという事がどんどん起きていくでしょう。
そうなると、その残り2人に選ばれるのは、DX化したシステムを扱える二人という事になります。
今子供たちの親で「デジタルがわからない」という事に危機感がある方は少ないです。
なぜならその方たちは「今生活ができているから困らない」からです。
今困ってないのに危機感が出るわけがないです。
困るのは実際に危機が迫ってからです。
さて、今小学生の子供を持つ親の場合、5年後、10年後社会はどうなっていると予測しますか?
販促を制すものはビジネスを制す。
私も今事業を始めて販促で大苦戦中ですが、まだWEBが使える分どうにか自分の事業をWEBで広めていっており、多少なりとも認知が拡大していってます。
今あなたがこの記事を見ているのも、私がデジタルを扱えるからここに辿り着いたわけで、デジタルが使えなければこのような接点を持てないわけです。
今やAIが台頭して大量に販促がAIに置き換わりつつあります。
私もAIを駆使してポスターデザインやライティングに活用してます。
そんな中での5年後、10年後に、今の子供たちがデジタルとの接点を持たずに成長し、大人になっていきなり全部覚えろと言われてできるでしょうか?
これができると言うなら、今の親たちもできて当然なんです。
それができないからデジタルアレルギーが生まれていくわけです。
そして、親がデジタルアレルギーの場合、子供のデジタルの接触点を奪います。
スマホは危険。
ゲームは危険。
Youtubeは危険。
サッカーやってなさい。
バスケやってなさい。
各家庭の教育方針もあるのでそれ自体を否定するわけではありませんが、なんでも吸収できる子供のうちにデジタルに触れさせる事で、子供はデジタルの仕組みを体で理解します。
例えばスマホにしても、
・タッチパネルというものが存在し、それを触るとマウスのように認識する。
・Wi-Fiというものを知る。
・アプリはストアにあり、ダウンロードしてインストールして利用する。
・画像や動画はクラウドに保存され、他の端末でも見ることができる。
・バッテリーというものが存在し、充電しないと減っていく。
・LINEというSNSアプリを知り、友達と文字で会話することで、文字の入力を知る
これらの経験を得るわけです。
タップ一つにしても押せる場所、押せない場所の存在を知る事で、自分が運営する側にまわった時に、その場所を作るというイメージが備わっているわけですね。
今までゲームもスマホも触った事がないという人は、そもそもタップ、クリックの概念がないのでどうしていいかわからないという状況になります。
現在の新卒社員はデジタルネイティブ世代と呼ばれてますが、その媒体はスマホが主流の為、業務に使用するパソコン操作にかなりの苦戦を強いられているとの情報も上がっています。
子供がゲームをしていたら、こう言うことを言い出したことはありませんか?
子ども「お父さん!!僕もゲーム実況を作ってYoutubeにアップしたい!!]
父親「お、おぅ…(やりかたわからん…)」
もしここで父親がこれを教えられるスキルがあれば、
・動画を撮影する
・ゲームの映像をPCに取り込む
・撮影した動画を編集する
・動画を適正なファイルサイズに調整し、Youtubeに合わせた形式に変換できる
・動画を面白くするために企画を作り、構成して台本を作る
・動画をアップする際の危険性や顔バレ、住所バレを防ぐ方法を知る。
・動画をアップした後に誰がどれくらい動画を見たかを知り、リアクションを知り、次の動画の対策にする。
これらのスキルを子どものうちに獲得できたかもしれません。
これらのスキルを持っていたら、本当にすごいですよね。
そして、デジタルへの接触点が少なければ少ないほど、子供たちはデジタルの理解が進まず、デジタルアレルギーになっていきます。
一番難しい問題は、一度デジタルアレルギーになってしまうと、大人になってからその挽回が非常に難しい事です。
それは、今の大人たちがデジタルを学び直せるか?を自分自身に当てはめて考えればわかると思います。
横文字を聞いただけで頭がこんがらがるようになってしまいます。
そうなる前に、まだ子供で好奇心が強い状態の内に、自然にデジタル教育を馴染ませていく事が大事です。
今当教室で受け持っている生徒さんは、元々PCも触ったことがない生徒さんで、タイピングも指一本からスタートしました。
ゆっくりゆっくり、一つずつ楽しめるように授業を行う事で、たった一か月でタイピングの基礎のホームポジションができるようになって来ています。
ファイル、フォルダの違いもわからなかったのに、今では「ファイルを保存する必要がある」という概念を理解してきています。
一度ここの基礎ができてしまえば理解は早いです。
子供のうちからパソコン教室って必要?と思うかもしれませんが、子供だからこそ今のうちに、デジタルアレルギーになる前に染み込ませることが大事なんです。
情報教育に興味がある方、子供のデジタル教育に危機感を持ってある方。
ぜひとも当教室にご相談下さい。
今の所ほぼすべての子供が無料体験で楽しいという感想を頂いています。
習い事の核は長く続いてスキルを獲得する事。
獲得したスキルが将来に役に立つ事だと思います。
それは体験してみないとわかりませんので、まずは体験をご検討下さい。
世の中には様々な種類のプログラミング教室がありますが、その違いについてはこちらの記事をご覧ください。
みなさんこんにちわ
佐賀市呉服元町でバレットキッズというプログラミング+パソコン教室を運営しています。
大学共通テストで情報Ⅰの試験がスタートし、みなさん情報Ⅰとはなんぞや?と思われたり、情報が大事なら子供にプログラミング教室を通わせるべきか?
というのを悩まれているかと思います。
「武道」のくくりで言うなら柔道や空手、剣道などの違いはわかるけど、「プログラミング教室」のくくりで言うと何が違うのか?がわからないという声が多いです。
ほとんどの教室が「論理的思考をやしなう」とうたってますが、何がどうなってそうなるのか?はイメージつかないですよね。
ですので今回の記事は各プログラミングの違いを記事にしていきたいと思います。
主にプログラミング教室を大きくわけると、
①ロボットプログラミング
②ビジュアルプログラミング
③マインクラフト系プログラミング
④パソコン教室
⑤Java,Python系プログラミング
とわけられるでしょう。
ロボットプログラミング(通称ロボプロ)
機械工学系プログラミングで、主にロボットを使ってそれを操作するプログラミングです。
機械を使うので「曲げる」「持ち上げる」「動かす」という動作などをプログラミングしていきます。
プログラミング自体のやる事は他のプログラミングと基本変わりませんが、対象であるロボットの機械的な構造を知る必要があるので、ギアであったりセンサーであったりという、物理的な機械工学の知識も養えます。
これの基礎知識が出来上がると、クレーンゲームがどういう理屈で動いているのか?
電車がどうやって電力を供給しているのか?
自動販売機がどういう理屈でペットボトルを取り出し口に落とすのか?などを理解できるようになります。
ロボプロのイメージはガンダム的なロボット開発のイメージがわきやすいですが、誰もが使っている「機械」のエンジニア向けの習い事になると思います。
より複雑になると工場機械や車などの方向になり、摩擦や加速なども扱うようになります。

私は元ゲームセンターで働いており、様々な機械のメンテナンスをしていたのでどちらかというとこちらの部類の方が強いです。
スマホの修理もこちらの知識でカバーしています。
時計やゲームのコントローラーを分解したりを繰り返すと、こういった知識が強くなります。
私は中身の構造に興味が出る「分解癖」がある子供はこちらをオススメします。
通常のプログラミング教室と違い、教材となるロボットが高額なため、習い事の費用としては非常に高額になりがちなのが難点です。
ビジュアルプログラミング
プログラミング言語を「文字」だけでなく「ブロック」や「絵」でわかりやすく直感的にプログラムが組めるプログラミングです。
私もそうでしたが、プログラミングを学ぶ際に途中で挫折してしまう原因が、文字だけなのでわかりにくいという所です。
ビジュアルプログラミングはレゴのようにコマンドを組み立てるだけでプログラムが組めますし、指導する側も「if構文がどうじゃいこうじゃい…」ではなく「赤のこのブロックを持って来て」と指導できるので、子供にも理解しやすい事が大きいです。
みなさんが使っているパソコンも昔はMS-DOSと呼ばれる文字だけのものでした。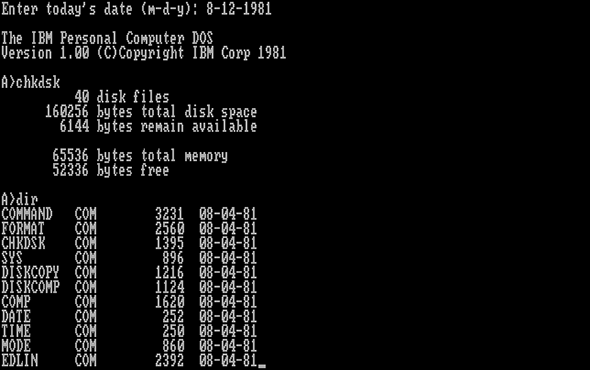
この画面で初心者がファイルをコピーする事はおろか、ファイルを探す事も不可能でしょう。
アイコン化、ビジュアル化する事で理解が深まり、そこで基礎知識を養うと、本格的な文字のみのプログラミングへの理解が進むようになります。
また、近年のアプリはHPにしろ、売上管理ソフトにしろ、こういったブロックでシステムを構築していくアプリが多く、よくCMで見る「キントーン」などもこれに近い形で社内システムをオリジナルで作れるという感じです。
パソコンは一度ダメだと思ってしまうとデジタルアレルギーという状態になり、デジタルを学ぶ意欲をごっそりと奪ってしまいます。
そうならない為にも自然と馴染めるビジュアルプログラミングが子どもには最適だと私は考えます。
マインクラフト系プログラミング(ゲーム系プログラミング)
最近爆発的に人気のプログラミングで、子供たちに大人気のマインクラフトや各社オリジナルのゲームを媒体としたプログラミングです。
基本的にはビジュアルプログラミングの考え方をベースとしており、ゲームのようにミッション式になって遊んでいる感覚でプログラミングの基礎を学べるというのがウリです。

ビジュアルプログラミングの要素とマイクラならでは建築の要素でロボットプログラミングの要素もあり非常に仕組みとしてよくできてます。
しかしながら、ゲームという部分で子供が脱線しやすいという弱点もあります。
もちろんマイクラプログラミングには子供が脱線しないようなフォローアップが多数存在しますが、興味として惹かれてしまうのが難しく、学んでるのか遊んでるのかちょっとわかりにくくなるという部分が難しいです。
パソコン教室
プログラミングではなくオフィス系などを学ぶ教室となります。
プログラミングが噛まないので論理的思考という部分は劣るかもしれませんが、将来に役に立つという視点で見るならこれが一番実戦として役に立ちます。
しかしながら「使える」事はできても「中身を理解する」というわけではないので一長一短だと思います。
Java,Python系プログラミング
プロ志向の本格的なプログラミンです。
基本文字のみでプログラムを書いていきます。
こちらも超実戦的で、今我々が扱っているアプリ、ソフト、インターネットはこのプログラムを活用しており、これを習得できれば明日から一人前のエンジニアとしてやっていけます。
難度が一気に上がるので、初心者がいきなりここからスタートはかなり無理があると思います。

各種様々なプログラミングがありますが、第一に重要なのは子供が興味をしめして、やってみて楽しめるか?が重要です。
入口はどこにしろ、触れてみないとわからない所が大きいので、体験させてみてから考えることが重要かと思います。
また、もう一つ重要なことが、どのプログラミング教室にしろ、学ぶのは「技術」です。
技術だけが伴う状態は、「モラルのない空手」と同じく危険な技術になってしまいます。
パソコンに強くなると共に「情報リテラシー」をしっかりと学べるかどうか?が教室を選ぶうえでの鍵になると思います
私もパソコン教室を開業するにあたって様々なプログラミング教室のフランチャイズを探しましたが、バレッドキッズに決めた理由は、プログラミングだけでなくパソコン教室も併用している事。
デジタルだけでなくプレゼンやマーケテイングなどビジネスに必須なスキルも学べる事。
そして情報リテラシーに注力して教えていく事。
このカリキュラムが決定打になりました。
収益だけを見れば流行りのマイクラプログラミングに飛びつくだけですが、それを学んだ先がどうなるのか?が明確になっていたのがバレッドキッズでした。
大人になって社会に出た時に戦える総合的なデジタルスキル、情報スキルを獲得する。
それがバレッドキッズです。
良い教室を見極める方法は、この教室を卒業したらどうなりますか?
何になれますか?プログラミングを学ぶとどうなりますか?が良いかと思います。
私は普通のサラリーマンや個人事業主ですが、社会で圧倒的有利になれるデジタル・情報スキルを持ったイケてるサラリーマンです。と答えます。

最後までお読みいただきありがとうございます。
当バレッドキッズ佐賀呉服元町教室では常時無料体験を募集しています。
まずはお子様に体験して頂き、見極めて下さい。
■バレッドキッズ公式HP



























