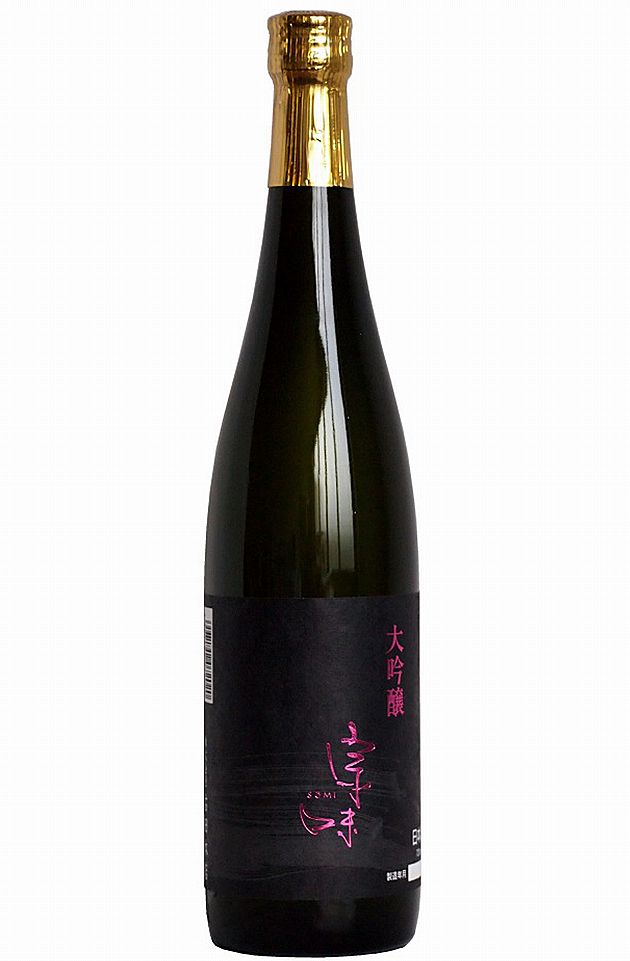令和5年12月31日。
1年最後の大晦日です。
前回も書きましたが、
この一年、あまり良い年ではありませんでした。
--->>>
また、例年、年末年始は高知県四万十市で過ごすのですが、
10月の「関東旅行」による散財で、
今回はいけなくなりました。
そのため、四万十市の一條神社で年末・年始詣でをするのですが、
それもかなわないことに。。。
そこで、今回は、
島根県大田市にある「物部神社」詣りをすることにしました。
実はこの物部神社では12月と6月に「大祓」を行います。
「大祓」とは、
「日々の生活の中で知らず知らずのうちについてしまった罪やけがれを祓い清め、
家族みんなが健康に暮らせますように、とお祈りする祭典」です。
(物部神社ホームページより)
物部神社は、島根県大田市にあり、
すぐ近くには世界遺産「石見銀山」もあります。
訪れた12月31日は雨風の吹く悪天候で、
駐車場に車を停めたときも大雨が降っていました。
しかし、境内に入るとほとんど雨は止んでいました。
駐車場から鳥居をくぐります。
物部神社の案内看板を見ると、
- 御祭神は御祭神宇摩志麻遅命(うましまじのみこと)
- 島根県内では出雲大社に次ぐ大きさ
- 春日造りでは全国一の規模
ということが分かりました。
正面からも見ると、
背後の山の前に構えた拝殿・本殿の立派さが際立ちます。
手水場の対面には、
鶴のオブジェがありました。
これは御祭神・宇摩志麻遅命が鶴の背に乗って降臨された
という伝説があることから造られたのでしょう。
物部神社の神使は「鶴」で、
御神紋も太陽を背に負った鶴「ひおい鶴」となっているそうです。
いよいよ拝殿に近づきます。
翌日が元旦なので、
初詣のための準備もできていました。
二礼二拍手一礼をし、
今年一年を無事に過ごせたことへの感謝を申し上げます。
参拝を済ませると、
拝殿から本殿の周りを一周します。
右横から見た本殿です。
春日造りの特徴である屋根の曲線が分かります。
見えにくいですが、庇と屋根も一体となっています。
拝殿・本殿を正面に見て右側には、
摂社や末社が並んでいます。
そのうちの一つ、「後神社」。
御祭神・宇摩志麻遅命の妃神である師長姫命(しながひめのみこと)を祀る摂社です。
二本の杉を前にして建立されているのですが、
厳かさ・威厳・畏怖を感じました。
気になったので、
しっかりと祈って参拝させていただきました。
こちらは「勝石」。
宇摩志麻遅命が石見の地に降臨された際にお腰を掛けられたと言われる岩で、
触れると全ての願いに通じる勝運を授かれると言われているそうです。
早速、石に手を当て、
病気などないように、と祈りました。
実は、12月にガンの疑いがあることが分かり、
年明けにMRIによる精密検査を受けることになっているのです。
果たして私の願いは叶うでしょうか・・・
そして、今回参拝した本当の目的、「大祓」をするために、
社務所へ向かいました。
早速、「人形」(ひとがた)をいただきます。
これは、罪や穢れをうつし依り代としてお祓いに用いる「人形」で、
この夜に行われる大祓の祭典で祈願していただくことになります。
人形に、住所、氏名、生年月日を男女別に記入し、
巫女さんにお渡ししました。
なお初穂料はお気持ちということでした。
大祓の人形をお渡しし、これで本来の目的は終了。
境内を帰る途中で馬の彫像を発見。
「パーソロン号御神馬像」で、
七冠馬シンボリルドルフの父馬だそうです。
氏子さんが馬主だったそうで、こちらに奉納されたとのことでした。
そのため競馬ファンもよく訪れるそうです。
すべてを終えて振り返ると、
本殿の千木、屋根が見えます。
立派ですね。
さて、神社で罪や心の汚れを落としたのであれば、
「からだ」の清めねばなりません。
帰路に温泉津温泉がありますので、
そこで「からだ」を清めることにしました。
温泉津は、石見銀山の積出港として賑わった町で、
古くから温泉もあります。
往時の賑わいを忍ばせる町並みは旅情を感じさせるもので、
「男はつらいよ!」のロケ地にもなりました。
木造の古い旅館も建ち並びます。
今回立ち寄ったのは、
日帰り温泉施設「元湯温泉」。
湯治・保養の温泉ですが、宿泊はありません。
しかし、自然自噴湧出温泉といい、
掘削、ボーリングなどを行っていない本当に自然の温泉です。
施設の前には、湯ノ花石が置かれています。
番台の女性に入浴料を払い
中に入ります。
すると、中は懐古させるのに十分な風景が広がります。
木造の脱衣室にはたくさんの説明書きがありました。
ロッカーも木製。
コイン式ではありませんが、鍵をかけることができます。
壁にはマンガで描かれた注意事項と古めかしいボンボン時計があります。
明治初期の温泉津温泉街の写真も飾られていました。

明治二十二年の温泉番付です。
番付表を見るとこの当時、
温泉津温泉は西前頭八番目に位置していたようですね。

そして、この先が浴室。
残念ながら入浴客がいたので写真撮影はできませんでした。
入浴した感想ですが、
まず第一に言えるのは、
非常に熱い!
ということです。
三つの浴槽があり、
- 「初めての方」と書かれている浴槽は38~40度、
- 次に「ぬるい湯」と書かれている浴槽は42~44度、
- そして「熱い湯」と書かれている浴槽は46~48度。
わたくし、2の「ぬるい湯」まではなんとか入れましたが、
3の「熱い湯」は入れませんでした。
東北の温泉並の熱さでした。。。。
約30分近く入浴したのち、
真っ赤になったカラダで脱衣室へ戻りました。
体中、ぽかぽかです。
冷たい空気でカラダを冷やすために外へと出ます。
「ありがとうございました~」
と番台の女性から声をかけられます。
ふと気になったことを番台の女性に聞いてみました。
「あの~、ここってNHKの『小さな旅』に出ませんでしたか?」
女性は、
「はい、出ましたよ」
と答えてくれました。
やはり!
以前、NHK「小さな旅」で、
温泉津温泉が舞台で、源泉からのお湯の温度調節を管理する女性の話が
放映されていたのです。
(「ふるさとつなぐ~島根県温泉津温泉~」を参照)
源泉から出る湯はかなり高温で、
これを適温にするために、毎日苦労しながら管理する様子が描かれていました。
まさにこの温泉施設の話だったのです。
しかも、その管理していたのはこの番台の女性!
なんとも嬉しい気持ちでいっぱいとなりました。
実は温泉津温泉には「薬師湯」という日帰り温泉施設があります。
薬師湯は有名なので、当初こちらに入浴しようと思っていたのですが、
なぜかこの元湯温泉のほうに入ったのです。
偶然でしたが、本望の場所を訪れることができたことは、
一年の最後を締めくくるのに最高の結果だと思いました。
[薬師湯]
温泉津温泉を出て、帰路につきます。
熱い湯でしたが、温泉のせいか、
カラダは芯から温まった状態が続いていました。
2023年、最後の一日。
最高の一日となりました。
--->>>

にほんブログ村
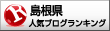
島根県ランキング

国内ランキング