
¥380
Amazon.co.jp
中島敦『李陵・山月記』(新潮文庫)を読みました。
中島敦はたしか国語の教科書に載っているかなにかで、みなさん「山月記」はご存知だろうと思います。虎になってしまうやつです。それからわりと最近では、森見登美彦が『新釈 走れメロス 他四篇』の中で「山月記」を下敷きにした作品を書いていました。
新釈 走れメロス 他四篇 (祥伝社文庫 も 10-1)/森見 登美彦

¥590
Amazon.co.jp
『新釈 走れメロス 他四篇』は、少し古い時代の日本文学を下敷きにした小説集です。現代語訳ではなくて、ストーリーとかなんとなくのイメージを借りているものです。
舞台を現代に移して、いつもの森見節とも言うべきドタバタ喜劇に仕上がっています。これはなかなか面白い小説集ですので、ぜひ下敷きになっている日本文学の作品とあわせて読んでみてください。
中島敦に話を戻していきますが、中島敦は「山月記」が有名なだけに、却って他の作品があまり読まれていないような気もします。
漢文がベースになっている小説が多いので、難しい熟語がたくさん出て来ますし、舞台になっているのが中国なので、ある種の読みづらさはあるかと思います。それはたしかにそうです。
ところがその読みづらさというのが、中島敦のなによりの魅力なんですよ。難しい文体で書かれていること、そして中国の歴史を下敷きにしていること。
この両方を両立させている作風というのは、中島敦独特のオリジナリティであって、日本文学史上ほとんど唯一無二の存在だろうと思います。
中国に寄り添った作家は他にもいます。たとえば戦後文学の武田泰淳は、『司馬遷』という評論を書いていますし、カンフーファンの人には、『十三妹』という中国の古典を元にした小説がおすすめです。
十三妹(シイサンメイ) (中公文庫)/武田 泰淳
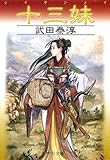
¥820
Amazon.co.jp
井上靖は、『蒼き狼』でチンギス・ハーンを、『孔子』で孔子の人生を書きました。司馬遼太郎も『項羽と劉邦』を書いていますし、宮城谷昌光や田中芳樹などの作家も、数多く中国を舞台にした小説を書いています。
中島敦の作品が、そうした中国を舞台にした小説と一線を画しているのは、まさに一見難解に思える文体があるからなんです。
つまり発想として中国の古典があって、それを単に日本語で小説にしたのではなく、漢文的な雰囲気と要素を残しつつ書いている稀有な作家なんですよ。こうした作家は他にはいないと思います。
少し話を変えます。これは『今昔物語』をリライトした芥川龍之介とある程度同じことが言えると思いますが、単に口語訳といって現代に翻訳したものではないんです。
漢文があって、それを訳したら中島敦の小説のようになるかと言えば、決してそうはならない。
古文や漢文のリライトをする時、どの作品を下敷きにするか、どの部分を採用してどの部分カットするか、あるいはどこを書き加えるか。そうした取捨選択がなされることは言うまでもありません。
しかし、そうした編集的な技法よりももっと重要なのは、芥川龍之介や中島敦が古文や漢文の枠組みを借りて、全く新しい小説を生み出しているという、まさにそこにあるのではないかと思います。
つまり、芥川龍之介の「鼻」や中島敦の「山月記」では原文に比べて、加わった感情的ななにかがあるんです。単に古典の焼き直しではなく、「鼻」や「山月記」を通して作者が描きたかったものというのが、確実にあるんです。
中島敦は、今では馴染みがなくなってしまった漢文の枠組みを使って、唯一無二の小説を書いた人です。文体、内容は多少難解かもしれませんが、興味を持ったらぜひ読んでみてください。おすすめの作家です。
作品のあらすじ
各短編に少しずつ触れていきます。『李陵・山月記』には、4つの短編が収録されています。「山月記」「名人伝」「弟子」「李陵」の4篇。
「山月記」
李徴という男の生き様を描いた短編です。分かりやすく言えば、すごく頭が良くて才能がある人です。そして才能があるだけに、プライドがすごく高い。詩を書いて、いつか世間に名を轟かすぞと思っています。ところが名前は全然轟かない。周りはなかなか認めてくれない。生活は苦しくなってくる。家族のため、暮らしていくために、自分の夢を捨てて仕事につくんですが、その時にはもう自分が馬鹿にしていた人の下につかないといけないわけです。
仕事で旅先にいたある夜のこと。「何か訳の分からぬことを叫びつつそのまま下にとび下りて、闇の中へ駆出した」(9ページ)李徴は、そのまま姿を消してしまいます。
ここで話は李徴から少し離れて、翌年、李徴の友達である袁傪が仕事で旅をしている時の話になります。なんでもそこから先に人食い虎が出るということなんです。供が大勢いるので、それでも先に進んで行くと、案の定虎が出ます。
虎が襲いかかって来ますが、袁傪に気がつくと、草むらに隠れてこう言います。「あぶないところだった」(9ページ)と。その声でその虎が李徴だということに気がついた袁傪は、李徴の話を聞きます。すると・・・。
「山月記」は色んな読み方ができます。たとえば、袁傪の立場と同じ目線で、虎になってしまった他人から、教訓的なものを読み取る読み方。こうなったらダメだよね、という読み方ですね。
それから、作者と虎を重ね合わせて、虎になってしまった李徴の叫びは、作者自身の叫びなのだという風に読み取る方法。
読み方は自由で構いませんが、ぼくがなぜこの作品が好きかというと、虎になってしまったのが他人ではなく、自分のように思えるからです。
あらすじを読んで、なんとなく気づいた方もいらっしゃるかと思いますが、李徴の生き方というのは、ミュージシャンを目指してバンド活動をしている若者にすごく似た部分があります。
音楽が好きで、それなりに才能があって、一心不乱にバンド活動をしているけれど、全然目が出ない。生活のために夢を諦めた頃には、自分の同年代はちゃんと働いて出世していて・・・。
なんらかの夢があって、努力しているのにむくわれない。そんなことがある人は、すごく共感できて面白い小説だろうと思います。悲しみを誰かに分かってほしくて吼えても、みんなはひれ伏すばかり。そんな虎になってしまった男に胸打たれる短編。
「名人伝」
「名人伝」は、ぼくが最も好きな短編です。これは面白いですよ。弓の達人の話なんですけど、もう完全に少年マンガの世界です。紀昌という男が、弓の名人に弟子入りするんです。そして機織り機が動いているのをひたすら見たり、髪の毛にシラミをぶら下げてそれをじっと見るなどの凄まじい修行をして、すごい弓の達人になります。すると、今度は師匠がいると天下一になれないと思って、師匠に矢を射つんです。
師匠も達人なので、矢を射ち返します。空中で、ぶつかって弓矢は落ちます。すごいですよね。結局勝負はつかなくて、師匠が言うには、ある山のてっぺんにもっとすごい老師がいると。
そこで紀昌は山に登って老師に会いに行きます。紀昌が腕前を見せると、老師曰く。
一通り出来るようじゃな、と老人が穏やかな微笑を含んで言う。だが、それは所詮射之射というもの、好漢未だ不射之射を知らぬと見える。(28ページ)
果たして老師の言う「不射之射」の意味とは一体?
この短編はもうほら話的というか、荒唐無稽すぎて、それが却っていいんです。そして修行して強くなるという少年マンガ的な展開にわくわくします。
短編全体には、ユーモラスさというか、ある種の馬鹿馬鹿しさみたいな感じもあって、なんだか面白いんですよ。達人が道を極めていくとどうなるのか、ぜひ注目してみてください。
「弟子」
「弟子」もかなり面白いです。胸にぐっとくる話です。ある意味において、「山月記」に似た部分があります。能力はあれどもむくわれないというところが。「弟子」というのは、孔子とその弟子の子路を描いた短編です。孔子というのは中国の思想家で、弟子に語ったことがまとめられたとされる『論語』が有名です。
血気盛んなところのある子路は、うさんくさい孔子というやつを懲らしめてやろうと思って孔子の所に乗り込んで行って、逆にその人柄に打たれて弟子入りします。
この短編は、『論語』のいい入門になる部分もあって、孔子と弟子とのやり取りが描かれています。ある弟子が聞くわけです。死んだらどうなるのか、魂はあるのかないのか。孔子はこう答えます。「未だ生を知らず。いずくんぞ死を知らん。」(62ページ)と。
まあ単なるへらず口と言えばそうなんですけど、ちょっと「おおっ」と思いますよね。そういった孔子さんのためになるお言葉も勉強できます。
時代は乱世。孔子はなかなか重く用いられず、諸国放浪が続きます。それに付き従う子路や弟子たち。やがて・・・。
「李陵」
「李陵」は、3人の男の生き様を描いた短編です。これもまたいいんですよ。すごくいいです。思い出したらまたちょっとぐっときました。武帝という皇帝の時代の中国が舞台なんです。匈奴といって、モンゴルの遊牧民と戦っているんです。李陵という将軍が、その匈奴と戦うんですけど、負けて捕まってしまうんですね。
そこにはちょっとした誤解もあったりするんですが、李陵は捕虜になった後に、裏切って匈奴についたとされ、故郷に残した家族が皆殺しにされてしまいます。激しい憤りを覚える李陵。
李陵のことを知っている司馬遷は李陵を弁護して、刑罰を受けることになってしまいます。男性として大切な部分を取られてしまうんです。司馬遷は殺されることは覚悟していたんですが、そうしたことは想定していなかったわけで、ものすごい屈辱を感じます。
一方、李陵は自分よりも先に匈奴に捕まっていた蘇武という男に匈奴に降るよう話に行きます。蘇武は草原で貧しい暮らしをしながら、漢に戻れる日を待っているんです。李陵は蘇武と自分の身を比較して様々考えます。
自分の身に突如降りかかった屈辱。それにどう対応するかという3人の生き様が描かれた短編です。怒りに燃えた李陵。屈辱を超えて『史記』を書き上げた司馬遷。自分の信念を貫き通そうとした蘇武。そんな男たちの熱い想いが渦巻く短編です。
そんな4篇が収録された短編集です。どの短編にも窮屈な世の中での男の生き様というような、共通したなにかがあるような気がします。それがすごく面白いです。
文体というか、読みなれない漢字がたくさんあって読みづらいとは思うんですが、新潮文庫だとほとんどすべてに注がついています。
もちろん注を参照しながらじっくり読んでもいいんですが、もしきついようだったら、名詞(たとえば町の名前など)は注を見ずに、そして形容詞など他の単語は文脈から判断するというやり方でも、ある程度楽しめると思います。
中島敦は独特の魅力のある面白い作家です。機会があればぜひ読んでみてください。おすすめです。