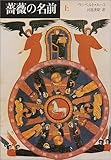
¥2,415
Amazon.co.jp
薔薇の名前〈下〉/ウンベルト エーコ

¥2,415
Amazon.co.jp
ウンベルト・エーコ(河島英昭訳)『薔薇の名前』(上下、東京創元社)を読みました。
イタリアの記号論学者であり、小説家のウンベルト・エーコの名前は、読書界に轟いているところがあって、その中でも『薔薇の名前』はぼくが長年読みたいと思っていた作品です。
記号論学者として著名な人が書いた小説であり、書物がたくさん収められた文書館が登場し、そしてどうやら書物が重要な役割を果たすらしい。それを聞いただけで、もうすごく面白そうですよね。わくわく!
ぼくは観ていませんが、映画化されたことでも話題になったようです。でもそれほど有名な作品にもかかわらず、なぜかずっと文庫化されていなくて、なかなか手を出しづらかったんですが、折角の〈その他の国の文学月間〉なので、ようやく読んでみました。
『薔薇の名前』は基本的には探偵小説だと思ってもらって大丈夫です。ホームズみたいな人(明晰な推理をする人)とワトソン(助手兼語り手)みたいな人が出て来て、僧院という密閉された空間での連続殺人事件の真相を追っていくというお話です。
ただ、それだけの物語ではなくて、少し前にダン・ブラウンの『ダ・ヴィンチ・コード』が話題になった時に『薔薇の名前』に言及されることがあったように、キリスト教(特に異端審問など)にまつわる話や、秘められた歴史の空白に迫っていくという面白さもあります。
これはオチと関わるので、あまりはっきりしたことは言いませんけど、読んでる最中に奇跡とも呼べる出来事がぼくの中で起こったんです。
ぼくのブログを読んでくださっていて、『薔薇の名前』も読んでらっしゃる方は、多分分かると思いますが、我ながらびっくりしました。このタイミングはもう奇跡としか言いようがなくて、読書界の神に祝福されている気がしました(笑)。
『薔薇の名前』は難解な小説のように語られることもあるんですが、要素としては探偵小説なので、わりと敷居は低いのではないかと思います。ただ上でも少し書きましたが、宗教的なことに踏み込んでいける奥深さがあります。
あと気をつけることとしては、登場人物の名前が馴染みがないせいか、若干覚えづらかったりします。登場人物の名前とどんな役職なのかはしっかり把握しながら進むようにした方がよいのではないかと思います。
作品のあらすじ
この本は、『J・マビヨン師の版に基づきフランス語に訳出せるメルクのアドソン師の手記』を手に入れた〈私〉が、イタリア語に翻訳したという体裁を取っています。つまり、ラテン語の回想記をフランス語にしたものをイタリア語に翻訳したという形式です。
ぼくら一般の読者は、この小説が誰かの手記であることさえ分かればそれでいいですが、あえてそうした形式にしていることは注目に値すると思います。
文中にラテン語が残ったりしていること、また、どこかの時点で細部が誰かに書き変えられている可能性があることなど、もう一段階深い読み方ができる可能性があるわけです。まあそれはともかく。
物語の本編である手記は、メルクのアドソという、見習修道士の手によって書かれています。このアドソが〈私〉であり、〈私〉が年を取ってからの回想記という形式です。
〈私〉はバスカヴィルのウィリアムという修道士の弟子になって、諸国を旅したりして修行に励みます。師匠(マエストロ)と呼ばれるこのウィリアムが頭がすこぶる良くて、知識がたくさんあるのはもちろん、推理力に優れているんです。
このウィリアムがホームズの役割を果たし、その助手であり、語り手というワトソンの役割を果たすのが〈私〉です。時おりファインプレイというか、本人も意図しないところで、ウィリアムの推理の手助けをするところもあります。
歴史的背景が結構分かりづらくてですね、ぼくも知識としてちょっと追いつかない部分があったりもしたんですが、政治的にちょっと荒れている時代の話なんです。まあとにかく、キリスト教の中でも対立が生まれてしまっているとだけ分かればなんとかなります。
教皇の派閥と、フランチェスコ会の派閥の対立があって、ウィリアムと〈私〉はその仲立ちのようなことをしに、ある僧院に行くんです。
僧院に着いたとたん、ウィリアムは鋭い推理力を見せます。ある修道僧と使用人たちがやって来て、あいさつをすると、ウィリアムはこう言うんです。
「かたじけない、厨房係どの」わが師は丁重に礼を述べた。「せっかくの追跡を中断されてまで、わざわざご挨拶いただいて、まことに恐縮です。しかし案ずるには及びまぬぞ。馬はここを通って右手の小径に入りましたから、そう遠くへは行けないでしょう。どうせ堆肥置場まで行けば立ち往生するでしょうから。利巧なあの馬のことゆえ、切り立つ崖から落ちるような真似はしないでしょう・・・・・・」
「いつ、ご覧になられたのですか?」厨房係がたずねた。
「いや、見たわけではない。そうだな、アドソ?」ウィリアムは私のほうを振り返って、おかしそうに答えた。「だがブルネッロをお探しならば、あいつはたしかに、いまわたしが申しあげたところへ、行っているはずだ」
厨房係はためらった。ウィリアムをじっと見つめ、ついで小径のほうを見やってから、最後にたずねた。「ブルネッロ? どうして馬の名前までご存知なのか?」(上、38~39ページ)
ウィリアムはすべてを推理から導き出したんです。雪道の蹄の跡。折れていた小枝。普通の人では気がつかない痕跡を読み取り、みんなが追っている状況や美しい馬にふさわしい名前など様々な知識をそこに混ぜ合わせて、真実を導き出したんです。
ウィリアムと〈私〉はそこの僧院の院長に会います。すると院長は、ウィリアムの明晰な頭脳を頼って、最近僧院を騒がしている、修道僧の死について調査してほしいと依頼します。断崖の底で死体になっていたアデルモ。
そして院長は僧院の中の誰と話しても、どこに行ってもいいけれど、文書館の最上階にだけは入ってはいけないと言います。ウィリアムと〈私〉は様々な人の話を聞きます。その中で、キリスト教や、異端審問に関してのやり取りがあったりもします。
ウィリアムと〈私〉は謎を解くために、文書館の建物の中に侵入しようとしますが、そこは迷宮のようになっているんです。その迷宮の暗号を解いていくという面白さもあります。
やがて〈私〉は修道士としてはあるまじき罪を犯します。修道士としては、です。そしてその罪は、単に〈私〉が堕落したということではなく、僧院全体の裏の顔が垣間見えたともいうべきことです。
やがて起こる第2、第3の殺人。死体の共通点としては、右手の親指と人差し指の指先がくすんでいること。それはなにを表しているのか? 果たして犯人は一体誰なのか?
そして文書館に隠された秘密とは・・・?
とまあそんなお話です。迷宮のようになっている文書館の設定が面白いですね。詳しくは触れませんけど、本好きの人は「わああ!」と思わず叫ぶような展開になります。その「わああ!」がうれしさなのか、悲しさなのか、驚きなのかは伏せておきます。
普通の探偵小説の場合、犯人が殺人を犯す動機って、怨恨だと思うんですよ。これは書いてもいいと思うんで書きますけど、そうした動機とは少し違います。宗教的なものが絡んできます。その動機についても色々考えさせられますねえ。
キリスト教の歴史、特に魔女狩りとか異端審問に興味のある方が読むとより面白いと思いますが、探偵小説としても面白いです。〈私〉の犯した罪について、なんだか不思議な印象が残る作品でもあります。
そしてなにより本好きの方は、本がたくさん集められた文書館が出てくるだけで楽しめると思いますので、ぜひ『薔薇の名前』を読んで、文書館の秘密を手にしてください。
明日は、中島敦『李陵・山月記』を紹介する予定です。